2018年2月、記録的な豪雪となった福井県鯖江市に酒井化学工業はあります。

鯖江といえば眼鏡が有名ですが、繊維産業や漆器なども存在感があります。酒井化学工業は創業当時の昭和30年代に石油化学の市場が拡大をみせはじめており、同社はポリエチレンの技術から出発し、いまでは「ユーザー数10,000社以上、代理店1,000社以上(同社HP)」と裾野の広いマーケットを開拓しました。
まずは、データをみてみましょう。
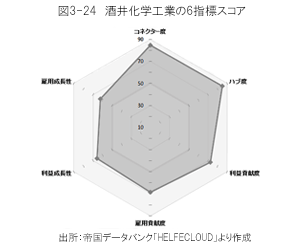
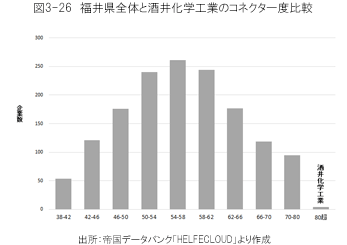
地域未来牽引企業の指標では、コネクター度とハブ度が高いことが特徴です(図3-24)。いずれもスコアは80超で、県内トップです。コネクター度は福井県の域外販売額に占める酒井化学工業のシェアを、ハブ度は域内仕入額でのシェアを示します。これは、酒井化学工業が県内の企業と取引を行い、県外に多くの製品を販売している会社であることを示しています。特に注目なのはコネクター度です。なぜ、このように高い値が出るのかをビジネスモデルからみてみます。
酒井化学工業のビジネスモデルの特徴は、チャネル開発にあります。主要品目である包装材は、産業財の中でも副資材という位置づけで、多くの企業が幅広く利用するという特徴があります。副資材は業務用供給品(プリンターのインク、帳票などの用紙類など)や保守・修理用品(塗料や洗浄剤など)、そして生産用の供給品(段ボールなどの包装材)のように、ビジネスの現場で日々必要とされています。専門商社や卸売業者が市場を有し、多様な選択肢がある品目であるだけに、発注する企業側に「認知されている」必要があります。
「認知される」方法として、消費者向けにはコマーシャルを打つ場合がありますが、酒井化学工業は企業向け生産が主であるBtoB企業ですので、認知されるためにはレピュテーション(評判)を高める必要があります。
そのプロセスを紹介するために創業期を振り返ります。
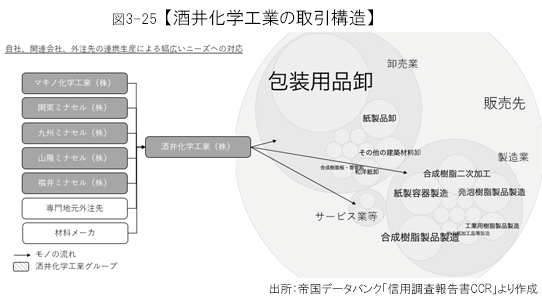
創業期は高度成長期で新しい商品が生まれ、大量に販売できた時代でしたので、新しい技術ニーズも大変多かった時代と言えます。酒井化学工業の場合もそうで、松下電器産業(現パナソニック)との取り引きがきっかけとなります。松下電器産業との取り引きでは、包装を合理化するために不織布とポリエチレンの2枚の袋を使って包装していたものを1枚に貼り合わせることで評価を得ました。しかしながら、テレビのきょう体(機械や機器などを納める外装のこと)が変わる中、この製品が使えなくなったため、新しくポリエチレンとフィルムを貼り合わせた製品を開発しました。これが再び松下電器産業に評価され、同社との取引が会社の信用にもつながり、その後、ソニーや日立製作所、東芝などから同様の用途に採用されていきました。業容が拡大したこともあり、仕入れていた原材料の発泡ポリエチレン(プラスチックをガスで発泡させたもの)を内製化するために工場を設立しました。
次の転機となったのはオイルショックです。原料の確保や為替の問題もありましたが、その後景気が低迷してテレビなど弱電産業が海外展開を図る中で、テレビの包装以外の「他の用途」を考えて開発に取り組むことになります。具体的には、日用雑貨や家具、自動車、農業資材、建築材料などの用途開発を進めました。
そういったプロセスにおいて大事にしていたのは顧客満足度(CS)でした。CSを高めるために、それまで築いてきた包材問屋や専門商社との関係をより緊密にして、問屋や商社とともに、顧客の現場を回って直接ニーズを聞き取ったのです。地域や市場分野が違えば、問屋や専門商社も変わりますので、結果としてすそ野の広い取引構造を持つことになったといえるでしょう。
取り引きを行う中で、酒井化学工業が重視していることは継続的な設備投資です。発泡ポリエチレンを内製化した際は売上高が十数億円程度でしたが、4~5億円の思い切った投資を行いました。「顧客の要求に対して必要な量と納期を守るためには投資が必要だ」という判断です。
副資材である包装材というものは、ビジネスの現場において不可欠なものです。ゆえに、納期の対応は非常に大切で、2018年2月の豪雪の際には、社員は休みを振り替えて生産対応に臨んだり、歩いて出勤をした社員もいたそうです。

もうひとつの特徴はハブ度が高いことでした。
酒井化学工業の製造プロセスを担っているのは、①自社工場、②グループ会社生産、③地元の協力工場(外注)の3つです。
自社工場については、地域での雇用を重視しています。これはグループ会社においても踏襲されており、滋賀県のマキノ化学の従業員は、工場長をはじめとしてほとんどの人が地元での雇用となっています。九州ミナセルや関東ミナセルも同様です。「地元で利益を上げて還元する」というのが全国展開する上での創業者の考えであったため、福井県内のみならず、工場が立地する地域にビジネスが広がっていきました。
地代表取締役社長の酒井清章氏は、「ビジネスの安定と拡大を考慮し、二次加工品を増やしていくため、地元に専業の協力工場(外注)を持つようにしている」と言います。生産の多数量をこれらの協力会社が担っています。

近隣での仕入れをデータから確認してみます。
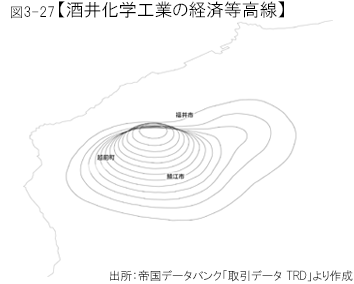
図3-27は、ハブ度を地域での取引量の多さと広がり(ハブ度)を等高線として示したものです。酒井化学工業の場合、県内の仕入先は鯖江市、福井市、越前町の近隣地域に集中しており、等高線の高さもあることから発注量も多いことが分かります。
取り巻く外部環境をみてみましょう。
包装材は新しい商品が生まれ、サイズや形状が変わり、それに伴って包装材の仕様が変化していきます。一例として、最近では運賃のコストダウンに重点が置かれることから、包装仕様の見直しが行われるようになりました。包装資材の仕様が変化することにより、取り扱う企業が変わる場合もあります。一般にプラスチック業界は、設備投資が先行するために販売数量を増やす必要があります。長期的な投資判断とともに新規の市場開拓が必須な産業です。
その中で酒井化学工業は、プラスチックを原料とする4品種(フィルム、発泡材、気泡緩衝材、プラスチック段ボール)を同時展開することで競争力を維持しています。特に、これら4品種に様々な加工を行った製品に力を入れることで、顧客のニーズの変化に対応し、用途を広げています。
一般に用途が広がると多様化に走りがちです。しかし酒井化学工業は、「安易な多様化はしないことを徹底している」(酒井社長)と言います。すなわち、用途は同じだが材料を変えた製品を生産する、材料は同じだが用途が異なる市場への販売をするなど、あくまで従来の延長線上に事業の軸足を置いています。これを酒井社長は「飛び石を打たない」という言葉で説明しています。
同時に「市場規模と市場における酒井化学工業の立ち位置(ポジショニング)を考えて」展開することにも気を配っています。市場を明確化し、自社が得意な分野に注力することで、立ち位置(ポジショニング)を明確にするというものです。ターゲティングの際には顧客との連携や自社の営業部隊が集めた情報から予測し判断をしているのです。

副資材という難しい市場を乗り切るには、人材の確保と活用が欠かせません。酒井化学工業では、「製販一体」を重視した製造、開発、販売を行っています。アメーバ経営*12を採用しているため、組織も小集団です。特に、従業員のベクトルを合わせるために、正社員雇用を中心にしています。縁あって入社した従業員として、人材教育には力を入れています。社員が会社においてだけではなく家庭や地域にも良い影響を与える人になることを目指し、「フィロソフィ」という考え方の共有に力を入れています。「フィロソフィ」とは、人間として何が正しいのかという考え方を述べたものです。
酒井社長は、「利益を生んで会社を支えているのは従業員一人ひとりです。現場で頑張って支えてくれている従業員にはいつも感謝しています」と語ります。人中心の経営を目指す揺るぎない姿勢が同社の強みとなり、地域を支えているのでしょう。
*12 「全員経営」、京セラ創業者の稲盛和夫氏が同社の経営理念を実現するために創り出した経営管理手法で、組織をアメーバと呼ぶ小集団に分けることが特徴。各アメーバのリーダーが中心となって計画を立て、メンバー全員で目標を達成する方式。
地域クラスター活用型
地域クラスター構築型
全国ネットワーク開拓型

