愛知県名古屋市の西側に隣接する愛知県海部郡蟹江町にあるポンプメーカー、アンレットは浄化装置用のブロア(送風機)や真空ポンプを製造するメーカーです。ポンプの代表的な用途は上下水道です。灌漑や排水処理など古くから使われてきていますが、技術開発が進むとともに医療用や工業用などあらゆる産業分野で様々な用途で使われる多品種少量化が進み、関連業種も多いため裾野が広い製品という特徴を持っています。アンレットは1944年創業の老舗メーカーで、多くの特許や実用新案を持つ技術力の高いメーカーです。
まずは、データをみてみましょう。
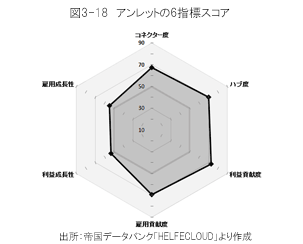
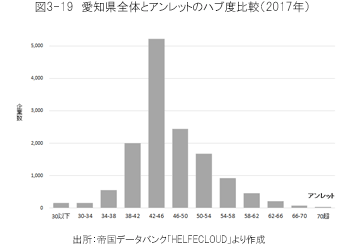
地域未来牽引企業の指標では、ハブ度、利益貢献度が高いことが特徴です。ここではハブ度に注目します(図3-18)。ハブ度は愛知県内で仕入れられる総額に対してのアンレットのシェアを示しますので、より多くの仕入れを県内で行っているということになります。アンレットの場合、70超と非常に高いスコアとなっていることから、実に様々な企業との取引を行っていることが推察されます。同社の横井啓人社長によれば、規模や取引関係、人材活用などあらゆる面で「身の丈にあった経営」を目指している点が、このスコアの高さにつながっているようです。その身の丈経営とはどのようなものかをみてみましょう。
先に利益貢献度の高さの要因を探ってみます。
同社の売上高は2017年で76億円です。ここ数年は安定した業績を維持しています。日本真空工業会の統計では真空ポンプやその部品の国内売上総計は1050億円です。その規模からすると76億円という売り上げは決して大きくはありませんが、実は業界大手の荏原製作所(4.7%※2017年12月期の同社決算より)やアルバック(12.7%※2017年6月期の同社決算より)を上回る、高い利益率をあげているのです。
その源泉が、本社工場の中に所狭しと置かれた工作機械の数々です。横井社長によれば、毎年の年間設備投資額は2億円です。常に最新の工作機械を導入し続け、生産力の強化を図っているそうです。最近導入した機械は、設計データをあらかじめ入力しておけば従業員がいなくても24時間稼働し続けるという、完全自動のマシニングセンターです。横井社長は、この設備投資の狙いは事業規模の拡大よりもまずは「徹底した納期の短縮化」と説明します。

次にハブ度の高さの背景を探ってみます。
同社が実践する「身の丈」にあった経営スタイルは、仕入先との付き合いにも表れています。仕入れる鋼材は同じ愛知県内の藤栄鋼業をはじめとする地元の卸売業者からです。ゴムやベアリングなどの部品やポンプに取り付けるモーターなど、部品の多くもまた地元の企業から納入しています。こうした企業の中には、すでに50年近くの付き合いがある企業もあり「よほどのことがない限り、付き合いがなくなるということのない関係」です。横井社長自身が得意先にこまめに通い、 供給体制に不安や問題を少しでも抱えていたら「前もって言ってもらえれば様々な形で支援を惜しまない」という家族的な関係作りを行っています。
一方で2億円の設備投資の仕入先となる工作機メーカーも、先に説明したマシニングセンターこそ埼玉の三井精機などから仕入れていますが、同社が特注する専用機はやはり地元の企業です。「素材にしても、専用の加工機にしても、自分たちなりの製造ノウハウや品質基準がある。そこを協力企業に理解してもらうには、こまめに行き来してコミュニケーションを重ね、難しい注文にも『一緒にやってみようか』という気持ちで仕事をしてくれる企業でないと難しい。結果的に、付き合いが長く、距離も近い企業との関係が深くなる」のです。
この考えは、人材の採用にも反映されています。「遠くに住む優秀な人より、近くの普通の人を優先して採用する」と言います。職場が住み慣れた環境に近いかは、その従業員に長く勤めてもらうためにも重要なのだそうです。
こういった取引構造や雇用に支えられたアンレットのビジネスとはどういったものなのでしょうか。同社の製造工程からみてみます。
まず工作機で鉄鋼を削り出して、ポンプ本体や羽根などの各部品を製造します。その後に研磨・表面加工を行って塗装します。そして組み立てから最終的な性能試験までという流れで、この生産プロセスを一貫して行い、顧客に出荷できる体制を整えています。製品の内製化率はおよそ9割、ベアリングやシール用のゴム、ギアなどの「一部標準的な部品を除いて、ほとんど全てを社内で製造している」と横井社長は話します。

内製化のメリットは、顧客の要望にきめ細かく応えられる製品作りができることです。ブロアでもポンプでも「通常の商品よりも、ほんのわずかだけ出力を抑えた商品が欲しいというように、細かな要望が顧客からは多い」(横井社長)そうです。カスタマイズを求めるこうした顧客の声に丁寧に耳を傾けつつ、しかもそれに「他社ができないほどの短納期」で応えられます。横井社長にいわせると「かゆいところに手が届く」という製造・販売体制を積極的な設備投資で実現し、他社との差別化を図っているのです。毎年2億円はそのための投資でした。
「製品開発の面でも、製造技術面でも基本的に難しいことをしない。自分たちの身の丈に合った『できること』を突き詰めて、そこには積極的に投資をしていく」のが横井社長の経営スタイルです。今いる顧客の要望に応えるために製造現場の自動化と24時間稼働化を行い、まずは製品あたりのリードタイムを短縮することを最優先に考えるのです。その結果として生産力が自然に上がれば、売上は自然についてきます。無理な業容の拡大を行うつもりはないそうです。
取り巻く外部環境をみてみましょう。
真空ポンプとは、簡単にいうと圧力の低い気体を吸いこんで圧縮して出すということを繰り返す機械です。実に様々な用途があり、その分、参入企業が多いことも特徴です。大手のアルバックや三浦工業、島津製作所などをはじめ、用途別に数多くの企業が存在しています。その中で、アンレットは独自の技術ノウハウをもって新しい製品を次々と世に送り出しています。その秘訣は、長期間取引をし、関係の深いサプライヤーとカスタマイズに強い一貫生産体制に支えられていることにあります。
そして、重点を置いている新規需要の開拓によって新しい用途に対応した製品を出し続けているのです。
同社のチャネルである商社の営業のみに頼ることなく、新規ユーザー獲得のため、自社の営業担当者が様々な企業に飛び込み営業をしながら、新たなニーズを獲得してきています。その戦略が功を奏して、現在は自動車や食品、薬品、化粧品業界など300社の顧客を抱えるまでになっています。今はなくなってしまいましたが、サーフィンができることで話題になった宮崎シーガイアの造波プールに使われたポンプは、同社が特注を受けて製造したものです。
あらゆる業界にニーズがあると考えて、積極的な営業活動を展開しています。
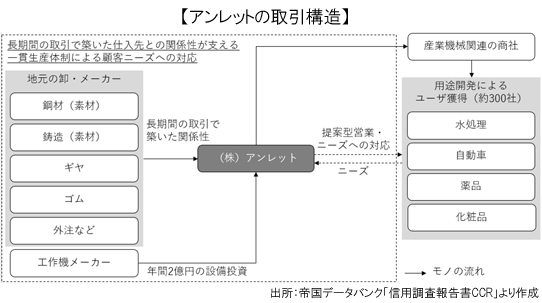
ひとつの業界に偏らず、常に新たな業界に対してポンプの需要開拓を行い、顧客の声を聞いて特注品を提供しているのです。特注品は取引先ごとに全て形状や色が異なり、ひとつとして同じものはないそうです。「時には営業担当者が1社に5年間も通って顧客ニーズに合う新製品を開発し、ようやく受注に至ることもある」(横井社長)。新規の業界に飛び込んでその分野の先駆者となることで得られるメリットは、価格決定権を自分たちで握れる点にあります。これにより、高い利益率を同社は維持してきたのです。また、多様な業界に顧客を持つことは、特定の業界の浮沈に影響を受けることなく、安定した経営基盤を築けるという利点もあります。

同社が新規顧客の開拓をするにあたって欠かせないのが、提案型営業を実施できる営業担当者と、その営業と一緒に新しい商品開発を行う技術者です。開発に携わる技術者は全社員240人中25人、1年に1人は必ず採用しています。 営業担当者は50人ほどで、理系出身者を中心に採用しています。新人の営業担当者は、半年ほど製造現場を経験した後に、何年か経験のある営業担当者とチームを組んで営業活動を行います。
重視するのは、開発部門との連携です。営業担当者は飛び込み営業もしながら顧客のニーズをつかみ、需要を感じたら開発部門の技術者も客先に積極的に赴き、顧客のニーズにあった商品開発を行う体制をとるのです。こうした開発にかける費用については「経営からはいくらかかっても気にしない、失敗しても決して怒らない」ことを社長自身が明言し、技術者や営業担当者の挑戦意識を高めています。
地域クラスター活用型
地域クラスター構築型
全国ネットワーク開拓型

