株式会社帝国データバンクは、保有する信用調査報告書ファイル「CCR」(200万社収録)など自社データベースから分析可能な企業を対象に、中華人民共和国(中国)国内の企業(現地法人など)と取引を直接・間接的に行う企業について調査・分析を行った。
SUMMARY
2025年10月時点における対中輸出企業は9250社判明し、2023年の調査時点に比べて微減にとどまった。このうち水産関連企業は172社となり、2023年(164社)から増加した。ただ、対中販売シェアは縮小しており、チャイナリスク認識の高まりから、米国・東南アジアなどへの販売先多角化といった動きが進んだことも考えられる。
[注1] 中国本土のほか「澳門(マカオ)」「香港(ホンコン)」両特別行政区も対象
[注2] 類似の調査は、国内の全輸出企業を調査した2023年以来3回目
中国の水産物輸入停止、水産関連172社に影響の可能性
在中国の企業に製品やサービスなどを販売(提供)する、対中国への輸出を直接・間接的に行う日本企業を調査した結果、2025年10月現在で国内に9250社あることが分かった。2023年調査時点で判明した9270社から新たに870社参入、890社が撤退し、差し引き計20社・0.2%の純減となった。

中国への輸出企業を関連産業別にみると、最も多いのは自動車や家電など電化製品、製造機械など「機械・設備」(3498社)で、全体の約4割を占めた。2023年時点に比べて5社減少と、ほぼ横ばいでの推移となった。中国の最終組み立て工場へ向けた部品供給のほか、電子部品や半導体関連素材、工作機械などの完成品輸出・販売などが多かった。次いで、漁業や農業など一次産業から、食品加工・販売までを含めた「食品分野」が733社・7.9%で続き、同6社増加した。取り扱い品目は、和牛や日本酒、菓子、健康食品など多岐にわたるほか、食品分野のうち水産加工や販売など水産品の取り扱いが本業に当たる企業が172社・1.9%を占め、2023年時点から8社増加した。ナマコ加工品やホタテ、スケソウダラと冷凍・鮮魚製品が多くを占めた。2023年8月から始まった東京電力福島第一原子力発電所の処理水海洋放出に伴う日本産水産物の全面禁輸措置により、ホタテなどの対中輸出で大打撃を受けたものの、取引社数は増加傾向で推移した。

また、自社の販売額のうち中国向け販売(輸出)が占める割合は、全産業平均(対象:約2000社)で1社あたり平均43.8%に上った。2023年時点(42.8%)に比べて1.0pt上昇し、取引シェアにおける対中輸出の比重が高まった。なかでも、資源リサイクルなど「金属」(31.7%、+6.8pt)をはじめ、「機械・設備」(36.4%、+1.8pt)や、アパレルなど「繊維産業」(39.0%、+3.5pt)は1社あたりシェアが増加した。他方、「建設関連」(18.8%、△15.2pt)や「医療」(54.4%、△3.4pt)、現地メーカーの台頭などで価格競争が激しい化粧品などの「美容」(55.4%、△1.7pt)では減少した。なかでも、中国の対日輸入規制で影響が出る可能性のある「食品」は、2023年:55.9%→2025年:53.9%と減少したほか、食品のうち「水産関連」でも同48.4%→47.8%と減少した。近年の日本食ブームを背景に中国向けの需要が高かったものの、中国政府による禁輸措置など不安定な環境が続いたことで、生産・作業工程や販売先を中国から米国や東南アジアなど第三国に求める動きや、日本国内へ回帰するといった動きが進んだことも寄与した可能性がある。
露呈する「チャイナリスク」 販売先の多角化など対応進む
台湾有事を巡る高市政権の国会答弁をめぐり、中国政府が日本産の水産品について事実上の全面輸入停止したことが判明した。東京電力福島第一原発の処理水放出をめぐる対立から2度目の禁輸措置となり、特に水産物においては取引正常化のメドが立たない状況が続く。
ただ、ここ2年間で企業における取り組みも大きく変化している。足元では、日中両政府間で輸出再開に向けた手続きや技術的要件について合意に至り、2025年11月上旬には北海道産の冷凍ホタテなどが中国向けに出荷再開となった。中国国内で人気の高いナマコなどのほか、日本食ブームを背景に日本産食品の需要は旺盛で、「最大の得意(販売)先」としての中国市場の存在感は依然大きい。他方、輸出企業側でも政治面を中心に経営環境が大きく一変する中国特有のリスク=チャイナリスクの認識が改めて広まり、中国以外の取引市場を開拓するなど「中国依存」を減らすリスク分散の取り組みも進んできた。そのため、今回の再禁輸措置についても比較的冷静な対応を行う企業が多いとみられ、2023年当時のような「ショック」までは至らない可能性もある。ただ、今後の成り行き次第では対中輸入の規制範囲が広がるといった事態も想定され、短期的には対中輸出の割合が高い企業を中心に一定の影響が出ることは不可避とみられる。
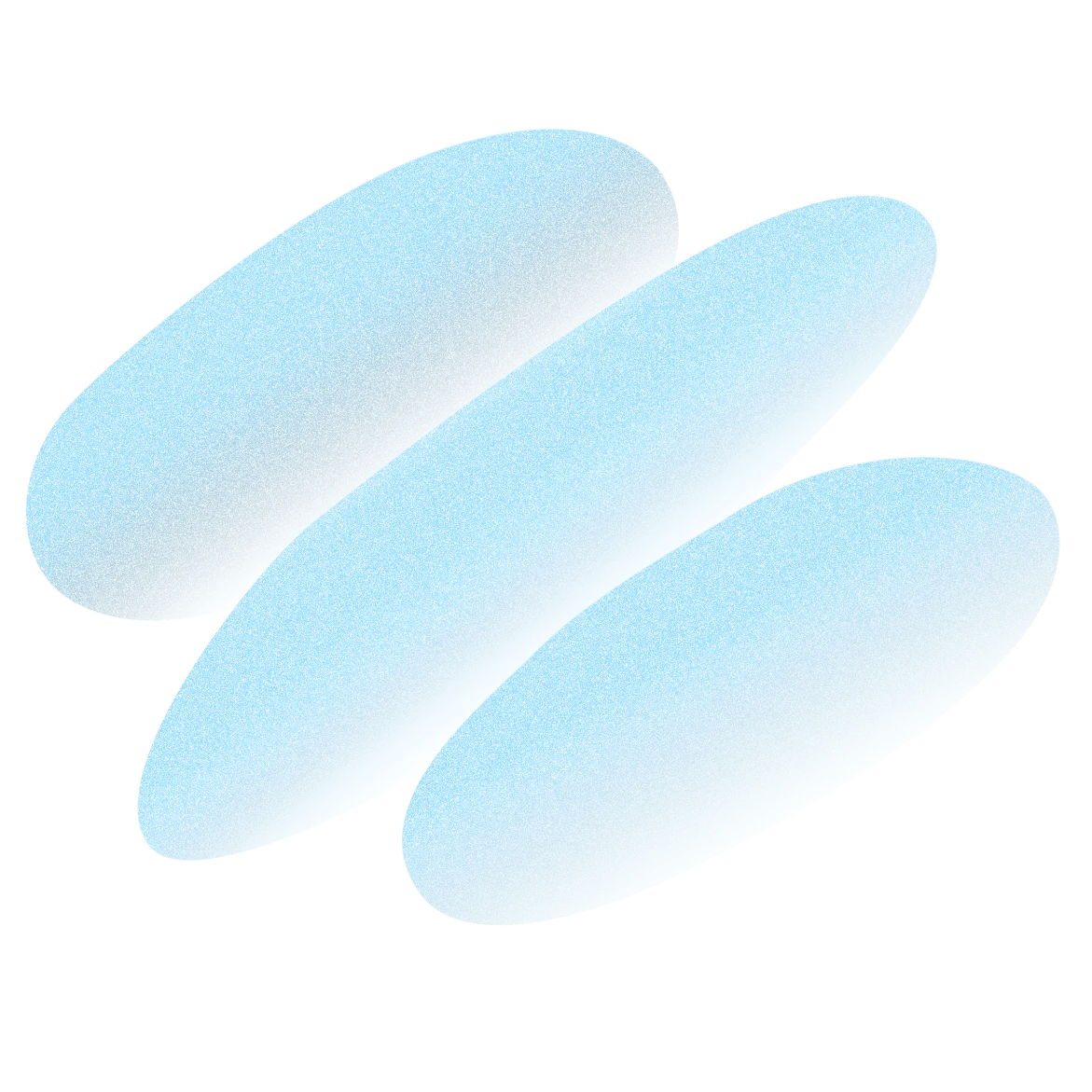
Contact Usお問い合わせ先
担当部署
株式会社帝国データバンク 情報統括部 TEL:03-5919-9343 Email:tdb_jyoho@mail.tdb.co.jp

