ここがポイント
- ポイント1
市町村毎の人口と企業数には人口33人に対して1企業という関係性があり、帝国データバンクの企業ビッグデータを読み解くことで、日本における人や産業の移動の理解につながる可能性がある。
- ポイント2
明治維新・戦後・バブル・不況期に創業した企業のうち現存する企業について調べたところ、明治維新期に企業数が最も多かった都道府県は新潟県であった。この背景には江戸時代から明治期に隆盛をふるった「北前船」の存在があり、帝国データバンクの事業所の地域分布にもその関連が見られた。
- ポイント3
老舗企業とそれ以外の企業において主要都市毎に従業員1人あたり売上高の分布を比較したところ、全体的に老舗企業の方が中央値は高い傾向があったが、京都市においては大きな違いはなかった。「古さの価値」があまねく知れわたっている京都であるからこその高水準争いが起こっている可能性がある。
1. はじめに:明治以来150年の経済推移を企業データから読み解く
「団塊の世代」や「バブル世代」などというように、同じ時期に生まれた人々をひとつの世代とみなして共通の特徴を見出そうとするアプローチは、マーケティングの領域に限らず一般的によくみられます。時代を反映するような出来事も、それを子供、学生、社会人、親世代としてなど、どのライフステージで経験するかによって印象が異なるように、同世代にはある種の同質性を帯びやすいといえます。同様のことは、企業についてもいえるのではないでしょうか。このような背景から、本レポートにおいては、企業が誕生した時期に着目し、帝国データバンクがもつ企業ビッグデータ分析を通じて、明治以来150年の経済推移を読み解きます。
2. 産業の中心地は時代と共に移動する
人口の将来推計は出生率と死亡率をどのように仮定するかによって異なります。国立社会保障・人口問題研究所は、両者に対し「高位・中位・低位」を定め、全9通りでの将来人口推計を本年4月に公表しました1。その結果によると、両者が中位である場合の2040年の日本の総人口は1億1092万人となり、2015年から12.7%減少する見込みとなります。一方で、日本の長期統計系列2によると図表1の通り、約150年前の総人口は約3500万人と、現在の3分の1以下でした。日本の総人口が1億を超えるようになったのは、わずかここ半世紀のことだったのです。
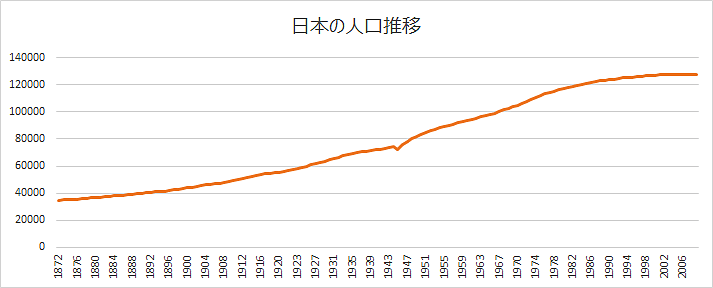
図表1 日本の人口推移。(出典:総務省統計局. “日本の長期統計系列: 第2章 人口・世帯”. 統計局ホームページ.http://www.stat.go.jp/data/chouki/02.html, (参照 2018-10-29)を元に帝国データバンクが作成。)
国内マーケット規模や税収の観点からは日本全体における人口変動のダイナミクスは重要ですが、都市計画や地方自治体における政策立案、そして、昨今増加している自然災害対策の優先順位付けの観点などにおいては、「より人口減少が加速している地域」の特定など、国内における人口移動の動向理解も重要になってきます。図表2は、市町村別の人口と企業数の散布図です。こちらは、RESAS(地域経済分析システム)3という、産業構造や人口動態、人の流れなどの官民ビッグデータを集約してわかりやすく「見える化」できるWEBシステムからダウンロードしたデータを加工し、作成しました。人口が多い市町村ほど企業数は多いという結果となり、全国的にはおおよそ人口33人に対して1企業という関係性であることがわかりました。
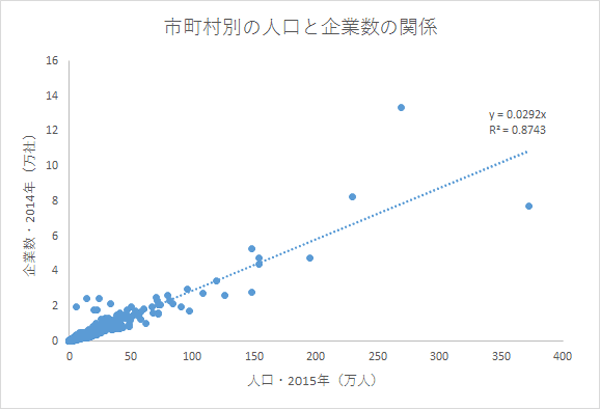
図表2 市町村別の人口と企業数の関係。人口(万人)をx、企業数(万社)をyとしたとき、両者はおおよそy=0.0292xという関係性がある。モデルの当てはまりを表し0から1の値をとる決定係数はR^2= 0.8734であり、1に近いほど当てはまりは良いことを表し、上記は当てはまりが良いと言える。(出典:RESASからダウンロードしたデータを使用して帝国データバンクが作成。人口は国勢調査、企業数は経済センサスを元に搭載されたもの。それぞれ調査間隔が異なるため、最新で調査年が近い2014年と2015年のデータを用いた。)
企業が多いから人口が増えるのか、人口が多いから企業が増えるのかについては、このデータからは明言はできませんが、いずれにしても、両者には強い相関があることは言えます。この結果をもとに、帝国データバンクがもつ企業ビックデータ分析を通じて、日本における人や産業の移動の理解に挑むことにしました。
現在の日本の企業活動の中心地は首都である東京ですが、昔からそうだったのでしょうか。時期による企業活動の地理的推移をみるために、近現代史における特徴的な4時期に着目し、その時期に創業した企業の地域分布を調べました。具体的には、明治維新期(1868~1873年)、戦後期(1945~1950年)、バブル期(1987~1990年)、不況期(2009~2013年)の4時期に創業した企業のうち現存する企業を調べ、時期ごとの全企業数のうち、ある都道府県が占める割合を調べたものを図表3に示しました。
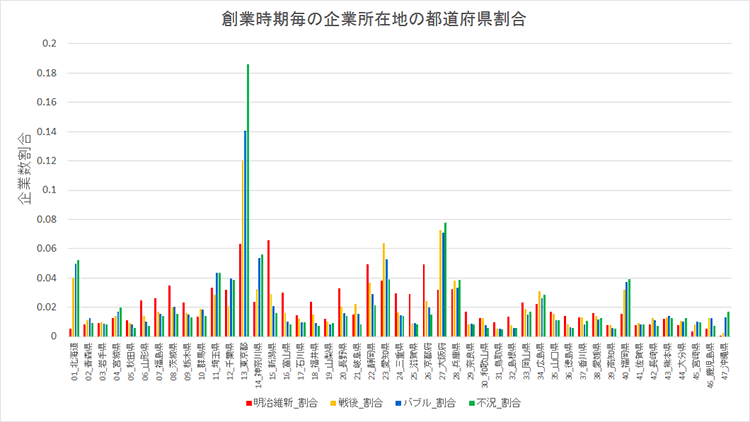
図表3 創業時期毎の企業所在地の都道府県割合。各時期に創業した全企業数を1とした場合の、その都道府県に存在する企業数割合。2018年1月時点に存在し、創業年もしくは設立年が判明する企業のみ使用。創業年が不明の企業は設立年を創業年とした。(出典:帝国データバンク企業概要データベース「COSMOS2」より作成)
こちらのグラフを日本地図上にプロットし、帝国データバンクが作成した動画をご紹介します。
動画からもお分かりいただけるように、例えば東京都に着目すると、明治維新期→戦後期→バブル期→不況期と現代に近づくに連れて、6%→12%→14%→18.5%と占める割合が単調増加していることがわかります。同様に、割合が増加し続けてかつ高い割合を占める例として、北海道、神奈川、福岡などがあり、現在の人口の多い都道府県が挙がります。反面、明治維新期においては東京都を超え1位である新潟県は、6.6%→3%→2%→1.6%と単調減少であり、同様の例として、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県などがあり、日本海に面する都道府県が多く含まれていることが特徴的です。各時期において企業が多く集まっている地域を特定するために、企業数上位10位の都道府県について、図表4に示しました。
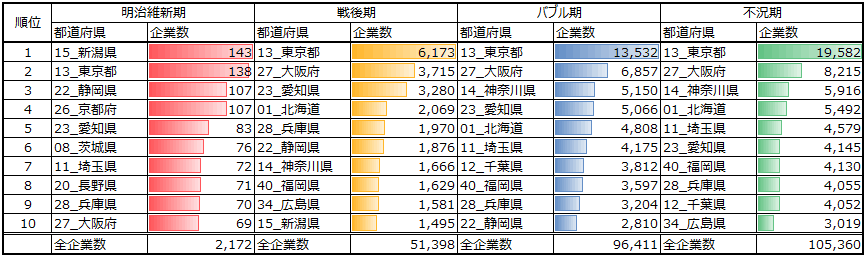
図表4 各時期における企業数上位10都道府県。図3は割合だが、こちらは実数値を用いている。(出典:帝国データバンク企業概要データベース「COSMOS2」より作成)
戦後期・バブル期・不況期の上位の多くが、太平洋ベルト(茨城から大分までの一連に連なる工業地帯)周辺の都道府県であり、この傾向は近年根強いものであることがわかります。また、明治以前は、職業や居住地を自由に選択することは大きな困難が伴っていましたが、経済の発展に伴う移動コストの低減や大量生産化による集団就職などが後押しとなり、移動の自由が一般的なものとなってきました。その結果、経済のチャンスの大きいところに人が動き、更にそこにチャンスが生まれるという正のフィードバックが働き、その傾向は近年さらに高まっているといえます。
一方で、明治維新期について注目するべき点として、先述の通り新潟県が1位であるということです。更に、1位と2位との企業数の差が、戦後期は約1.66倍、バブル期は1.97倍、不況期は2.38倍と近年高まっているのに対して、明治維新期においては、1位と2位がほとんど変わらず、1位と10位の差も2倍程度という結果です。地域格差や東京への一極集中が加速している現在と比較すると、150年前の日本は現在とは随分様子が異なっていたようです。人や企業の移動の背景にはどのような歴史があるのでしょうか。
3. TDBの事業所分布から浮き上がる海運から陸運への移行
企業が多く存在する地域には、信用調査のニーズも同様に高まると考えられるため、企業数の地域分布は帝国データバンクの事業所分布との関連が考えられます。1900年に創業した帝国興信所(帝国データバンクの前身)の全国への事業所展開の過程について、帝国データバンク史料館(東京都新宿区)4では動画でご覧いただくことができます。図表5は、戦前と戦後に開設された帝国データバンクの事業所の所在地を色別に日本地図にプロットしたものです。
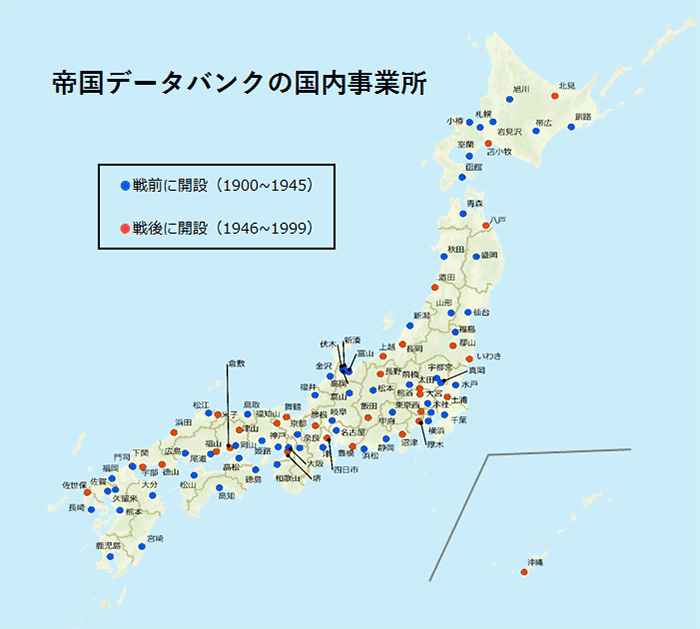
図表5 帝国データバンクの国内事業所所在地。後に閉鎖された事業所も含まれる。(出典:株式会社帝国データバンク「情報の世紀: 帝国データバンク創業百年史」5を元に作成)
ここで、青色は戦前、赤色は戦後に開設されたものであり、TDBの事業所は全国に分布していることがわかります。中でも特徴的なエリアとして、図表6に着目してみましょう。
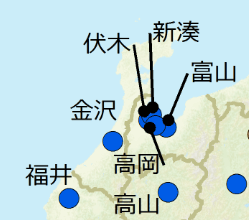
図表6 北陸エリアにおける帝国データバンクの事業所。図表5の一部を拡大したもの。
富山県・石川県・福井県エリアにおいて存在する事業所はすべて戦前に設立されており、かつ、富山県には富山支所、伏木出張所、新湊出張所、高岡支所と4か所も事業所が存在していました。しかし、伏木出張所は1919年、高岡支所・新湊出張所は共に1933年に閉鎖されており、現在富山県内の事業所は富山支店のみです。4つの事業所は1910~1922年の間に開設されておりますが、当時このエリア特有の産業が存在したのでしょうか。
この背景の1つとして考えられるのが、江戸時代から明治時代にかけて活躍した、「北前船」の存在です。北前船の定義は様々ありますが、北前船日本遺産推進協議会によるホームページ6によると、①大阪と北海道(江戸時代の地名では大坂と蝦夷地)を日本海回りで往復していた、②寄港地で積荷を売り、新たな仕入れもした、③帆船というのが共通的な特徴と言えるようです。幕末である1857年(安政4年)時点において、江戸、銚子、水戸、仙台、南部の太平洋側を通る東回りの航路に対して、日本海側航路、とくに北前船による輸送は北海道全体の輸送量の83%を占めていたというデータがあります7。鉄道や自動車が普及していなかった当時において、海運が物流において重要な位置を占めていたことを考えると、現在とは異なり日本海側が日本の産業の中心であったといえます。また、蝦夷地が「北海道」と改称されたのは明治2年であり、それから開拓使が管轄統治するようになりました。本州からの集団移民政策などに伴い北海道の開発は進み、明治5年は総生産高が194万円(うち水産物99%)であったのが、明治14年には904万円(うち水産物75%)と、わずか9年で約4.7倍という著い伸びをみせました8。それを裏付ける1つとして、図表7をご覧ください。開拓から100年程度という短い期間内に北海道には戦前すでに8か所も事業所が存在しており、広大な大地には経済活動が集積する地域が複数個所にわたり築かれていたことを示唆しているといえます。
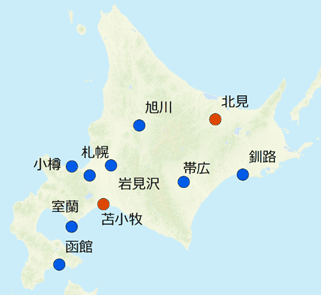
図表7 北海道における帝国データバンクの事業所。図表5の一部を拡大したもの。
このような背景から、今度は事業所の所在地の沿岸部からの距離に着目して、図表8を見てみましょう。すると、西日本において多くの事業所が沿岸部付近に存在しており、特に瀬戸内海沿岸部では顕著です。
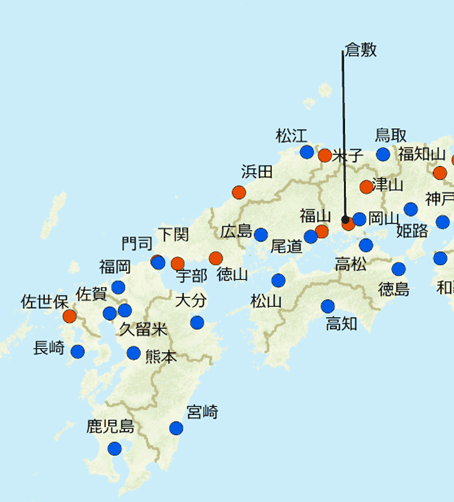
図表8 西日本における事業所の所在地。図表5の一部を拡大したもの。
明治期における瀬戸内地方の理解を助けるデータ9として、図表9があります。これによると、瀬戸内地方は北海道からの移入がずば抜けて多く、移出については裏東北信越が最も多く、次いで北陸、瀬戸内の順で多いことがわかります。
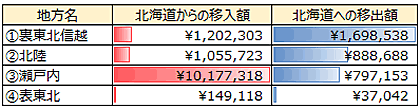
図表9 北海道と内地諸港の移出入(明治11-13年)。
(出典:牧野隆信.“第六章 北前船の盛衰”.「北前船」を元に作成。)
北前船の全国への影響ということに観点において、瀬戸内地方も日本海側(①裏東北信越、②北陸)に十分匹敵する程影響が強かったことが確認され、港周辺には人や産業が集まり易い傾向があったことが想像されます。事業所の沿岸部への集中傾向と関連があった可能性は高いでしょう。
このように、江戸期から明治期にかけて物流の中心であった海運でしたが、1872年には新橋―横浜間で鉄道が開通、そしてちょうど100年後の1972年には田中角栄前総理による「日本列島改造論」が打ち出され、高速道路拡充・新幹線開通などにより、陸運が重要な位置を占めるようになりました。このように、人や企業の移動の背景には、海運から陸運という物流の変遷が隠されていたのです。
4. 老舗は強いのか?10
2017年時点における企業の平均寿命は36.2歳11であり、1989年の18.4歳の約2倍となり、長寿化傾向にあります。一方で、毎年様々な理由で倒産・休廃業を余儀なくされる企業も存在し、内的・外的環境の変化に対応できない企業は淘汰の危機にさらされます。そのような状況下で、長年企業活動を継続し、「老舗企業」といわれるようになった企業には何らかの特徴があるのでしょうか。
まず、日本における146万8千社の2018年1月時点の企業データを用いて、主要都市における老舗企業の割合を調べた結果が図表10です。
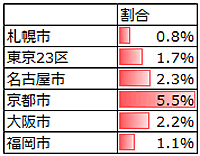
図表10 主要都市における老舗企業数割合。2018年1月時点に存在する企業を対象に集計した。(出典:帝国データバンク企業概要データベース「COSMOS2」より作成)
ここで老舗企業とは、創業から100年以上経過している企業とし12、創業年が不明の場合は設立年を用いて算出しました。すると、6都市においては京都市が5.5%と最も多く、20社に1社が老舗企業という結果となりました。かつての日本の中心地であり、神社仏閣など「古さの価値」のブランド力で観光客に人気の土地ならではの結果といえます。それでは、それらの老舗企業というのは実際に、数々の試練を乗り越えてきた「強い」企業であるのでしょうか。企業の強さを測る指標として、ここでは、企業毎に従業員1人当たりの売上高を用い、都市毎に中央値 を比較したものが図表11です。
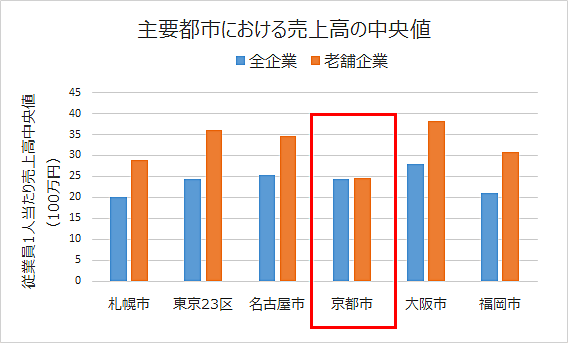
図表11 主要都市毎の老舗企業の従業員1人あたり売上高中央値の比較。2018年1月時点に存在し、直近の決算期間が1年間である企業のみを対象とし、集計した。(出典:帝国データバンク企業概要データベース「COSMOS2」より作成)
ほとんどの都市において、老舗企業の方が従業員1人あたり売上高の中央値が高いという結果になり、やはり老舗企業の方が「強い」といえます。例外的なのが京都市であり、老舗企業であっても、「強さ」は全企業と同水準という結果でした。図表10の結果と合わせて考えてみますと、京都市においては100年を超える老舗企業は珍しくなく、そのため老舗であることのブランド力が働きにくいということが考えられるかもしれません。「古さの価値」があまねく知れわたっている京都であるからこその高水準争いが起こっているとすると、京都という街の別の側面として、興味深い結果だといえるのではないでしょうか。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.国立社会保障・人口問題研究所.“日本の将来推計人口(平成29年推計)”. 国立社会保障・人口問題研究所. http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp_zenkoku2017.asp, (参照 2018-10-29).
2.総務省統計局.“日本の長期統計系列: 第2章 人口・世帯”. 統計局ホームページ. http://www.stat.go.jp/data/chouki/02.html, (参照 2018-10-29).
3.内閣官房まち・ひと・しごと創生本部. RESAS 地域経済分析システム. https://resas.go.jp/#/13/13101, (参照 2018-10-29).
4.http://www.tdb-muse.jp/index.html
5.株式会社帝国データバンク.“資料編 3事業所・関連会社”. 情報の世紀: 帝国データバンク創業百年史. 株式会社帝国データバンク 創業百周年記念プロジェクト百年史編纂室編. p.580-581.
6.北前船日本遺産推進協議会.“北前船とは”. 北前船 KITAMAE 公式サイト【日本遺産・観光案内】. https://www.kitamae-bune.com/about/main/, (参照 2018-10-29).
7.牧野隆信.“第六章 北前船の盛衰”. 北前船. 柏書房(株), 1972, p.133-136.
8.牧野隆信.“第六章 北前船の盛衰”. 北前船. 柏書房(株), 1972, p.137-138.
9.牧野隆信.“第六章 北前船の盛衰”. 北前船. 柏書房(株), 1972, p.139を元に作成。.
10.日経BP社. 特集, 日本企業の新事実: 会社×巷の「常識」,老舗は強いのか?. 日経ビジネス. 2018, (1960), p.41. https://www.nikkeibpm.co.jp/item/nb/661/bn/NB1960.html, (参照 2018-10-29).
11.日経BP社. 特集, 日本企業の新事実: 会社×巷の「常識」, 今の「企業の寿命」はどれくらい?. 日経ビジネス. 2018, (1960), p.40. https://www.nikkeibpm.co.jp/item/nb/661/bn/NB1960.html, (参照 2018-10-29).
12.老舗企業の定義を創業から30年以上とする例もあるが、本分析においては創業年数(不明の場合は設立年数)が100年以上の企業を老舗企業と定義した。
13.中央値とは、N個のデータを値の大きさで順位を付けた場合、Nが奇数の場合は(N+1)/2位の値、偶数の場合はN/2位と(N/2)+1位の値の平均を言う。売上高のように非常に大きな値を持つデータが少数でも含まれているようなべき分布に従うデータの場合、平均値を用いると非常に大きな値の影響を大きく受けるため、中央値など用いてデータの特徴量とすることが一般的である。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
株式会社帝国データバンク プロダクトデザイン部 プロダクトデザイン課
髙木英美子
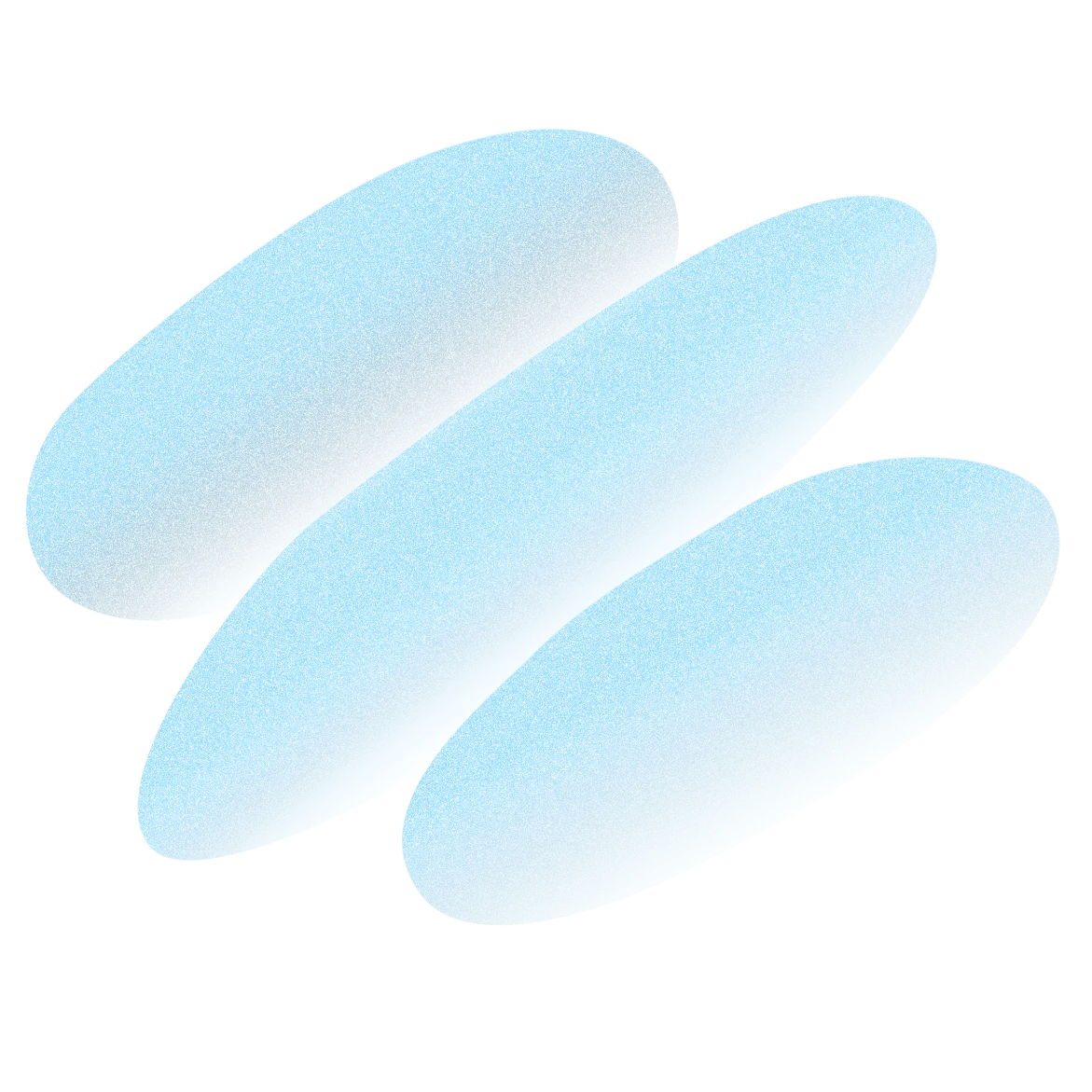
Contact Usお問い合わせ先
担当部署
プロダクトデザイン部 プロダクトデザイン課 TEL:03-5775-1092 FAX:03-5775-3168 E-mail:bigdata@mail.tdb.co.jp

