ここがポイント
- ポイント1
金融庁は2019年3月期決算から、上場企業に対し役員報酬の決め方の情報開示を義務付けた。今後は役員人材の流動性への影響も考えられる。
- ポイント2
2017年中の約5万社の企業財務データによると、売上高が高い企業ほど、1人当たり役員報酬が高い傾向があり、最も役員報酬の高い企業は外資系企業であった。
- ポイント3
2017年の約16万社の企業ビックデータによると、同じ従業員規模単位においては、役員数が多い企業の方が、売上高が高い傾向があった。
- ポイント4
上場企業2,614社の2008年と2017年時点での役員数と売上高の増減の関係を調べた。役員数について、「減らす」「変えない」「増やす」の3つの戦略のうち、「増やす」の戦略をとった企業が最売上高を伸ばした企業数割合が多く、役員数と売上高の増減の連動制は統計的にも有意であることが確認できた。
1. はじめに:役員争奪戦時代を前に
最近ニュースで話題となっている役員報酬に関する一連の騒動を受け、金融庁は上場企業に役員報酬の決め方を開示するように義務付けました1。2015年の経済産業省のレポートによると、日本の役員報酬は諸外国と比較すると低い水準である一方、報酬の仕組みが不透明であることが問題視されています2。今回の金融庁の取り組みにより、今後、報酬体系の透明性が高まれば、企業間で役員人材の奪い合いが激しくなる可能性も考えられます。すでに、生産労働人口の減少により一般労働市場においても人材の奪い合いや、人手不足による倒産も3年連続で件数が増加3している状況です。「変化の時代」において、企業を成長の方向に導く強いリーダーシップが取れる役員人材を確保するためにも、適正な役員報酬決めは経営に関わる重要な事項の1つと言えるでしょう。
本レポートにおいては、企業の売上高と役員報酬・役員数との関係を調べます。「御社の役員報酬は、他社と比較して高い?安い?」、「役員数は増やした方がよい?」などといった、経営における重要な意思決定に、帝国データバンクが保有する企業ビッグデータはどのような傾向を示すのでしょうか。
2. 御社の役員報酬は高い?低い?
まず、1人当たりの役員報酬が高い企業は売上高も高いのか?について調べてみます。帝国データバンクが保有する企業データから、44,997社を対象として4、1人当たりの役員報酬と売上高の関係を調べた結果を図表1に示します。
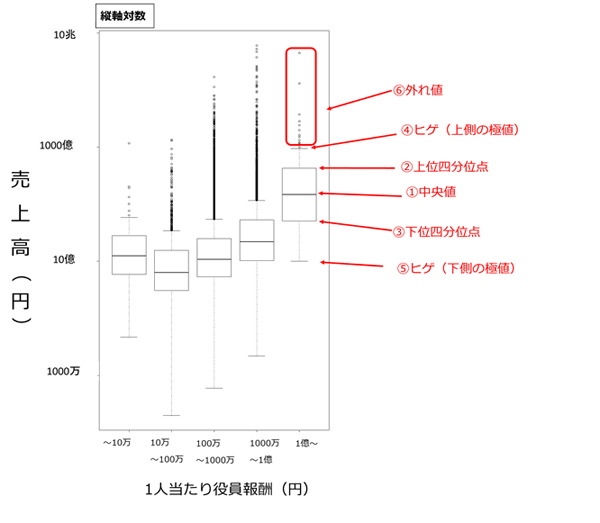
図表1 1人当たり役員報酬に対する売上高の箱ひげ図。役員報酬毎に各企業の売上高がどのように分布しているのかを示している。箱の中央の太い線は①「中央値」で、データを大きい順に並べたときの中央位の値を示す。②「上位四分位点」は上位から25%位の値、③「下位四分位点」は下位から25%位の値である。また、②から③の値の差を「四分位範囲」と言い、四分位範囲の1.5倍の値を④⑤のように「ヒゲ」となる。ヒゲより外側に存在するデータについては、⑥のように外れ値として表現される。値の散らばりが大きいデータの場合は外れ値が多く発生し、平均値では外れ値の影響を受けやすいため、箱ひげ図や中央値がデータの特性を表す量として用いられることが多い。
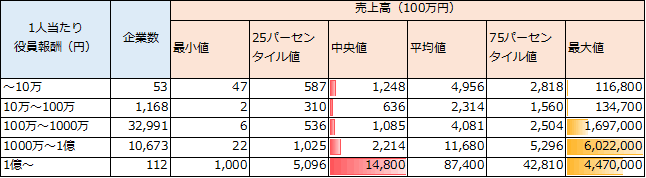
図表2 図表1の統計量表(小数点以下四捨五入)。すべての役員報酬群において中央値と平均値に乖離があり、さらにすべて平均値が中央値より上回っていることから、少数の非常に大きな値を含むべき分布に従うデータであることがわかる。
すると、1人あたり役員報酬が10万円以下の企業を除き、役員報酬が高くなるほど売上高の中央値は高くなる傾向があることがわかります。10万円以下の企業が例外的である理由として考えられることは、複数の会社役員を兼務している場合や役員数が多い企業などでは、1人当たり報酬が低水準になることなどが考えられるのではないでしょうか。また、44,997社中で売上高が最も高い6兆円の企業の一人当たり役員報酬は1000万~1億円であり、最も高いグループに含まれているわけではありませんでした。これは、業種によって利益率に違いがあるため、売上高が必ずしも役員報酬に直結するわけではないことなどが背景に考えられるでしょう。
また、「会社役員」というと高所得なイメージが一般的にありますが、1人当たり役員報酬が1000万円以上の企業は44,997社において24%であり、約4社に1社という結果でした。そして、役員報酬1000万円以上企業のうち76%が売上高10億円以上企業であり、役員へ高い報酬を払うことができる企業というのは、それだけ規模が大きく効率化が進んだ企業である、もしくは、役員の高い報酬によりそのような効率化が進んだ企業であると言えるのでしょう。
次に、売上高に着目して役員報酬を見てみましょう。図表 1の縦軸と横軸を入れ替え、売上高と役員報酬の関係を売上高規模毎にみたものが図表3、統計量表が図表4です。
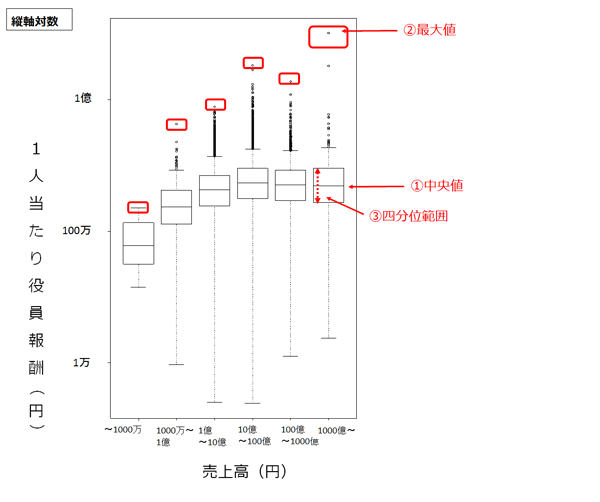
図表3 売上高に対する1人当たり役員報酬の箱ひげ図。箱の中央の太い線は①「中央値」、各売上高区分内で最も高い値は②「最大値」、箱の縦の範囲を③「四分位範囲」である。
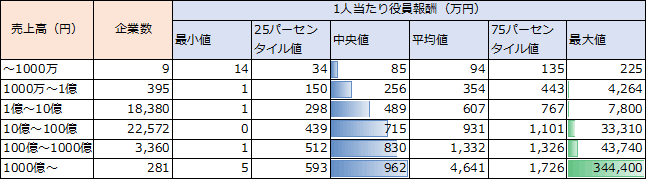
図表4 図表3の統計量表(小数点以下四捨五入)。売上高の高い企業ほど、1人当たり役員報酬の中央値・四分位範囲・最大値は大きくなっている。
すると、売上高が高い企業ほど、1人当たり役員報酬の中央値・最大値は高くなっていることがわかります。中央値の伸びと比較すると、最大値の伸び方は特に売上高1000億円以上企業においては急激であり、1人当たり役員報酬の最大値は実に約34億円という超高水準です。この企業は外資系企業であり、やはり内資系企業よりも役員報酬の水準が高いことを示す良い例と言えます
これらのデータは、「自社の報酬水準が同規模の企業内においてどれくらいのポジションであるのか?」を知る指標となります。また、異なる集計時点で比較することで、役員人材市場の動向を把握する材料にもなります。帝国データバンクの企業ビックデータから経営上の意思決定へ活用する一例と言えるでしょう。
3. 役員数が多い企業ほど売上高は高い
事業拡大や海外進出により、企業経営においてより多くのリーダーを必要とされ、役員数を増やすことも一つの選択肢となります。しかし、当然ながら役員数の増加は人件費の拡大になるため、株主に対しても納得のいくような増員であってしかるべきでしょう。そこで、売上高と役員数の関係について詳しく調べた結果が図表5です。
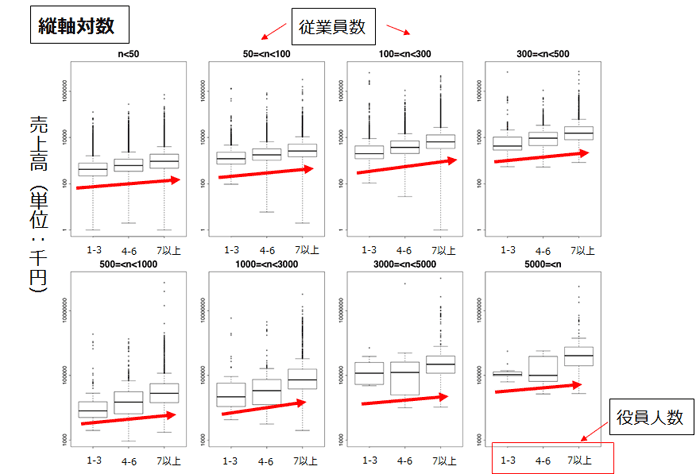
図表5 役員数による売上高の違い。企業概要ファイル(COSMOS2)のうち、2017年に登録された企業情報約16万社のデータを用いた。企業概要ファイルには、登録役員数は上限10名であるため、役員数は上記のように「1-3」、「4-6」、「7以上」の3グループの区分とした。
こちらは、従業員数により企業を8つのカテゴリーに分け、それぞれに役員数が「1~3名」「4~6名」「7名以上」の3つのグループ毎の売上高を比較しました。すると、ほとんどのカテゴリーにおいて、役員数が多い企業ほど売上高が高いという結果になりました。それに加えて、当然かもしれませんが、従業員数の多い企業ほど売上高が高いという結果になりました。やはり従業員の持つ力を活かすためにも、役員によるリーダーシップは有効であると言えるのでしょう。
4. 役員数を増やした企業の売上はどうなった?5
これまでは、ある1時点での企業の売上高と役員数の関係を調べたものでしたが、「役員数を増やした企業の売上はどうなった?」という観点から、2時点における売上高と役員数の増減の関係についても調べました。上場企業2,614社において調べた結果を図表6に示しました。
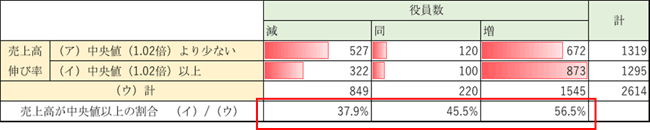
図表6 役員数と売上高の増減の関係。
こちらは、2008年と比較し、2017年での役員数について「減った」「同じ」「増えた」の3つの動向で企業を分け、売上高がどのように変化したかを調べてみたところ、「増えた」企業は1,545社あり、過半数を占めていたことがわかりました。その中でも、売上高の伸び率を調べてみたところ、「増えた」企業のうち873社である56.5%が、売上高の伸び率も中央値以上6であったことがわかりました。これは、「減った」企業においては37.9%、「同じ」企業においては45.5%であったことを考えると、役員数が「増えた」企業が一番売上高を伸ばしたと言えます。実際に、上記のデータをもちいて、「売上高の増減」と「役員数の増減」について有意な関係があるかをフィッシャーの統計検定を行った結果、p値=2.2e-16という結果となり、有意であると判定されました。
本レポートで報告した内容は、用いるデータの時点と比較する時点により傾向は変化するでしょう。しかしながら、少なくとも今回の使用した時点の結果からいえることは、会社役員数は業績に大きく関係しているということです。イギリスの人類学者、ロビン・ダンバーは、「人間が安定した社会関係を維持できる人数はせいぜい150人程度である」といい、これは脳の大きさと平均的な群の大きさとの相関関係から見出された「ダンバー数」という概念として知られています7。コミュニケーションツールは年々進化し続けていますが、会社役員のようにリーダーが取りまとめられる従業員の数には限度があり、企業規模の拡大などにより役員の増員が有効であるということが、この概念からも裏付けるものと言えるでしょう。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.日経新聞社. 役員報酬「決め方」開示義務化 : 金融庁、上場企業に . 日経新聞. 2018/12/6.
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO38601600W8A201C1MM8000/, (参照 2018-12-25).
2.経済産業省. " 日本と海外の役員報酬の実態及び制度等に関する調査報告書 ". DATA GO JP.
http://www.data.go.jp/data/dataset/meti_20150706_0307, (accessed 2018-12-25).
3.株式会社帝国データバンク. "「人手不足倒産」の動向調査(2018年上半期): 景気・経済動向記事". 株式会社帝国データバンク.
https://www.tdb.co.jp/report/economics/h-wwi-kxo/, (accessed 2018-12-25).
4.ここで1人当たり役員報酬とは、損益計算書における「販売費及び一般管理費」内に含まれる「役員報酬」と「役員賞与」の和を、全役員数で割った額としている。「販売費及び一般管理費」内項目については企業により異なるため、役員が存在する企業においても、今回の企業リストに含まれなかった場合がある。また、役員数については、「企業概要ファイル(C2)」と「信用調査報告書(CCR)」の両方にデータが存在するが、C2については登録できる役員数の上限が10名であるため、正確な役員数の算出が可能なCCRが2017年中に存在する企業のみを用いた。このような条件があり、企業数が5万社弱となったことに注意が必要である。
5.日経BP社. 特集, 日本企業の新事実: 会社×巷の「常識」, 役員の数と業績はどう関係する?. 日経ビジネス. 2018, (1960), p.40.
https://www.nikkeibpm.co.jp/item/nb/661/bn/NB1960.html, (参照 2018-12-25).
6.2008年と2017年では経済状況や物価も異なるため、2時点における単純な売上高比較ではなく2614社の売上高伸び率(=2017年の売上高 / 2008年の売上高)の中央値を基準とし、それ以上かそれ以下に分類した。小数点2桁以下を切り捨てたため、中央値以上と中央値以下の企業数が同数ではない。
7. R.I.M.Dunbar. Neocortex size as a constraint on group size in primates. Journal of Human Evolution. 1992, 22(6), p.469-493.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
株式会社帝国データバンク プロダクトデザイン部 プロダクトデザイン課
髙木英美子
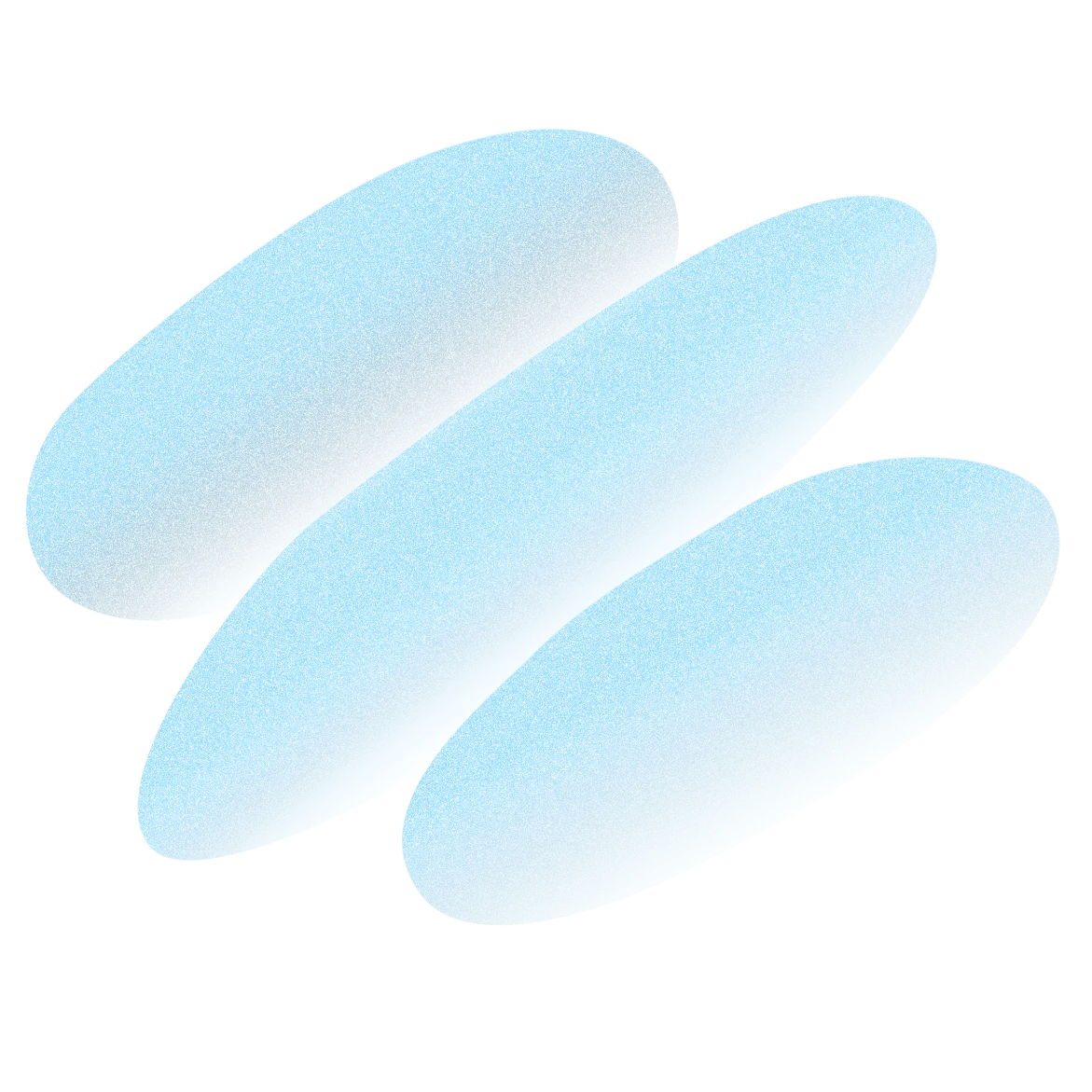
Contact Usお問い合わせ先
担当部署
プロダクトデザイン部 プロダクトデザイン課 TEL:03-5775-1092 FAX:03-5775-3168 E-mail:bigdata@mail.tdb.co.jp

