はじめに
今年5月1日に元号が「令和」へと改元され、約30年間続いた「平成」時代の歴史は幕を下ろした。「平成」時代を振り返ると、高い経済成長率を誇った「昭和」時代から一変、バブル経済の崩壊とその後遺症の苦しみから始まり、経済の低迷と再生に喘いだ時代だったと言えよう。不良債権を抱えた金融機関の破綻から始まった「平成」不況は、今日まで続く景気の冷え込みや賃金抑制、雇用体系の変化を招いた。また、相次ぐ大災害、未曾有の金融危機だったリーマン・ショックも重なった。この間、記録的な円高や海外新興国の台頭で製造業など第二次産業は「空洞化」が進み、日本経済は「失われた20年」とも「30年」とも表現される長い低成長時代を経験した。
一方、「平成」終盤にはアベノミクスの推進によってようやく経済の低迷状態から脱しつつある。また、IT化の進行のほかインバウンドの拡大による第三次産業も新たに台頭。国内産業は、平成30年間のなかで大きく変容した。
そこで、帝国データバンク高松支店は、保有する企業概要データベース「COSMOS2」(約147万社収録)を用いて、1989年(平成元年)~2018年(平成30年)の過去30年間について、四国地区に本社が所在する企業の売上高をベースに産業構造の変化を調査・分析した。
■調査対象の業種は、帝国データバンクの業種分類に準じた(「電気・ガス・水道・熱供給業」「金融・保険業」「公務」を除く)
■構成比の比較対象は、各年末に判明した各企業の「売上高」をベースとした
調査結果
- 1989年~2018年の平成30年間における四国地区の産業変遷をみると、全9業種のうち、構成比が拡大したのは「小売業」「運輸・通信業」「サービス業」「不動産業」「農林水産業」の5業種。縮小したのは「建設業」「製造業」「卸売業」「鉱業」の4業種。
- 最も大きく拡大したのは、「医療業」(平成元年0.5%→平成30年4.4%、3.9ポイント増)。
- 地域産業に占める売上高の割合が最も拡大した業種は、徳島県の「化学工業、石油・石炭製品製造」(平成元年4.1%→平成30年14.5%、10.4ポイント増)。
詳細はPDFをご確認ください
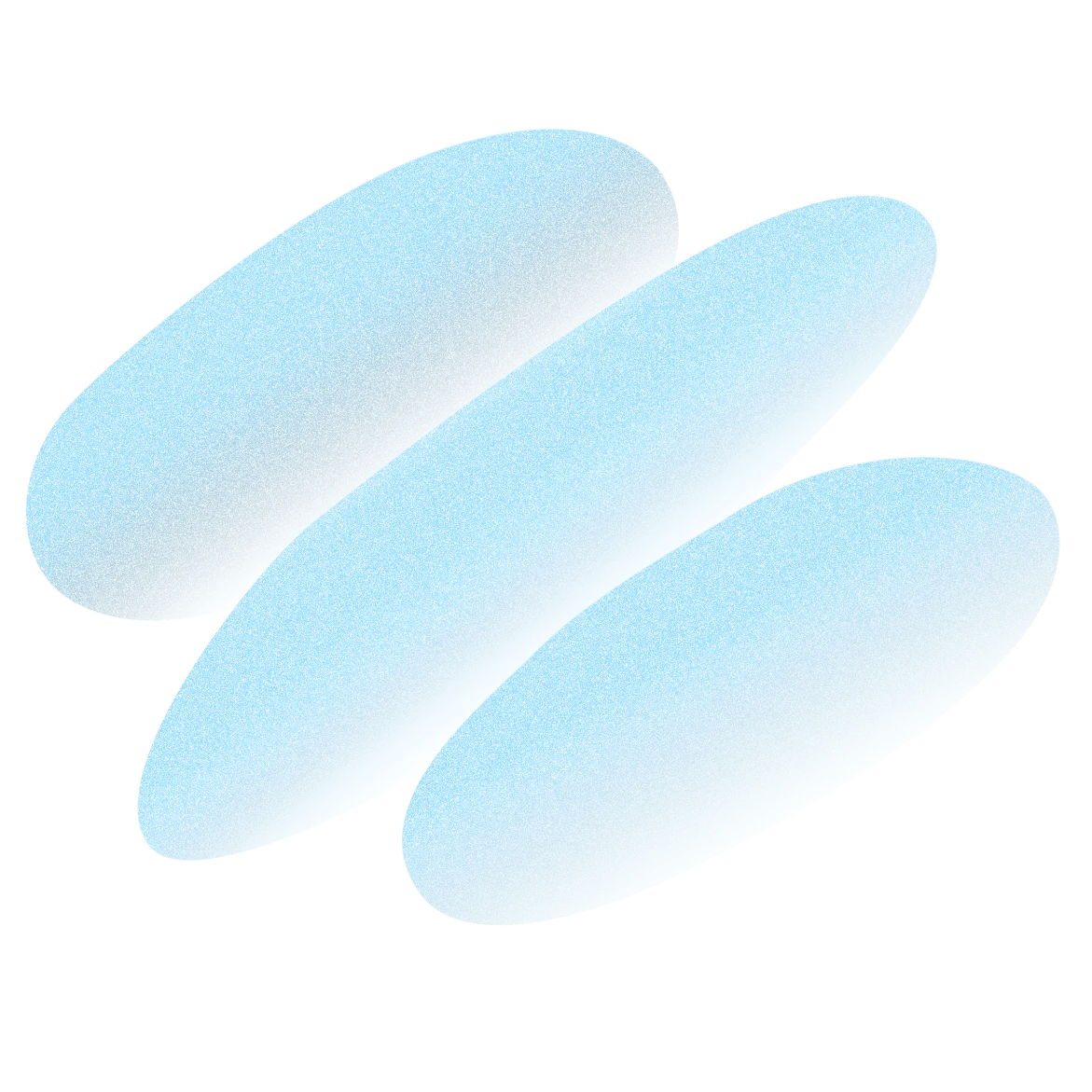
Contact Usお問い合わせ先
担当部署
お問い合わせ先 株式会社帝国データバンク 高松支店 TEL:087-851-1571 FAX:087-851-3837

