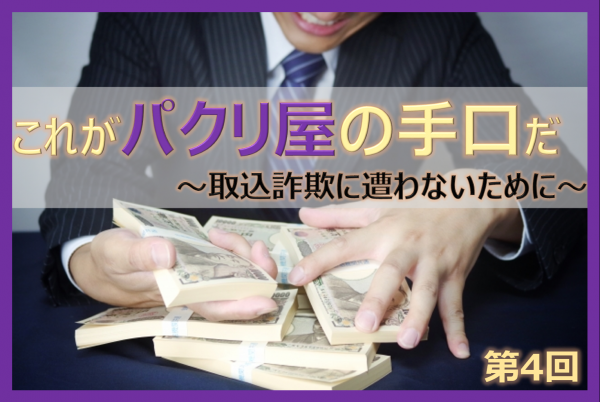
パクリ屋対策 ~被害に遭わないために~
パクリ屋の被害に遭わないためには基本的な確認を忘れないことが大切です。以下に最低限のチェックポイントを記載します。
商業登記のチェック
1.商号・本店・目的・代表者・役員が頻繁に変更されていないか
2.目的欄の事業内容が不自然に多く設定されていないか
3.目的欄の事業内容が急激に変化していないか
4.大手企業と類似した商号ではないか
インターネットや同業他社からの情報をチェック
5.過去にトラブル発生など、事件・事故の記事はないか
6.代表者・役員が別の企業を兼務していないか
7.取引先や同業者から収集した情報に不審な点はないか
信用調査報告書の取得
8.信用調査会社からの情報取得
9.調査報告書に添付されている決算書の確認
10.信用調査会社における取材時の状況確認
先方との接触
11.実際に先方事務所を訪問して確認した事務所内や従業員の様子におかしな様子はないか
12.先方より直接入手した決算書を複数期分比較して、連続性があるか(違和感がないか)
もしパクリ屋被害に遭ったら ~弁護士の見解~
万一パクリ屋被害に遭ったら、民事・刑事双方の責任追及を求めることができます。
田辺総合法律事務所の橋本裕幸弁護士にお聞きしました。
民事的な責任追及とは
裁判をして売掛金の回収を図っていくことになります。事案としてはシンプルで勝訴判決を得ることは難しくありません。ただ、裁判で勝ってもそれがゴールではなく、あくまでスタートラインととらえてください。
自発的に支払いを行ってくれることは期待できないため、強制執行により回収する必要があります。既にパクリ屋が第三者にお金を流出させてしまっているケースが大半で、勝訴判決を持っていたとしてもただの紙切れに過ぎない結果になってしまう可能性が高いことに注意が必要です。
刑事的な責任追及とは
詐欺としての刑事処罰を求める手続きになります。ただし、一般論として詐欺というのは非常に立証が難しいです。取込詐欺の場合、当初は通常の取引のように装ってお金の支払いも実際に約定どおりに行っているケースが多いため、経営破綻を原因とする未払いとの区別がつきにくい状況になります。そのため、「当初から代金を支払うつもりがなかった」と客観的な証拠で立証できるかがポイントとなります。警察は、必ずしも詐欺罪の立件に対して積極的に取り組んでくれるとは限りません。事実上は、被害者側で証拠収集活動の大半を行わざるを得ないケースがほとんどです。
最終的に起訴・有罪にまで持ち込めるのは、被害全体のうち確実に立証が可能な一部のみです。また、「刑事処罰は民事的な救済とは必ずしもリンクしていない」という点には十分注意が必要です。処罰が実現してもお金が返ってくるわけではありません。
以上、4回にわたってパクリ屋の特徴と事例、対策としてのチェックポイントをご紹介しました。パクリ屋被害に巻き込まれないためには、取引開始前の「事前確認」が重要となります。少しでも不審な点があったら、弊社最寄りの事業所へご相談ください。
◆関連コラム
取り込み詐欺に関してはこちらでも説明しています。
■パクリ屋の手口 ~商業登記に表れる異常~
■連休と取り込み詐欺 ~彼らの収穫期~
≪ 【第3回】

