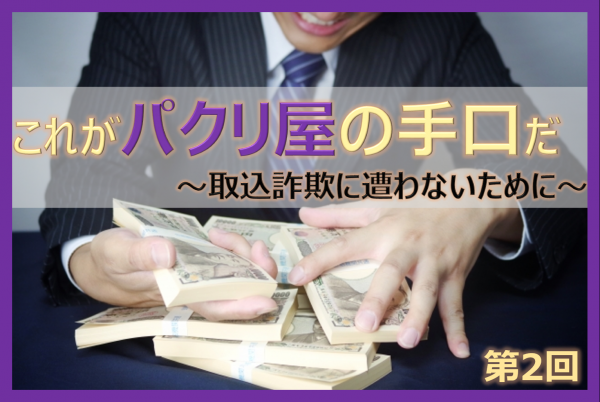
実際の事件をモデルにパクリ屋の手口と特徴を確認していきましょう。
TDB調査員が見た!パクリ屋の事例1
~休眠会社から食料品販売会社を騙ったW社のケース~
W社の概要
商業登記上では1994年3月の設立となっていました。しかし実態は代表のS氏が2006年に休眠会社だったW社を買収し、20××年6月に住所を埼玉県熊谷市から東京都豊島区に移転して営業活動を開始しました。OA機器の卸の他、食料品販売を手掛けており、特に食料品販売に注力しているとターゲットにされた会社に説明し、開示した決算書には20××年6月期は売上高1億6,000万円が計上されていました。
W社の手口
都内で本格的な“営業”を開始した20××年9月以降の半年間で手当たり次第に商品を取り込み、初回は小口の現金決済で信用を得て、2回目以降取引高を引き上げ、ごく短期間で相手先の与信枠の上限に達するまで矢継ぎ早に注文を繰り返していきました。
ある時、決済日に支払いが行われなかったため取引先が当社に問い合わせると、「不況の煽りを受けて業績が低迷し、メインバンクから融資を受けられませんでした。今、セーフティネット保障の審査を受けているところで承認される見通しですが、万一承認が下りなければ3か月の分割払いでもいいですか?」という回答を繰り返したといいます。
被害にあったのは東京、埼玉の企業が多かったほか、東北で開催された物産展をきっかけに東北地方南部の企業も多く含まれていました。また、W社ホームページへのアクセスによって接点を持った企業も含まれており、少なくとも20~30社が被害にあったとされており、1社あたりの焦げ付き額は200~500万円、被害総額は1億円を超えたと聞かれます。
W社の動き
20××年3月29日にW社の社長名で取引先に突然通知が送付されました。「売掛金の回収ができず、仕入先からの納品もストップしました。金融機関からの融資も受けられず、破産手続きの方向で進めています。今後について、近日中に弁護士からご連絡差し上げます。」という内容で、実際4月7日には弁護士名の通知を受けました。弁護士からの通知には「W社の営業部長より破産手続きの相談を受けています。代表S氏とは連絡が取れない状況ですが、早急に正式な事後処理の依頼を受ける予定です。」とありましたが、一般的な受任通知と比べるとやや違和感を覚えるものでした。
その後4月15日に再度通知が届きましたが、今度は「W社の破産手続きについて、営業部長とも連絡が取れなくなったため、事後処理の依頼を受けることもできなくなりました。」というもので、W社から正式な破産手続きの依頼はなく、同社とは無関係であることを強調するものでした。
債権者の動き
W社の一連の動きを不審に思っていた取引先の中には、債権回収や保全のための動きをしていた企業もありました。某飲料メーカーは支払遅延後すぐに訴訟に踏み切りましたが、分割返済を行うとの回答を得て和解に至りました。しかしながら、その後支払いはありませんでした。また都内の酒類卸業者は、差し押さえも辞さない覚悟で支払いを督促しましたが、東京地裁に出頭してきた代表S氏との話し合いの末、調停に応じてしまいました。W社と連絡がつかなくなったのはその1週間後のことでした。
債権者の声
【A社】
商業登記に記載されている代表者S氏自宅の千葉県のアパートまで押しかけましたが、大家から「契約していたのは別の名義の方でした。その方も昨年秋に退去しました。Sという方がここに住んでいたことはありません。」という言葉に唖然としました。
【B社】
豊島区の事務所は、営業会社でありながら社員は常に席におり、代表だけが常に不在でした。今にして思えば違和感がありました。
【C社】
警察に被害届を出しましたが、「弁護士もアリバイ作りに利用する極めて悪質で巧妙な手口だが、詐欺事件として断定するには難しい。」と言われました。
債権者の中には訴訟に踏み切った先もありましたが、結果としてW社と連絡がつかなくなり、売掛金を回収できた企業はありませんでした。債権者の声を聞くと「あの時は少しおかしいと思ったが、そのまま取引を続けてしまった。」「最初は現金取引で信用してしまった。」など、反省の弁が多数でした。
パクリ屋の被害に遭わないためには「基本行動を忘れないこと」に尽きます。古典的なパクリ屋は商業登記から見破ることができます。また、企業の事務所を実際に訪問し、自らの目で確かめることで相手方の反応を見極めることができます。
取り込み詐欺に関してはこちらでも説明しています。
■パクリ屋の手口 ~商業登記に表れる異常~
■連休と取り込み詐欺 ~彼らの収穫期~

