今回はIFRS導入後の非上場株式の評価について取り上げます。金融業以外の企業では、IFRSのうち金融商品会計基準は自社に影響がないと考えがちです。しかし、わが国の上場企業の中には、子会社や関連会社でなくとも、円滑な取引関係の維持やその他の戦略的な目的から他社の株式を保有することも多いと思います。このような企業は、IFRSにおける非上場株式の取扱いに注目しておきたいところです。
まず、非上場株式の評価について日本基準(J-GAAP)とIFRSの違いを押さえておきましょう。
J-GAAPにおける非上場株式の評価
子会社にも関連会社にも該当しない会社の株式で、短期的な売買を目的としないものは、その他有価証券に分類されます。その他有価証券は、時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額は純資産の部に計上されます(全部純資産直入法の場合)。 ただし、株式の時価を把握することが極めて困難と認められる場合には、取得原価をもって貸借対照表価額とすることが定められています(金融商品会計基準18、19項)。株式の時価を把握することが極めて困難と認められる場合とは、「市場価格に基づく価格」のない場合とされています。したがって、時価評価という原則に関わらず、非上場株式(=市場価格のない株式)は、取得価額により評価されます(金融商品会計に関する実務指針63項)。
ただし、投資先会社の財政状態の悪化で実質価額が著しく低下したときは、減損処理が求められます。具体的には、取得価額を実質価額まで減額し、評価差額は当期の損失とすると定めています(金融商品会計基準21、22項)。実務上、実質価額はBSの純資産額に持分割合を乗じて計算するケースが多く、実務指針もこれを認めていました。したがって、減損する場合ですら、直近の投資先会社の財務諸表(特にBS)を入手するだけで非上場株式を評価できたのです。いわゆるバリュエーション(企業価値評価)の必要に迫られなかったのです。
IFRSにおける非上場株式の評価
従来の金融商品会計基準であるIAS39号でも、株式は原則公正価値で評価しますが、公表市場価格がなく、公正価値を信頼性をもって測定できない株式に限って、例外的に取得原価で測定する旨を定めていました(IAS39 46項参照)。
ところが、2009年11月に発行された新基準であるIFRS9「金融商品」において、株式全般を公正価値で評価し、期末の評価差額は純損益もしくはその他の包括利益に計上することを求める一方で(5.4.1)、非上場株式を公正価値評価の例外として認めなかったのです。
さらに、取得原価が公正価値の適切な推定値となるのは限定的という立場をとり(B5.5参照)、取得原価が公正価値を表現していない場合を以下のように例示しました(B5.6参照)。
■予算、計画、目標と比較して、被投資企業の業績が著しく相違する場合
■被投資企業の技術上の製造目標達成に関する予想に変化がある場合
■被投資企業の株式の市場、又はその製品若しくは潜在的な製品の市場に著しい変化がある場合
■世界経済又は被投資企業が事業を行っている経済環境に著しい変化がある場合
■類似企業の業績又は市場全体から示唆される評価に著しい変動がある場合
■不正、事業上の紛争、訴訟、経営者の変更や戦略の変更など、被投資企業内に問題が生じている場合
■被投資企業の新規株式発行や、第三者間での株式の譲渡のいずれかにより、被投資企業の株式に関する外部取引から証拠が得られる場合
特に長期間投資を継続している非上場株式については、過去に期待した投資先会社の状況と、今日の状況が相違する場合も多いでしょう。したがって、わが国にIFRSが適用されると、上記の例示に該当し、非上場株式も公正価値評価を迫られる可能性があります。
J-GAAPでも公正価値で評価することになるのか?
2010年8月16日、わが国の企業会計基準委員会(ASBJ)が、「金融商品会計基準(金融資産の分類及び測定)の見直しに関する検討状況の整理」をリリースしました。この「整理」では、金融商品会計基準についてのJ-GAAPとIFRSのコンバージェンスに関する検討点が明らかにされています。その中には、非上場株式(公表される市場価格のない株式)の投資の分類も含まれており、
■IFRS9のように、公正価値で測定するものと分類した上で、取得原価が公正価値の適切な見積りとなる場合の適用指針(案)を定める。この適用指針(案)は、さきほど紹介したIFRS9のものとほぼ同内容。
■IAS39のように、公正価値を信頼性をもって測定できない場合、取得原価で測定するものとして分類する。
という、2つの案が提案されています。
いずれの案が採用されても、従来のJ-GAAPより、取得原価で評価するケースが限定されるかもしれません。1案の参照するIFRS9はもちろん、2案が参照するIAS39でも、「非上場」という理由だけでは取得原価を認められず、わが国の実務で見られる実質価額による減損処理も、無条件には認められないからです。
このため、今後の非上場株式の評価に関するJ-GAAPコンバージェンスの行方も気になるところです。
公正価値の測定方法は?
ここまで非上場株式の公正価値の測定が必要になる可能性を説明しました。では、非上場株式の公正価値をどのように測定すべきなのでしょうか?次回は、IASBの「公正価値測定」(2009年5月公開草案)で示されたバリュエーションのアプローチを紹介して、この疑問にお答えします。
非上場株式の評価(その1)まとめ
[J-GAAP]
■取得原価で評価
■減損が必要と判断されても、バリュエーションは必須でない(実質価額による評価)
↓
[IFRS]
■公正価値で評価
■「取得原価 ≒ 公正価値」とみなせるケースは限定的
■投資先会社の状況によって、バリュエーションが必要
(注)新金融商品会計基準(J-GAAP)のコンバージェンス動向によっては、IFRS導入前に公正価値による測定へ
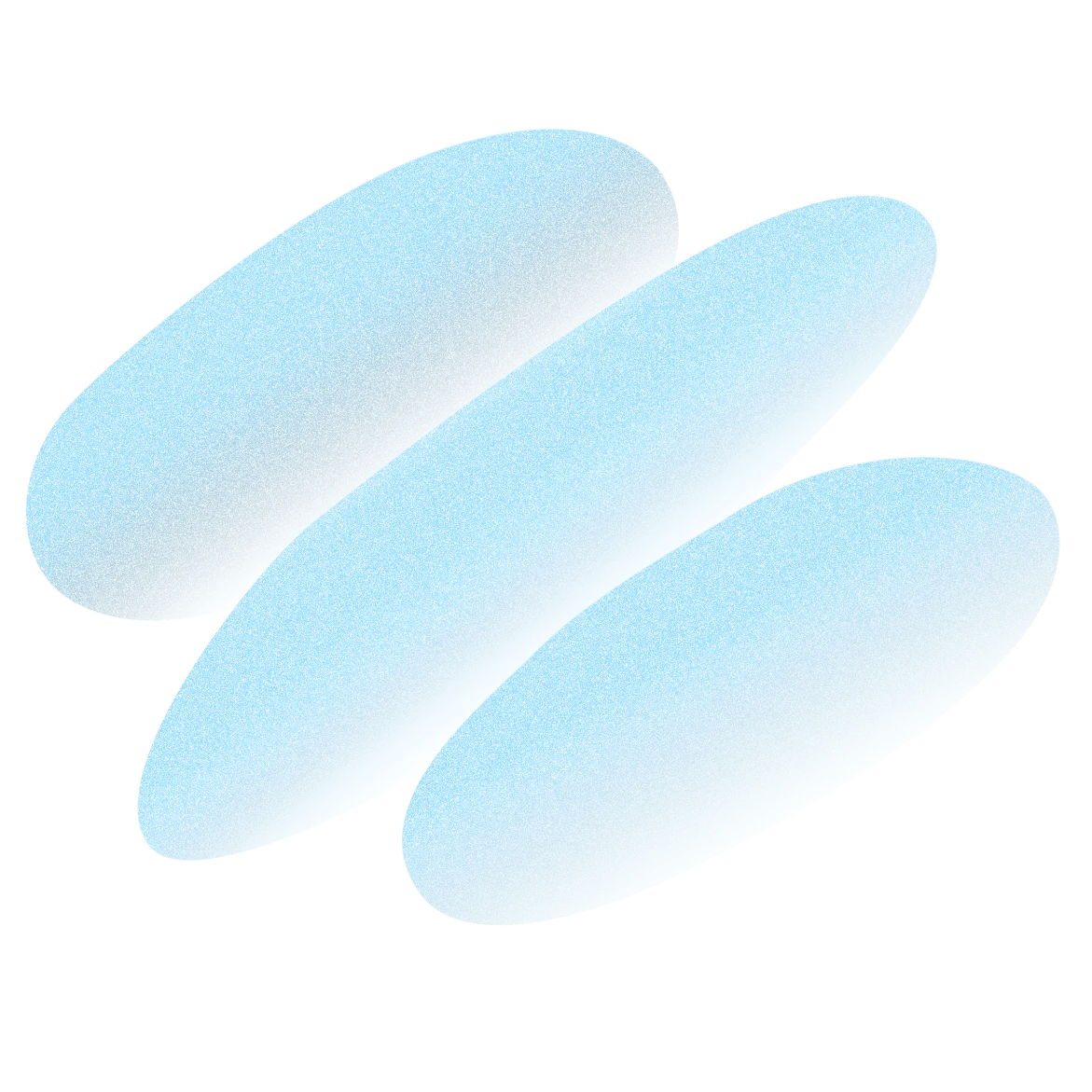
Contact Usお問い合わせ先
担当部署
株式会社帝国データバンク プロダクトデザイン部官公庁ソリューション課 TEL:03-5775-3161

