倒産件数は694件、2カ月ぶりの前年同月比増加
負債総額は1723億5600万円、3カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数 | 694件 |
|---|---|
前年同月比 | +12.8% |
前年同月 | 615件 |
負債総額 | 1723億5600万円 |
|---|---|
前年同月比 | +71.5% |
前年同月 | 1004億7700万円 |
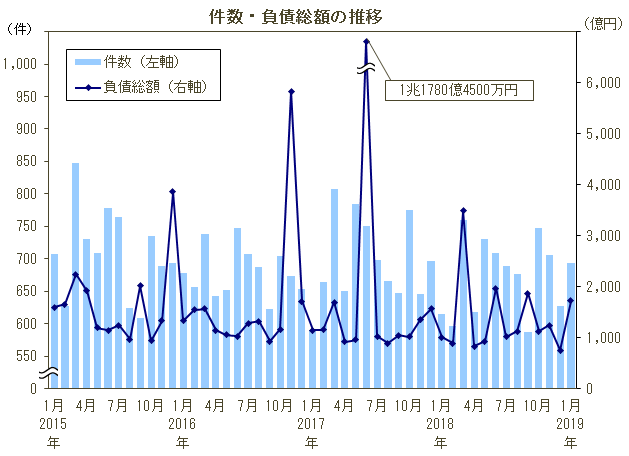
主要ポイント
- ■倒産件数は694件と、2カ月ぶりに前年同月を上回り、2017年10月(前年同月比10.1%増)以来、1年3カ月ぶりの前年同月比2ケタ増
- ■負債総額は、負債100億円以上の倒産が2件発生したことなどを受け、前年同月比71.5%増の1723億5600万円
- ■業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を上回った。小売業(158件、前年同月比17.9%増)は2カ月ぶり、サービス業(179件、同30.7%増)は4カ月連続の増加
- ■主因別に見ると、「不況型倒産」の合計は544件、構成比78.4%を占める
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は420件(前年同月比13.5%増)、構成比60.5%を占める
- ■地域別に見ると、9地域中7地域で前年同月を上回った。近畿(183件、前年同月比10.2%増)は2カ月ぶりの増加。九州(60件)は前年同月比50.0%増
- ■「人手不足倒産」は20件(前年同月比66.7%増)、6カ月連続の前年同月比増加
- ■負債トップは、(株)エメラルドグリーンクラブ(東京都、民事再生法)の450億円
- ■東証JASDAQ上場の(株)シベール(山形県、民事再生法)が倒産し、上場企業倒産が2018年6月以来、7カ月ぶりに1件発生
調査結果
■件数・負債総額
倒産件数は694件と、2カ月ぶりに前年同月を上回り、2017年10月(前年同月比10.1%増)以来、1年3カ月ぶりの前年同月比2ケタ増となった。東証JASDAQ上場の(株)シベール(山形県、民事再生法)が倒産し、上場企業倒産が2018年6月以来、7カ月ぶりに1件発生した。 負債総額は、負債100億円以上の倒産が2件発生したことなどを受け、前年同月比71.5%増の1723億5600万円となった。
■業種別
業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を上回った。
小売業(158件、前年同月比17.9%増)は、原材料費や人件費の高騰を背景に飲食料品小売(29件)や飲食店(50件)の倒産が増加し、2カ月ぶりの前年同月比増加。また、サービス業(179件、同30.7%増)は広告業(8件)や美容業(5件)の倒産が目立ち、4カ月連続の増加となった。 一方、製造業(73件、同12.0%減)は2カ月連続で前年同月を下回り、卸売業(102件)は前年同月と同数だった。
■主因別
主因別に見ると、「不況型倒産」の合計は544件(前年同月比10.6%増)となり、2カ月ぶりに前年同月を上回った。構成比は78.4%(同1.6ポイント減)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は420件(前年同月比13.5%増)、構成比は60.5%を占めた。負債5000万円未満の倒産では、サービス業(127件)が構成比30.2%(同6.2ポイント増)を占め最多、小売業(112件)が同26.7%(同2.0ポイント減)で続く。 資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人事業主含む)の倒産が441件(同12.2%増)、構成比は63.5%を占めた。
■地域別
地域別に見ると、9地域中7地域で前年同月を上回った。
近畿(183件、前年同月比10.2%増)は、ソフトウェア開発などのサービス業(59件)が地域全体を押し上げ、2カ月ぶりの前年同月比増加。また、九州(60件)は、復興需要効果で低水準だった前年同月からの反動で、前年同月比50.0%増となった。一方、北海道(16件、前年同月比11.1%減)、中部(92件、同12.4%減)の2地域は前年同月を下回った。
■態様別
態様別に見ると、破産は635件(構成比91.5%)、特別清算は28件(同4.0%)となった。民事再生法(31件)は、負債5000万円未満(16件、前年同月比45.5%増)や同10億円以上(9件、同125.0%増)で増加が目立った。
■特殊要因倒産
人手不足倒産
20件(前年同月比66.7%増)発生。6カ月連続で前年同月を上回り、前月に続き調査開始(2013年1月)以降の最多
後継者難倒産
28件(前年同月比7.7%増)発生。3カ月連続の前年同月比増加
返済猶予後倒産
59件(前年同月比55.3%増)発生。2カ月連続で前年同月を上回り、2013年10月(69件)以来の高水準
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは48.1、2カ月連続で悪化
1月の国内景気は、米中貿易摩擦を背景として、中国向けを中心とした機械や半導体関連の輸出減少による製造業の大幅な悪化が、関連する卸売業や物流にマイナスの影響を及ぼした。世界経済減速への警戒感が高まるなかで、発注量の抑制や新規案件を見送る動きも一部で生じてきた。加えて、暖冬傾向による冬物商材の需要低迷や一部地域で低調な公共工事が悪材料となったほか、人手不足の深刻化はコスト増や企業活動の停滞を招いた。
国内景気は、中国向けなど輸出の減速に加えて、暖冬傾向や人手不足もマイナス材料となり悪化、後退局面入りの兆しが表れてきた。
消費税率の引き上げや海外リスクの高まりなど、不透明感が一層強まる
今後、設備投資は省力化投資を中心に当面底堅く推移し、個人消費は緩やかな回復傾向が続くであろう。消費税率引き上げにともなう一時的な消費の悪化が見込まれるものの、大規模な経済対策でそうした落ち込みが一部緩和されると予想される。また、人件費や物流費の上昇などによる企業のコスト負担増加は、今後も続くとみられる。輸出は、米中貿易摩擦の激化などによる中国や欧州の景気低迷を受け、減速すると見込まれる。日米通商交渉の行方や、英による合意なきEU離脱の可能性など、海外を中心としたリスクの高まりが国内景気にさらなる悪影響を及ぼす可能性があり、注視していく必要がある。
今後の国内景気は、消費税率の引き上げやコスト負担の増加に加え、海外を中心としたリスクの高まりによって、下押しされる可能性があり、不透明感が一層強まっている。
今後の見通し
■倒産件数は1年3カ月ぶりの前年同月比2ケタ増
2019年1月の倒産件数(694件)は2カ月ぶりに前年同月を上回り、2017年10月(前年同月比10.1%増)以来、1年3カ月ぶりの前年同月比2ケタ増(12.8%増)となった。業種別では7業種中5業種で前年同月を上回り、とくに広告業、デザイン業、美容業などのサービス業(179件、同30.7%増)で小規模倒産の増加が目立った。
負債総額(1723億5600万円)は、エメラルドグリーンクラブ(負債約450億円、会員制リゾートホテル経営、東京都)とサンユウ産業(同約232億円、ゴルフ場経営、栃木県)の大型倒産が発生し、この2件で負債総額全体の4割を占めた。
■菓子店の倒産、増勢続く
1月は、主力商品のラスクなど洋菓子の製造・販売を手掛ける東証JASDAQ上場のシベール(負債約19億5900万円、山形県、民事再生)をはじめ、菓子製造販売業者の倒産が4件(前年同月2件)発生した。2018年の菓子製造販売業の倒産は過去最多の43件(前年比4.9%増)発生し、増勢が続いている。これまで売り上げを下支えしてきた贈答品としての需要は縮小傾向にあるうえ、地域密着で強い営業基盤を築いてきた菓子店でも、地域人口の減少やコンビニスイーツの台頭、全国的なブランド力を誇る銘菓との競合などから集客力が低下し、倒産に追い込まれるケースが目立つ。今後も人件費や物流費のほか、乳製品、チョコレートなど原料費の負担が高まるなか、業界の優勝劣敗が加速する可能性もある。
■人手不足倒産のさらなる増加を懸念
政府は現在の景気拡大期間(74カ月)が2019年1月で戦後最長を更新したとみられるとの認識を示した。有効求人倍率は2018年平均で1.61倍と9年連続で上昇し、2014年以降は求人数が求職数を上回る1倍超の状態が続いている。こうしたなか、従業員の離職や採用難等で収益が悪化したことなどを要因とする人手不足倒産は、2018年(153件、前年比44.3%増)まで3年連続で増加。1月は20件(前年同月比66.7%増)と、前月に並び調査開始(2013年1月)以降の最多となった。IT技術者が離職したソフトウェア開発業者や、慢性的な現場職人や施工管理者の不足による労務費上昇が深刻化している建設業などで倒産が増加した。働き方改革関連法の4月以降の順次施行を前に、大手企業を中心に労働条件や職場環境の改善が進む一方、高待遇での従業員確保が困難な小規模企業では人手不足倒産のさらなる増加が懸念される。
■増加傾向続く可能性は低いが、各種リスク要因には十分注視を
金融機関から返済条件の変更等(リスケジュール)を受けた企業による返済猶予後倒産が1月は59件と、2カ月連続で前年同月を上回った。日本政策金融公庫が全国259の金融機関に対して実施したアンケート調査の結果(2018年12月公表)によれば、現時点でリスケの解消・正常化の見通しが明確になっている企業の割合は「2割未満」との回答が68.1%と約7割を占め、リスケの解消・正常化の難しさを改めて裏付けた。返済猶予後倒産のなかには、抜本的な事業再生が進まないまま二度、三度とリスケを繰り返すことで年月が経過し、代表の高齢化や後継者不在と相まって事業継続を断念した企業も散見されてきており、その動向が注目される。
今後も金融機関による資金繰り支援環境が続くとすれば、倒産件数が急激に増加トレンドに転じる可能性は低い。ただし、米中貿易摩擦の影響による中国経済の減速などを背景に、企業業績の下振れ懸念が高まっており、為替や株価動向など各種リスク要因には十分注視したい。

