倒産件数は596件、3カ月ぶりの前年同月比減少
負債総額は887億4600万円、2000年以降で最小
倒産件数 | 596件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲10.2% |
前年同月 | 664件 |
前月比 | ▲3.1% |
前月 | 615件 |
負債総額 | 887億4600万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲23.4% |
前年同月 | 1158億5500万円 |
前月比 | ▲11.7% |
前月 | 1004億7700万円 |
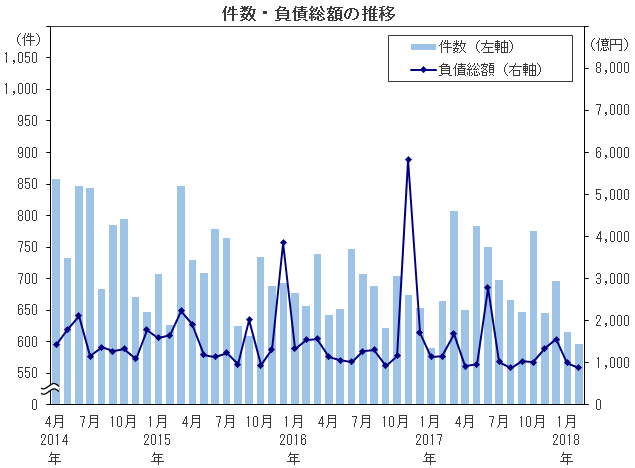
主要ポイント
- ■倒産件数は596件(前年同月比10.2%減)で、3カ月ぶりに前年同月を下回り、2017年1月(591件)以来1年1カ月ぶりに600件を下回った。負債総額は887億4600万円(同23.4%減)と、5カ月連続で前年同月を下回り、2000年以降で最小となった
- ■業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を下回った。なかでも、製造業(57件、前年同月比31.3%減)は2017年11月の68件を下回り、2000年以降で最少。また、建設業(110件、同5.2%減)は3カ月連続、小売業(127件、同14.2%減)は2カ月連続の前年同月比減少となった
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は486件(前年同月比8.3%減)となり、6カ月ぶりに前年同月を下回った。構成比は全体の倒産件数が減少したことにともない、前年同月比1.7ポイント増の81.5%となった
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は383件(前年同月と同数)となった。構成比は64.3%となり、依然として小規模倒産が大半を占める傾向が続いた。資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が367件、構成比は61.6%を占めた
- ■地域別に見ると、9地域中3地域でいずれも前年同月比20%超の大幅減少となった。なかでも、関東(175件)は2005年2月(199件)以来13年ぶりに200件を下回り、全体を押し下げた。また、九州(29件)は2000年1月の31件を下回り、2000年以降で最少
- ■負債トップは、翼システム(株)(東京都、破産)の151億6700万円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント倒産件数は596件、負債総額は2000年以降で最小
倒産件数は596件(前年同月比10.2%減)で、3カ月ぶりに前年同月を下回り、2017年1月(591件)以来1年1カ月ぶりに600件を下回った。負債総額は887億4600万円(同23.4%減)と、5カ月連続で前年同月を下回り、2000年以降で最小となった。
要因・背景
件数…業種別では7業種中5業種で、地域別では9地域中3地域で前年同月比減少
負債総額…負債100億円以上の倒産は2件発生も、小規模倒産が約6割を占めた
■業種別
ポイント7業種中5業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を下回った。なかでも、製造業(57件、前年同月比31.3%減)は2017年11月の68件を下回り、2000年以降で最少。また、建設業(110件、同5.2%減)は3カ月連続、小売業(127件、同14.2%減)は2カ月連続の前年同月比減少となった。一方、運輸・通信業(25件、同13.6%増)、不動産業(30件、同3.4%増)の2業種は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 製造業は、機械、電子部品、自動車などの生産が回復傾向のなか、鉄鋼・金属製品製造(7件、前年同月比36.4%減)などが前年同月を下回った
- 2. 小売業は、各種商品小売(2件、前年同月比77.8%減)、飲食料品小売(16件、同44.8%減)などが前年同月を下回った
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比81.5%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は486件(前年同月比8.3%減)となり、6カ月ぶりに前年同月を下回った。構成比は全体の倒産件数が減少したことにともない、前年同月比1.7ポイント増の81.5%となった。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1.不況型倒産のうち、製造業、卸売業、小売業など5業種は前年同月比減少
- 2.「人手不足倒産」は9件(前年同月比50.0%増)、3カ月連続の前年同月比増加
- 3.「後継者難倒産」は24件(前年同月と同数)
- 4.「返済猶予後倒産」は25件(前年同月比34.2%減)、4カ月ぶりの前年同月比減少
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比64.3%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は383件(前年同月と同数)となった。構成比は64.3%となり、依然として小規模倒産が大半を占める傾向が続いた。資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が367件、構成比は61.6%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産では、広告、ソフトウェア、経営コンサルタントなどのサービス業が105件(前年同月比5.0%増)を占め、構成比(27.4%)で最多
- 2. 負債100億円以上の倒産は2件と、大型倒産は低水準が続いている
■地域別
ポイント9地域中3地域で前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中3地域でいずれも前年同月比20%超の大幅減少となった。なかでも、関東(175件、前年同月比33.0%減)は2005年2月(199件)以来13年ぶりに200件を下回り、全体を押し下げた。また、九州(29件、同37.0%減)は2000年1月の31件を下回り、2000年以降で最少。一方、中部(96件、同5.5%増)など6地域は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 関東は、出版・印刷などの製造業(18件、前年同月比50.0%減)、飲食料品などの卸売業(30件、同42.3%減)を中心に減少が目立ち、6業種で前年同月を下回った
- 2. 九州は、小売業(4件)が前年同月比66.7%の大幅減少となったほか、復興工事需要を背景に建設業(7件、前年同月比12.5%減)が5カ月連続の減少
■上場企業倒産
上場企業の倒産は発生しなかった。
2017年度では、東証1部上場のタカタ(株)(民事再生法、6月)の1件が発生。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは50.3、1年1カ月ぶりに悪化
2018年2月の景気DIは前月比0.8ポイント減の50.3となった。50台は維持したものの、2017年1月以来1年1カ月ぶりに悪化した。
2月の国内景気は、一部地域を襲った猛烈な寒波や大雪が企業活動および消費活動の停滞を招き、悪化した。人手不足の深刻化にともなう受注見送りや供給制約が一部企業でみられたほか、人件費や燃料価格、食品価格の高値推移も重なるなどコスト負担が企業経営を圧迫。また円高進行や株価下落といった為替・株式相場の変動が、企業取引やマインドに悪影響を与えた。国内景気は、拡大基調が続くなか、大雪や人手不足の深刻化、コスト負担増が下押し圧力となり一服した。
企業部門がけん引し景気拡大が見込まれる一方、金融市場の動向に注視が必要
先行きについては、世界経済の回復を受け輸出の増加基調が続くほか、好調な企業収益を背景に設備投資も堅調に推移すると見込まれる。個人消費は緩やかに回復すると予想されるが、景気のけん引役となるには実質可処分所得の増加が不可欠となる。また五輪関連需要や消費税率引き上げ前の駆け込み需要も景気を押し上げるであろう。一方で、米連邦準備制度理事会(FRB)による利上げや、国内外の金融市場動向に注視する必要がある。雇用過不足DI(正社員)で過去最高更新が続くなど、人手不足深刻化にともなう人件費増や事業活動の停滞といった悪影響も懸念される。
今後の国内景気は、輸出や設備投資など企業部門がけん引し拡大が見込まれる一方で、金融市場の動向などを注視する必要がある。
今後の見通し
■高まる保護貿易主義、日本の景気を腰折れさせる懸念も
米商務省は2月16日、鉄鋼・アルミニウムの輸入を安全保障上の理由から大幅に制限するようトランプ大統領に提言、トランプ大統領も輸入を制限する方針を表明した。これに対して、WTO(世界貿易機関)や各国から懸念が表明されるなど、“貿易戦争”という言葉が頻繁に飛び交う事態となっている。
鉄鋼・アルミニウムの輸入制限が実施された場合、米国に進出あるいは輸出を行っている日本企業に直接的に悪影響を及ぼすだけでなく、米国内の企業・消費者に対するマイナスの側面が各国経済に波及することを通じて、日本企業への間接的な影響も想定される。
急速に進む円高ドル安は倒産要因となることに加え、保護貿易主義の高まりは世界貿易を縮小させ、日本の景気を腰折れさせる懸念もあり、倒産動向にも影響する可能性が高い。
■拡大するシェアリング・エコノミー、既存ビジネスへの影響広がる
自動車や住宅分野を中心にシェアリング・エコノミーが広がりを見せている。個人が持つ不稼働資産やスキルを互いに活用するビジネスが急増しており、C to C(個人対個人の取引)ビジネスが従来型ビジネスとぶつかるケースも表れている。生産者かつ消費者としてのプロシューマー(生産消費者)経済が本格化してきたといえる。
特に、民泊利用者の拡大は、顧客層が近い周辺地域の旅館・ホテルへの影響も懸念されよう。訪日外客数が2017年には過去最多となる2869万人に達したなか(日本政府観光局「訪日外客統計」)、民泊利用者は1割を超えると推計されるなど、民泊が旅行者にとって一般化しつつある。また、2018年6月15日には住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されるなど、シェアリング・エコノミーに関する法整備が進められている。
他方、シェアリング・エコノミーは、宿泊施設紹介(Airbnb)やライドシェア(Uber、滴滴出行)などに代表されるギグエコノミー(インターネットを通じて単発の仕事を受注する働き方や、それによって成り立つ経済形態)の拡大などを通じて労働者の働き方が変わる可能性もあり、今後、既存ビジネスを展開する企業への影響も注視する必要がある。
■2017年度の倒産件数は9年ぶりの増加に転じる見込み
国内経済は、輸出の拡大基調が維持されるほか、好調な企業収益を背景として設備投資も堅調に推移すると見込まれる。個人消費は緩やかに回復すると予想されるが、さらなる押し上げには実質可処分所得の増加が不可欠といえる。ただし、保護貿易主義の高まりに加え、FRB(米連邦準備制度理事会)による利上げや国内外の金融市場動向、人手不足の深刻化に伴う人件費増や事業活動の停滞などは懸念材料であろう。倒産動向は、景気の拡大基調が見込まれる一方で、海外における政治経済情勢の変化に影響を受ける可能性がある。
さらに、長時間労働の是正や女性登用、職場環境の整備など、働き方改革の行方は企業活動全般に影響を与えると見られ、働き方改革関連法案の動向も注目される。
2月の倒産件数は3カ月ぶりの減少となったが、2017年4月~2018年2月累計では7525件(前年同期比2.4%増)と増加している。こうした国内外における状況下で、当面の倒産動向は、増減を繰り返しつつ低水準で推移すると見られるが、2017年度の倒産件数は9年ぶりの増加に転じると見込まれる。

