倒産件数は2938件、1966年度以来55年ぶりの3000件割れ
負債総額は5784億7000万円、2年ぶりの前年同期比減少
倒産件数 | 2938件 |
|---|---|
前年同期比 | ▲25.7% |
前年同期 | 3956件 |
負債総額 | 5784億7000万円 |
|---|---|
前年同期比 | ▲3.8% |
前年同期 | 6012億5000万円 |
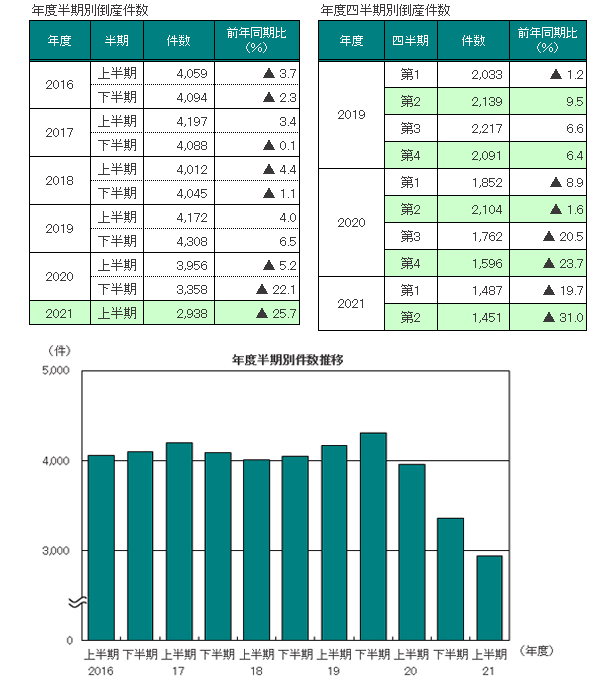
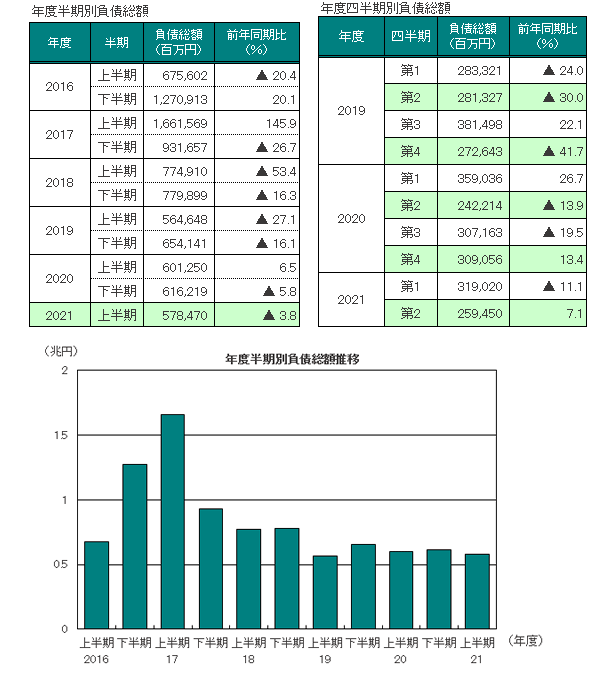
主要ポイント
- ■2021年度上半期の倒産件数は2938件と、1966年度以来55年ぶりの3000件割れとなった
- ■2021年度上半期の負債総額は5784億7000万円と、上半期として2年ぶりの前年同期比減少
- ■負債額最大の倒産は、(株)東京商事(特別清算、東京都、5月)の約1004億8300万円
- ■業種別にみると、7業種中6業種で前年同期を下回った。なかでも建設業(512件、前年同期比15.5%減)、製造業(324件、同26.2%減)、卸売業(373件、同27.4%減)、不動産業(109件、同11.4%減)は、2000年度以降の年度半期ベースで最少となった
- ■主因別の内訳をみると、「不況型倒産」の合計は2248件(前年同期比28.8%減)で、2000年度以降の年度半期ベースで最少
- ■負債額別にみると、負債5000万円未満の倒産は1777件(前年同期比28.1%減)。構成比は60.5%(同2.0ポイント減)を占め、小規模倒産が過半を占める傾向が続いている
- ■地域別にみると、全地域で前年同期から2ケタ減少。特に、北海道(65件、前年同期比31.6%減)、東北(107件、同37.1%減)、中部(405件、同28.4%減)、近畿(750件、同30.1%減)、中国(121件、同35.6%減)、九州(225件、同22.9%減)の6地域は、2000年度以降の年度半期ベースで最少となった
- ■態様別にみると、民事再生法は89件となり、施行後初めて100件を下回った
- ■「人手不足倒産」は49件(前年同期比24.6%減)、2年連続の前年同期比減少
- ■「後継者難倒産」は218件(前年同期比5.2%減)、4年ぶりの前年同期比減少
- ■「返済猶予後倒産」は210件(前年同期比20.8%減)、3年ぶりの前年同期比減少
調査結果
■件数
1966年度以来55年ぶりの3000件割れ
2021年度上半期の倒産件数は2938件(前年同期3956件、前年同期比25.7%減)となった。2000年度以降では最少、1999年度以前と比較しても、1966年度以来55年ぶりの3000件割れと記録的な低水準となった。四半期別では、第1四半期は前年同期から19.7%減、第2四半期は31.0%減と、大幅な減少率を記録した。
なお、上場企業による倒産は発生しなかった。
■負債総額
2年ぶりの前年同期比減少
2021年度上半期の負債総額は5784億7000万円(前年同期6012億5000万円、前年同期比3.8%減)と、上半期として2年ぶりに前年同期比で減少。四半期別では、第1四半期は前年同期比11.1%の減少となったものの、第2四半期は同7.1%の増加に転じた。負債額最大の倒産は、令和最大の倒産となった元ホテル・レジャー施設運営の(株)東京商事(特別清算、東京都、5月)で約1004億8300万円。
■業種別
6業種で前年同期比減少、うち4業種は2000年度以降最少
業種別にみると、7業種中6業種で前年同期を下回った。なかでも建設業(512件、前年同期比15.5%減)、製造業(324件、同26.2%減)、卸売業(373件、同27.4%減)、不動産業(109件、同11.4%減)は、2000年度以降の年度半期ベースで最少となった。また、サービス業(685件、同28.7%減)は、前年同期比で2000年度以降最大の減少率を記録した。
一方、運輸・通信業(133件、前年同期比3.9%増)は、年度半期ベースで2年ぶりに前年同期を上回り、なかでも軽貨物など貨物運送関連が大幅に増加した。
■主因別
「不況型倒産」の構成比76.5%
主因別の内訳をみると、「不況型倒産」の合計は2248件(前年同期比28.8%減)で、2000年度以降の年度半期ベースで最少。構成比は76.5%(同3.4ポイント減)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
負債5000万円未満の構成比60.5%、5年連続で6割を超える
負債額別にみると、負債5000万円未満の倒産は1777件(前年同期比28.1%減)。構成比は60.5%(同2.0ポイント減)を占め、5年連続で6割を超えるなど、小規模倒産が過半を占める傾向が続いている。一方、50億円以上100億円未満は前年同期から33.3%増加し、6年ぶりに10件台となった。
資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人事業主含む)の倒産は1934件(前年同期比27.3%減)、構成比は65.8%(同1.4ポイント減)を占めた。
■地域別
全地域で前年同期から2ケタ減少、うち6地域が2000年度以降最少
地域別にみると、全地域で前年同期から2ケタ減少。特に、北海道(65件、前年同期比31.6%減)、東北(107件、同37.1%減)、中部(405件、同28.4%減)、近畿(750件、同30.1%減)、中国(121件、同35.6%減)、九州(225件、同22.9%減)の6地域は、2000年度以降の年度半期ベースで最少となった。また、関東(1092件、同18.6%減)では、前年同期から2000年度以降最大の減少率を記録し、多くを占める小売業(222件)やサービス業(307件)、製造業(109件)などが大幅に減少したことで、関東全体の件数を押し下げた。
■態様別
民事再生法が89件、施行開始の2000年度以降で初の100件割れ
態様別にみると、破産は2707件(構成比92.1%)、特別清算は142件(同4.8%)。民事再生法は89件(同3.0%)となり、施行後初めて100件を下回った。
■特殊要因倒産
人手不足倒産
2021年度上半期は49件(前年同期比24.6%減)、2年連続の前年同期比減少
後継者難倒産
2021年度上半期は218件(前年同期比5.2%減)、4年ぶりの前年同期比減少
返済猶予後倒産
2021年度上半期は210件(前年同期比20.8%減)、3年ぶりの前年同期比減少
今後の見通し
■倒産は55年ぶり低水準 負債総額も減少の一方、大型倒産が複数発生
2021年度(21年4-9月)の倒産件数は前年同期比25.7%減となる2938件となり、2000年度以降で最少、1999年度以前と比較しても55年ぶりの低水準を記録した。持続化給付金など政府による事実上の資本注入策に加え、各金融機関による無利子・無担保融資、既存融資のモラトリアム対応など、考えうる金融支援を総動員した万全の資金繰り対策が行われたことで、業種を問わず経営不振に陥った多くの中小零細企業が「手元資金の枯渇」という最悪の事態を回避し続けていることも、法的整理としての倒産発生を大きく抑え込んだ要因となった。
一方で、負債総額は前年同期から3.8%減少となる5784億7000万円となり、倒産に比べて減少率は小幅に留まった。倒産が減少するなかでも、負債10億円以上の中大型倒産が複数発生。事業再生による旧会社の清算などで負債が大型化した側面もあるものの、コイケ(5月民事再生)やサン宝石(8月同)など、従前から過大な負債を抱えた中でコロナ禍の急激な業績悪化が直撃し、資金繰りが限界に達した業界中堅企業の倒産が発生している。
■宿泊業の倒産、足元で反転増の傾向 「秋の行楽シーズン」の成否が先行き占う
コロナショックで最も大きな影響を受けたのが、対個人サービスである宿泊業と飲食店だ。緊急事態宣言をはじめとした人流抑制策の影響を特に大きく受けた2業種だが、21年度上半期の倒産は宿泊業で前年同期比47.9%減の38件、飲食店は同24.0%減の298件と、ともに前年同期を下回った。ただ、飲食店では6カ月中5カ月で前年比減となった一方、宿泊業では7-8月で増加、9月も前年同月に並ぶなど、足元の倒産動向には異なる動きがみられる。
事業意欲を図るバロメーターの一つとなる借入金動向も、飲食店と宿泊業では近時の傾向がK字に分かれる。日本銀行の統計では、中小企業が多く利用する信用金庫の貸付残高のうち、21年4-6月期の宿泊業向けは20年4月以降、前年同期比約1割増で推移した3月までから一転、最も小さい2%程度の伸びにとどまった。2ケタ増となお高い伸びが続く飲食店に比べると大幅な低下がみられる。宿泊業は協力金などが飲食店に比べると比較的少なく、そのため当初は売上高急減による固定費補填への緊急対応として長短借入金に頼らざるを得ないケースは多かった。ただ、結果的に宿泊業の有利子負債は月商の約26倍と膨れ上がっており、金融機関の融資や支援姿勢はコロナ禍で軟化しているとはいえ、借入限度を既に使い切り「借りたくても借りることができない」旅館やホテルが増えている可能性を示唆している。
緊急事態宣言が全国的に解除され、Go To 事業の再開なども要望されるなか、観光産業は抑制された需要の反動増=ペントアップ(繰越需要)に望みをかける。一方、宿泊業では傷口が浅いうちに事業を畳む休廃業などは既に前年を超えており、コロナ禍前の売り上げ水準に回復するか懐疑的な見方をする事業者も多い。そのため、既に金融支援を限度枠まで使い切った宿泊業では、年内最後の繁忙期である「秋の行楽シーズン」で売り上げ回復が期待に届かなければ、先行きへのあきらめ、資金調達が新たに受けられない息切れの倒産が増加する可能性がある。
■各種救済措置で経営危機の表面化は先送りも、「コロナ支援」からの卒業が今後の課題
全国的な倒産傾向としては、微細な増減はあるものの今後も急激な増加はないだろう。4日に発足した岸田政権が、10月末に投開票が行われる衆議院総選挙の行方によるものの、金融支援を中心とした企業支援から経営不振企業に退場を促す内容へと大きく舵を切る事態は短期的に考えづらく、2021年後半にかけても倒産動向は比較的落ち着いた推移をみせるとみられる。
一方で、強力な金融支援が生み出した企業の過剰債務問題といった副作用を、資金面だけでなく本業を含めてどう立て直すかが求められる局面に来ている。金融庁は2021事務年度の金融行政方針において、地域金融機関がコロナ禍で傷んだ中小企業の経営改善や事業再生支援に向けた環境整備を明記した。政府も、中小企業でも円滑に私的整理が行えるガイドライン策定を目指すなど、コロナ禍の中小企業支援は抜本的再生へと主眼が移りつつある。ただ、過去の金融円滑化法で借入金などのリスケを実行した企業のうち、実際に経営改善計画を策定できた企業は3割ほどとされ、今回も自力で経営再建を果たす企業がどれ程に上るかは未知数だ。
足元では半導体や食品など各種原材料、賃金など労務費が上昇する一方、国内消費の停滞で販売価格に転嫁できない状況が長く続いており、特にサービス業や小売業では売り上げの維持や利益確保で精一杯のケースが少なくない。手厚い中小企業支援が倒産を抑制し続ける一方で、将来的な事業再建への道筋が見込めないまま、コロナ支援に依存し続ける経営不振企業が増加する懸念は残ったままであり、これら企業の倒産リスクは依然として燻る状態が続く。

