倒産件数は689件、8カ月ぶりの前年同月比増加
負債総額は1328億7000万円、2カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数 | 689件 |
|---|---|
前年同月比 | +2.7% |
前年同月 | 671件 |
前月比 | ▲6.3% |
前月 | 735件 |
負債総額 | 1328億7000万円 |
|---|---|
前年同月比 | +20.8% |
前年同月 | 1100億2300万円 |
前月比 | +40.9% |
前月 | 943億2800万円 |
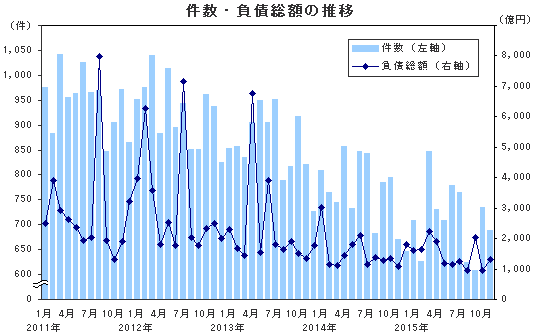
主要ポイント
- ■倒産件数は689件で、前月比で6.3%減少したものの、前年同月比で2.7%増加となり、8カ月ぶりに前年同月を上回った
- ■負債総額は1328億7000万円で、前年同月比20.8%増と、2カ月ぶりに前年同月を上回った
- ■業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を上回り、なかでも製造業(93件、前年同月比16.3%増)、卸売業(111件、同15.6%増)、小売業(135件、同18.4%増)の3業種は増加率が前年同月比2ケタの大幅増加となった
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は590件(構成比85.6%)となった
- ■負債額を規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は374件(前年同月比0.5%減)で、構成比は54.3%と、前年同月を1.7ポイント下回った。一方、負債50億円以上の倒産は5件(前月0件、前年同月1件)発生した
- ■地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を上回り、なかでも倒産件数全体の約4割を占める関東をはじめ、3地域は増加率が前年同月比2ケタの大幅増加。一方、14カ月連続の前年同月比減となった北陸(18件、前年同月比21.7%減)など、5地域は前年同月を下回った
- ■上場企業の倒産は発生しなかった
- ■負債上位は、(株)オプティファクター(東京都、破産)の70億300万円、(株)ニューグリーンステイくじゅう(大分県、民事再生法)の62億8700万円、ソマテック(株)(宮城県、特別清算)の60億円と続いた
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は8カ月ぶり、負債総額は2カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数は689件で、前月比で6.3%減少したものの、前年同月比で2.7%増加となり、8カ月ぶりに前年同月を上回った。負債総額は1328億7000万円で、前年同月比20.8%の増加と、2カ月ぶりに前年同月を上回った。
要因・背景
件数…業種では製造業、卸売業、小売業の3業種で、地域では倒産件数全体の約4割を占める関東のほか、北海道、九州の3地域で、増加率が前年同月比2ケタの大幅増加
負債総額…円安・株高の進展による大企業を中心とした好業績を背景に、大型倒産が沈静化
■業種別
ポイント7業種中4業種で前年同月比増加
業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を上回り、なかでも製造業(93件、前年同月比16.3%増)、卸売業(111件、同15.6%増)、小売業(135件、同18.4%増)の3業種は前年同月比2ケタの大幅増加となった。一方、サービス業(134件、同18.3%減)は前年同月を下回り、建設業(141件)、運輸・通信業(31件)の2業種は前年同月と同数となった。
要因・背景
- 1. 製造業・卸売業…円安による原材料などの輸入コストの増加や、SPA型企業などとの競争激化を背景に、衣料品・繊維製品の製造(12件、前年同月比71.4%増)や卸売(26件、同52.9%増)で大幅増加
- 2. 小売業…個人消費の伸び悩みや大手スーパーとの価格競争など受け、飲食料品小売で増加
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比85.6%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は590件(前年同月比10.9%増)となった。構成比は85.6%(前月86.1%、前年同月79.3%)と、前月を0.5ポイント下回ったものの、前年同月を6.3ポイント上回った。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、 業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1.中国関連事業を手がけ、中国固有のリスクが要因となって倒産した「チャイナリスク関連倒産」は8件(前年同月比100.0%増)判明、2カ月連続で前年同月を上回った
- 2.「円安関連倒産」は14件(前年同月比66.7%減)判明、3カ月連続の前年同月比減少
- 3.「返済猶予後倒産」は38件(前年同月比72.7%増)判明、1年7カ月ぶりの増加
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比54.3%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は374件(前年同月比0.5%減)で、構成比は54.3%と、前年同月を1.7ポイント下回った。一方、負債50億円以上の倒産は5件(前月0件、前年同月1件)発生した。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が383件となり、構成比は55.6%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産、運輸・通信、不動産で増加も、製造、サービスなどで大幅減
- 2. 負債50億円以上の倒産、2012年1月(8件)以降47カ月連続で10件未満にとどまる
■地域別
ポイント北陸は14カ月連続の前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を上回り、なかでも北海道(21件、前年同月比16.7%増)、関東(264件、同14.8%増)、九州(48件、同11.6%増)の3地域は増加率が前年同月比2ケタの大幅増加。一方、14カ月連続の前年同月比減少となった北陸(18件、同21.7%減)をはじめ、5地域は前年同月を下回った。
要因・背景
- 1. 関東は、建設業(57件、前年同月比32.6%増)、製造業(36件、同38.5%増)などの増加が東京都を中心に目立ち、2カ月連続で前年同月を上回る
- 2. 北陸は、新幹線開業効果による景況感の改善など受け、富山県と石川県で大幅減少
■上場企業倒産
上場企業の倒産は発生しなかった。
2015年の累計は3件にとどまっており、上場企業の倒産は沈静化が続いている。
■主な倒産企業
負債上位は、(株)オプティファクター(東京都、破産)の70億300万円、(株)ニューグリーンステイくじゅう(大分県、民事再生法)の62億8700万円、ソマテック(株)(宮城県、特別清算)の60億円と続いた。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは44.8、景気は膠着状態
2015年11月の景気DIは44.8となり前月と同水準で、景気は横ばいとなった。
11月は、内閣府から2015年7~9月期の実質GDP成長率が前期比0.2%減と2四半期連続のマイナス成長だったことが公表された。中東産ドバイ原油が一時7年ぶりに1バレル=40ドルを割るなど原油価格が安値圏で推移したことで、ガソリンや軽油価格が5週連続で低下し、企業のコスト負担を和らげる要因となった。一方、実質賃金が伸び悩むなかで家計の節約志向は高まってきており、『小売』は3 カ月連続で悪化している。中国景気減速の影響が『製造』を中心として表れているが、アルミや銅など国際市場で決まる商品価格は中国などの需要低迷を受けて低下しており、輸入を通じた仕入価格は徐々に落ち着きを取り戻しつつある。9年9カ月ぶりに「大企業」と「中小企業」が同時に横ばいを示すなど、国内景気は膠着状態となっている。
国内景気は企業業績が好調な一方、先行き不透明感が漂い一進一退で推移
海外経済では、新興国や資源国経済の下振れによる世界経済の減速懸念のほか、米国による金利引き上げの影響は輸出にマイナス材料となろう。国内では、在庫調整圧力が残るほか、先行き不透明感を背景とした設備投資の様子見姿勢や人材不足による人件費の上昇など企業のコスト負担が懸念材料となる。他方、2016年度に入ってからは、2017年4月の消費税率引き上げを控えた駆け込み需要が住宅や高額耐久財などで発生すると予測される。また、雇用者数の増大とともに所得の増加が期待される。今後の国内景気は、企業業績が堅調なものの、先行きに不透明感が漂うなか、一進一退で推移していくとみられる。
今後の見通し
■11月の倒産件数、8カ月ぶりに前年同月比増
11月の倒産件数は、689件(前年同月比2.7%増)と、前年同月比では8カ月ぶりに増加に転じた。なかでも、構成比で20%を占める東京都(138件)が2カ月連続で前年同月比で増加した点が注目される。負債総額は1328億7000万円で、負債50億円以上の倒産が今年3月の7件に次ぐ5件発生し、前年同月比20.8%増、前月比40.9%増となった。
11月27日に公表された10月の完全失業率は3.1%と20年3カ月ぶりの低水準となり、雇用環境は大幅に改善されたものの、10月の家計消費支出は前年同月比2.4%減と2カ月連続で前年同月比減となった。消費者の節約志向は根強く、国内景気は足踏み状態にある。加えて、中国を含む新興国経済の減速や米国の利上げ観測、パリ同時多発テロ以降各国で警備体制が強化されるなど、世界経済・政治でも不安材料は多く、国内外で楽観視できない状況が続く。
■好調な2015年度中間期業績、一方で大手メーカーの事業再構築の影響注視
上場企業を中心に2015年度中間期業績が出揃い、円安や原油安を追い風に自動車、化学、ゼネコンなど通期で過去最高益を見込む企業が相次いでいる。
一方で、改めて注目されたのが東芝やシャープなど問題を抱える大手メーカーだ。不正会計により過年度業績の大幅修正を余儀なくされた東芝は、構造改革の一環として10月下旬に半導体事業での一部事業の売却を発表したのに続き、ここにきてパソコン事業で他社との統合が報道された。シャープは、人員削減や本社をはじめとする資産売却を進めているが、外資系企業による買収やファンドによる出資案が浮上しては消え、迷走を続けている。
大手メーカーは製造拠点の海外移転を進める中で、国内にはコアとなる研究開発・製造拠点を残してきた。しかし、今後の事業再構築の展開次第ではこれらの国内拠点も聖域ではなくなる。
東芝グループは国内に仕入先・下請先などの取引先を約2万2000社*1、シャープグループは同じく国内に下請先約1万1200社を有する*2。拠点の統廃合や閉鎖、縮小が行われた場合、その影響は下請企業、物流、調達、さらには地域の飲食店、ホテル・旅館、建設、不動産など幅広い業種の中小企業に及ぶ。こうした大手メーカーの事業再構築の進展が、中小企業や地域経済に及ぼす影響は注視していく必要がある。
*1 帝国データバンク特別企画2015年7月発表
*2 同4月発表
■中小企業をめぐる政策、変化の兆し
11月30日、金融庁で「中小企業等の金融の円滑化に関する意見交換会」が開催された。資金需要が高まる年末に向けて金融関係団体トップへ資金繰りへの協力を要請する定例の場だ。近年、こうした政府主導による手厚い中小企業への支援を背景に倒産は減少傾向をたどってきた。
しかし、ここにきて変化の兆しが見え始めている。一端が金融機関により多くのリスクを求める「信用保証制度」の見直しだ。中小企業庁は11月に中小企業政策審議会に金融ワーキンググループを立ち上げ、関係機関へのヒアリングを開始した。信用保証制度は、2007年に信用保証協会と金融機関がリスク分担する「責任共有制度」が導入されたが、翌2008年に発生したリーマン・ショック対策として緊急保証が実施され100%保証の対象業種が拡大。さらに2009年12月には金融円滑化法が施行され、2013年3月の同法の期限到来後も金融機関によるリスケなど実質的な支援態勢は継続されてきた。
2015年は、2014年に続き2年連続で倒産件数が1万件を下回ることは確実となった。だが「GDP600兆円」の実現に向けて、政府による中小企業への支援政策は従来の雇用優先の手厚い保護から、成長性を備え“稼ぐ力”のある企業を重視し、新陳代謝を促進する方向へ変化しつつある。当面、倒産件数が大幅に上昇する見込みは低いが、2016年は円安基調も続くことが見込まれ、金融円滑化法の出口戦略として設けられたメニューの「暫定リスケ」(3年)の最終年度が到来する企業が相次ぐ。環境変化に対応できず、経営体質の改善が困難で競争力に乏しい中小企業は、倒産や廃業により市場退出を余儀なくされる可能性は高まっていくだろう。

