倒産件数は9180件、8年ぶりの1万件割れ
負債総額は1兆8678億円、戦後最大となった2000年の10分の1以下に
倒産件数 | 9180件 |
|---|---|
前年比 | ▲11.1% |
2013年 | 1万332件 |
負債総額 | 1兆8678億円 |
|---|---|
前年比 | ▲32.3% |
2013年 | 2兆7575億4300万円 |
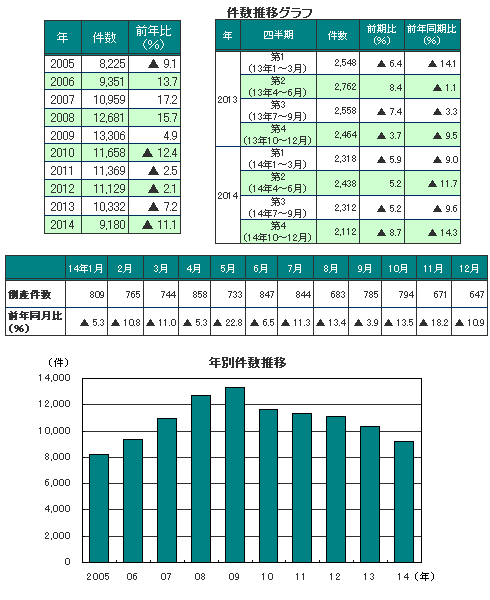
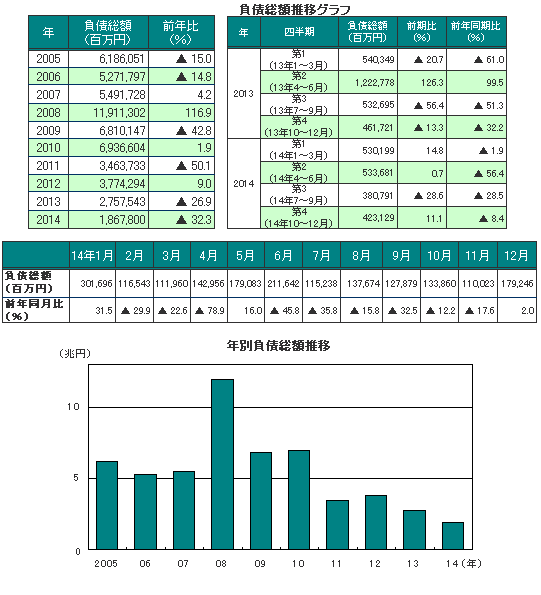
■件数
ポイント8年ぶりの1万件割れ
2014年の倒産件数は9180件と、2013年の1万332件に比べ11.1%減少し、8年ぶりの1万件割れとなった。減少率11.1%は、2000年以降では中小企業金融円滑化法が効果を発揮し始めた2010年(12.4%減)に次ぐ水準である。
要因・背景
- 1.金融緩和や財政出動により、企業の資金調達環境など経営環境が改善
- 2.中小企業金融円滑化法終了後も金融機関の支援が継続し、経営不振企業の倒産を抑制
- 3. 駆け込み需要や公共工事の増加により、建設業(1859件)が前年比20.8%の大幅減少
■負債総額
ポイントピークとなる2000年の10分の1以下に
2014年の負債総額は1兆8678億円と、2013年の2兆7575億4300万円に比べ32.3%の大幅減少となった。戦後最大となった2000年(21兆8390億700万円)と比べると、10分の1以下にとどまった。
要因・背景
- 1.負債トップは、エヌ・エス・アール(株)(1月、東京都)の1650億円
- 2.金融機関による支援や事業再生ADRの活用などにより大型倒産が抑制され、負債100億円以上の倒産は8件(前年20件)と、2000年以降で最少にとどまる
■業種別
ポイント7業種中6業種で前年比減少
業種別に見ると、不動産業(319件、前年比6.3%増)を除く6業種で前年を下回った。なかでも、建設業(1859件、同20.8%減)、製造業(1225件、同16.1%減)、卸売業(1381件、同14.4%減)の3業種は前年比2ケタの大幅減少となった。建設業は6年連続の前年比減少で、2000年以降で最少を記録した。
要因・背景
- 1.建設業…消費税率引き上げ前の駆け込み需要に加え、公共工事が高水準で推移したことで好況が続き、近時のピークだった2008年(3446件)の約半数に減少
- 2.輸出関連の大手メーカーの業績回復を背景に、機械器具などの製造・卸で減少が目立つ
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比は82.7%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は7593件(前年8520件)となり、5年連続で前年を下回った。構成比は82.7%と前年(82.5%)を0.2ポイント上回った。
要因・背景
- 1.「円安関連倒産」は345件判明、前年(130件)の約2.7倍に急増
- 2.高齢化を背景に「経営者の病気、死亡」(208件、前年209件)が高水準で推移
■規模別
ポイント負債5000万円未満の小規模倒産が過半数を占める
負債額別に見ると、負債5000万円未満の小規模倒産は5069件と、前年(5619件)を9.8%下回ったものの、構成比は55.2%と全体の過半数を占めた。一方、負債100億円以上の大型倒産は8件(前年20件)にとどまり、2000年以降で最少となった。
要因・背景
- 1.倒産の小型化に拍車がかかり、負債5000万円未満の構成比55.2%は過去10年で最高
- 2.大型倒産は金融機関による支援や事業再生ADRの活用などにより抑制が続く
■地域別
ポイント9地域中7地域で前年比減少
地域別に見ると、9地域中7地域で前年を下回り、なかでも北陸(293件、前年比20.8%減)、中部(1281件、同17.4%減)、関東(3358件、同13.1%減)の3地域は前年比2ケタの大幅減少となった。一方、四国(180件、同7.8%増)、東北(358件、同1.1%増)の2地域は前年を上回った。
要因・背景
- 1.関東は、製造業(421件、前年比23.9%減)と建設業(611件、同23.4%減)で大幅減少
- 2.中部は、6県すべてが前年を下回り、なかでも静岡と愛知は卸売業中心に20%以上減少
■態様別
ポイント破産の構成比は93.7%
態様別に見ると、破産は8605件(前年9731件)と前年比11.6%の減少となったものの、構成比は93.7%と高水準が続いた。このほか、民事再生法(291件)、会社更生法(2件)も前年を下回った一方、特別清算(282件)は前年を上回った。
要因・背景
- 1.再建型手続きが困難な中小零細企業の構成比が高まり、破産や特別清算が高水準で推移
- 2.民事再生法による倒産は、前年(331件)を下回り2000年の同法施行以降で最少
■上場企業倒産
2014年は、上場企業倒産が発生しなかった。年間を通して上場企業倒産が発生しなかったのは、1990年以来24年ぶり。
上場企業の倒産は、資金調達環境の改善や事業再生ADRの広がりにより、2013年8月のワールド・ロジ(株)(破産)以降16カ月連続で発生していない。
■大型倒産
2014年の負債トップは、エヌ・エス・アール(株)(破産、1月)の1650億円。(株)インターナショナルイーシー(破産、12月)の485億5300万円、(株)白元(民事再生法、5月)の254億9400万円がこれに続く。
負債1000億円以上の倒産は1件にとどまり、大型倒産の沈静状態が続いている。
■注目の倒産動向
建設業 件数は3年連続で前年比2ケタの大幅減少
2014年の建設業の倒産は1859件(前年比20.8%減)となり、6年連続の前年比減少。また、月ベースでみても、12月(136件)が前年同月比7.5%の減少となったことで、2012年10月以降27カ月連続で前年同月を下回った。これは、2003年9月から2005年5月までの21カ月前年同月比減少の連続記録を抜き、2000年以降の最長記録となっている。
減少局面となった2003年から2005年にかけては、ゼネコンなどの過剰債務問題やメガバンクの不良債権処理が峠を越えた時期であったほか、政府の中小企業支援策が奏功した時期でもあった。その後、2007年6月の建築基準法改正や2008年9月のリーマン・ショックの影響を大きく受け、倒産件数が著しく増加。2008年には2000年以降で年ベースの最多となる3446件の倒産が発生。また翌2009年の倒産件数も3441件という高水準で推移した。2014年はそのピーク時と比べるとほぼ半減。「緊急保証制度」や「中小企業金融円滑化法」の倒産抑制効果のほか、2011年に東日本大震災が発生して以降は、復興需要、政権交代後の公共工事増加、消費税率引き上げ前の駆け込み需要などを受け、倒産件数の減少傾向が続いている。
しかし、近時では資材不足、職人不足が倒産に結び付くケースが散見されるように、資材価格高騰、労務費高騰が建設業者の収益に大きな影響を与えている。また、地方の建設業者の拠り所となっている公共工事も、公共工事前払金保証実績が2014年8月から11月まで4カ月連続で前年同月比減少となるなど、一時の勢いを感じられなくなっているのも現実だ。今後、地方の中小零細建設業者など資本力の弱い下請け業者を中心とした淘汰が進めば、それにより建設業の倒産件数が前年同月比増加に転じる局面を迎えることが想定される。
今後の見通し
■24年ぶりに上場企業倒産が発生せず、民事再生法は過去最少
2014年は、上場企業の倒産が1990年以来24年ぶりに発生しなかった。2013年8月のワールド・ロジ(ジャスダック、破産)以降16カ月連続で発生しておらず、上場企業の倒産未発生期間としては、1964年の調査開始以降3番目の長さとなっている。背景には、株価上昇や量的金融緩和策などで資金調達環境が改善したことがある。事業再生ADRの広まりも一因だ。同制度は、2014年3月末までに50件の手続利用申請があり42件が受理された。そのうち16件が上場企業である。なかには日本航空(東証1部、会社更生法)など法的整理に移行した案件が3件あるが、13件は債権者の合意を得て手続きが成立している。こうした状況下、2015年も上場企業の倒産が発生し難い地合いが続くとみられる。
また、民事再生法による倒産が291件と同法施行(2000年4月)以降で最少の件数となっていることも2014年の特徴だ。2013年(前年比27.9%減)、2014年(同12.1%減)と2年連続で2ケタの大幅減少で、ピーク時(2001年:965件)の3分の1以下と、企業倒産全体の減少ペースを大きく上回るペースで減少している。言い換えれば、再建型の法的整理を選択する企業が減少しているということだ。大手企業を中心として“アベノミクス”による経営環境改善の恩恵を受けている企業がある一方、経営改善が進まない企業については再生の余地なく破産手続きを取らざるを得ないという状況が年々顕著になってきており、この状況は2015年も続くであろう。
■合併自治体の地方交付税特例分減額開始で地元企業への影響懸念
基礎自治体の行財政基盤確立のため、全国的に市町村合併が推進されたいわゆる「平成の大合併」により、市町村数は3232(1999年3月末)から1727(2010年3月末)にまで減少した。この合併を大きく後押ししたのが、手厚い財政措置だ。自治体は、合併後10年間、合併算定替により特例として合併前の旧自治体が受ける地方交付税の合計額を受け取ってきた。その特例分は2013年度の全国合計で約9500億円にものぼる。それが、合併後11年目以降5年間で新自治体単位での算定(一本算定)に移行する。つまり、特例分が順次減額されるということである。ある自治体の試算によれば「一本算定に移行した場合、2割以上地方交付税が減少する」という。
特例分の減額により自治体の財源先細りが懸念されている。建設事業費削減などでの対応が想定され、公共工事の約3分の1は市町村発注のものであることを踏まえれば、地元企業に影響を与える可能性が高いと言えよう。2015年度は、2004年度(合併関係市町村数826)に合併した自治体に対する特例分の減額が始まる年。翌年は、さらにピークとなった2005年度(同1025)合併自治体の減額が始まる。総務省は“新たな財政需要”を算定に反映させるなどして、激変緩和の追加措置を2014年度から開始しているが、特例分が大幅に減少することに違いはない。地方の中小零細企業は、公共工事、公共サービス付随事業に依存した経営から脱却できなければ、仕事先細り懸念を抱えながらの経営を強いられてしまう。
■原材料費・労務費高騰のなか、暫定リスケ中の企業は正念場をむかえる
2014年の企業倒産件数は、9180件となり2006年(9351件)以来8年ぶりに1万件を下回った。復興需要をはじめとする公共工事の増加、消費税率引き上げ前の駆け込み工事などを受け、建設業の倒産が大幅に減少(前年比20.8%減)したことが大きい。もちろん、中小企業金融円滑化法、および同法期限到来後の資金繰り支援継続により、業種を問わず経営不振に陥っていた多くの中小零細企業が資金繰り破綻を回避しているということもある。
ただし、2015年は、金融円滑化法の出口戦略として実施されていた暫定リスケを通して、立ち直っているか否かを見極められる年となる企業が多いとみられる。暫定リスケは、本格的な再生計画を作成する準備段階として「3年程度の暫定計画+3年間のリスケ」を実施しているもの。暫定期間後には本格的な再生計画の実行を求められることから、期間後に向けて正念場をむかえる企業が多いということである。また、足元をみれば、原材料費高騰、労務費高騰などのコスト上昇問題が中小零細企業に重くのしかかっている。さらに今年は、地域金融機関の再編を通して、資金調達環境が変化する可能性がある。2014年は1万件割れとなった企業倒産件数であるが、2015年はこうした倒産増加要因をもにらみながら、一進一退で推移するものとみられる。

