倒産件数は708件、4カ月連続の前年同月比増加
負債総額は1596億2200万円、2カ月連続の前年同月比増加
倒産件数 | 708件 |
|---|---|
前年同月比 | +12.9% |
前年同月 | 627件 |
負債総額 | 1596億2200万円 |
|---|---|
前年同月比 | +110.8% |
前年同月 | 757億3800万円 |
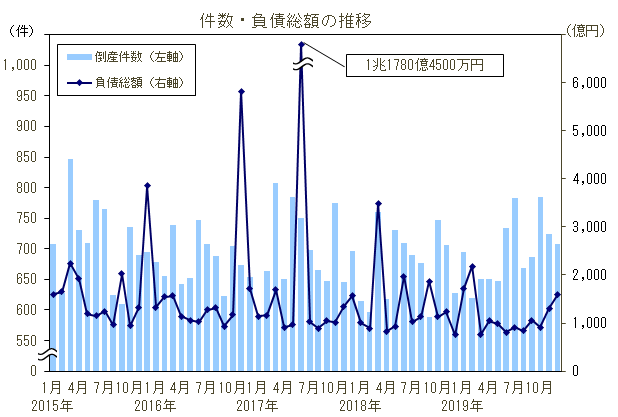
主要ポイント
- ■倒産件数は708件(前年同月比12.9%増)と、4カ月連続の前年同月比増加
- ■負債総額は、(株)AWH(旧:(株)淡島ホテル、負債約400億円、破産)や(株)AIコーポレーション(旧:(株)T.F.K、負債約194億6330万円、民事再生)など負債100億円規模の倒産が3件発生したことを受け、前年同月比110.8%増の1596億2200万円
- ■業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を上回った。なかでも、小売業(162件、前年同月比20.0%増)は競合激化や消費者の外食離れの影響を受け、飲食料品小売(28件、同12.0%増)や飲食店(64件、同30.6%増)などで増加。サービス業(172件、同15.4%増)は、ソフトウェア業(17件)が前年同月の2.9倍に増加し、業種全体を押し上げた
- ■主因別に見ると、「不況型倒産」の合計は563件、構成比79.5%を占める
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は420件、構成比59.3%を占める。また、負債1億円以上の倒産(186件)は前年同月比24.0%増となり、件数全体を押し上げた
- ■地域別に見ると、9地域中6地域で前年同月を上回った。なかでも、東北(32件、前年同月比88.2%増)は飲食店などの小売業で増加が目立った。関東(259件、同17.2%増)は、東京都で建設業、製造業などが大幅増となり、全体を押し上げた
- ■負債トップは、(株)AWH(旧:(株)淡島ホテル、静岡県、破産)の負債約400億円
調査結果
■件数・負債総額
2年ぶりの前年比増加
倒産件数は708件(前年同月比12.9%増)と、4カ月連続で前年同月を上回った。
負債総額は、(株)AWH(旧:(株)淡島ホテル、負債約400億円、破産)や(株)AIコーポレーション(旧:(株)T.F.K、負債約194億6330万円、民事再生)など負債100億円規模の倒産が3件発生したことを受け、前年同月比110.8%増の1596億2200万円となった。
■業種別
小売業、サービス業など5業種で前年同月比増加
業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を上回った。なかでも、小売業(162件、前年同月比20.0%増)は競争激化や消費者の外食離れの影響を受け、飲食料品小売(28件、同12.0%増)や飲食店(64件、同30.6%増)などで増加。サービス業(172件、同15.4%増)は、ソフトウェア業(17件)が前年同月の2.9倍に増加し、業種全体を押し上げた。
一方、運輸・通信業(21件)は前年同月と同数、不動産業(23件、前年同月比8.0%減)は唯一前年同月を下回った。
■主因別
「不況型倒産」は563件、構成比は79.5%
主因別に見ると、「不況型倒産」の合計は563件(前年同月比12.2%増)となり、4カ月連続で前年同月を上回った。構成比は79.5%(同0.6ポイント減)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
負債5000万円未満の構成比59.3%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は420件、構成比は59.3%を占めた。また、負債1億円以上の倒産(186件)は前年同月比24.0%増となり、件数全体を押し上げた。
資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人事業主含む)の倒産が449件(前年同月比6.7%増)、構成比は63.4%を占めた。
■地域別
9地域中6地域で前年同月比増加
地域別に見ると、9地域中6地域で前年同月を上回った。なかでも、東北(32件、前年同月比88.2%増)は飲食店などの小売業(9件)で増加が目立った。関東(259件、同17.2%増)は、東京都(146件、同29.2%増)で建設業(21件)、製造業(24件)などが大幅増となり、全体を押し上げた。近畿(180件、同11.8%増)は、飲食料品小売(10件)や飲食店(28件)、衣服などの身のまわり品小売(7件)など、小売業を中心に増加した。
一方、北海道(17件、前年同月比5.6%減)、北陸(13件、同7.1%減)、中国(26件、同13.3%減)の3地域は前年同月を下回った。
■態様別
「破産」は645件、構成比は91.1%
態様別に見ると、破産は645件(構成比91.1%)、特別清算は18件(同2.5%)となった。民事再生法は45件(同6.4%)、このうち個人事業主による小規模民事再生が30件を占めた。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは42.5、3カ月連続で悪化
2019年12月の景気DIは前月比1.1ポイント減の42.5となり、3カ月連続で悪化した。
12月の国内景気は、企業および消費活動が停滞し、年末需要が例年と比べて低迷したことが響いた。世界経済の減速を背景とした輸出減少や設備投資意欲の減退から製造業を中心に景況感の悪化が続き、荷動きの停滞や経費削減の動きなどへとつながった。また消費税率引き上げによる消費低迷が、住宅関連を含め幅広い業種へ悪影響を及ぼした。暖冬傾向や燃料価格の上昇などもマイナス要因となった。他方、公共工事の増加基調や、世界経済における懸念が後退したことによる日経平均株価の上昇は好材料となった。 国内景気は、一部で好材料もあるものの、後退局面に入っているとみられる。
緩やかな後退が見込まれ、海外情勢の変化に注視を要する
今後は、米中貿易摩擦や英EU離脱に向けた動き、中東地域での地政学的リスク、近隣国の動向などが、日本経済に与える影響を注視する必要がある。国内では、消費税率の引き上げで落ち込んだ個人消費が、緩やかながらも持ち直していくと見込まれる。海外経済の減速を受け輸出の減少が続く一方、設備投資は省力化需要などが寄与し底堅く推移すると予想される。また人手不足や輸送費が企業経営に重荷となるであろう。一方で補正予算実行による公共投資、東京五輪による消費マインド上昇やインバウンド拡大が期待される。 今後の国内景気は緩やかな後退が見込まれるなか、海外情勢の変化が国内景気へ及ぼす影響を注視する必要がある。
今後の見通し
■倒産件数は2年ぶり増、粉飾発覚による倒産が続発
2019年1~12月の倒産件数(8354件、前年比3.6%増)は、小売業(1945件、同7.0%増)の倒産が件数全体を押し上げたことなどから、2年ぶりの前年比増加となった。昨年10月には5年半ぶりに消費税率が引き上げられ、消費者のさらなる節約志向の高まりも懸念されるなか、飲食店の倒産(732件、同12.1%増)は過去最多を記録。地域人口の減少などから食品スーパー、飲食料品小売のほか、病院、診療所などの医療機関でも倒産が増加した。製造業は10年ぶりに増加に転じ、建設業は前年比横ばいで連続減少が10年でストップした。また、負債総額は1兆4135億8500万円と、負債1000億円超の倒産が1件にとどまったことなどで過去最小を更新。2019年も小規模倒産が大半を占める傾向は続いたものの、負債1億円以上の件数(2047件、同4.2%増)が10年ぶりの増加に転じるなど、変化の兆しがみられた。
2019年は不適切な会計処理が発覚した企業による倒産事例が目立った。アパレルブランド「J.FERRY」展開の(株)リファクトリィ(5月、東京都)、子供服店「motherways」経営のマザウェイズ・ジャパン(株)(6月、大阪府)、飲食店経営の(株)ひびき(8月、埼玉県)など続発。融資エリアを拡大した地銀や信金など含め、20前後にもおよぶ複数金融機関から融資を受けた都市部の企業で、負債数十億円規模の倒産が相次いだ。
■事業承継問題の深刻化で「後継者難倒産」が過去最多
後継者不在による事業継続の断念などが要因となった後継者難倒産は2019年に460件発生。これまで最多だった2013年の411件を6年ぶりに更新し、負債総額は487億9200万円にのぼった。代表の体調不良などから経営意欲を失い事業継続を断念した企業や、後継者不在により当初廃業を予定していた企業でも、債務超過から倒産に追い込まれたケースなどが散見された。
全国銀行協会と日本商工会議所は2019年12月、2013年策定の「経営者保証に関するガイドライン」を補完するため、金融機関が事業承継時に新旧経営者へ保証を求める二重保証を原則禁止とする特則(今年4月より適用)を公表。今後は同ガイドラインが積極的に運用されることなどにより、円滑な事業承継が進むとみられるものの、後継者不在のまま業績不振が続く中小企業などは多く、今後の動向が注目される。
■国内外にリスク要因多く、倒産増加懸念強まる
金融機関から返済条件の変更等(リスケジュール)を受けながら、継続支援が困難となった企業などの返済猶予後倒産は、2019年に524件(前年比22.4%増)と6年ぶりの高水準となった。金融機関の収益環境が厳しさを増すなか、2019年12月には金融検査マニュアルが廃止されるなど、各金融機関は融資、支援に対するスタンスを変えざるを得なくなっている。2019年の民事再生件数(351件、同39.3%増)の増加などからも、スポンサー先選定などで早期再生を目指す動きの高まりがうかがわれ、事業の将来性を重視した支援姿勢の広がりがみられる。
今年4月からは約120年ぶりの見直しとなる改正民法(債権関係)が施行され、中小企業への融資における経営者以外の第三者個人保証について、第三者による保証意思確認手続き(公正証書作成)の徹底がルール化される。すでに2011年の金融庁による監督指針など受け、第三者個人保証は原則禁止にあることから、大きな混乱はないと想定されるものの、法制化により今後は零細企業や個人事業主の借入などに影響が出てくる可能性もある。
人件費や物流費、原材料費などの上昇や高止まりで、中小零細企業ほど負担感は強い。中東情勢の緊張の高まりによる原油価格への影響や、為替や株価動向も不安視され、各種リスク要因には引き続き注視を要する。今後の倒産件数は、人口や企業数の減少、産業構造の変化などとも相俟って、緩やかな増加トレンドを辿る可能性が高まっている。

