倒産件数は785件、14ヵ月連続の前年同月比減少
負債総額は1278億7900万円、4ヵ月連続の前年同月比減少
倒産件数 | 785件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲3.9% |
前年同月 | 817件 |
前月比 | +14.9% |
前月 | 683件 |
負債総額 | 1278億7900万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲32.5% |
前年同月 | 1895億800万円 |
前月比 | ▲7.1% |
前月 | 1376億7400万円 |
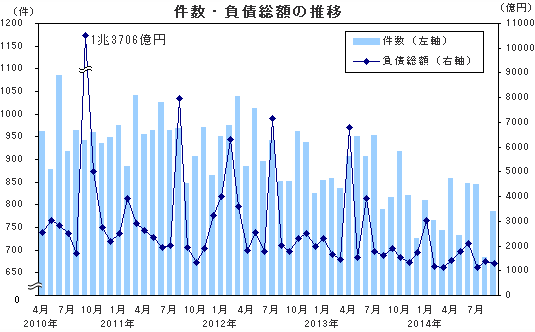
主要ポイント
- ■倒産件数は785件で、前月比は14.9%の増加となったものの、前年同月比は3.9%の減少となった。14ヵ月連続で前年同月を下回り、9月としては2007年(785件)以来7年ぶりに700件台にとどまった
- ■負債総額は1278億7900万円となり、前月比は7.1%、前年同月比も32.5%の減少と、4ヵ月連続で前年同月を下回った
- ■業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を下回り、なかでも建設業(前年同月比21.1%減)、運輸・通信業(同32.6%減)の2業種は前年同月比20%超の大幅減少となった
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の構成比は84.2%(前月81.6%、前年同月84.0%)と、前月を2.6ポイント、前年同月を0.2ポイントそれぞれ上回った
- ■「返済猶予後倒産」は46件(前年同月比24.6%減)判明
- ■負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は453件で、構成比は57.7%と23ヵ月連続で過半数を占め、2000年以降では2013年8月(58.2%)に次いで2番目の高水準となった
- ■地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を下回り、なかでも九州(49件、前年同月比31.0%減)、近畿(214件、同12.3%減)の2地域は、前年同月比2ケタの大幅減少となった。一方、北海道(19件、同11.8%増)、東北(33件、同10.0%増)など5地域は前年同月を上回った
- ■負債トップは、(株)キッチンファクトリー(愛媛県、破産)の50億円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は14ヵ月連続、負債総額は4ヵ月連続の前年同月比減少
倒産件数は785件で、前月比は14.9%の増加となったものの、前年同月比は3.9%の減少となった。14ヵ月連続で前年同月を下回り、9月としては2007年(785件)以来7年ぶりに700件台にとどまった。負債総額は1278億7900万円となり、前月比は7.1%、前年同月比も32.5%の減少と、4ヵ月連続で前年同月を下回った。
要因・背景
件数…公共工事の増加などを受け、近畿や九州など9地域中6地域で建設業が前年同月割れ
負債総額…負債100億円以上の大型倒産は発生せず、同10億円以上も23件の低水準
■業種別
ポイント7業種中4業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を下回り、なかでも建設業(153件、前年同月比21.1%減)、運輸・通信業(29件、同32.6%減)の2業種は前年同月比20%超の大幅減少となった。一方、小売業(150件、同7.9%増)、サービス業(154件、同10.8%増)、不動産業(33件、同37.5%増)の3業種は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1.建設業…災害復旧工事やインフラ整備の受注増加など受け、24ヵ月連続の前年同月比減少
- 2.消費税率引き上げの影響や、価格競争の激化もあり、小売業とサービス業がともに5ヵ月ぶりの前年同月比増加
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比84.2%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は661件(前年同月比3.6%減)となった。構成比は84.2%(前月81.6%、前年同月84.0%)と、前月を2.6ポイント、前年同月を0.2ポイントそれぞれ上回った。
要因・背景
- 1.「返済猶予後倒産」は46件(前年同月比24.6%減)判明
- 2.「不況型倒産」の構成比、小売業(93.3%、前年同月比9.8ポイント増)で増加目立つ
■倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比57.7%、過去10年で2番目の高水準
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は453件で、前年同月比3.7%の増加。構成比は57.7%と23ヵ月連続で過半数を占め、2000年以降では2013年8月(58.2%)に次いで2番目の高水準となった。一方、負債10億円以上の倒産は23件にとどまった。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が453件、構成比は57.7%を占めた。
要因・背景
- 1.負債5000万円未満の倒産、広告制作・代理や労働者派遣などのサービス業で増加が目立つ
- 2.大企業、中堅企業を中心に業績回復や資金繰り改善を受け、大型倒産の抑制状態続く
■地域別
ポイント9地域中4地域で前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を下回り、なかでも九州(49件、前年同月比31.0%減)、近畿(214件、同12.3%減)の2地域は前年同月比2ケタの大幅減少となった。一方、北海道(19件、同11.8%増)、東北(33件、同10.0%増)など5地域は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1.近畿は、建設業(前年同月比39.1%減)、製造業(同24.3%減)などで減少が目立ち、2ヵ月連続の2ケタ減
- 2.九州は、福岡県で小売業(前年同月比72.7%減)、建設業(同50.0%減)が大きく減少
■主な倒産企業
負債トップは、(株)キッチンファクトリー(愛媛県、破産)の50億円。加藤組土建(株)(北海道、破産)の40億100万円、東中国開発(株)(岡山県、民事再生法)の36億円が続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは45.1、アベノミクス効果にブレーキ、全国に波及
2014年9月の景気動向指数(景気DI:0~100、50が判断の分かれ目)は、前月比1.1ポイント減の45.1となり2ヵ月連続で悪化した。
『不動産』など一部の業界では改善傾向もみられたが、『製造』では消費税率引き上げ後も駆け込み需要による受注残が消化されてきた自動車関連が、ここにきて息切れ。生産量の減少が顕著に現れた。また、『運輸・倉庫』では製造業の減産や建設業界での工事遅れや入札不調などの影響を受けたほか、『小売』は実質所得の減少に対する家計の支出抑制もあり2ヵ月ぶりに悪化した。9月は為替レートが約6年ぶりの円安水準となり、原材料価格高騰などを通じた収益悪化の要因ともなった。
政策頼みの状況が強まるが悪材料も多く、効果は限定的
地域別にみると、『北海道』や『中国』『四国』など10地域中9地域が悪化した。これまでアベノミクス効果で景気上昇が顕著だった地方圏で景況感の悪化が急速に進むなか、同一域内で景況感が二分する状況が出てきた。また、夏季の豪雨や台風被害の影響が9月も続いた地域もあった。国内景気は、手持ちの受注残が減少するなかで、反動減の影響が生産減少や物流停滞につながりやすい状況となっており、景気の下押し圧力が続いている。今後は景気対策頼みの状況が強まるが、原材料価格上昇や人手不足など企業活動を抑制する悪材料も多く、その効果は限定的にとどまるとみられる。
今後の見通し
■急激な円安、経営リスクとして意識される
10月1日の東京外国為替市場では、一時リーマン・ショック以前の水準である1ドル110円台をつけた。8月に入ってから円安が急速に進み、わずか2ヵ月で約8円も円安方向に振れている。円安は、自動車メーカーをはじめとする輸出企業の利益を押し上げる一方、海外からの調達が前提となっている企業に対してはマイナスの影響を与える。「円安に振れたことで為替差損が発生したことに加え、中国における生産コストが上昇。多額の赤字を計上し行き詰まった企業」(婦人靴卸・小売)など、急激な円安で採算が悪化し倒産に至る企業も出てきた。
さらに、円安は原材料などの輸入価格上昇に繋がる。内需型の製造業や消費者に対する価格転嫁が難しい小売業では、利益の押し下げ要因となり得る。また、足元では生活必需品の値上げが相次いでいることから、4月の消費税率引き上げと相俟って、消費マインドの低下が警戒されるところだ。実際に「円安による原材料の調達コスト上昇で一段と採算が悪化」(めん類製造)など、製造業を中心としてコスト増加が倒産の一因となる企業倒産が散見され始めている。
こうした状況下、経済産業省は、10月2日付で同省関連の431団体に対し、下請事業者との取引に際して、原材料・エネルギーコスト増加分の適正な価格転嫁を求めた。中小企業・小規模事業者の収益がこれ以上圧迫されないようにするためだ。また、同時に公的金融機関に対し、中小企業向け融資について、返済猶予等の対応に努めるように要請するなど、資金繰り面からも中小企業を支援する。原材料・エネルギーコスト増加、そしてそれを引き起こす急激な円安は、経営上のリスクとして意識し対応していかなければならない。
■地域経済活性化と産業の新陳代謝を両睨み
安倍総理は第187回国会の所信表明演説で、地域活性化の成功事例をいくつもあげ、地方創生に注力していく方針を明確にした。この背景には、同演説で「人口減少や超高齢化など、地方が直面する構造的な課題は深刻」と述べたように、地方経済に対する将来的な危機感がある。もっとも、企業倒産件数をみれば、将来ではなくすでに、全体的な倒産減少局面(2014年度上半期は前年同期比10.7%の大幅減少)にあるにも関わらず、倒産が増加している地域が確認できる。
2014年度上半期の企業倒産件数を地域別にみると、9地域中7地域で前年同期を下回った。しかし、東北(185件、前年同期比5.1%増)、四国(95件、同6.7%増)の2地域は増加している。この2地域の倒産を業種別にみると、大幅に件数が増加しているのは共通して製造業であり、東北(36件)は前年同期比56.5%増、四国(16件)は同77.8%増である。地方の製造業では過剰債務を抱えている企業は珍しくない。また、2次請け、3次請けの製造業者においては、近年、得意先メーカーが生産拠点を海外へ移転することへの対応を迫られるケースも多い。
こうした企業は、“産業の新陳代謝”の流れのなかで変革を求められていると言える。地域経済活性化のためには、地域における各産業や個別企業の生産性向上が不可欠。赤字体質の企業や、構造的な経営課題を抱えている企業は、“塩漬け”や“先延ばし”といった小手先の延命策ではなく、抜本的な経営改善が急務となっている。政府は「日本産業再興プラン」として、地域のベンチャー企業支援策や、中小企業の競争力強化に向けた取り組みを推し進める方針だ。この地域活性化プラットフォームのなかで収益性・生産性を向上させ、抜本的な経営改善を果たす企業が出てくることが期待されている。地域活性化プロセスにおいて、2014年度下半期の企業倒産の推移は、その実行性を問うものといえ、減少が続く現状を変えていく方向性にあるものとみられる。

