倒産件数は609件、2015年最少を記録
負債総額は2021億6900万円、2カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数 | 609件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲22.4% |
前年同月 | 785件 |
前月比 | ▲2.6% |
前月 | 625件 |
負債総額 | 2021億6900万円 |
|---|---|
前年同月比 | +58.1% |
前年同月 | 1278億7900万円 |
前月比 | +109.5% |
前月 | 964億8500万円 |
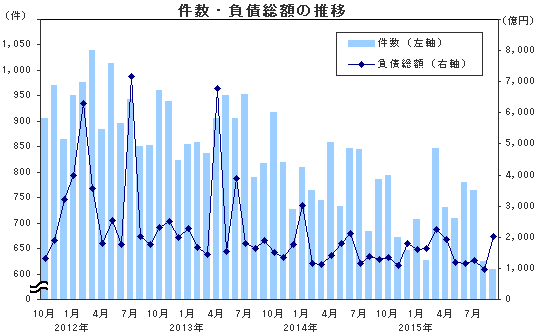
主要ポイント
- ■倒産件数は609件で、前年同月比22.4%の大幅減少となった。6カ月連続で前年同月を下回り、2005年4月(605件)以来の低水準で、2015年最少を記録した
- ■負債総額は2021億6900万円で、前年同月比58.1%の増加となり、2カ月ぶりに前年同月を上回った
- ■業種別に見ると、建設業(103件、前年同月比32.7%減)、製造業(85件、同28.0%減)など7業種中6業種で前年同月を下回った
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の構成比は85.4%と、前月を1.0ポイント下回ったものの、前年同月を1.2ポイント上回った
- ■負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は360件(前年同月比20.5%減)で、構成比は59.1%と、前年同月を1.4ポイント上回った
- ■地域別に見ると、関東(225件、前年同月比16.4%減)、近畿(147件、同31.3%減)など9地域中8地域で前年同月を下回り、なかでも東北(18件)は前年同月比45.5%の大幅減少となった
- ■負債トップは、東証1部上場の第一中央汽船(株)(東京都、民事再生法)で1196億800万円。負債1000億円以上の大型倒産がエヌ・エス・アール(株)(東京都、2014年1月)以来1年8カ月ぶりに発生した
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は今年最少、負債総額は2カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数は609件で、前年同月比22.4%の大幅減少となった。6カ月連続で前年同月を下回り、2005年4月(605件)以来の低水準で、2015年最少を記録した。負債総額は2021億6900万円で、前年同月比58.1%の増加となり、2カ月ぶりに前年同月を上回った。
要因・背景
件数…建設業(103件)が2000年以降最少を記録したほか、製造業、卸売業などで大幅減
負債総額…東証1部上場の第一中央汽船(株)(東京都、負債1196億800万円)が民事再生法の適用を申請し、負債1000億円以上の大型倒産がエヌ・エス・アール(株)(東京都、2014年1月)以来1年8カ月ぶりに発生
■業種別
ポイント7業種中6業種で前年同月比減少
業種別に見ると、建設業(103件、前年同月比32.7%減)、製造業(85件、同28.0%減)など7業種中6業種で前年同月を下回った。なかでも建設業は2015年1月(117件)を下回り、2000年以降最少となるなど、5業種で前年同月比の減少率が2ケタとなり、大幅に減少した。一方、運輸・通信業(32件、同10.3%増)は唯一前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 建設業…土木工事や建築工事のほか、内装工事や電気通信工事などで大幅減
- 2. 製造業…食料品や繊維など一部で増加も、金属製品(9件、前年同月比30.8%減)や機械(11件、同57.7%減)などで減少目立つ
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比85.4%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は520件(前年同月比21.3%減)となった。構成比は85.4%(前月86.4%、前年同月84.2%)と、前月を1.0ポイント下回ったものの、前年同月を1.2ポイント上回った。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、 業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1.「返済猶予後倒産」は29件(前年同月比37.0%減)判明
- 2.「円安関連倒産」は19件(前年同月比38.7%減)判明、集計開始(2013年1月)以降で初の前年同月比減少
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比59.1%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は360件(前年同月比20.5%減)で、構成比は59.1%と、前年同月を1.4ポイント上回った。一方、負債100億円以上の倒産は2件、うち同1000億円以上が1件発生した。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が364件となり、構成比は59.8%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産、不動産業(7件)が前年同月比65.0%の大幅減
- 2. 負債1000億円以上の大型倒産が2014年1月以来1年8カ月ぶりに発生
■地域別
ポイント9地域中8地域で前年同月比減少
地域別に見ると、関東(225件、前年同月比16.4%減)、近畿(147件、同31.3%減)など9地域中8地域で前年同月を下回り、なかでも東北(18件)は前年同月比45.5%の大幅減少となった。一方、北海道(20件、同5.3%増)は唯一前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 東北は、宮城県を中心に製造業(1件、前年同月比83.3%減)、小売業(3件、同62.5%減)、サービス業(1件、同80.0%減)などで減少目立つ
- 2. 地方圏では、北海道や九州の建設業、四国の製造業、中国の小売業などで増加目立つ
- ■主な倒産企業
負債トップは、東証1部上場の第一中央汽船(株)(東京都、民事再生法)の1196億800万円。以下、ヴィンテージリゾート(株)(山梨県、破産)の109億円、協和産業(株)(大阪府、破産)の35億円がこれに続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは44.6、国内景気は2極化進む
2015年9月の景気DIは前月比0.5ポイント減の44.6となり2カ月連続で悪化した。
9月は、台風などによる天候不順に加えて、国内の設備投資が軟調に推移したほか、国内自動車生産の低迷や中国経済の減速により、工作機械の受注が大幅に減少した。さらに、関連する製造業や卸売業へと波及していったことで、全体の景況感を押し下げる要因となった。また、公共工事は依然として減少が続いているうえ、地域により増減傾向が異なるため、減少した地域の経済を悪化させる一因となった。他方、ガソリンや軽油価格の低下でコスト負担が緩和したことや、住宅着工戸数の増加により建設業が改善したことで資材運搬の荷動きが上向いたこともあり、『運輸・倉庫』は3カ月連続で改善した。国内景気は、国内外の不安定な経済状況を受け生産活動に弱含みがみられることに加え、集中豪雨により経済が下押しされ、二極化が進んでいる。景気好転への材料が乏しいものの、年明け以降に徐々に上向く
8月下旬以降の株価急落の影響に対する不透明感が増している。さらに、中国経済の先行き懸念にともなう輸出減少や設備投資意欲の低下のほか、米国の金利引き上げ懸念も加わり、しばらくは停滞した状態で推移するとみられる。しかしながら、ひっ迫する労働需給は雇用者所得を増加させ、個人消費を押し上げる要因となる。公共工事の発注増加が見込まれるが、景気の行方は来年の参議院選挙に向けた景気対策次第ともいえよう。また、2014年4月の消費税率引き上げ時にみられたように、次回の税率引き上げにともなう駆け込み需要も住宅などを中心に 2016年度初めから発生すると予測される。今後の国内景気は、好転への材料が乏しいものの、年明け以降に徐々に上向いていくとみられる。
今後の見通し
■大企業の再編や事業再構築、取引先企業へ波及
9月29日、東証1部上場の第一中央汽船が、東京地裁へ民事再生法の適用を申請した(負債1196億800万円、10月5日付けで再生手続き開始決定)。2015年度における上場企業倒産としては2件目となった。過去の船舶投資負担や海運市況の悪化が倒産原因としてあげられたが、注目されたのは取引先企業の再編による影響だ。同社は住友金属工業と長く取引関係にあり、2012年に新日本製鐵と住友金属工業が合併し新日鐵住金が誕生したことでグループ内の海運会社との統合の可能性が注目されていた。しかし、鉄鋼減産による輸送需要の減少や海運市況のさらなる悪化もあり、最終的に統合案は見送られたようだ。
近年、国内外の市場環境の変化にともない、企業間をまたぐ事業統合や再編は珍しくない。東芝やシャープなど大手電機各社も大規模な事業再構築に取り組んでおり、その過程で、取引関係の見直しや事業所の移転、閉鎖などが行われた場合、取引先や地域経済への影響は免れない。依存度の大きい一次下請や二次下請、財務内容が弱体化している取引企業などへの影響には、今後注視していく必要があるだろう。
■企業倒産のトレンドは当面は低水準、金融支援は継続
2015年度上半期の企業倒産件数は4217件と前年同期比11.2%の大幅減少、負債総額は8485億8700万円と同7.2%の減少となった。前期比でもそれぞれ倒産件数(1.8%減)、負債総額(12.7%減)ともに減少しており、企業倒産は依然として減少傾向が続いている。
業種別では、全ての業種が前年同期比で減少を示すなか、建設業803件(前年同期比17.0%減)、卸売業649件(同11.2%減)、運輸・通信業161件(同27.1%減)などは減少率2ケタ台を記録した。倒産が低水準で推移する背景には、金融機関による支援の維持が大きい。
金融庁が9月18日に発表した平成27事務年度の「金融行政方針」では、重点政策が市場の公正性・透明性、金融システムの健全性の維持やIT化や国際化への対応などとなっており、不良債権処理方針や中小企業への融資および支援姿勢は大きく変わらないとみるべきであろう。
■内需セクターは安定も、新たなリスクに注目
今春以降食品の値上げが続き、消費者の生活防衛意識は根強いながらも、百貨店、スーパー、コンビニエンスストアなど主要流通業界の売り上げ推移は堅調で、ホテル・旅館などサービス分野もインバウンド需要の取り込みが寄与し、国内需要は底堅い動きが続いている。有効求人倍率(季節調整値)もバブル期並みの高水準が続くなど、雇用環境も改善しており、ペースは緩やかながら景気回復下にあり、倒産が大きく増加に転じる材料に乏しい。少なくとも年内いっぱいは低水準傾向が続くことが見込まれる。
ただし、懸念材料はゼロではない。経済産業省が発表した8月の鉱工業生産指数(速報値、季節調整済)は97.0と前月比で0.5%下回り、2カ月連続で前月を下回るなど、中国経済の減速の影響を受け工作機械や産業機械で生産活動がやや弱まっている。今後、中国向けの生産や輸出が減少すると幅広い業種への波及が懸念され、チャイナリスクを含めた新興国を中心とする海外経済の先行きの不透明感は払拭されていない。
倒産の低水準傾向が続くなか、9月に公表された安倍政権の『新三本の矢』では「希望を生み出す強い経済」が掲げられ、その具体的政策が期待されている。一方で、前述のとおり中国経済の減速やそれに伴う世界的金融の混乱懸念、国内では人手不足や円安の定着によるコスト高に加えて、公共工事の発注が前年度を下回る状況も続いており、これらリスク要因の動向次第では企業倒産が増加に転じる可能性も否定できない。

