倒産件数、3年ぶりに増加に転じる
手厚い資金繰り支援終了、前年度比14.9%増
倒産件数 | 6799件 |
|---|---|
前年度比 | +14.9% |
前年度 | 5916件 |
負債総額 | 2兆3385億9100万円 |
|---|---|
前年度比 | +97.7% |
前年度 | 1兆1828億7100万円 |
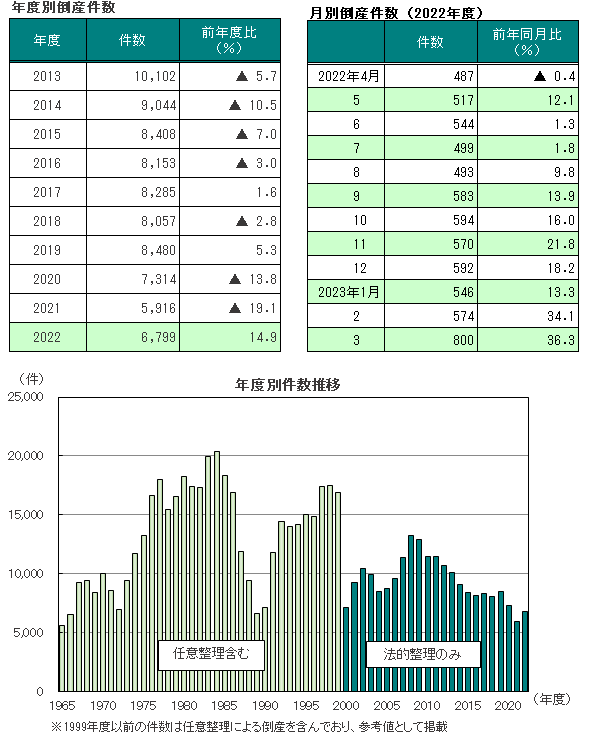
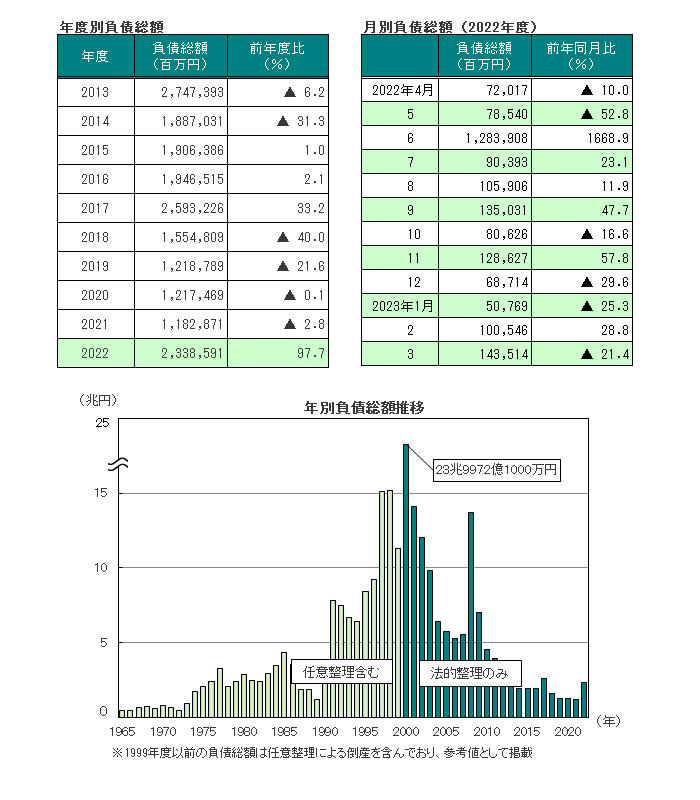
主要ポイント
- ■2022年度の倒産件数は6799件(前年度5916件、14.9%増)となり、2019年度以来3年ぶりに増加した。2022年5月から2023年3月まで11カ月連続で前年同月を上回り、前年度から800件以上の大幅増となったのは2008年度以来14年ぶり
- ■負債総額は2兆3385億9100万円(前年度1兆1828億7100万円、97.7%増)と、2022年6月に発生したマレリホールディングス㈱(埼玉、民事再生法、負債1兆1856億2600万円)が総額の50.7%を占め、全体を押し上げた。2兆円台となるのは2017年度以来5年ぶり
- ■業種別にみると、14年ぶりに全業種で前年度を上回った。最多は『サービス業』(前年度1427件→1699件、19.1%増)で、『小売業』(同1287件→1315件、2.2%増)が続き、コロナ関連の倒産が目立った
- ■主因別にみると、『不況型倒産』の件数は5249件、「経営者の病気、死亡」は過去最多更新
- ■態様別にみると、「破産」は6341件で、全体の93.3%を占めた
- ■規模別にみると、負債「5000万円未満」の倒産は3927件、零細規模で大幅増加
- ■業歴別にみると、業歴10年未満の新興企業は14年ぶりに400件以上増加
- ■地域別にみると、『四国』除く全地域で前年度を上回った。『北海道』(前年度142件→206件、45.1%増)は、全地域で唯一コロナ禍直前の2019年度(201件)を超えた。『中部』(同789件→956件、21.2%増)は食品関連産業で増加が目立った
調査結果
■業種別
14年ぶりに全業種で増加 『サービス業』『小売業』などコロナ関連目立つ
業種別にみると、2008年度以来14年ぶりに全業種で前年度を上回った。最多は『サービス業』(前年度1427件→1699件、19.1%増、負債1859億5200万円、1648億5000万円減)で、『小売業』(同1287件→1315件、2.2%増、同1583億5300万円、225億2700万円増)が続き、コロナ関連の倒産が目立った。そのほか、『建設業』(同1084件→1291件、19.1%増、同1296億4400万円、227億2200万円増)や、『運輸・通信業』(同273件→371件、35.9%増、同834億5300万円、396億3800万円増)は前年度比30%以上の大幅増となった。
業種を詳細にみると、『サービス業』では、特に「老人福祉事業」(前年度76件→131件)で大幅に増加し、2000年度以降で最多となった。『建設業』では、品不足の影響を受けた「設備工事」(同220件→305件)などで増加が目立った。『運輸・通信業』は、2024年問題が迫るトラック運送など「道路貨物運送」(同183件→255件)で大幅増、2014年度以来8年ぶりに200件台を記録した。
■倒産主因別
『不況型倒産』の件数は5249件、「経営者の病気、死亡」は過去最多を更新
主因別にみると、『不況型倒産』は5249件(前年度4574件、14.8%増)となった。構成比は77.1%(対前年度0.2ポイント減)を占め、3年ぶりに前年度を上回った。
「販売不振」の5148件(前年度4505件、14.3%増)が最も多く、構成比は75.7%(対前年度0.5ポイント減)を占めた。「業界不振」(前年度35件→60件、71.4%増)は、2008年度以来の前年度比50%超を記録した。「経営者の病気、死亡」(同275件→277件、0.7%増)は、過去20年間で最も多かった2021年度を超え、過去最多を更新した。このほか、「売掛金回収難」(同14件→30件、114.3%増)は倍増した。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■倒産態様別
「破産」は800件以上増加、リーマン・ショック時以来の増加幅
倒産態様別にみると、『清算型』倒産の合計は6590件(前年度5749件、14.6%増)となり、構成比は97.0%(対前年度0.2ポイント減)を占めた。『再生型』倒産は209件(同167件、25.1%増)発生し、『清算型』『再生型』ともに3年ぶりに前年度を上回った。
「破産」は6341件(前年度5454件、16.3%増)が最も多く、リーマン・ショック時の2008年度以来14年ぶりに800件以上の増加を記録した。会社分割など第二会社方式で多用される「特別清算」は249件(同295件、15.6%減)で2年連続の減少となった。
このほか、「民事再生法」は206件(前年度165件、24.8%増)発生し、うち136件を個人事業主が占めた。「会社更生法」は3件(同2件、50.0%増)だった。
■規模別
負債「5000万円未満」の倒産は57.8%、零細規模が目立つ
負債規模別にみると、「5000万円未満」の倒産は3927件(前年度3546件、10.7%増)、構成比57.8%を占め最も多く、零細規模が目立った。次いで「5億円未満」が1416件(同1173件、20.7%増)、「1億円未満」が1061件(同832件、27.5%増)で続いた。
資本金規模別では、『1000万円未満(個人事業主含む)』の倒産は4623件(前年度3953件、16.9%増)発生し、全体の68.0%を占めた。
■業歴別
業歴10年未満の新興企業は400件以上増加、14年ぶりの増加幅
業歴別にみると、業歴「30年以上」が2259件(前年度2037件、10.9%増)で最も多く、全体の33.2%を占めた。このうち、老舗企業(業歴100年以上)の倒産は71件(同62件)発生し、3年ぶりの増加となった。
「3年未満」(前年度266件→352件、32.3%増)、「5年未満」(同407件→475件、16.7%増)、「10年未満」(同876件→1182件、34.9%増)を含めた業歴10年未満の新興企業(同1549件→2009件、29.7%増)は、2019年度以来3年ぶりに増加した。新興企業全体で前年度から400件以上増加したのは、2008年度以来14年ぶり。また、新興企業を業種別にみると、サービス業(同473件→640件、35.3%増)が最多。特に娯楽業(同23件→48件)や旅館・その他宿泊所(同7件→18件)などで増加が目立った。
■地域別
『四国』除く全地域で前年度比増、『北海道』はコロナ禍直前の2019年度超え
地域別にみると、『四国』を除く全地域で前年度を上回った。『北海道』(前年度142件→206件、45.1%増)は、全地域で唯一コロナ禍直前の2019年度(201件)を超えた。『中部』(同789件→956件、21.2%増)は、食料品・飼料・飲料製造(同15件→28件)や飲食店(同73件→86件)など食品関連産業で増加が目立った。以下、増加率順では、『中国』(同237件→280件、18.1%増)、『東北』(同286件→336件、17.5%増)の順となった。このほか、『近畿』(同1482件→1694件、14.3%増)は全府県で増加し、2008年度以来14年ぶりに200件以上の増加。『関東』(同2196件→2457件、11.9%増)は、3年ぶりに増加となった。
一方、唯一減少した『四国』(前年度116件→114件、1.7%減)は、前年度と比べて2件少なく、ほぼ横ばいに近かった。
注目の倒産動向-1
■「建設業」倒産動向
建設業の倒産が急増、3年ぶり増加 経営を襲う「三重苦」
工期長期化・人手不足・資材高で、中小建設の苦境鮮明に
2022年度(22年4月-23年3月)の建設業における倒産は1291件だった。歴史的低水準が続いた20-21年度に比べて大幅に増加したほか、単月でも23年3月(155件)は、16年8月(154件)以来約6年半ぶりに150件を超え、急増傾向が鮮明となった。
コロナ禍での商談や工事の遅れといったマイナスの影響があったものの、コロナ融資をはじめ政府の資金繰り支援策が奏功し、倒産件数は2021年度に過去20年で最少を更新するなど、記録的な低水準が続いた。他方で、鉄骨や木材、給湯器をはじめとした住設機器など多岐にわたる建設資材の品不足や価格の急騰により、工事原価が上昇した。こうした「物価高」を要因とした倒産は徐々に割合が高まり、22年7月の建設業倒産では1割超が物価高を要因としたものだった。また、22年度の人手不足倒産全体のうち4件中1件は建設業が占めるなど人手不足も深刻化しており、建築士や施工管理者など業務遂行に不可欠な資格を持つ従業員の離職で事業運営が困難になったケースも目立った。その結果、建設現場で「資材が来ない」「予算よりも価格が高い」「人がいない」などの常態化により、工期も「ずれ込む」悪循環が発生しやすい環境となり、中小建設業の倒産を押し上げる要因となっている。
建設業では今後も、国交省直轄工事ではじまった総合評価落札方式の「賃上げ加点」などをはじめ、人手確保目的など内外からの賃上げ圧力に晒される。コロナ禍で多くが導入したゼロゼロ融資の返済もピークを迎えるなか、各種コストの増加分を十分に価格へと転嫁することができない中小零細規模の企業を中心に、倒産リスクが高まるだろう。
■コロナ融資後倒産
2022年度は445件発生、前年度から倍増し過去最多
「コロナ融資後倒産」は、2022年度において445件(前年度216件、106.0%増)発生した。月次ベースで2023年3月が過去最多を更新するなど、前年度から倍増した。実際の融資額が判明した約220社のコロナ融資借入額平均は約5900万円だった。コロナ融資損失総額は推計413億1453万円にのぼり、国民一人当たり約330円の負担が既に発生している計算になる。
■人手不足倒産
2022年度は146件発生、3年ぶりに増加 「2024年問題」運輸業は大幅増
「人手不足倒産」は、2022年度において146件(前年度118件、23.7%増)発生した。コロナ禍前となる2019年度(199件)以来、3年ぶりに前年度を上回った。業種別では「建設業」(41件)「運輸業」(26件)で多く、特に「運輸業」は前年から2倍以上増加し、残り1年に迫った「2024年問題」を前に人手不足による悪影響が深刻化している。
注目の倒産動向-2
■「脱毛サロン」倒産動向
「通い放題」トラブル相次ぐ脱毛サロン、倒産が過去最多に
年度内には業界大手「脱毛ラボ」が破綻、一般利用者3万人に被害
「通い放題」などの契約でトラブルが相次ぐ脱毛サロンの倒産が急増している。医療行為を伴わないエステ脱毛を専門とする「脱毛サロン」の倒産は、2022年度(22年4月-23年3月)に7件判明。前年度の1件から大幅に増加して過去最多を更新したほか、年度内には「脱毛ラボ」など大手脱毛サロンが経営破綻、3万人の一般利用者が被害を受けた。ただ、水面下の私的整理や廃業などを含めれば、実際はより多くの脱毛サロンが淘汰されたとみられる。
脱毛サロン業界では、医療レーザー脱毛に比べて施術難易度が低いことや、1台100万円以下の安価で高性能な脱毛マシンなどの普及から参入障壁が低く、異業種からの参入が相次いでいた。また、会員獲得を目的に著名人を起用した大規模な広告、「月額1万円以下」「通い放題」など施術費用の低価格化で利用者が増加。女性だけでなく男性専用の脱毛サロンなど新たな事業領域の開拓も進んだほか、若者を中心にSNS映えなど美容意識の高まり、脱毛のステータス化も背景に一定の需要を獲得し、「脱毛サロン専門市場」は成長を続けてきた。
そうした一方で、店舗の急拡大や利用者急増で施術スタッフの確保が追い付かず「予約が取れない」などの契約トラブルを抱えて利用者の信用を失い、解約が増加するケースが少なくない。新規の会員獲得も同業他店との顧客獲得競争で厳しく、低価格の施術費用も重なって広告宣伝費や固定費などの販管費が重くのしかかり、資金繰りが急激に悪化した脱毛サロンも過去に複数発生している。安さを強調した顧客の目を引くための広告や、提供サービスの質など、利用者保護に立った脱毛サロンのありかたが問われている。
■後継者難倒産
2022年度は487件発生、年度ベースで過去最多
後継者難倒産は、2022年度において487件(前年度476件、2.3%増)発生し、年度ベースで過去最多を更新した。2022年の後継者不在率が60%を下回り過去最低を更新するなか、事業承継を円滑に進められなかった中小企業の倒産が増加している。特に、「代表者の病気・死亡」が直接的な原因となった倒産は全体の半数を占め、高止まりの傾向が続いた。
■物価高(インフレ)倒産
2022年度は463件発生 前年の3.4倍に急増
物価高(インフレ)倒産は、2022年度において463件(前年度136件、240.4%増)発生し、前年度の3.4倍に急増、過去最多を更新した。業種別にみると、原材料高騰が続く「製造業」と「建設業」が90件を超えた。前年度からの増加が最も大きいのは、燃料費高騰などの要因を受けたトラック運送業など「運輸業」で、前年度比4.6倍に急増した。
今後の見通し
■企業倒産「潮目」が変化 22年度は3年ぶり増加、コロナ融資返済本格化前に
2022年度の倒産件数は前年度を883件上回る6799件が発生し、3年ぶりに増加した。22年5月以降、23年3月まで11カ月連続して前年同月を上回っており、増加期間はリーマン・ショック後の08年6月-09年8月(15カ月連続)にせまった。特に3月は800件(前年同月587件、36.3%増)となり、長く続いた月間500件台の水準を大幅に超えて単月としてはコロナ禍直後の20年7月以来2年8カ月ぶり、3月としては17年以来6年ぶりに800件台を突破した。23年度半ばと想定されるコロナ融資の返済本格化を前に足元の企業倒産は増加基調を強めており、倒産動向の“潮目”が明らかに変わりつつある。
2022年度の倒産動向の特徴は、手厚い資金繰り支援が終了したところに「物価高(インフレ)」「人手不足」「コロナ融資」「円安」など四重・五重の苦境が襲い、事業継続を断念した中小企業が多い点だ。「物価高倒産」や「コロナ融資後倒産」はそれぞれ前年度から急増、「人手不足倒産」も建設や運輸業を中心に146件判明し3年ぶりの増加となった。
■負債総額は5年ぶり2兆円台 倒産の7割が中小零細
負債総額は2兆3385億9100万円となり、2021年度(1兆1828億7100万円)のほぼ2倍に膨らんだ。1兆円を超える負債を抱えて経営破綻した自動車部品製造のマレリHD(22年6月民事再生)、有機ELディスプレイ製造のJOLED(23年3月同)など、負債100億円を超える大型倒産が12件発生し、4年ぶりに前年度を上回った。2022年度の負債総額はエアバッグ製造大手の「タカタ」(17年6月民事再生)が破綻した17年度(2兆5932億2600万円)以来、5年ぶりに2兆円台を超えた。企業倒産の7割超が負債1億円に満たない中小・零細企業で占める状況に変わりはないものの、20年度をピークにその割合は低下している。一方、負債1~10億円クラスの割合は高まり、中堅クラスの倒産も増加の動きが強まっている。
■2023年度は「ゾンビ」の動向注視 抜本的再生が必要な企業は3万社規模
帝国データバンクの推計では、稼いだ利益で借入金の利子を支払えない、国際決済銀行(BIS)の定義に基づく「ゾンビ企業」の数は、2021年度に全国18.8万社にのぼる。20年度(推計16.6万社)から2年連続で増加するなど増加傾向が続いており、自社の経営体力に見合わない過大な借入金を背負った中小企業の出口戦略が早急に求められている。
実際、推計した18.8万社のうち、経常赤字など「収益力改善」が課題の企業(=経常赤字)はゾンビ全体の6割に上る。また、「過剰債務解消」や、債務超過など「資本力の改善」が課題の企業もそれぞれ4割前後を占め、これら3つの課題がすべて該当する企業も約2割の3.3万社を占めた。これらゾンビはすぐに倒産するわけではないが、年間倒産件数の約5倍に匹敵する規模の企業が“潜在的な倒産リスク”を抱えていることを示している。コロナ融資の返済本格化や今後予想される金利上昇局面などを踏まえると、これらの企業群が事業継続を断念し、倒産件数を押し上げる影響力は過小評価できない。
■企業倒産、コロナ前水準への到達視野に緩やかな増加局面続く
国内景気はアフターコロナに向けた前向きな動きが加速している。企業の景況感を示すTDB景気動向指数(DI)も、2022年度中は期初→期末にかけて3.1ポイント改善し、17年度(+3.9)以来5年ぶりの景気改善幅を記録した。こうした局面では、「景気の変わり目に倒産が増える」と謂われるように、仕入増や人件費増、設備増強に伴う運転資金需要に資金調達が追い付かない「黒字倒産」の発生も懸念され、今後の倒産増加を後押しする可能性がある。コロナ禍の企業支援として特例的に認められた社会保険料など公租公課の支払い猶予も終了し、滞納が続く企業ではその支払いが強く求められるようになる。各種コスト増も重なり、こうした資金繰り負担に耐えきれない中小企業の「淘汰」「選別」が一段進む可能性もある。
2023年度の企業倒産は、コロナ禍前の水準(年間8000件台)も視野に、緩やかな増加局面が続きそうだ。

