倒産件数、12カ月連続で前年同月を上回る
前年同月比25.3%増、2カ月連続で600件超
倒産件数 | 610件 |
|---|---|
前年同月比 | +25.3% |
前年同月 | 487件 |
負債総額 | 2088億700万円 |
|---|---|
前年同月比 | +189.9% |
前年同月 | 720億1700万円 |
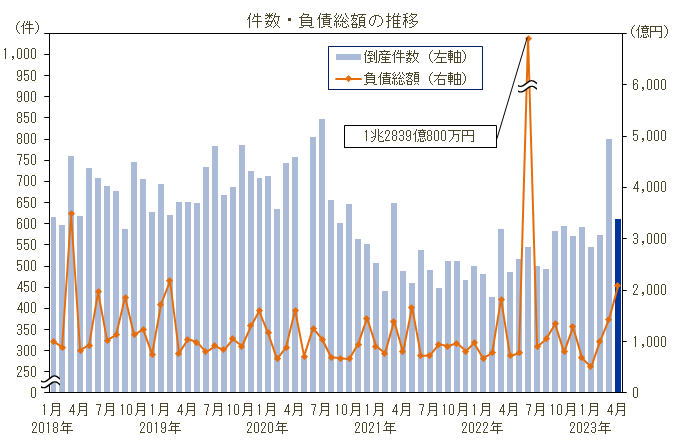
概況・主要ポイント
- ■倒産件数は610件(前年同月487件、25.3%増)となり、12カ月連続で前年同月を上回った。前月に比べると190件(23.8%減)少なく、3カ月ぶりに前月を下回ったが、2カ月連続で600件を超えた
- ■負債総額は2088億700万円(前年同月720億1700万円、189.9%増)となり、3カ月連続で前年同月を上回った。単月での負債が2000億円を超えたのは2022年6月以来
- ■業種別にみると、全業種で前年同月を上回った。件数が最も多かったのは、『サービス業』(前年同月139件→145件、4.3%増)で、『建設業』(同85件→133件、56.5%増)が続いた。『サービス業』は14カ月連続で前年同月を上回った
- ■主因別にみると、『不況型倒産』の合計が490件で、全体の80.4%を占めた
- ■態様別にみると、「破産」が576件発生し、8カ月連続で前年同月比2ケタの増加率となった
- ■規模別にみると、負債「5000万円未満」の倒産が334件で、小規模な倒産増加が目立った
- ■業歴別にみると、『新興企業』が9カ月連続で前年同月比2ケタの増加率となった
- ■地域別にみると、全地域で前年同月を上回った。『四国』(前年同月5件→13件、160.0%増)は、3カ月ぶりに増加率が3ケタとなった。『関東』(同157件→245件、56.1%増)は、2カ月連続で前年同月比50%以上の増加率となった
■業種別
全業種で前年同月比増加、『サービス業』は14カ月連続増加
業種別にみると、全業種で前年同月を上回った。件数が最も多かったのは、『サービス業』(前年同月139件→145件、4.3%増)で、『建設業』(同85件→133件、56.5%増)が続いた。『小売業』(同94件→121件、28.7%増)、『製造業』(同55件→79件、43.6%増)、『卸売業』(同52件→68件、30.8%増)は前年同月に比べて20%以上増えた。
業種を詳細にみると、『サービス業』では、「広告・調査・情報サービス業」(前年同月40件→55件)が全体の件数を押し上げ、2009年8月以来13年8カ月ぶりに14カ月連続で増加した。資材価格の高騰や人手不足が続く『建設業』では、「職別工事」(同34件→58件)で増加が目立った。『小売業』では、「飲食店」(同25件→57件)が倍増、7カ月連続で増加が続いた。
■倒産主因別
『不況型倒産』は490件 構成比は80.4%、9カ月ぶり80%超え
主因別にみると、「販売不振」が481件(前年同月350件、37.4%増)で最も多く、全体の78.9%(対前年同月7.0ポイント増)を占めた。業種別にみると、「建設業」(前年同月61件→112件)が最も多く、「サービス業」(同94件→108件)が続いた。「売掛金回収難」などを含めた『不況型倒産』の合計は490件(同367件、33.5%増)となり、全体の80.4%(同5.0ポイント増)を占め、9カ月ぶりに80%を超えた。
「放漫経営」(前年同月10件→11件、10.0%増)は4カ月ぶりに前年同月を上回った。「その他の経営計画の失敗」(同19件→20件、5.3%増)は2カ月連続で増加した。一方、「経営者の病気、死亡」(同23件→18件、21.7%減)は2カ月連続で減少した。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■倒産態様別
「破産」は576件発生、8カ月連続で前年同月比2ケタの増加率
倒産態様別にみると、『清算型』倒産の合計は594件(前年同月474件、25.3%増)となり、全体の97.4%(対前年同月0.1ポイント増)を占めた。『再生型』倒産は16件(同13件、23.1%増)発生し、4カ月連続で前年同月を上回った。
『清算型』では、「破産」が576件(前年同月451件、27.7%増)で最も多く、8カ月連続で前年同月比2ケタの増加率となった。一方、「特別清算」は18件(同23件、21.7%減)にとどまり、5カ月連続で前年同月を下回った。
『再生型』では、「民事再生法」は16件(前年同月13件、23.1%増)発生した。法人、個人事業主でそれぞれ8件発生した。
■規模別
負債「5000万円未満」の倒産は334件、小規模な倒産増加が目立つ
負債規模別にみると、「5000万円未満」の倒産は334件(前年同月290件、15.2%増)で、全体の54.8%を占め最も多かった。次いで、「5億円未満」が131件(同96件、36.5%増)、「1億円未満」が114件(同72件、58.3%増)で続き、小規模な倒産の増加が目立った。
資本金規模別では、『個人+1000万円未満』の倒産が397件(前年同月322件、23.3%増)となり、全体の65.1%を占めた。
■業歴別
業歴「30年以上」が最多、『新興企業』は9カ月連続で前年同月比10%超の増加率
業歴別にみると、「30年以上」が206件(前年同月175件、17.7%増)で最も多く、全体の33.8%(対前年同月2.1ポイント減)を占めた。このうち、老舗企業(業歴100年以上)の倒産は5件(同13件、61.5%減)だった。
「3年未満」(前年同月26件→27件、3.8%増)、「5年未満」(同27件→52件、92.6%増)、「10年未満」(同96件→93件、3.1%減)を含めた業歴10年未満の『新興企業』(同149件→172件、15.4%増)は、9カ月連続で前年同月比2ケタの増加率となった。業種別にみると、「サービス業」(同55件→62件、12.7%増)が最多、「小売業」(同29件→50件、72.4%増)が続いた。
■地域別
全地域で前年同月比増加、『四国』『関東』で大幅な増加
地域別にみると、全地域で前年同月を上回った。『四国』(前年同月5件→13件、160.0%増)は、3カ月ぶりに増加率が3ケタとなった。『中国』(同16件→25件、56.3%増)は、「建設業」(同2件→6件)や「運輸・通信業」(同1件→3件)で増加が目立った。『関東』(同157件→245件、56.1%増)は、「東京」(同76件→126件)や「千葉」(同14件→25件)の大幅増もあり、全体でも2カ月連続で前年同月比50%以上の増加率となった。以下、増加率順では、『北陸』(同12件→17件、41.7%増)、『北海道』(同16件→18件、12.5%増)、『東北』(同24件→27件、12.5%増)の順となった。
『中部』(前年同月74件→77件、4.1%増)は9カ月連続で増加した。
注目の倒産動向-1
■「放漫経営による倒産」動向
「放漫経営」で倒産、過去10年で最高 コロナ禍で露見相次ぐ
放漫経営の内容「悪質化」も 4割超がコンプラ違反、2年連続増加
アフターコロナに向け企業活動が再び活発化するなか、「放漫経営」による倒産が増加している。経営者の判断ミスやずさんな管理体制、本業以外への資金流出などの会社の私物化により経営が困難になった「放漫経営」倒産は、2022年に144件発生し、前年(124件)から16.1%・2年ぶりの増加となった。また、全倒産に占める割合は2.3%となり、過去10年では最高を記録。2000年以降ではリーマン・ショック直後の2009年(2.4%)以来となる高水準だった。
放漫経営倒産は近年、悪質化の傾向もみられる。放漫経営の末に、粉飾決算や業法違反、脱税といった「コンプライアンス違反」に抵触した倒産の割合は2022年に4割を占め、2年連続で増加した。最も多いのは事業外への資金流出など「資金使途不正」によるもので、放漫経営倒産のうち29件・約2割を占めた。不適切な会計処理など「粉飾」による倒産も16件・約1割を占め、売上高減少などで支援を要請したものの、不適切な会計処理で大幅な債務超過状態が明るみに出たことで周囲の協力を得られず、自力再建を断念したケースも多かった。
放漫経営は一般に好況期に多く発生する傾向にある。最近ではアフターコロナに向け景況感や企業活動が上向くなか、コロナ関連融資などで膨らんだ債務整理といった場面で、無理な事業展開による過剰投資や粉飾決算といった過去の放漫経営が発覚するケースが多く発生している。コロナ禍での資金繰りを支えてきた各種支援も段階的に終了していくなか、事業再生などの場面で過去の放漫経営が表面化し、最終的に法的整理を余儀なくされる中小企業が今後増加する可能性がある。
■コロナ融資後倒産
2023年4月は40件発生 損失総額は推計約433億円
「コロナ融資後倒産」は、2023年4月に40件(前年同月32件、25.0%増)発生し、今年に入り4カ月連続で40件以上となった。また、実際の融資額が判明した約240社のコロナ融資借入額平均は約5800万円だった。「焦げ付き」に相当するコロナ融資損失総額は推計で約433億5875万円にのぼり、国民一人あたり約350円の負担が発生している計算になる。
■人手不足倒産
2023年4月は30件発生 集計開始後初の30件到達
「人手不足倒産」は、2023年4月において30件(前年同月7件、328.6%増)発生し、過去最多を更新。2013年1月の集計開始後初の30件に達した。前月(21件)に引き続き、今月も前年同月から大幅増加となり、急増の様相を呈してきた。業種別にみると、『建設業』(11件)と『サービス業』(11件)が全体の大多数を占めた。
注目の倒産動向-2
■「酪農業」倒産動向
国産牛乳に危機 酪農業の倒産など過去10年で最多
飼料高騰に需要低迷の「ダブルパンチ」、あきらめ相次ぐ要因に
食卓に欠かせない「牛乳」に危機が迫っている。牛乳やチーズなどの原料となる生乳生産を行う「酪農業」の倒産や休廃業などが、2022年に合計14件発生した。前年(8件)から大幅に増加し、過去10年で過去最多を更新する急増となった。
酪農業では、過去に国産生乳不足に伴うバター不足などが度々発生した。そのため、政府は施設整備や機械導入を最大半額補助する「畜産クラスター事業」を開始するなど生乳増産を要請。酪農家もこれに応える形で乳牛増頭や牛舎拡大など積極的な設備投資を行い、規模を拡大してきた。しかし、増産体制が整った直後にコロナ禍が直撃し、業務用や学校給食用の牛乳消費が急減。コスト増分の価格転嫁も難しい状況が続いたなか、ロシアのウクライナ侵攻や円安による輸入コスト増でエサ代が前年から最大1.6倍まで高騰する「ダブルパンチ」に直面した。副収入の仔牛雄牛も外食需要減を背景に競り落とし価格が低迷し、コスト増を補うことも難しかった。もともと高齢化や後継者不足、昨今の設備投資による借入負担も重なり「生産するだけ赤字」の状況に耐える経営体力がない事業者も多い。そのため、昨今の飼料高といった経営環境の急変を前に、倒産や休廃業の決断を余儀なくされたケースが急増したとみられる。
足元では政府による飼料代補助に加え、生乳出荷価格を段階的に引き上げるなど酪農業への支援が広がっている。ただ、消費者も物価高の影響を受けるなか、乳製品価格のさらなる上昇は一段の消費低迷も招きかねない。飼料高騰と値上げ難を前に酪農家が経営をあきらめる状況が続けば、国産牛乳が入手困難となる「酪農危機」が現実に起きる可能性も否定できない。
■物価高(インフレ)倒産
2023年4月は75件発生 累計1000件を突破
「物価高(インフレ)倒産」は、2023年4月において75件(前年同月12件、525.0%増)発生、過去最多であった前月(67件)を超え、10カ月連続で過去最多を更新した。また、2018年1月に集計を開始して以降、累計で1000件を超えた。業種別にみると、資材価格の高止まりが続く『建設業』(23件)が最多、『製造業』『運輸・通信業』(13件)の順となった。
■後継者難倒産
2023年4月は50件発生 集計開始後初の2カ月連続50件台
「後継者難倒産」は、2023年4月に50件(前年同月44件、13.6%増)発生し、2カ月連続で前年同月を上回った。50件台を2カ月連続で記録したのは2013年1月の集計開始後で初となり、高水準での推移が続いた。業種別では『建設業』が13件と最多となり、以下、『小売業』(8件)、『製造業』(7件)、『卸売業』『サービス業』(6件)が続く。
今後の見通し
■倒産は12カ月連続増、増加局面に突入
2023年4月の企業倒産は610件だった。コロナ禍前の水準に達した前月(800件)に比べると多くはないものの、4月単月としては1964年以降で最少を記録した前年同月(487件)より123件(25.3%)増加した。また、2022年5月以降12カ月連続で前年同月を上回り、リーマン・ショック後の08年6月-09年8月(15カ月間)にせまる勢いとなった。「建設業」や「運輸・通信業」など、単月でコロナ禍前の水準を超えた業種もあった。コロナ禍での各種資金繰り支援によって経営が支えられた前年からの“反動増”という要因が大きいほか、経営を左右する複合的なマイナス要因により、倒産動向は増加局面に突入している。
負債総額は2088億700万円となり、前年同月(720億1700万円)の約3倍に達した。4月としては江守グループホールディングス(HD、福井、東証1部、負債711億円)が民事再生法を申請した2015年以来、8年ぶりの高水準だった。ホテル事業などを展開するユニゾHD(負債約1262億円、民事再生法)が総額を大きく押し上げており、全体では負債「1億円」未満の企業が70%超となるなど、依然として小規模な倒産が多かった。他方で、旅館運営の白扇(鳥取、負債16億円)や、木製家具製造の森繁(香川、負債10億6400万円)など、負債が10億円を超える中規模クラスの倒産が地方部で目立った。
■金融支援は相次ぎ縮小 コロナ融資「返済できない」企業の倒産、今夏以降急増も
「実質無利子・無担保融資」、いわゆるゼロゼロ融資をはじめ各種の経営支援プログラムが縮小・打ち切りとなるなか、支援策に依存してきた中小企業の「あきらめ」が色濃く表面化している。ゼロゼロ融資などを利用した後に倒産した「コロナ融資後倒産」は、初めて発生が確認された2020年7月以降、累計で748件に上った。このうち、23年1-4月は182件に達し、前年同期(108件)に比べ約2倍ペースで増えた。時間の経過とともに発生件数の水準が高まっており、とりわけゼロゼロ融資の取り扱いが開始してから3年目となる22年3月以降は加速度的に増加している。
帝国データバンクの調査では、2023年2月時点でコロナ融資を借り入れた企業の8割超が「条件通り、全額返済」を見込み、返済に支障がないことが分かった。一方、1割超の企業では今後の返済に「不安」を抱いており、1%の企業では既に「事業継続が不可能」と回答した。ゼロゼロ融資の承諾件数は官民合わせて230万件を超えるなか、概ね延べ約2万社が返済開始により経営破綻の瀬戸際に立たされている可能性がある。
今年4月以降は借入企業で最長3年に及ぶ利子補給期間が順次終了し、返済開始の“ピーク”が「2023年7月から2024年4月」にかけて到来する。この時期にアフターコロナの回復局面における資金需要の高まりが予想されるが、金利が上昇すれば追加の借り入れ負担増や、物価高による各種コスト高が収益を圧迫する可能性がある。キャッシュフローの急激な悪化に耐え切れず、コロナ融資の返済がままならない企業が事業継続を「あきらめる」事態が相次ぐことが懸念される。
■「人手不足倒産」が過去最多に アフターコロナに向けて人手不足リスク急上昇
5月8日をもって、新型コロナの感染症法上の分類が「5類」に移行した。アフターコロナが本格化し、宿泊業などでは需要が急回復する一方で、「人手不足リスク」が急激に深刻さを増しつつある。従業員の採用難や退職などで事業が回らなくなった「人手不足倒産」は、4月に30件を記録し、2013年以降単月として過去最多を更新した。帝国データバンクの調査では、「人手不足感」を感じる企業は全体の半数を超えた。各業界で人材獲得競争も過熱するなか、中小企業の人手不足により事業の継続ができなくなるリスクが上昇している。
2023年1-4月の企業倒産は2530件に上り、前年同期の1984件に比べて約3割増のペースで推移している。今後はコロナ禍前の水準となる年間8000件台への到達も視野に、緩やかな増加局面が続くとみられる。倒産件数は例年、年後半に増える傾向にあり、コロナ融資の返済ピークに重なる「年下半期」にかけてペースが早まる可能性がある。

