倒産3割増 増加率はバブル崩壊後で最も高く
15年ぶりに全7業種・全9地域で前年を上回る
倒産件数 | 8497件 |
|---|---|
前年比 | +33.3% |
2022年 | 6376件 |
負債総額 | 2兆3769億300万円 |
|---|---|
前年比 | +0.2% |
2022年 | 2兆3723億8000万円 |
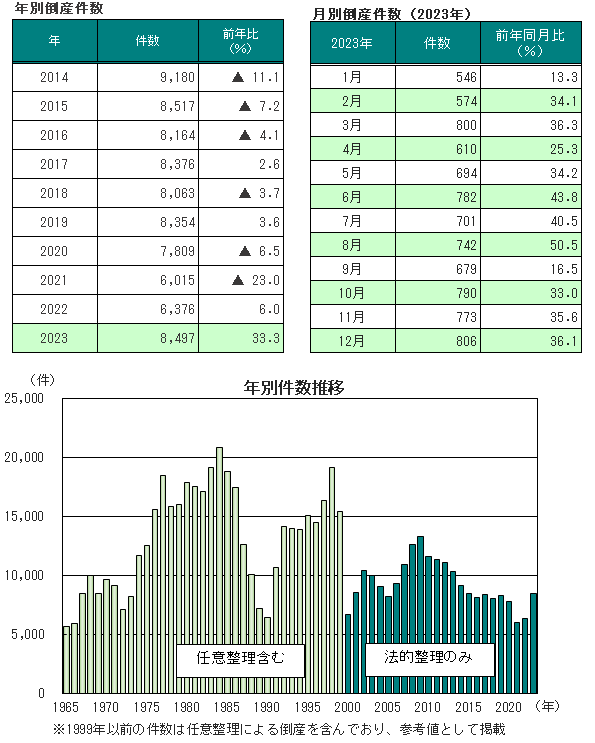
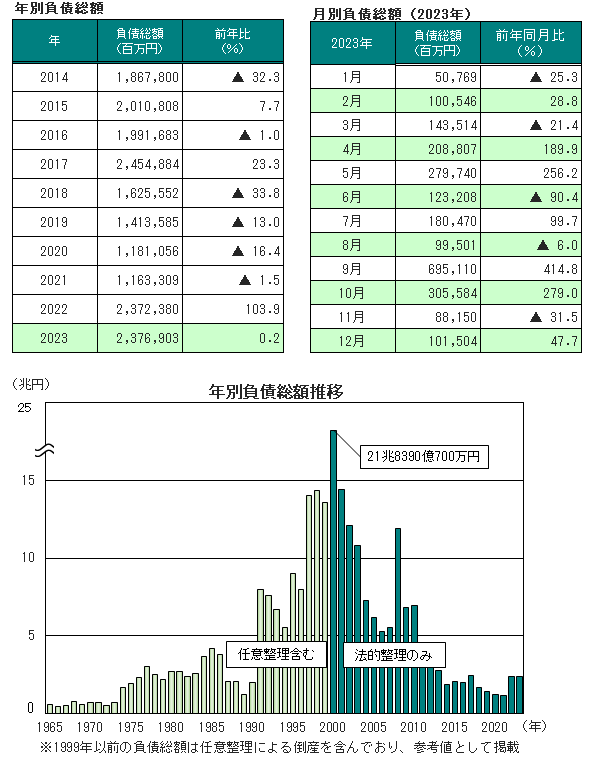
概況・主要ポイント
- ■2023年の倒産件数は8497件(前年6376件、33.3%増)と、前年から2000件以上上回った。2年連続で前年を上回り、2015年(8517件)に迫る件数となった。前年からの増加率が33.3%となり、バブル崩壊後で最も高かった
- ■負債総額は2兆3769億300万円(前年2兆3723億8000万円、0.2%増)だった。パナソニック液晶ディスプレイ(株)やユニゾホールディングス(株)など、負債100億円以上の大型倒産が18件(同14件)発生し、10年ぶりに2年連続で2兆円を超えた
- ■業種別にみると、15年ぶりに全7業種で前年を上回った。『サービス業』(前年1601件→2099件、31.1%増)が最も多かった。『小売業』(同1207件→1783件、47.7%増)は「飲食店」(同452件→768件)が前年から約7割の大幅増となった
- ■主因別にみると、『不況型倒産』が2000年以降で初めて前年から3割以上増えた
- ■態様別にみると、「破産」が7986件で、2015年(7985件)以来8年ぶりの高水準となった
- ■規模別にみると、負債「5000万円未満」が5000件を超え、全体の6割近くを占めた
- ■業歴別にみると、『新興企業』が2527件で、11年ぶりに2500件を超えた
- ■地域別にみると、15年ぶりに全9地域で前年を上回った。『北海道』(前年191件→258件、35.1%増)、『東北』(同348件→443件、27.3%増)、『関東』(同2348件→3066件、30.6%増)、『九州』(同504件→708件、40.5%増)では、コロナ禍前の水準を超えた
■業種別
15年ぶりに全7業種で前年を上回る 「飲食店」は前年から約7割増
業種別にみると、2008年以来15年ぶりに全7業種で前年を上回った。『サービス業』(前年1601件→2099件、31.1%増)が最も多く、『小売業』(同1207件→1783件、47.7%増)、『建設業』(同1204件→1671件、38.8%増)と続いた。『サービス業』は2012年(2091件)以来11年ぶりに2000件を超えた。『運輸・通信業』(同334件→453件、35.6%増)は、ドライバー不足に悩む「道路貨物運送」(同238件→315件)の大幅増もあり、全体では2010年(452件)以来13年ぶりに450件を記録した。
業種を細かくみると、『小売業』では、「飲食店」(前年452件→768件)が前年から約7割の大幅増となった。人手不足と資材価格の高騰が続く『建設業』では、内装工事など「職別工事」(同505件→763件)の増加が目立った。
■倒産主因別
『不況型倒産』は6797件、2000年以降で初めて前年から3割以上増える
主因別にみると、「販売不振」が6672件(前年4836件、38.0%増)で最も多く、全体の78.5%(対前年2.6ポイント増)を占めた。「売掛金回収難」(前年15件→44件、193.3%増)などを含めた『不況型倒産』の合計は6797件(同4923件、38.1%増)となった。前年からの増加率は、2000年以降で初めて30%を超えた。
「その他の経営計画の失敗」(前年255件→295件、15.7%増)は3年ぶりに前年を上回った。「経営者の病気、死亡」(同279件→278件、0.4%減)は、2000年以降で最多であった前年と同水準となった。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■倒産態様別
「破産」は7986件、2015年以来8年ぶりの高水準
倒産態様別にみると、『清算型』倒産の合計は8265件(前年6186件、33.6%増)となり、全体の97.3%(対前年0.3ポイント増)を占めた。『再生型』倒産は232件(同190件、22.1%増)発生し、4年ぶりに前年を上回った。
『清算型』では、「破産」が7986件(前年5912件、35.1%増)で最も多く、2015年(7985件)以来8年ぶりの高水準となった。「特別清算」は279件(同274件、1.8%増)と、3年ぶりに前年を上回った。
『再生型』では、「民事再生法」が230件(前年186件、23.7%増)発生した。個人事業主(151件)が2年連続で、法人(79件)が2年ぶりに前年を上回った。
■規模別
負債「5000万円未満」は5000件を超え、構成比は6割近くに
負債額規模別にみると、「5000万円未満」の倒産が5024件(前年3682件、36.4%増)で最も多く、構成比は59.1%(対前年1.4ポイント増)となった。「5億円未満」では1722件(同1341件、28.4%増)発生し、2016年(1781件)以来7年ぶりに1700件を上回った。
資本金規模別では、『1000万円未満(個人事業主含む)』の倒産が5853件(前年4297件、36.2%増)発生し、全体の68.9%を占めた。
■業歴別
業歴「30年以上」が最多 『新興企業』は11年ぶり2500件超え
業歴別にみると、「30年以上」が2740件(前年2138件、28.2%増)で最も多く、全体の32.2%(対前年1.3ポイント減)を占めた。このうち、老舗企業(業歴100年以上)の倒産は96件(同65件、47.7%増)発生し、4年ぶりに前年を上回った。
業歴10年未満の『新興企業』[「3年未満」(前年319件→361件、13.2%増)、「5年未満」(同469件→596件、27.1%増)、「10年未満」(同1087件→1570件、44.4%増)]は2527件(前年1875件、34.8%増)と、11年ぶりに2500件を超えた。内訳を業種別にみると、「サービス業」(同608件→785件、29.1%増)が最多、「小売業」(同395件→614件、55.4%増)、「建設業」(同360件→495件、37.5%増)が続いた。
■地域別
15年ぶりに全9地域で前年を上回る 4地域はコロナ禍前の水準超える
地域別にみると、2008年以来15年ぶりに全9地域で前年を上回った。このうち、『北海道』(前年191件→258件、35.1%増)、『東北』(同348件→443件、27.3%増)、『関東』(同2348件→3066件、30.6%増)、『九州』(同504件→708件、40.5%増)の4地域では、コロナ禍前にあたる2019年の水準を超えた。『北海道』は、「建設業」(同20件→62件)の大幅増が全体の件数を押し上げた。『関東』は、「東京」(同1157件→1549件)の大幅増もあり、全体でも2017年(3129件)以来となる3000件超えを記録した。『九州』は、「小売業」(同108件→175件)などで増加が目立った。『東北』は、東日本大震災の影響を受けた2011年(446件)以来12年ぶりの水準となった。『近畿』(同1578件→2106件、33.5%増)は、「サービス業」(同398件→516件)が4年ぶりに500件を超えた。
注目の倒産動向-1
■「建設業」倒産動向
8年ぶりに1600件超える
前年比38.8%増、深刻な「人手不足」「資材高」が背景
2023年に発生した建設業者の倒産件数は1671件となり、前年比+38.8%と急増した。増加率が30%を超えるのは2000年以降では初めて。8年ぶりの1600件超えでコロナ禍前の2019年(1414件)を上回り、2014年以降の10年間でみると2番目に多かった。コロナ禍で政策的に抑制されていた倒産の揺り戻しと見られるが、急激な業者数の減少は、仕掛り案件の停滞や計画の見直し・先送りを招く可能性もあり、地域経済への影響も懸念される。
地域別にみると、「北海道」は資材価格の上昇や職人不足もあり小規模業者を中心に倒産が急増した。「九州」は大型再開発プロジェクトや半導体関連投資など案件が活発化しているため、仕入れや人手確保に伴うキャッシュアウトが先行、資金がショートする事例も多かった。
倒産急増の背景には、資材の高騰と人手不足などに伴う「建設コストの上昇」が挙げられる。請負単価が上がらないなかで資材高騰の局面が続き、元請け、下請けともに収益力が低下したり、人手不足により工期の延長が引き起こされたりした。完工時期の後ズレに伴う下請業者への支払延期要請も多く、孫請け以下の工事に関係する業者全体の資金繰りにも影響を与えた。つなぎ融資を調達しようにも、借入余力が乏しい業者も多く、受注は確保できているにもかかわらず、手元現金が足りなくなる「黒字倒産」も見られた。
価格転嫁や工期の適正化が進められることになるが、残業時間の上限規制(2024年問題)が2024年4月から適用されることで、さらなる建設コスト上昇を招き、倒産増加につながるリスクも高まりそうだ。
■ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産
2023年は651件発生 22年比1.7倍、倒産全体の8%を占める
「ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産」は、2023年に651件(前年386件、68.7%増)発生、20年以降で最多を更新した。ゼロゼロ融資を利用後の倒産が全体の8%を占める。実際の融資額が判明した約400社のゼロゼロ融資借入額の平均は約5800万円となり、「不良債権(焦げ付き)」に相当するゼロゼロ融資喪失総額は推計で約716億3800万円にのぼる。
■人手不足倒産
2023年は260件発生 22年比1.9倍、過去最多を更新
「人手不足倒産」は、2023年に260件(前年140件、85.7%増)発生した。年間で初の200件台となり、過去最多を更新した。業種別では、『建設業』(91件)が最も多く、全体の3割を占めた。『サービス業』(57件)では特にソフトウェア開発などIT産業や人材派遣などの業種が目立った。『運輸・通信業』(44件)は前年(20件)から倍増した。
注目の倒産動向-2
■「飲食店」倒産動向
前年比7割増 居酒屋は過去最多
2023年は768件発生、コロナ禍直後の20年に迫る
飲食店を取り巻く経営環境は厳しさを増している。2023年に発生した「飲食店」の倒産は768件発生し、過去10年で最も少なかった前年(452件)から1.7倍に急増した。また、新型コロナの感染拡大に伴う休業や時短営業など経営環境が大幅に悪化し、事業の継続を断念した飲食店が多く発生した2020年の780件に次ぐ過去2番目の高水準を記録した。
2023年の飲食店倒産で最も多いのは「居酒屋」で204件となり、夜間営業の休止などによる影響を大きく受けた20年の189件を上回って年間最多を更新した。ラーメン店や焼肉店などの倒産が増加した「中華料理店」(109件)、コーヒー豆の価格高騰などが打撃となった「カフェ(喫茶店)」(72件)でも過去最多を更新した。新規参入の障壁が低いため、少ない資本で開店したり、開店後の事業計画や見通しが甘かったりした事業者があるなかで、コロナ禍や人手不足、物価高など、当初の経営計画からは「想定外」の事態に直面し、早期に破綻したケースが多く発生したことも2023年の飲食店倒産の特徴といえる。
飲食店の倒産が増加した大きな要因のひとつに、食材価格や電気・ガス代など「物価高」があげられる。仕入価格の上昇度を示す仕入価格DIは、食品の値上げが本格化した2022年以降、80を超える割合で推移した。一方、販売価格への転嫁(上昇)を示す販売価格DIは60~70前後で推移し、仕入価格の上昇が販売価格への転嫁を上回った状態が続いた。足元ではメニューの値上げも進んだものの、頻繁な価格改定が客離れを招きかねないとの懸念も根強く、コストアップとの「我慢比べ」が2023年中により鮮明となった。
■後継者難倒産
2023年は564件発生、初の年間500件超え
「後継者難倒産」は、2023年に564件(前年476件、18.5%増)発生した。年間で初めて500件を超え、過去最多を大幅に更新した。後継者難倒産のうち、「経営者の病気・死亡」による倒産が全体の約4割を占めるものの、過去最高の21年(49.1%)に比べると低下している。後継者不在を最後のきっかけとして、事業継続を自らあきらめるケースが増加した。
■物価高(インフレ)倒産
2023年は775件発生 22年比で2.4倍、建設や製造で急増
物価高(インフレ)倒産は、2023年に775件(前年320件、142.2%増)発生した。年間で初めて700件を超え、過去最多を大幅に更新した。業種別では、『建設業』(186件)が最も多く、前年(70件)から2.7倍に増加。『製造業』(160件)も前年(61件)から2.6倍に増加した。『サービス業』(52件)は宿泊業で初めて物価高倒産が発生した。
今後の見通し
■2023年の企業倒産は8年ぶりの水準、増加率もバブル崩壊後で最も高く
2023年の企業倒産は8497件に達し、前年(6376件)を2121件上回った。2年連続で前年を上回り、2015年(8517件)以来8年ぶりの水準となった。コロナ支援策の縮小に加え、物価高や人手不足等によるコスト増に耐え切れなくなった中小企業の倒産が急増した。前年からの増加率(33.3%)は、バブル崩壊後で最も高くなった。月別推移をみても、2022年5月から20カ月連続で前年同月を上回った。とくに12月(806件)は2023年で最多となり、中小・零細企業を中心に年後半にかけて増加基調を強めた。
負債総額は2兆3769億300万円で、前年(2兆3723億8000万円)からほぼ横ばい(0.2%増)となった。負債トップはパナソニック液晶ディスプレイ(9月特別清算、負債5836億円)で、全体の4分の1を占めた。上場企業など大企業では原則として私的整理スキームを活用する経営再建が定着しており、年間を通じて大型倒産は沈静化が続いた。
■「令和6年能登半島地震」による企業活動への影響注視
2024年元旦、石川県・能登半島を震源とする大地震が発生した。今回の「令和6年能登半島地震」による死者は1月9日に200人を超えた。被害の全容は明らかになっていないが、最大震度7を記録した能登地方を中心に、今後は企業活動への影響も無視できない。帝国データバンクが1月5日に発表した調査で、能登地方に本社を置く企業数は、2023年11月時点で4075 社を数えた。建設業のほか、伝統工芸や観光産業、エレクトロニクス産業でとくに影響が懸念される。
地元企業だけでなく、大手企業の工場進出もある。東日本大震災や平成28年熊本地震など過去の震災を振り返っても、直接的な被害を受けた企業だけでなく、取引先の被災や原材料の調達難など間接的な影響を受けた関連倒産も多発した。被災住民の安全確保や生活再建が最優先であることは言うまでもないが、復旧・復興が長期化すれば、これらのサプライチェーンを通じて全国の企業にも影響が広がりかねない。
■2024年はさらなる増加局面へ、「4月」以降に倒産リスク高まる可能性
2024年の企業倒産も増加局面が続くとみられる。とくに年度初めとなる「4月」以降にさらに加速する可能性がありそうだ。すでに深刻な人手不足と人件費高騰に直面する建設業や運輸業を中心に「時間外労働の上限規制」が4月から適用され、「2024年問題」の影響が本格化する。また、実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済開始を迫られる企業が昨年7月に続き、4月に最後のピークを迎える。返済負担に耐えかねて、年度末前後の節目に事業継続をあきらめる経営者がさらに増える可能性がある。
金融庁による金融機関向けの監督指針も今春に改定される。金融機関は資金繰り支援からの転換が求められるなかで、従来のような安易な返済条件の変更(リスケ)や借り換えに応じることは難しくなりそうだ。とくにリスケはコロナ禍以降、企業からの要請に対して金融機関は原則応じてきたが、融資先の「選別」が進むことで4月以降、金融機関が返済条件の変更に応じる比率が下がる可能性も十分ある。
「金利のある世界」に向けて、日銀が4月にもマイナス金利解除に動くとの見方も根強い。今後、ゼロ金利・利上げに進めば、新たな借り入れに苦慮する企業が増えることも考えられる。ゼロゼロ融資で膨らんだ過剰債務の返済もままならず、物価高や賃上げ等によるコスト増に苦しむ中小・零細企業にとっては死活問題となりかねない。帝国データバンクが2022年12月に発表した調査では、借入金の利払い負担を事業利益で賄えない『ゾンビ企業』は、2021年度で推定18万8000社を数える。倒産予備軍ともいえるゾンビ企業の数は、足元でさらに増加している可能性が高く、その動向は潜在的なリスク要因のひとつとして注視していく必要がある。

