倒産件数は713件、5カ月連続の前年同月比増加
負債総額は1172億5000万円、3カ月ぶりの前年同月比減少
倒産件数 | 713件 |
|---|---|
前年同月比 | +2.7% |
前年同月 | 694件 |
負債総額 | 1172億5000万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲32.0% |
前年同月 | 1723億5600万円 |
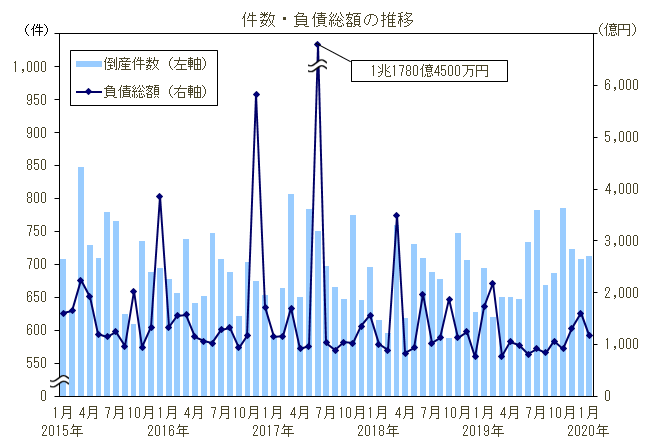
主要ポイント
- ■倒産件数は713件(前年同月比2.7%増)と、5カ月連続の前年同月比増加
- ■負債総額は1172億5000万円と、前年同月に(株)エメラルドグリーンクラブ(東京都、民事再生、負債約450億円)の大型倒産が発生したことなどから、前年同月比32.0%減
- ■業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を上回った。なかでも卸売業(122件、前年同月比19.6%増)は、飲食料品卸(39件、同95.0%増)などが増加。小売業(173件、同9.5%増)では、昨年に引き続き飲食店などの増加が目立つ
- ■主因別に見ると、「不況型倒産」の合計は578件、構成比は81.1%を占める
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は440件、構成比は61.7%を占める
- ■地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を上回った。なかでも東北(46件、前年同月比119.0%増)は、東日本大震災前の2011年1月(51件)以来の40件超を記録。中部(98件)は前年同月比6.5%の増加
- ■人手不足倒産は21件(前年同月比5.0%増)発生。3カ月連続の前年同月比増加
- ■後継者難倒産は43件(前年同月比53.6%増)発生。2カ月連続の前年同月比増加
- ■返済猶予後倒産は49件(前年同月比16.9%減)発生。3カ月連続の前年同月比減少
- ■負債トップは、(株)ヤマニシ(宮城県、会社更生)の約123億円
調査結果
■件数・負債総額
倒産件数は713件、5カ月連続の前年同月比増加
倒産件数は713件(前年同月比2.7%増)と、5カ月連続で前年同月を上回った。
負債総額は1172億5000万円と、前年同月に(株)エメラルドグリーンクラブ(東京都、民事再生、負債約450億円)の大型倒産が発生したことなどから、前年同月比32.0%減となった。
■業種別
卸売業、小売業など4業種で前年同月比増加
業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を上回った。なかでも卸売業(122件、前年同月比19.6%増)は、昨年の天候不順や不漁に伴う仕入値の上昇が響き、青果・鮮魚卸などを中心に飲食料品卸(39件、同95.0%増)が増加。卸売業は7カ月連続の増加で、7カ月以上の連続増は、2008年9月~2009年4月(8カ月連続)以来。小売業(173件、同9.5%増)では、昨年に引き続き飲食店(75件、同50.0%増)の増加が目立った。
一方、サービス業(156件、前年同月比12.8%減)、製造業(69件、同5.5%減)、不動産業(18件、同5.3%減)の3業種は前年同月を下回った。
■主因別
「不況型倒産」は578件、構成比81.1%
主因別に見ると、「不況型倒産」の合計は578件(前年同月比6.3%増)と、5カ月連続で前年同月を上回った。構成比は81.1%(同2.7ポイント増)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
負債5000万円未満の構成比61.7%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は440件(前年同月比4.8%増)、構成比は61.7%を占めた。負債5000万円未満の倒産では、小売業(127件)が構成比28.9%(同2.2ポイント増)を占め最多、サービス業(113件)が同25.7%(同4.5ポイント減)で続く。
資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人事業主含む)の倒産が478件(前年同月比8.4%増)、構成比は67.0%を占めた。
■地域別
東北、中部など4地域で前年同月比増加
地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を上回った。なかでも東北(46件、前年同月比119.0%増)は復興需要の収束などを背景に、建設業のほか卸売業、小売業などで幅広く増加し、1月としては東日本大震災前の2011年1月(51件)以来となる40件超を記録。また、中部(98件、同6.5%増)は建設業(19件)や製造業(13件)などで増加した。
一方、4地域は前年同月を下回り、なかでも近畿(176件、前年同月比3.8%減)は7カ月ぶり、北陸(25件、同13.8%減)は3カ月連続の前年同月比減少となった。
■態様別
「破産」は659件、構成比92.4%
態様別に見ると、破産は659件(構成比92.4%)、特別清算は31件(同4.3%)となり、1月としては2012年以来8年ぶりの30件超え。会社更生法による倒産は、2019年2月(1件)以来、11 カ月ぶりに発生した。
■特殊要因倒産
人手不足倒産
21件(前年同月比5.0%増)発生。3カ月連続の前年同月比増加
後継者難倒産
43件(前年同月比53.6%増)発生。2カ月連続の前年同月比増加
返済猶予後倒産
49件(前年同月比16.9%減)発生。3カ月連続の前年同月比減少
※特殊要因倒産では、主因・従因を問わず、特徴的な要因による倒産を集計
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは41.9、4カ月連続の悪化
2020年1月の景気DIは前月比0.6ポイント減の41.9となり、4カ月連続で悪化した。
1月の国内景気は、記録的な暖冬で季節需要や農業の落ち込みが響いたほか、海外経済の減速にともなう製造業の低迷が関連業種へと波及した。中国発の新型肺炎が春節時期に世界的に拡大、旅館・ホテルや輸出・生産関連などに影響が表れた。また生産・出荷量DIが3カ月連続で減少するなど生産活動の停滞がみられるなか、設備稼働率の低下とともに在庫調整の動きが製造業や中小企業を中心に広がってきた。さらに軽油など燃料価格の上昇でコスト負担の高まりも続いた。他方、米中貿易協議による第1段階合意がプラス要因となったほか、5G(第5世代移動通信システム)向けの動きなども好材料だった。 国内景気は、在庫調整が進むなかで記録的暖冬も加わり、後退局面が続いている。
海外動向が最大のリスク要因、緩やかな後退が見込まれる
今後は、海外経済の動向が最大のリスク要因になるとみられ、輸出は当面、弱めの動きで推移すると見込まれる。新型肺炎の拡大や米中貿易摩擦、英EU離脱後の展開、中東地域情勢などが懸念材料となろう。国内では燃料価格の上昇や人手不足の深刻化などが企業経営の負担となるほか、中国からの訪日客の一時的減少が長引くことなども懸念される。また消費者ポイント還元事業終了後の消費動向も注視する必要がある。他方、世界的なシリコンサイクルの好転や省力化需要、東京五輪、補正予算の実行などは好材料である。 今後の国内景気は、海外動向が最大のリスク要因となり、緩やかな後退が見込まれる。
今後の見通し
■倒産件数は5カ月連続増、5年ぶりの高水準
2020年1月の倒産件数(713件、前年同月比2.7%増)は、5カ月連続で前年同月を上回り、1月としては2015年1月(708件)以来5年ぶりに700件を超えた。業種別では卸売業(122件、同19.6%増)、小売業(173件、同9.5%増)などで増加。消費税率引き上げなど受け、消費者のさらなる節約志向の高まりが懸念されるなか、2019年10月以降の小売業の累計件数(689件)は前年同期比9.5%増と、倒産件数全体(2930件、同5.6%増)の増加幅を上回る。
負債額上位には、ドライブインで飲食店を経営していたNF管理(株)(旧:ナガサワ食品(株)、兵庫県、負債約30億円)や、創業以来1300年超の老舗旅館「法師」を粟津温泉で経営していた(株)ゼット(旧:(有)善吾楼、石川県、負債約12億円)など、会社分割や事業譲渡により事業を別会社に移転させ、第二会社方式で再生を図る目的での特別清算手続きが目立った。特別清算の件数(31件)も、1月としては2012年1月(33件)以来8年ぶりに30件を超えた。
■商圏人口の減少が一段と深刻化
2019年の人口移動報告(総務省)によると、東京圏では転入者が転出者を14万8783人上回り、1996年以降24年連続の転入超過となった。超過人数も3年連続の増加と、東京圏への一極集中が加速するなか、1月は山形県で創業320年の歴史を誇る老舗百貨店である(株)大沼(破産、負債約30億円)が倒産。昨年8月には米沢店を閉鎖し、山形本店のみでの経営再建を目指していたものの、台風被害や消費税率引き上げの影響による10月以降の大幅な売り上げ減少が追い打ちとなった。また、北九州市では百貨店の井筒屋を中核テナントとして商業施設「クロサキメイト」を経営していた(株)メイト黒崎(破産、負債約25億2600万円)が倒産。当初は昨年5月末で閉店予定だった井筒屋が、売り場面積縮小と賃料引き下げにより営業を継続してきたなか、空きフロアへの後継テナントも存在せず、賃料収入の減少により事業継続を断念した。
商圏人口の減少を受け、衣料品を主力とする従来型の百貨店や商業施設は、ネット通販の拡大や郊外型の大型SCとの競合などで厳しい経営環境が続く。とくにインバウンド効果が波及しにくい地域などでは、すでにリストラ策が一巡した企業による倒産が今後も発生する可能性があり、こうした企業を販路とするメーカー、卸売各社への影響も広がる見通し。
■内外にリスク要因多く、倒産は緩やかに増加続く
今月4日、福井県で「雁が原スキー場」を経営していた勝山観光施設(株)(破産、負債約2億8000万円)が倒産。近年のスキー人口の減少などで来場客が漸減し赤字経営が続いていたなか、今シーズンは雪不足で1日もオープンできないまま、事業継続の断念を余儀なくされた。記録的な暖冬を受け、今後はスキー場のみならず幅広い企業へのマイナスの影響が懸念される。
また、中国での新型コロナウイルスの感染拡大で、武漢を中心に春節以降も多くの地域で経済活動が実質停止状態にあり、現地工場を持つ日本企業や中国への依存度が高い各社のサプライチェーンが不安視されている。すでに世界全体での感染者数や死者数も、2003年に猛威をふるったSARS(重症急性呼吸器症候群)を上回っている。当時SARS流行に起因した倒産が、製造業のほか宿泊業や旅行業、飲食店などで散発したことからも、今後の倒産発生が危惧される。
人件費や物流費、原材料費などの上昇や高止まりを受け、中小零細企業ほど負担感は強い。飲食店や小売店では、消費税率引き上げ後も価格転嫁せず、実質値下げ対応も散見されるうえ、キャッシュレス決済での手数料負担の増加や、ポイント還元事業終了後の消費の落ち込みなども懸念される。引き続き国内外にリスク要因は多く、今後の倒産件数は、地域人口や企業数の減少、産業構造の変化などとも相俟って、緩やかな増加トレンドを辿る可能性が高い。

