倒産件数は587件、10カ月連続の前年同月比減少 減少期間はコロナ禍以降では最長
負債総額は1825億8200万円、2カ月連続の前年同月比増加
倒産件数 | 587件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲9.4% |
前年同月 | 648件 |
負債総額 | 1825億8200万円 |
|---|---|
前年同月比 | +30.4% |
前年同月 | 1400億5300万円 |
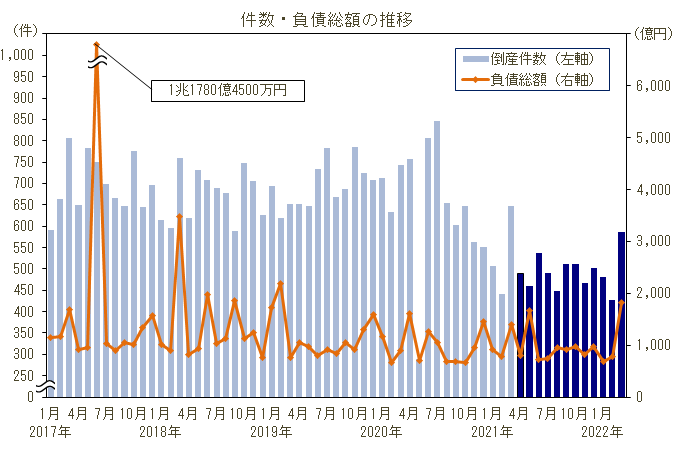
主要ポイント
- ■倒産件数は587件(前年同月比9.4%減)と、10カ月連続で前年同月を下回った。10カ月以上の連続減少は、コロナ禍以降では2020年8月~2021年4月(9カ月連続)を上回り最長
- ■負債総額は1825億8200万円(前年同月比30.4%増)と、2カ月連続で前年同月を上回った。負債100億円以上の大型倒産が4件発生し、コロナ禍の2020年3月以降で最多
- ■負債額最大の倒産は、(株)ホープエナジー(福岡県、破産)の約300億円
- ■業種別にみると、サービス業(前年同月140件→148件、5.7%増)は10カ月ぶりに増加した。一方、卸売業(前年同月82件→71件、13.4%減)、小売業(同164件→119件、27.4%減)の流通2業種は減少するなど、業種間で傾向が異なる、まだら模様での推移となった
- ■主因別にみると、「不況型倒産」の合計は459件(前年同月505件、9.1%減)で、2カ月ぶりに減少した一方、「放漫経営」と「設備投資の失敗」は増加した
- ■負債規模別にみると、負債5000万円未満の倒産は349件(前年同月411件)で、10カ月連続で減少。一方、負債100億円以上の倒産は4件発生し、2015年3月以来7年ぶりの多さ
- ■地域別にみると、9地域中5地域で減少し、四国(前年同月14件→7件、50.0%減)が半減。一方、東北(前年同月29件→45件、55.2%増)は1年9カ月ぶりの40件超え、九州(同46件→61件、32.6%増)は宿泊業などサービス業が3年9カ月ぶりの高水準
■件数・負債総額
倒産件数は10カ月連続減も、大型倒産が複数発生 負債総額はコロナ禍以降で最多
倒産件数は587件(前年同月比9.4%減)と、10カ月連続で前年同月を下回った。10カ月以上の連続減少は2013年8月~2015年2月(19カ月連続)以来で、コロナ禍で大幅な減少となった2020年8月~2021年4月(9カ月連続)を上回る長さだった。
負債総額は1825億8200万円(前年同月比30.4%増)と、2カ月連続で前年同月を上回った。負債100億円以上の大型倒産が4件発生し、コロナ禍の2020年3月以降で最多。
■業種別
まだら模様で推移 建設・製造・サービスは増加、卸売・小売・不動産は減少
業種別にみると、7業種中3業種では前年同月から増加した。なかでもサービス業(前年同月140件→148件、5.7%増)は10カ月ぶりに増加した。市場の縮小が続くパチンコホールなど娯楽業(同3件→11件、266.7%増)などで増加しており、減少が続いた対面接客産業で反転増の兆しがみられる。
一方、卸売業(前年同月82件→71件、13.4%減)、小売業(同164件→119件、27.4%減)の流通2業種は減少、不動産業(同33件→15件、54.5%減)は前年同月から半減した。総じて業種間で傾向が異なる、まだら模様での推移となった。
■主因別
「不況型倒産」は459件、構成比は78.2% 「放漫経営」などは増加
主因別にみると、「不況型倒産」の合計は459件(前年同月505件、9.1%減)で、2カ月ぶりに減少した。構成比は78.2%(対前年同月0.3ポイント増)だった。一方で、「放漫経営」(同9件→12件、33.3%増)と「設備投資の失敗」(同2件→4件、100.0%増)は増加した。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模・業歴別
負債100億円以上の大型倒産、単月としては2015年3月以来7年ぶりの多さ
負債規模別にみると、負債5000万円未満の倒産は349件(前年同月411件、15.1%減)で、10カ月連続で減少した。減少期間は2020年9月~21年4月の8カ月を上回り、過去最長だった。総じて、小規模倒産は減少傾向で推移している。
一方、負債5億円以上の倒産ではいずれも前年同月を上回った。なかでも負債100億円以上の大型倒産は4件発生し、単月の発生としては2015年3月以来7年ぶりの多さだった。
■地域別
東北は1年9カ月ぶり40件超え、九州はサービス業が3年9カ月ぶりの多さ
地域別にみると、9地域中5地域で前年同月を下回り、4地域では上回るまだら模様での推移となった。減少した地域では、四国(前年同月14件→7件、50.0%減)が半減、関東(同236件→178件、24.6%減)は小売業の減少などが全体を押し下げた。一方、東北(前年同月29件→45件、55.2%増)は1年9カ月ぶりの40件超え、九州(同46件→61件、32.6%増)は宿泊業などサービス業が3年9カ月ぶりの高水準となり、前年同月比でも3カ月ぶりの増加。
■態様別
「破産」は537件、構成比は91.5% 「会社更生法」は2件発生
態様別にみると、破産は537件(構成比91.5%)、特別清算は32件(同5.5%)となり、「清算型」倒産の割合は全体の9割強を占めた。また、会社更生法は2件発生した。
■景気動向指数(景気DI)
仕入価格の上昇が過去20年で最高、価格転嫁追い付かず
2022年3月の景気DIは前月比0.5ポイント増の40.4となり、3カ月ぶりに改善した。
3月の国内景気は、新規感染者数の漸減などのプラス要因と、ウクライナ情勢の長期化などにともなう原材料価格の高騰といったマイナス要因が入り混じるなかで、小幅な改善となった。プラス要因では、まん延防止等重点措置が対象地域すべてで解除され人出が徐々に活発となったほか、旺盛な自宅内消費の継続や値上げ前の駆け込み需要などが景況感を押し上げた。マイナス要因では、原油価格の高値推移や福島県沖地震は景況感を下押しした。特に原油価格は一時1バレル=123ドルに上昇し石油製品の値上げが相次いだうえ、急激な円安の進行で輸入物価が上昇するなど、仕入単価DIは過去最高の水準を記録した。
国内景気は、好悪両面の要因が顕在化したなかで下落傾向が停止し、わずかに上向いた。
下振れリスクを抱えながらも、緩やかな上向きへ
今後1年程度の国内景気は、新型コロナウイルスの感染動向のほか、ウクライナ情勢の行方や原油を含む原材料価格の高騰などに注視する必要があろう。特に、「ガソリン・経費・材料の値上げ幅が大きく価格転嫁には半年かかる」(給排水・衛生工事)といった、仕入価格の上昇に対する販売価格への転嫁の状況次第で、企業の収益力に大きな影響を及ぼす可能性がある。他方、旺盛な自宅内消費の継続や5G関連の環境整備、半導体需要の増加などはプラス材料となろう。さらに、対面型サービス需要の拡大や挽回生産も期待される。
今後は、下振れリスクを抱えながらも、人出の増加などで緩やかに上向くと見込まれる。
今後の見通し
■56年ぶりの倒産低水準 件数は引き続き抑制傾向も、負債は大型化
2021年度の倒産件数は前年度比19.1%減の5916件となった。件数にして1000件超の大幅減少となり、1965年度以来56年ぶりの6000件割れと、半世紀ぶりの歴史的低水準を記録した。国や自治体による資金繰り支援が支えになって中小企業の「資金繰り破たん」を回避できていることが、引き続き倒産の発生を低水準に抑制する要因となっている。
一方で、負債総額は前年度比2.8%減の1兆1828億7100万円と、倒産件数の減少率に比べ落ち込みは小さく、ほぼ横ばいで推移した。これまで多数を占めていた負債5000万円未満の小規模な倒産が2割以上減少した一方、負債50億円以上の倒産が大幅に増加しており、倒産1社の負債額平均(トリム幅上下1%)でみても、2019年度の約9500万円/社をボトムに2年連続の増加で推移。21年度は約1億1600万円/社と、前年度(約1億100万円/社)から1割超の増加となるなど、1社あたりの負債がコロナ禍以降、大型化している点が特徴的だ。月商対比で見た企業の有利子負債も、2021年12月時点でコロナ前から1カ月ほど多い平均約5.6カ月に膨らんでいた。ゼロゼロ融資などを中心に、過去2年間で金融債務が増加したことが要因の一つに挙げられる。
ただ、コロナ禍の収束見通しがつかないなか、手厚い支援が続く現在の状況が却って中小零細企業の倒産を大幅に抑制し、代わって業界中堅や地場大手の企業が、アフターコロナを見据え、過剰債務を抱えた不採算事業の子会社整理や事業譲渡などを積極的に進めたため、との見方もできる。実際に、過剰な金融債務を切り離して事業再生を図る「第二会社方式」で多用される「特別清算」の割合は、2021年度で5.0%と過去最高だった。
■急増する「コロナ融資後倒産」、前年の5倍・206件が発生 支援効果に陰りも
コロナ融資を利用した後に経営破綻した「コロナ融資後倒産」が急増している。2021年度は前年の約5倍となる206件が判明したほか、22年3月は単月として最多となる32件に達した。こうした破綻の多くは、コロナ融資を得たものの経営再建を果たせず、先行きの見通し難から自ら事業を畳んだ「ギブアップ型」の倒産が多い。ただ、最近では事業継続に必要な追加融資が得られず、破綻を余儀なくされた「息切れ型」のケースも散見される。
帝国データバンクの調査では、約1万社のうち5割超がコロナ融資を受けていたことが判明。このうち、約8割の企業では3月時点で約定通り返済可能との回答があった一方で、約1割の企業では返済に不安を抱えている・返済不能状態に陥っていることが分かった。政府は今年6月までコロナ融資の受付を延長するものの、これらの資金繰り支援策はあくまでもコロナ禍の影響を救済するための「時限的措置」に過ぎない。足元では信用保証協会が肩代わりする代位弁済が増加するなど、企業の資金繰りには変調の兆しもある。コロナ融資の返済が今年度から本格化する企業も多いとされるなか、大量の資金供給で抑え込んできた経営不振企業の倒産抑制効果も、ここにきて陰りが見え始めている。
■「コロナの長期化」が倒産抑制効果を発揮へ コントロール不能なコストアップが懸念材料
2022年度の企業倒産は、「コロナ禍の長期化」で比較的落ち着いた推移を見せそうだ。コロナ禍が収束の兆しを見せないなかでは、ゼロゼロ融資をはじめ当面は政府の金融支援が打ち切られる可能性は低い。そのため、経営不振に喘ぐ企業でも支援策に支えられる形で、却って倒産は小康状態での推移になるものと予想される。ただ、中堅・大企業など経営体力に余力のある企業ではアフターコロナを見据え、私的整理の活用などで早めの事業再生などに踏み切る動きもあり、減少が続く中小零細企業とは倒産動向が「真逆」になる展開も考えられる。
一方で、今後は歯止めのかからない円安の進行と物価高が、中小零細企業の経営に懸念材料となってくる。ロシアによるウクライナ侵攻を発端とした、コントロール不能な原油や食料品といった資源価格の高騰は、企業収益の下押し要因となりつつある。帝国データバンクの調査では、2022年3月時点における販売価格と仕入価格のギャップはリーマン・ショック前の2008年8月と同じ水準まで拡大した。特に中小零細企業では、大企業に比べ、仕入価格の上昇分を販売価格に転嫁できていない実情が鮮明となっている。円安は「経済・物価にプラスとなる基本的な構造は変わりない」(黒田東彦・日本銀行総裁)など、輸出企業・グローバル企業にとっては収益押し上げの要因にはなる。一方で輸入に頼るエネルギーや食糧など内需を中心とした企業や消費者にはコストアップの痛みが増すなど、功罪双方を伴う。「これ以上コストアップが続くようなら事業継続は不可能だ」(旅館)といった声も聞かれるなかで、企業努力の限界を超えた青天井のコストアップがコロナ禍で懸命に事業継続を図ってきた経営者の心を砕き、結果的に事業を畳む「あきらめ倒産」へと誘発する可能性もあり、注視が求められそうだ。

