倒産が急増、コロナ禍前の水準に
倒産件数 | 800件 |
|---|---|
前年同月比 | +36.3% |
前年同月 | 587件 |
負債総額 | 1435億1400万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲21.4% |
前年同月 | 1825億8200万円 |
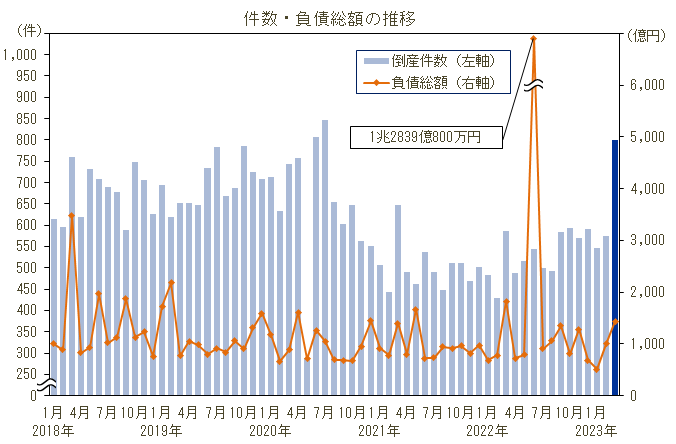
概況・主要ポイント
- ■倒産件数は、前年同月に比べて36.3%多い800件となった。11カ月連続で前年同月を上回り、月次ベースでは2020年7月(847件)以来2年8カ月ぶりに800件を超え、コロナ禍前の700-800件/月の水準に達した
- ■負債総額は1435億1400万円(前年同月1825億8200万円、21.4%減)と、前年同月から2カ月ぶりに20%以上の大幅減となった
- ■業種別にみると、全業種で前年同月を上回った。人手不足・高齢化が進む『建設業』(前年同月110件→155件、40.9%増)は前年同月から40%以上増加したほか、『小売業』(同119件→164件、37.8%増)は前月に続き「飲食店」(同49件→72件)が大幅増となった
- ■主因別にみると、『不況型倒産』が2カ月連続で前年同月に比べて30%以上の増加
- ■態様別にみると、「破産」は760件(前年同月537件)で、13年9カ月ぶりの増加幅を記録
- ■規模別にみると、負債1-10億円の中堅規模の倒産増加が目立つ
- ■業歴別にみると、業歴10年未満の新興企業は13カ月連続で前年同月を上回った
- ■地域別にみると、『東北』を除く全地域で前年同月を上回った。『関東』(前年同月178件→292件、64.0%増)では、「東京」や「神奈川」などの増加もあり13年8カ月ぶりの100件以上増。その他、『近畿』、『中部』、『中国』などでも大幅増となった
■業種別
全業種で前年同月比増加 「飲食店」の大幅増続く
業種別にみると、全業種で前年同月から増加した。人手不足・高齢化が進む『建設業』(前年同月110件→155件、40.9%増)は、とび工事や型枠大工工事といった「職別工事」(同46件→72件)などで増加したこともあり、前年同月から40%以上増加。『小売業』(同119件→164件、37.8%増)では、前月に引き続き「飲食店」(同49件→72件)が大幅増となった。
『運輸・通信業』(前年同月28件→37件、32.1%増)は、2009年7月以来13年8カ月ぶりの6カ月連続2ケタ増を記録した。『サービス業』(同148件→197件、33.1%増)では、学習塾など教育関連業者の倒産が目立ち、全体として13カ月連続で前年同月から増加。2000年以降最長の増加期間である08年5月-09年8月(16カ月連続)に迫った。
■倒産主因別
『不況型倒産』は625件 2カ月連続の大幅増
主因別にみると、『不況型倒産』の合計は625件(前年同月459件、36.2%増)発生、11カ月連続で増加となり、2カ月連続で前年同月から30%以上増加した。
最多は「販売不振」の617件(前年同月452件、36.5%増)で、構成比は77.1%(対前年同月0.1ポイント増)、2020年7月以来2年8カ月ぶりに600件台を記録した。
このほか、「放漫経営」(前年同月12件→9件、25.0%減)は2カ月連続の2ケタ減となった一方、「その他の経営計画の失敗」(同19件→38件、100.0%増)は、前月までの4カ月連続減から倍増に転じた。「経営者の病気、死亡」(同31件→25件、19.4%減)では3カ月ぶりの前年同月比減少となった。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■倒産態様別
『清算型』倒産は779件 破産は13年9カ月ぶりの増加幅を記録
倒産態様別にみると、破産と特別清算を合わせた『清算型』倒産は779件(前年同月569件、36.9%増)で、構成比は97.4%を占めた。民事再生法と会社更生法を合わせた『再生型』倒産は21件(同18件、16.7%増)で、3カ月連続で前年同月を上回った。
「破産」は760件(前年同月537件、41.5%増)で、12カ月連続の前年同月比増加となった。前年同月から200件以上増加したのは、2009年6月以来13年9カ月ぶり。一方、「特別清算」は19件(同32件、40.6%減)で、4カ月連続の2ケタ減少と大幅減が続いた。
また、「民事再生法」は20件(前年同月16件、25.0%増)発生し、うち14件を個人事業主が占めた。「会社更生法」(1件)は4カ月ぶりに発生した。
■規模別
負債1-10億円の中堅規模倒産が大幅増
負債規模別にみると、「1億円未満」(前年同月93件→150件、61.3%増)は8年ぶり、「5億円未満」(同99件→156件、57.6%増)は4年5カ月ぶりに150件台に達し、負債1-10億円の中堅規模の倒産増加が目立った。
資本金規模別では、『1000万円未満(個人事業主含む)』の倒産が538件(前年同月399件、34.8%増)発生し、構成比は67.3%を占めた。
■業歴別
業歴「30年以上」が最多、業歴10年未満の新興企業の増加続く
業歴別にみると、業歴「30年以上」が276件(前年同月193件、43.0%増)で最多、前年同月比40%以上の大幅増となった。このうち、老舗企業(業歴100年以上)は10件発生し、2ケタ件数を記録したのは2022年4月以来11カ月ぶり。
また、業歴10年未満の新興企業(前年同月177件→215件、21.5%増)は、13カ月連続で前年同月を上回った。このうち、「10年未満」(同97件→136件、40.2%増)は、2009年1月以来、14年2カ月ぶりに7カ月連続で前年同月比2ケタ増加となった。
そのほか、「20年未満」(前年同月65件→109件、67.7%増)は2014年4月以来、「30年未満」(同84件→110件、31.0%増)は2021年3月以来の100件台を記録した。
■地域別
『東北』を除き、全国的に大幅増加の推移
地域別にみると、『東北』を除く全地域で前年同月を上回った。『関東』(前年同月178件→292件、64.0%増)では、「東京」(同96件→148件)や「神奈川」(同21件→58件)などの大幅増もあり、全体として2009年7月以来13年8カ月ぶりの100件以上の増加を記録。『近畿』(同147件→178件、21.1%増)は、製造業(同10件→26件)の急増が全体の件数を押し上げた。また、『中部』(同78件→119件、52.6%増)は、2011年9月以来11年6カ月ぶりの8カ月連続増加だった。このほか、『中国』(同27件→41件、51.9%増)は、2018年9月以来の2カ月連続で50%以上の増加となった。
景気動向指数(景気DI)
■2023年3月の景気DIは43.9、上向きに転じる
2023年3月の景気DIは前月比1.8ポイント増の43.9となり、4カ月ぶりに改善した。
3月の国内景気は、新型コロナの感染者数の落ち着きやマスク着用ルールの緩和にともない消費者のマインドが明るくなるなどアフターコロナに向けた動きが加速。新型コロナ流行時の年度末と異なり旺盛な旅行需要や卒業、歓送迎会にともなう消費活動が目立ち、個人消費関連を中心に幅広く景況感は上向いた。また、卒業や就職などの季節需要の増加も押し上げ要因となった。一方、仕入れ価格の高止まりや人手不足・技術者不足による機会損失の発生は悪材料だったほか生活必需品などの高騰継続はマイナス要因に。国内景気は、懸念材料はあるものの人出の増加にともなう消費活動がけん引し、上向きに転じた。
■今後の見通しはおおむね横ばい傾向で推移
今後1年間程度の国内景気は、経済社会活動の正常化に向けた動きが一段と進むことが、景気を支える原動力になるとみられる。4月以降も延長される全国旅行支援やインバウンド、新型コロナの5類移行などによる人出の増加は個人消費を中心に幅広い業界でプラスに作用していくと見込まれる。さらに、IT投資をはじめとするDXの推進、各種イベントの通常開催、都市部の再開発なども好材料となろう。一方で、海外経済やロシア・ウクライナ情勢は不透明感が強く、原材料価格の高騰や人手不足などの長期化は懸念材料となる。構造的な問題に加えて、コロナ関連融資の返済、金利動向なども悪材料に。今後は、原材料価格高騰など下振れ要因はあるものの、おおむね横ばい傾向で推移するとみられる。
今後の見通し
■企業倒産「潮目」が変化 22年度は3年ぶり増加、コロナ融資返済本格化前に
2022年度の倒産件数は前年度を883件上回る6799件が発生し、3年ぶりに増加した。22年5月以降、23年3月まで11カ月連続して前年同月を上回っており、増加期間はリーマン・ショック後の08年6月-09年8月(15カ月連続)にせまった。特に3月は800件(前年同月587件、36.3%増)となり、長く続いた月間500件台の水準を大幅に超えて単月としてはコロナ禍直後の20年7月以来2年8カ月ぶり、3月としては17年以来6年ぶりに800件台を突破した。23年度半ばと想定されるコロナ融資の返済本格化を前に足元の企業倒産は増加基調を強めており、倒産動向の“潮目”が明らかに変わりつつある。
2022年度の倒産動向の特徴は、手厚い資金繰り支援が終了したところに「物価高(インフレ)」「人手不足」「コロナ融資」「円安」など四重・五重の苦境が襲い、事業継続を断念した中小企業が多い点だ。「物価高倒産」や「コロナ融資後倒産」はそれぞれ前年度から急増、「人手不足倒産」も建設や運輸業を中心に146件判明し3年ぶりの増加となった。
■負債総額は5年ぶり2兆円台 倒産の7割が中小零細
負債総額は2兆3385億9100万円となり、2021年度(1兆1828億7100万円)のほぼ2倍に膨らんだ。1兆円を超える負債を抱えて経営破綻した自動車部品製造のマレリHD(22年6月民事再生)、有機ELディスプレイ製造のJOLED(23年3月同)など、負債100億円を超える大型倒産が12件発生し、4年ぶりに前年度を上回った。2022年度の負債総額はエアバッグ製造大手の「タカタ」(17年6月民事再生)が破綻した17年度(2兆5932億2600万円)以来、5年ぶりに2兆円台を超えた。企業倒産の7割超が負債1億円に満たない中小・零細企業で占める状況に変わりはないものの、20年度をピークにその割合は低下している。一方、負債1~10億円クラスの割合は高まり、中堅クラスの倒産も増加の動きが強まっている。
■2023年度は「ゾンビ」の動向注視 抜本的再生が必要な企業は3万社規模
帝国データバンクの推計では、稼いだ利益で借入金の利子を支払えない、国際決済銀行(BIS)の定義に基づく「ゾンビ企業」の数は、2021年度に全国18.8万社にのぼる。20年度(推計16.6万社)から2年連続で増加するなど増加傾向が続いており、自社の経営体力に見合わない過大な借入金を背負った中小企業の出口戦略が早急に求められている。
実際、推計した18.8万社のうち、経常赤字など「収益力改善」が課題の企業(=経常赤字)はゾンビ全体の6割に上る。また、「過剰債務解消」や、債務超過など「資本力の改善」が課題の企業もそれぞれ4割前後を占め、これら3つの課題がすべて該当する企業も約2割の3.3万社を占めた。これらゾンビはすぐに倒産するわけではないが、年間倒産件数の約5倍に匹敵する規模の企業が“潜在的な倒産リスク”を抱えていることを示している。コロナ融資の返済本格化や今後予想される金利上昇局面などを踏まえると、これらの企業群が事業継続を断念し、倒産件数を押し上げる影響力は過小評価できない。
■企業倒産、コロナ前水準への到達視野に緩やかな増加局面続く
国内景気はアフターコロナに向けた前向きな動きが加速している。企業の景況感を示すTDB景気動向指数(DI)も、2022年度中は期初→期末にかけて3.1ポイント改善し、17年度(+3.9)以来5年ぶりの景気改善幅を記録した。こうした局面では、「景気の変わり目に倒産が増える」と謂われるように、仕入増や人件費増、設備増強に伴う運転資金需要に資金調達が追い付かない「黒字倒産」の発生も懸念され、今後の倒産増加を後押しする可能性がある。コロナ禍の企業支援として特例的に認められた社会保険料など公租公課の支払い猶予も終了し、滞納が続く企業ではその支払いが強く求められるようになる。各種コスト増も重なり、こうした資金繰り負担に耐えきれない中小企業の「淘汰」「選別」が一段進む可能性もある。
2023年度の企業倒産は、コロナ禍前の水準(年間8000件台)も視野に、緩やかな増加局面が続きそうだ。

