倒産件数は687件、2カ月ぶりの前年同月比増加
負債総額は1059億1600万円、4カ月連続の前年同月比減少
倒産件数 | 687件 |
|---|---|
前年同月比 | +16.8% |
前年同月 | 588件 |
負債総額 | 1059億1600万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲43.3% |
前年同月 | 1867億6200万円 |
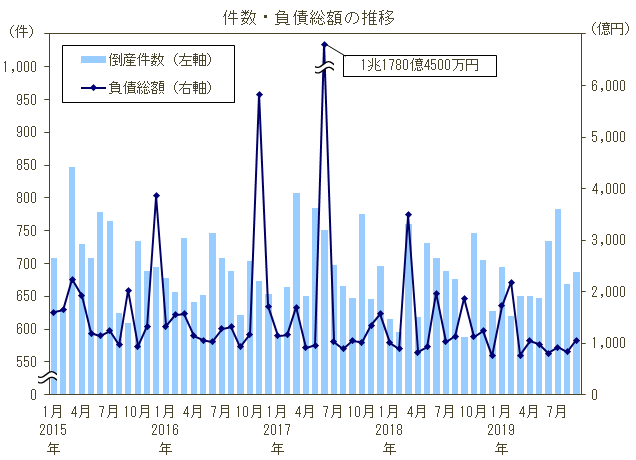
主要ポイント
- ■倒産件数は687件(前年同月比16.8%増)と、2カ月ぶりの前年同月比増加
- ■負債総額は、前年同月に(株)ケフィア事業振興会(負債1001 億9462万円)とそのグループの倒産が発生した反動もあり、前年同月比43.3%減の1059億1600万円
- ■業種別に見ると、7業種中すべてで前年同月を上回った。全業種の増加は2009年4月以来、10年5カ月ぶり。製造業(82件、前年同月比32.3%増)は、金属製品製造や機械製造の増加が目立った。小売業(155件、同27.0%増)は衣料・雑貨など繊維製品小売(20件、同11.1%増)、飲食料品小売(26件、同13.0%増)などの増加で、4カ月連続の前年同月比増加
- ■主因別に見ると、「不況型倒産」の合計は569件。構成比は82.8%を占める
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は429件(前年同月比19.8%増)、構成比は62.4%を占める
- ■地域別に見ると、9地域中5地域で前年同月を上回った。近畿(182件)は、製造業(24件、前年同月比166.7%増)などの増加で前年同月比51.7%増。一方、中部(89件、同2.2%減)は製造業などの減少で2カ月連続の減少
- ■負債トップは、上海国際(株)(民事再生、東京都)の約200億円
調査結果
■件数・負債総額
倒産は687件、2カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数は687件(前年同月比16.8%増)と、2カ月ぶりに前年同月を上回った。
負債総額は、前年同月に(株)ケフィア事業振興会(負債1001億9462万円)とそのグループの倒産が発生した反動もあり、前年同月比43.3%減の1059億1600万円となった。
■業種別
10年5カ月ぶりに全業種で前年同月比増加
業種別に見ると、7業種中すべてで前年同月を上回った。全業種の増加は2009年4月以来、10年5カ月ぶり。
建設業(120件、前年同月比22.4%増)は、総合工事(55件、同48.6%増)と設備工事(21件、同31.3%増)が前年同月比2ケタ増。製造業(82件、同32.3%増)は、原材料価格の高止まりや設備投資にともなう借入過多などで、金属製品製造や機械製造の増加が目立った。小売業(155件、同27.0%増)は衣料・雑貨など繊維製品小売(20件、同11.1%増)、飲食料品小売(26件、同13.0%増)などの増加で、4カ月連続の前年同月比増加。
■主因別
「不況型倒産」は569件、構成比は82.8%
主因別に見ると、「不況型倒産」の合計は569件(前年同月比28.4%増)となり、2カ月ぶりに前年同月を上回った。構成比は82.8%(同7.5ポイント増)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
負債5000万円未満の構成比62.4%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は429件(前年同月比19.8%増)、構成比は62.4%を占めた。負債5000万円未満の倒産では、小売業(122件)が構成比28.4%(同3.5ポイント増)を占め最多、サービス業(111件)が同25.9%(同3.4ポイント減)で続く。 資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人事業主含む)の倒産が467件(前年同月比19.7%増)、構成比は68.0%を占めた。
■地域別
9地域中5地域で前年同月比増加
地域別に見ると、9地域中5地域で前年同月を上回った。
近畿(182件、前年同月比51.7%増)は、金型メーカーや繊維製品メーカーの小規模倒産が増え、製造業(24件、同166.7%増)が大幅増。九州(58件、同75.8%増)は、災害復興関連工事の落ち着きなどから、低水準だった前年を上回り、建設業(12件、同300.0%増)の増加が目立った。東北(42件、同75.0%増)は、建設業(10件、同150.0%増)、卸売業(5件、同150.0%増)など5業種で増加した。
一方、中部(89件、前年同月比2.2%減)は2カ月連続の減少。北陸(12件、同42.9%減)は建設業やサービス業の減少で、6カ月ぶりの減少となった。
■態様別
「破産」は641件、構成比は93.3%
態様別に見ると、破産は641件(構成比93.3%)、特別清算は22件(同3.2%)となった。民事再生法は24件(同3.5%)と、前年同月(14件)を大きく上回った。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは45.0、2カ月連続で改善
2019年9月の景気DIは前月比0.3ポイント増の45.0となり、2カ月連続で改善した。
9月の国内景気は、消費税率の引き上げを翌月に控え、緩やかながらも駆け込み需要が耐久財や高額品で発生したほか、軽減税率対応への需要も好材料となった。加えて、公共工事の前倒し執行や東京五輪を控えた建設投資から工事関連が活発化。燃料価格の低下やラグビーW杯日本大会の開催もプラス材料となった。一方、世界的な自動車販売および半導体関連の低迷や、工作・産業機械の受注減を背景に製造業の悪化が続いた。深刻な人手不足が負担増につながったほか、台風15号の被害により一部地域で企業活動が停滞した。
消費税率引き上げによる消費の落ち込みや輸出減速など、不透明感が一層強まる
今後は、消費税率の引き上げによる消費の落ち込みが、最大の懸念材料となる。貿易摩擦を背景とした世界経済の低迷による輸出および設備投資の減速に加え、人件費や燃料費などの負担も重荷になると予想される。また、日韓関係の悪化や世界的な金融緩和政策の動向、地政学的リスクが及ぼす影響は、注意深く見ていく必要がある。他方、政府の経済対策や都市部の再開発、東京五輪、省力化投資などはプラス材料となろう。
今後の国内景気は、消費の落ち込みに加えて、輸出減速や設備投資の慎重化など懸念材料が多く、不透明感が一層強まっている。
今後の見通し
■アパレル不振が深刻化、中規模クラスの倒産相次ぐ
2019年度上半期(2019年4~9月)の倒産件数(4172件、前年同期比4.0%増)は、2年ぶりに前年同期を上回った。負債総額は5646億4800万円と、2016年度上半期(6756億200万円)を下回り、比較可能な2000年度以降の半期ベースで最小を更新した。
業種別では、小売業(988件、前年同期比7.9%増)の増加が件数全体を押し上げたほか、製造業(479件、同6.2%増)、運輸・通信業(145件、同16.9%増)など計5業種で前年同期を上回った。衣料品や靴、鞄などのアパレル関連企業では、負債数億円から数十億円規模の倒産が相次いで発生したことなどから、負債1億円以上の倒産(999件、同1.5%増)は、リーマン・ショック直後の2009年度上半期(2670件、同0.9%増)以来10年ぶりのプラスに転じた。
■建設業の倒産、減少傾向は底打ちか
建設業の倒産は、直近ピークの2008年度(3556件)以降減少基調で推移し、とくに近年は国土強靭化に基づくインフラ整備や災害復興、都市部での再開発案件の増加などを背景に、前年度には過去最少(1375件)を更新した。しかし、2019年度上半期(718件)は前年同期比2.1%の増加と、震災復旧・復興工事が最盛期を過ぎた東北(前年同期比10.0%増)で2年連続増加したほか、北海道(同23.1%増)、四国(同62.5%増)、九州(同59.5%増)など地方圏で、労務費や建材費の上昇を背景とした採算悪化による倒産が目立った。
直近2019年8月の新設住宅着工戸数(国土交通省)は2カ月連続で減少し、このうち持ち家は11カ月ぶりに、また貸家は12カ月連続で前年割れとなるなど、住宅建設では落ち込みがみられている。業界全体では、公共事業を中心に今後も底堅い受注動向が見込まれるものの、地域人口の減少が進むなか、地方圏を中心にさらなる倒産増加も懸念される。
■リスケ後倒産の増勢続く
金融機関から返済条件の変更等(リスケジュール)を受けた企業による返済猶予後倒産は、2019年度上半期255件と前年同期を23.8%上回り、増加率は2半期連続で20%を超え、2014年度上半期(257件)以来5年ぶりの高水準となった。負債総額は1154億7000万円にのぼる。
金融庁は9月10日、金融機関の経営を監督するための「金融検査マニュアル」を12月に廃止する方針を公表。過去の実績を基にした画一的な検査を改め、持続可能な経営に向けた収益性や地域貢献などに重点を置いた検査に移行する。今後は柔軟な貸倒引当金の計上による将来性などを考慮した融資先支援が期待される一方、抜本的な経営改善が進まずにリスケ解消が見込めない企業の整理は緩やかに進むと想定され、その動向が注目される。
■中小零細の負担感強まり、倒産は増加傾向たどる可能性も
消費マインドが弱まるなか、5年半ぶりに消費税率の引き上げが実施された。引き上げ分の料金を価格に転嫁できていない飲食店や小売店は多いとみられるうえ、消費者の節約志向のさらなる高まりなども予想され、経営への影響が懸念される。また、この10月からは最低賃金が全国平均で過去最大の27円引き上げられ、東京都と神奈川県では全国で初めて1000円を超えた。物流費や原材料費なども上昇もしくは高止まり傾向のなか、負担感は中小零細企業ほど強い。
今後は、収益環境のさらなる悪化が見込まれる飲食店、小売店など労働集約的な業種の倒産が件数全体を押し上げながら、緩やかな増加傾向をたどる可能性が高まっている。

