倒産件数は506件、1月としては2000年以降2番目の低水準
負債総額は912億5800万円、1月としては2000年以降最小
倒産件数 | 506件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲29.0% |
前年同月 | 713件 |
負債総額 | 912億5800万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲22.2% |
前年同月 | 1172億5000万円 |
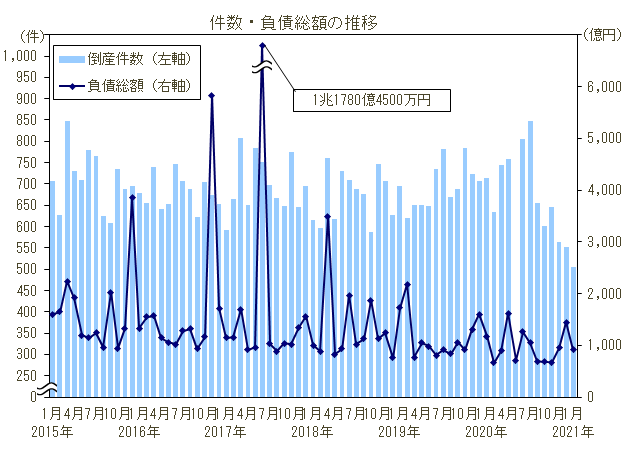
主要ポイント
- ■倒産件数は506件(前年同月比29.0%減)と、1月としては2000年以降2番目の低水準
- ■負債総額は912億5800万円(前年同月比22.2%減)と、1月としては2000年以降最小
- ■負債額最大の倒産は大興製紙㈱(静岡県、会社更生)の約140億800万円
- ■業種別にみると、7業種中6業種で前年同月を下回った。製造業(42件、前年同月比39.1%減)は2020年5月に次ぐ過去2番目の低水準。小売業(121件、同30.1%減)の飲食料品小売(19件)は巣ごもり需要や、外食や宴会を控える動きの影響で減少傾向が続き、7カ月連続の減少となった
- ■主因別にみると、「不況型倒産」の合計は391件(前年同月比32.4%減)と、6カ月連続で前年同月を下回った。構成比は77.3%(同3.8ポイント減)を占める
- ■負債規模別にみると、負債5000万円未満の倒産は321件(前年同月比27.0%減)、構成比は63.4%を占める
- ■地域別にみると、全地域で前年同月比2ケタ減となった。東北(17件、前年同月比63.0%減)は、全県・全業種で減少。北陸(10件、同60.0%減)は、過去2番目の低水準。関東(180件、同28.6%減)は1都5県で減少。東京都(77件)は過去3番目の低水準となった
- ■人手不足倒産は8件(前年同月比61.9%減)発生、5カ月連続の前年同月比減少
- ■後継者難倒産は31件(前年同月比27.9%減)発生、4カ月連続の前年同月比減少
- ■返済猶予後倒産は29件(前年同月比40.8%減)発生、5カ月連続の前年同月比減少
■件数・負債総額
件数、負債総額ともに低水準
倒産件数は506件(前年同月比29.0%減)と、1月としては2000年以降2番目の低水準。負債総額は912億5800万円(同22.2%減)と、1月としては2000年以降最小となった。
また、件数・負債総額ともに6カ月連続の前年同月比減少。■業種別
6業種で前年同月比減少
業種別にみると、7業種中6業種で前年同月を下回った。製造業(42件、前年同月比39.1%減)は2020年5月に次ぐ過去2番目の低水準。卸売業(65件、同46.7%減)は、繊維製品卸(7件)や機械器具卸(10件)などで減少し、7カ月連続の2ケタ減となった。また、小売業(121件、同30.1%減)も7カ月連続の減少。なかでも飲食料品小売(19件)は巣ごもり需要や、外食や宴会を控える動きの影響で減少傾向が続き、7カ月連続の減少となった。
一方、不動産業(20件、前年同月比11.1%増)は唯一の増加。4カ月ぶりに増加へ転じた。■主因別
「不況型倒産」は391件、構成比77.3%
主因別にみると、「不況型倒産」の合計は391件(前年同月比32.4%減)と、6カ月連続で前年同月を下回った。構成比は77.3%(同3.8ポイント減)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
負債5000万円未満の構成比63.4%
負債規模別にみると、負債5000万円未満の倒産は321件(前年同月比27.0%減)、構成比は63.4%を占めた。負債5000万円未満の倒産では、小売業(90件)が構成比28.0%(同0.9ポイント減)を占め最多、サービス業(88件)が同27.4%(同1.3ポイント減)で続く。
資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人事業主含む)の倒産が358件(前年同月比25.1%減)、構成比は70.8%を占めた。■地域別
全地域で前年同月比減少
地域別にみると、全地域で前年同月比2ケタ減となった。東北(17件、前年同月比63.0%減)は、全県・全業種で減少。県別では宮城県や秋田県が、業種別では建設業などで減少が目立ち、7カ月連続の減少。
北陸(10件、同60.0%減)も全県で減少し、2005年6月に次ぐ過去2番目の低水準。関東(180件、同28.6%減)は千葉県を除く1都5県で減少。なかでも東京都(77件)は前年同月比33.0%減と、過去3番目の低水準となった。■態様別
「破産」は462件、構成比91.3%
態様別にみると、破産は462件(構成比91.3%)、特別清算は29件(同5.7%)となった。
民事再生法は14件で、うち9件を個人事業主が占めた。また、2カ月連続で会社更生法による倒産が発生(大興製紙㈱、静岡県、負債約140億800万円)。■特殊要因倒産
人手不足倒産
8件(前年同月比61.9%減)発生、5カ月連続の前年同月比減少
後継者難倒産
31件(前年同月比27.9%減)発生、4カ月連続の前年同月比減少
返済猶予後倒産
29件(前年同月比40.8%減)発生、5カ月連続の前年同月比減少
※特殊要因倒産では、主因・従因を問わず、特徴的な要因による倒産を集計
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは33.9、2カ月連続で悪化
2021年1月の景気DIは前月比1.1ポイント減の33.9となり、2カ月連続で悪化した。
1月の国内景気は、11都府県で2回目となる緊急事態宣言が発出され、外出自粛や飲食店を中心とした営業時間の短縮要請などが実施されたことで、再び下押し圧力が強まった。また、政府による各種支援策の一時停止や、企業の出張が抑制されたことなどで宿泊業界が一段の悪化となった。日本海側を中心とした寒波と記録的な大雪などによる個人消費の落ち込みのほか、自動車メーカーの減産の影響もみられた。
他方、半導体製造装置が高水準で推移したほか、パソコンや暖房器具などを含む自宅内消費関連は上向き傾向が続いた。一時的に後退するも春ごろから緩やかな上向きか
今後1年程度の国内景気は、緊急事態宣言の延長による影響のほか、社会経済活動の抑制などにともなう下振れリスクを抱えつつ推移すると見込まれる。新型コロナウイルスの感染状況次第ながら、地域間や業種間で景気動向が二極化していく可能性もある。また、雇用・所得環境の悪化による個人消費への影響は懸念材料であろう。他方、ワクチン接種の開始による経済活動の正常化に向けた動きに加え、自宅内消費など新しい生活様式に対する需要の拡大、米国や中国など海外経済の回復などはプラス要因になるとみられる。
今後の景気は、一時的な後退はみられるものの、春頃を底として、緩やかに上向いていくとみられる。今後の見通し
■1月の企業倒産、件数は過去2番目の低水準、負債は過去最小
2021年1月の倒産件数(506件、前年同月比29.0%減)は6カ月連続で前年同月を下回り、1月としては2000年1月(354件)に次ぎ2番目の低水準となった。各種給付金や金融機関の特別融資など支援策の効果が持続するなか、全7業種中、不動産を除く6業種が前年同月比で減少、なかでも建設、製造、卸売の3業種は1月では2000年以降最少を記録した。
負債総額(912億5800万円、前年同月比22.2%減)は、1月として過去最小となった。負債5000万円未満の倒産の構成比(63.4%)は1月の過去最高となり、小規模倒産が大半を占めた。1月の負債額最大の倒産は、特殊紙の製造を手がける大興製紙㈱(静岡県、会社更生、負債約140億800万円)で、競合激化や借入金過多が続くなか、コロナ禍の受注減が追い打ちをかけた。■原材料価格が上昇、生産・販売計画や収益性への影響に注目
2021年1月、ジョー・バイデン氏が第46代米国大統領に就任した。新政権では、新型コロナ感染拡大による米国経済失速から早期の回復を目指し、現金給付など家計支援を重視した大規模な景気対策が予定されている。日本企業への影響について、予算実行の動向にもよるが製造業など関連産業の追い風となる可能性もある。他方、コロナ禍からのV時回復をはかる中国経済などを背景として、足元では原材料などの価格上昇が懸念材料に浮上している。
TDB景気動向調査(2021年1月調査)によると、仕入れ単価DIは53.7となり8カ月連続で上昇した。半導体部品の調達が難航し生産に影響が出ているケースもあり、原材料や部品を始めとした仕入れ単価の上昇を販売単価にスムーズに転嫁できるか、収益性や資金繰りへの影響が注目される。■緊急事態宣言が延長、業態で明暗が分かれるなか各種支援策の動向を注視
2020年の訪日外客数は、コロナ禍における入国制限などを背景に前年比87.1%減の約411万人(日本政府観光局 JNTO)と極端に減少した。過去最多の訪日外客数を記録した2019年から一転、インバウンド需要の消滅は、恩恵を直接受けてきた産業以外へもマイナスの影響を与えつつある。ホテル建設にかかわる工事を中心に手がけていた鉄骨工事業者や、ショッピングバッグなどに利用される包装用紙メーカーなど、これまで間接的にインバウンド需要に支えられてきた企業の経営破綻も見受けられる。
新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした緊急事態宣言に目をむけると、東京など10都府県について3月7日までの期限延長が決定した。在宅勤務や巣ごもり需要を背景に好業績をあげる業態がある一方、飲食業を始めとする対面型のサービス業態などは、厳しい事業環境が長期化し、今後、取引業者の業績へもマイナスの影響が予想される。コロナ禍で事業環境が大きく変化するなか、企業の20.3%が業態転換の予定があると回答している(「新型コロナウイルス感染症に対する企業の意識調査2020年12月」 帝国データバンク 2021年1月発表)。インバウンド需要なども含め短期的な回復が見込めないなか、新たな需要への対応を模索する企業がある一方で、既存業態に終始し収益性の改善に難航する企業は多い。
雇用調整助成金などの特例措置は継続されるものの、コロナ禍で業績が低迷した事業者の納税を猶予する特例制度の対象期間が終了したほか、持続化給付金や家賃支援給付金の申請も2月中に期限をむかえる。他方、2020年春頃から、多くの金融機関はコロナ対応融資をスピード重視で実施してきた。緊急融資金の導入から時間が経過するなか、業績回復に難航し追加融資などが必要な企業の事業計画や取引金融機関の対応が注目される。借入金の返済猶予などを要請している企業においては、業態転換の難航や後継者不在などを理由に事業継続を断念することが危惧されるなど、引き続き楽観できない状況が続く。

