倒産件数は615件、2カ月連続の前年同月比増加
負債総額は1004億7700万円、4カ月連続の前年同月比減少
倒産件数 | 615件 |
|---|---|
前年同月比 | +4.1% |
前年同月 | 591件 |
前月比 | ▲11.6% |
前月 | 696件 |
負債総額 | 1004億7700万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲12.2% |
前年同月 | 1144億円 |
前月比 | ▲35.8% |
前月 | 1565億7200万円 |
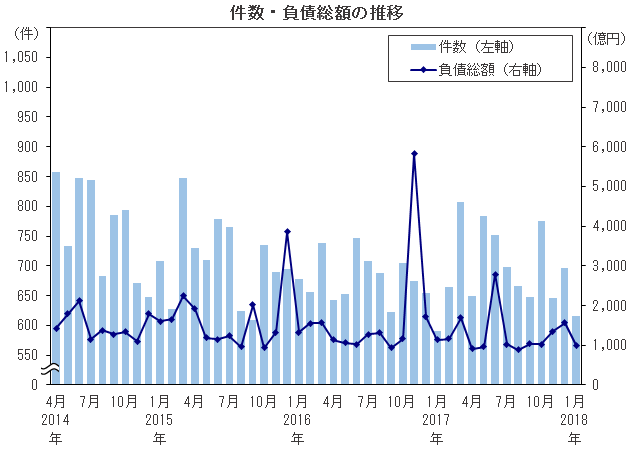
主要ポイント
- ■倒産件数は615件(前年同月比4.1%増)で、2カ月連続で前年同月を上回った。負債総額は1004億7700万円(同12.2%減)と、4カ月連続で前年同月を下回った
- ■業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を上回った。このうち、卸売業(102件、前年同月比13.3%増)、サービス業(137件、同10.5%増)の2業種は2カ月連続の前年同月比増加となった。一方、3業種は前年同月を下回り、このうち建設業(104件、同7.1%減)は2カ月連続の前年同月比減少となった
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は492件(前年同月比1.4%増)となり、5カ月連続で前年同月を上回った。構成比は80.0%(同2.1ポイント減)を占めた
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は370件(前年同月比0.8%増)、構成比は60.2%(同1.9ポイント減)を占めた。資本金規模別に見ると、資本金1000万円未満(個人含む)の倒産は393件(同11.6%増)、構成比は63.9%(同4.3ポイント増)となった
- ■地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を上回った。このうち、中部(105件、前年同月比36.4%増)は5カ月連続、九州(40件、同11.1%増)は2カ月連続の前年同月比増加となった。一方、5地域では前年同月を下回り、このうち北海道(18件、同10.0%減)、北陸(10件、同44.4%減)の2地域は2カ月連続の前年同月比減少となった
- ■負債トップは、(株)大黒地所(愛知県、破産)の72億円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント倒産件数は615件、2カ月連続の前年同月比増加
倒産件数は615件(前年同月比4.1%増)で、2カ月連続で前年同月を上回った。負債総額は1004億7700万円(同12.2%減)と、4カ月連続で前年同月を下回った。
要因・背景
件数…業種別では7業種中4業種で、地域別では9地域中4地域で前年同月比増加
負債総額…負債100億円以上の大型倒産は発生せず、小規模倒産が約6割を占めた
■業種別
ポイント7業種中4業種で前年同月比増加
業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を上回った。このうち、卸売業(102件、前年同月比13.3%増)、サービス業(137件、同10.5%増)の2業種は2カ月連続の前年同月比増加となった。一方、3業種は前年同月を下回り、このうち建設業(104件、同7.1%減)は2カ月連続の前年同月比減少となった。
要因・背景
- 1. サービス業は、学習塾・教室経営や、デザイン業などの専門サービス(33件、前年同月比13.8%増)、診療所・整体院などの医療業(13件、同18.2%増)などが増加
- 2. 建設業は、底堅い建設需要を背景に、土木・建築などの総合工事(36件、前年同月比5.3%減)、電気配線・管工事などの設備工事(28件、同20.0%減)が減少
■主因別
ポイント「不況型倒産」は492件、構成比は80.0%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は492件(前年同月比1.4%増)となり、5カ月連続で前年同月を上回った。構成比は80.0%(同2.1ポイント減)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1.不況型倒産のうち、製造業、卸売業、運輸・通信業の3業種は前年同月比増加
- 2.「人手不足倒産」は12件(前年同月比100.0%増)、2カ月連続の前年同月比増加
- 3.「返済猶予後倒産」は38件(前年同月比35.7%増)、3カ月連続の前年同月比増加
- 4.「チャイナリスク関連倒産」は8件(前年同月比33.3%増)、2カ月ぶりの前年同月比増加
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比60.2%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は370件(前年同月比0.8%増)、構成比は60.2%(同1.9ポイント減)を占めた。資本金規模別に見ると、資本金1000万円未満(個人含む)の倒産は393件(同11.6%増)、構成比は63.9%(同4.3ポイント増)となった。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産では、製造業(36件、前年同月比24.1%増)、小売業(106件、同5.0%増)など4業種で前年同月を上回った
- 2. 負債100億円以上の大型倒産は発生しなかった
■地域別
ポイント9地域中4地域で前年同月比増加
地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を上回った。このうち、中部(105件、前年同月比36.4%増)は5カ月連続、九州(40件、同11.1%増)は2カ月連続の前年同月比増加となった。一方、5地域では前年同月を下回り、このうち北海道(18件、同10.0%減)、北陸(10件、同44.4%減)の2地域は2カ月連続の前年同月比減少となった。
要因・背景
- 1. 中部は、愛知県を中心に増加が目立ち、建設業(23件、前年同月13件)、サービス業(26件、同15件)の2業種で大幅増
- 2. 北陸は、個人消費の持ち直し傾向を受け、小売業が3カ月連続の前年同月比2ケタ減
■上場企業倒産
上場企業の倒産は発生しなかった。
2017年度では、東証1部上場のタカタ(株)(民事再生法、6月)の1件が発生。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは51.1、過去最高を更新
2018年1月の景気DIは前月比0.2ポイント増の51.1となり8カ月連続で改善、2002年の調査開始以降、過去最高(これまでの最高は2014年3月の51.0)を更新した。
1月の国内景気は、中国や米国への半導体関連や機械の輸出増加が継続、製造業の好調が部品や測定器製造、サービスにも波及した。また、寒波到来で季節商品の需要が膨らんだほか、日経平均株価が一時2万4000円を突破するなど高値で推移したことが高額品の購入に一部寄与した。10業界中3業界、3規模中1規模、10地域中3地域が過去最高を更新した一方で、食品および燃料価格の上昇や円高進行はマイナス要因となった。国内景気は、機械類を中心に製造業が好調なことに加え、寒波による季節需要の増加なども寄与し拡大が続いた。
今後の国内景気は、企業の好調が継続し拡大基調で推移する見込み
国内経済は、中国などへの輸出好調の継続や、製造業を中心とした堅調な設備投資が景気の押し上げ要因になると見込まれる。個人消費は、物価の上昇を上回る賃上げを通じた実質可処分所得の増加がカギとなろう。日本国内や米国の税制改革および2019年10月に予定される消費税率引き上げにともなう駆け込み需要は、景気にプラスに働くと見られるが、深刻化する人手不足による悪影響に加えて、欧米の金融政策や為替の動向には注視する必要がある。
個人消費の本格的な回復が一段と重要性を増すとみられるなか、今後の国内景気は、輸出や設備投資など企業部門の好調が継続し拡大基調で推移すると見込まれる。
今後の見通し
■倒産件数、都市圏から地方圏に広がる可能性も
1月の倒産件数は615件(前年同月比4.1%増)となり、2カ月連続で増加した。「東京都」「大阪府」「愛知県」の3都府県を見ると、「大阪府」は減少したが、3都府県合計では255件(同5.4%増)と、8年ぶりに増加した2017年に引き続き、2018年も増加傾向で推移している。他方、2017年に減少していた他の地域においても、1月は360件(同3.2%増)で、4カ月連続の増加となった。倒産件数は都市圏から地方圏へと広がる可能性が示唆される。
しかし、業種別に見ると、3都府県では2017年に建設業や製造業、運輸・通信業などの倒産件数が増加した一方、他の地域ではこれらの業種は減少するなど、都市圏と地方圏で倒産傾向が異なっている。また、小売業やサービス業などでは両圏域とも増加するという共通点もみられ、変化する倒産業種の傾向を注視する必要がある。
■問われるシステムリスクへの管理態勢、ネットを活用する事業者に影響する可能性も
金融庁は2月2日、みなし仮想通貨交換業者であるコインチェック(東京都)への立入検査に着手するとともに、同社以外の全仮想通貨交換業者に対して、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出した。インターネットを通じた新サービスが急速に広がりを見せるなか、改めてシステムリスクに対する注目が集まっている。
また、2019年にマネー・ローンダリング(資金洗浄)対策における国際協調を推進するための政府間会合であるFATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査が予定されるなか、同庁は、マネー・ローンダリングに関する新しいガイドラインを策定、2月1日に対策企画室を設置し、金融機関にシステム管理等に対する取り組み強化を求めている。今後は、金融機関だけでなく、インターネット上でのセキュリティ対策の強化を計画している企業や、インターネットを活用したEC(電子商取引)サービスなど個人情報を含む事業を展開する企業も管理強化を求められる可能性がある。
■増減を繰り返しながら、緩やかな増加基調で推移する見通し
国内経済は、輸出拡大の継続や製造業を中心とした設備投資が景気を押し上げる要因になるとみられる。一方で、個人消費の本格的な回復が一段と重要性を増してこよう。特に、実質可処分所得の増加がカギとなる。1月は美容業の倒産件数が増加するなど消費動向に敏感な業種で増加しており、今後の動向が注目される。また、2兆8千億円規模の2017年度補正予算(2月1日成立)による災害復旧・防災等の公共工事や生産性向上対策費などの執行で、建設業界やソフトウェア関連業界にとってプラス要因となりうる。ただし、人手不足倒産が2カ月連続で増加しており、人手不足は深刻度を増している。加えて、原油・素材価格の上昇や欧米における政治・経済情勢の行方、中東や東アジアなど地政学リスク、外国為替市場や株式市場といった金融市場動向など、今後の経済環境に対する懸念材料は多い。
さらに、金融庁による金融検査・監督の考え方と進め方が変更されるなかで、事業性評価や融資判断など、金融機関による融資姿勢も変化していかざるを得ないとみられる。
当面の倒産件数は、国内景気が拡大基調で推移すると予測されるなかで、増減を繰り返しながら、緩やかな増加基調で推移していくと見込まれる。

