倒産件数は647件、2014年最少を記録
負債総額は1792億4600万円、7カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数 | 647件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲10.9% |
前年同月 | 726件 |
前月比 | ▲3.6% |
前月 | 671件 |
負債総額 | 1792億4600万円 |
|---|---|
前年同月比 | +2.0% |
前年同月 | 1757億9500万円 |
前月比 | +62.9% |
前月 | 1100億2300万円 |
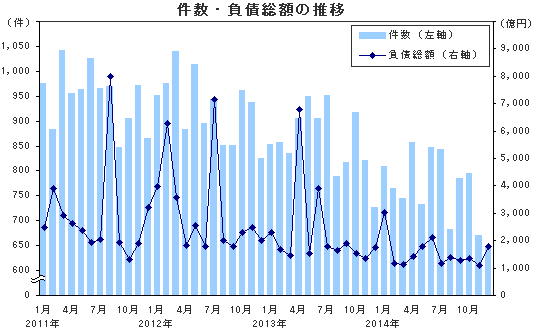
主要ポイント
- ■倒産件数は647件で、前月比は3.6%、前年同月比も10.9%の減少となった。17カ月連続で前年同月を下回り、2014年最少を記録。12月としては2000年(684件)以来14年ぶりの600件台にとどまった
- ■負債総額は1792億4600万円となり、前月比は62.9%、前年同月比も2.0%の増加と、7カ月ぶりに前年同月を上回った
- ■業種別に見ると、建設業(136件、前年同月比7.5%減)、小売業(128件、同4.5%減)など、7業種中5業種で前年同月を下回り、うち製造業(82件、同32.2%減)、卸売業(93件、同19.1%減)など3業種は前年同月比2ケタの大幅減
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の構成比は80.7%(前月79.3%、前年同月82.8%)。前月を1.4ポイント上回ったものの、前年同月を2.1ポイント下回り、2カ月ぶりの80%台
- ■「返済猶予後倒産」は24件(前年同月比20.0%減)判明
- ■「円安関連倒産」は44件(前月42件)判明し、4カ月連続で最多件数を更新
- ■負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は366件で、前年同月比6.9%の減少。構成比は56.6%と26カ月連続で過半数を占めた
- ■地域別に見ると、関東(241件、前年同月比15.4%減)、近畿(178件、同0.6%減)など9地域中5地域で前年同月を下回り、うち4地域は前年同月比2ケタの大幅減
- ■負債トップは、(株)インターナショナルイーシー(東京都、破産)の485億5300万円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は2014年最少、負債総額は7カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数は647件で、前月比は3.6%、前年同月比も10.9%の減少となった。17カ月連続で前年同月を下回り、2014年最少を記録。12月としては2000年(684件)以来14年ぶりの600件台にとどまった。負債総額は1792億4600万円となり、前月比は62.9%、前年同月比も2.0%の増加と、7カ月ぶりに前年同月を上回った。
要因・背景
件数…関東の製造業(27件、前年同月比53.4%減)、近畿の建設業(35件、同14.6%減)、卸売業(24件、同35.1%減)などで減少目立つ
負債総額…負債100億円以上の大型倒産が4カ月ぶりに発生
■業種別
ポイント7業種中5業種で前年同月比減少
業種別に見ると、建設業(136件、前年同月比7.5%減)、小売業(128件、同4.5%減)など、7業種中5業種で前年同月を下回り、うち製造業(82件、同32.2%減)、卸売業(93件、同19.1%減)など3業種は前年同月比2ケタの大幅減少となった。一方、サービス業(136件、同2.3%増)は唯一前年同月比で増加。不動産業(23件)は前年同月と同数となった。
要因・背景
- 1.建設業…災害復旧工事やインフラ整備の受注増加により、27カ月連続の前年同月比減少
- 2.製造業…金属製品製造(6件、前年同月比57.1%減)や電気機械器具製造(6件、同57.1%減)、自動車部品製造(3件、同62.5%減)などを中心に幅広く減少
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比80.7%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は522件(前年同月比13.1%減)となった。構成比は80.7%(前月79.3%、前年同月82.8%)と、前月を1.4ポイント上回ったものの、前年同月を2.1ポイント下回り、2カ月ぶりに80%台となった。
要因・背景
- 1.「返済猶予後倒産」は24件(前年同月比20.0%減)判明
- 2.「円安関連倒産」は44件(前月42件)判明し、4カ月連続で最多件数を更新
■倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比56.6%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は366件で、前年同月比6.9%の減少。構成比は56.6%と26カ月連続で過半数を占めた。一方、負債10億円以上の倒産は30件、うち同100億円以上の大型倒産が4カ月ぶりに1件発生した。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が378件、構成比は58.4%を占めた。
要因・背景
- 1.負債5000万円未満の倒産、業種別では卸売業(37件、前年同月比31.5%減)で大幅減
- 2.大企業、中堅企業の業績回復や資金繰り改善を受け、大型倒産の小康状態続く
■地域別
ポイント9地域中5地域で前年同月比減少
地域別に見ると、関東(241件、前年同月比15.4%減)、近畿(178件、同0.6%減)など9地域中5地域で前年同月を下回り、うち4地域は前年同月比2ケタの大幅減少となった。一方、四国(11件、同22.2%増)、九州(55件、同22.2%増)の2地域は前年同月を上回り、中国(24件)は前年同月と同数となった。
要因・背景
- 1.関東は、埼玉、東京、神奈川などで、製造業(27件、前年同月比53.4%減)の減少目立つ
- 2.近畿は、大阪を中心に建設業(前年同月比14.6%減)、卸売業(同35.1%減)が大幅減少
■主な倒産企業
負債トップは、(株)インターナショナルイーシー(東京都、破産)の485億5300万円。以下、姫路土地(株)(大阪府、特別清算)の90億円、(株)J-NEXT(東京都、特別清算)の77億7400万円がこれに続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは43.0、国内景気は一段と悪化
2014年12月の景気DIは前月比0.5ポイント減の43.0となり5カ月連続で悪化した。12月は、人件費上昇や円安による仕入価格高騰の継続などで企業の景況感が弱含んでいたなか、全国的に大雪や強風・高波などの悪天候に見舞われ、建設業や運輸業、北海道や東北、北陸などに大きな悪影響を及ぼした。特に、『運輸・倉庫』では、公共工事関連の物流量減少と相まって、体力の弱い小規模企業ほど収益環境の厳しさが増したこともあり景況感が悪化した。他方、原油価格は1バレル=53ドル(12月NY原油先物相場)と2013年8月(107ドル)から50%以上下落した。その結果、燃料価格は低下したものの依然として高水準にあり、中小企業の収益に対する影響は限定的だった。国内景気は、中小企業の業績に厳しさが広がるなか、全国的な大雪が追い打ちをかけ、一段と悪化している。
今後はほぼ横ばいで推移の見込み
総選挙の結果、今後もアベノミクスが継続されることとなった。2015年度には法人実効税率の引き下げや地方創生に向けた新制度の導入が見込まれる。さらに、2014年度補正予算が期待されるほか、原油価格の下落は徐々に企業のコスト負担を軽減させよう。しかし、今後も円安傾向は継続すると予想されており、原材料価格の上昇は懸念材料である。また、人手不足にともなう人件費上昇や仕入価格上昇を転嫁できない企業も多く、中小企業を中心に収益環境は悪化していくとみられる。今後は、景気対策による下支えが落ち込みを緩和するものの、原材料価格の高止まりや人件費上昇など下振れ材料は依然として残り、ほぼ横ばいで推移すると見込まれる。
今後の見通し
■24年ぶりに上場企業倒産が発生せず、民事再生法は過去最少
2014年は、上場企業の倒産が1990年以来24年ぶりに発生しなかった。2013年8月のワールド・ロジ(ジャスダック、破産)以降16カ月連続で発生しておらず、上場企業の倒産未発生期間としては、1964年の調査開始以降3番目の長さとなっている。背景には、株価上昇や量的金融緩和策などで資金調達環境が改善したことがある。事業再生ADRの広まりも一因だ。同制度は、2014年3月末までに50件の手続利用申請があり42件が受理された。そのうち16件が上場企業である。なかには日本航空(東証1部、会社更生法)など法的整理に移行した案件が3件あるが、13件は債権者の合意を得て手続きが成立している。こうした状況下、2015年も上場企業の倒産が発生し難い地合いが続くとみられる。
また、民事再生法による倒産が291件と同法施行(2000年4月)以降で最少の件数となっていることも2014年の特徴だ。2013年(前年比27.9%減)、2014年(同12.1%減)と2年連続で2ケタの大幅減少で、ピーク時(2001年:965件)の3分の1以下と、企業倒産全体の減少ペースを大きく上回るペースで減少している。言い換えれば、再建型の法的整理を選択する企業が減少しているということだ。大手企業を中心として“アベノミクス”による経営環境改善の恩恵を受けている企業がある一方、経営改善が進まない企業については再生の余地なく破産手続きを取らざるを得ないという状況が年々顕著になってきており、この状況は2015年も続くであろう。
■合併自治体の地方交付税特例分減額開始で地元企業への影響懸念
基礎自治体の行財政基盤確立のため、全国的に市町村合併が推進されたいわゆる「平成の大合併」により、市町村数は3232(1999年3月末)から1727(2010年3月末)にまで減少した。この合併を大きく後押ししたのが、手厚い財政措置だ。自治体は、合併後10年間、合併算定替により特例として合併前の旧自治体が受ける地方交付税の合計額を受け取ってきた。その特例分は2013年度の全国合計で約9500億円にものぼる。それが、合併後11年目以降5年間で新自治体単位での算定(一本算定)に移行する。つまり、特例分が順次減額されるということである。ある自治体の試算によれば「一本算定に移行した場合、2割以上地方交付税が減少する」という。
特例分の減額により自治体の財源先細りが懸念されている。建設事業費削減などでの対応が想定され、公共工事の約3分の1は市町村発注のものであることを踏まえれば、地元企業に影響を与える可能性が高いと言えよう。2015年度は、2004年度(合併関係市町村数826)に合併した自治体に対する特例分の減額が始まる年。翌年は、さらにピークとなった2005年度(同1025)合併自治体の減額が始まる。総務省は“新たな財政需要”を算定に反映させるなどして、激変緩和の追加措置を2014年度から開始しているが、特例分が大幅に減少することに違いはない。地方の中小零細企業は、公共工事、公共サービス付随事業に依存した経営から脱却できなければ、仕事先細り懸念を抱えながらの経営を強いられてしまう。
■原材料費・労務費高騰のなか、暫定リスケ中の企業は正念場をむかえる
2014年の企業倒産件数は、9180件となり2006年(9351件)以来8年ぶりに1万件を下回った。復興需要をはじめとする公共工事の増加、消費税率引き上げ前の駆け込み工事などを受け、建設業の倒産が大幅に減少(前年比20.8%減)したことが大きい。もちろん、中小企業金融円滑化法、および同法期限到来後の資金繰り支援継続により、業種を問わず経営不振に陥っていた多くの中小零細企業が資金繰り破綻を回避しているということもある。
ただし、2015年は、金融円滑化法の出口戦略として実施されていた暫定リスケを通して、立ち直っているか否かを見極められる年となる企業が多いとみられる。暫定リスケは、本格的な再生計画を作成する準備段階として「3年程度の暫定計画+3年間のリスケ」を実施しているもの。暫定期間後には本格的な再生計画の実行を求められることから、期間後に向けて正念場をむかえる企業が多いということである。また、足元をみれば、原材料費高騰、労務費高騰などのコスト上昇問題が中小零細企業に重くのしかかっている。さらに今年は、地域金融機関の再編を通して、資金調達環境が変化する可能性がある。2014年は1万件割れとなった企業倒産件数であるが、2015年はこうした倒産増加要因をもにらみながら、一進一退で推移するものとみられる。

