倒産件数は844件、12ヵ月連続の前年同月比減少
負債総額は1152億3800万円、2ヵ月連続の前年同月比減少
倒産件数 | 844件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲11.3% |
前年同月 | 952件 |
前月比 | ▲0.4% |
前月 | 847件 |
負債総額 | 1152億3800万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲35.8% |
前年同月 | 1796億1700万円 |
前月比 | ▲45.6% |
前月 | 2116億4200万円 |
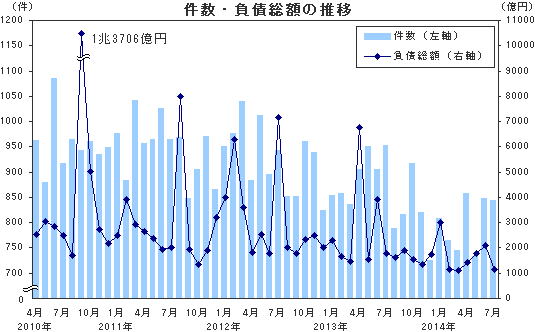
主要ポイント
- ■倒産件数は844件で、前年同月と比べ11.3%の大幅減少。12ヵ月連続で前年同月を下回り、7月としては2006年(746件)に次ぐ低水準となった
- ■負債総額は1152億3800万円で、前年同月比35.8%の減少となり、2ヵ月連続で前年同月を下回った
- ■業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を下回り、なかでも建設業(184件、前年同月比16.4%減)は22ヵ月連続の前年同月比減少となった。また、製造業(102件、同18.4%減)、卸売業(132件、同10.8%減)など4業種で前年同月比2ケタの大幅減少となった
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は703件(前月710件、前年同月791件)と、前月、前年同月ともに下回った
- ■「返済猶予後倒産」は38件(前年同月比26.9%減)判明
- ■負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は475件で、構成比は56.3%と、21ヵ月連続で過半数を占めた一方、負債100億円以上の大型倒産が3ヵ月連続で発生した
- ■地域別に見ると、中部(89件、前年同月比42.6%減)、九州(40件、同36.5%減)など9地域中6地域で前年同月を下回り、6地域ともに前年同月比20%以上の大幅減少となった。一方、関東、近畿、四国の3地域は前年同月比増加となった
- ■負債トップは、(株)三貴(東京都、民事再生法)の126億600万円。(株)きむら食品(新潟県、民事再生法)の49億3300万円、(株)後藤組(大分県、破産)の41億7500万円が続く
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は12ヵ月連続の前年同月比減少、負債総額は2ヵ月連続の前年同月比減少
倒産件数は844件で、前年同月に比べ11.3%の大幅減少。12ヵ月連続で前年同月を下回り、7月としては2006年(746件)以来の低水準となった。負債総額は1152億3800万円で、前年同月比35.8%の減少となり、2000年以降では2014年3月(1119億6000万円)に次いで2番目の低水準となった。
要因・背景
- 1.件数…減少数108件の内訳では、建設業が最多の36件(寄与率33.3%)を占め、製造業の23件(同21.3%)がこれに続く
- 2.負債総額…負債10億円以上の倒産が16件と、2000年以降で最少にとどまる
■業種別
ポイント7業種中6業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を下回り、なかでも建設業(184件、前年同月比16.4%減)は22ヵ月連続の前年同月比減少。また、製造業(102件、同18.4%減)、卸売業(132件、同10.8%減)など4業種で前年同月比2ケタの大幅減少となった。一方、不動産業(26件、同36.8%増)は唯一前年同月を上回った。
要因・背景
- 1.建設業…住宅需要が駆け込み需要の反動減したことにより、木造建築工事などで増加が見られるも、引き続き好調な公共工事を背景に土木工事などで減少が続く
- 2.製造業…大企業の好業績が中小企業にも及び始め、負債1億円未満で減少が目立つ
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比83.3%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は703件(前年同月比11.1%減)となった。一方、構成比は83.3%で、前月を0.5ポイント下回ったが、前年同月を0.2ポイント上回った。また、好況期に増加する「放漫経営」は15件(同25.0%増)判明した。
要因・背景
- 1.「返済猶予後倒産」は38件(前年同月比26.9%減)判明
- 2.「不況型倒産」の件数、建設業(156件、前年同月比17.5%減)などで大幅に減少
■倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比56.3%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は475件で、前年同月を8.1%下回ったものの、構成比は56.3%と、21ヵ月連続で過半数を占めた。一方、負債10億円以上の倒産は16件と、2000年以降最少となった。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が504件、構成比は59.7%を占めた。
要因・背景
- 1.負債5000万円未満の倒産、業種別では建設業(94件、前年同月比20.3%減)で大幅減
- 2.大型倒産は金融機関による支援効果などにより抑制状態が続く
■地域別
ポイント9地域中6地域で前年同月比減少
地域別に見ると、中部(89件、前年同月比42.6%減)、九州(40件、同36.5%減)など9地域中6地域で前年同月を下回り、6地域ともに前年同月比20%以上の大幅減少となった。一方、関東(362件、同1.4%増)、近畿(224件、同6.2%増)、四国(18件、同12.5%増)の3地域は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1.中部は、卸売業(8件、前年同月比63.6%減)を中心に7業種中6業種で減少
- 2.関東は、住宅需要の反動減を受け、木造建築工事や内装工事などで増加が目立つ
■上場企業倒産
11ヵ月連続で、上場企業の倒産は発生しなかった。
2014年は上場企業の倒産が発生しておらず、2013年に引き続いて沈静化の傾向が顕著となっている。
■大型倒産
負債トップは、(株)三貴(東京都、民事再生法)の126億600万円。(株)きむら食品(新潟県、民事再生法)の49億3300万円、(株)後藤組(大分県、破産)の41億7500万円が続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは46.9、消費税ショックは底打ちも回復力弱く
2014年7月の景気DIは、前月比0.4ポイント増の46.9となり2ヵ月連続で改善した。インフラ投資など公共工事や省エネ関連の設備投資が活発化したことで建設や建機レンタルなどの需要が旺盛だった。また、東南アジアに対する訪日ビザ緩和による外国人旅行客の増加や、金融機関による事業再生ニーズに応える経営コンサルタントなどを含む専門サービス業も改善するなど、10業界中7業界が改善した。
他方、消費税率引き上げの影響を直接受けた『小売』では、6月まで2ヵ月連続で改善していたが、7月は生活必需品を中心に3ヵ月ぶりに悪化した。価格の上昇とともに所得の目減り感が現れるなかで夏物商材の動きが鈍かったほか、商品価格に敏感な飲食料品や日用雑貨ではガソリン価格高騰や天候不順などで客足が鈍ったうえ、消費単価や購入数量も減少した。消費税ショックの影響は底を打ったとみられるが、改善の勢いは弱く、全体的には伸び悩みの状況にある。
10地域中8地域が改善、景況感は東高西低
地域別では、製造業による設備投資需要の増加や公共投資が主要産業となる『北関東』や『東北』など、概ね東日本で景況感の改善がみられたものの、台風8号など自然災害に見舞われた西日本では全国を下回る水準となった。規模別にみると、「中小企業」や「小規模企業」で生産設備向け設置工事や、人手不足から引き合いが活発な人材派遣などサービス関連を中心に景況感が改善した。
今後の見通し
■建設業は倒産件数が22ヵ月連続で前年同月比減少するも、人手不足リスクは解消せず
7月における建設業の倒産件数は、184件で前年同月比16.4%の減少となり、2012年10月以降22ヵ月連続で前年同月を下回った。これにより、2003年9月から2005年5月までの21ヵ月前年同月比減少の連続記録を抜き、2000年以降の最長記録を更新した。
2003年から2005年にかけては、ゼネコンなどの過剰債務問題やメガバンクの不良債権処理が峠を越えた時期であり、また「セーフティネット保証」や「資金繰り円滑化借換保証」など政府の中小企業支援策が奏功した時期でもあった。その後、建設業界は、2007年6月の建築基準法改正や2008年9月のリーマン・ショックの影響を大きく受け、倒産件数が著しく増加。事態を重く見た時の政府が打ち出した「緊急保証制度」や「中小企業金融円滑化法」の効果により、何とか小康状態を保つという状況が続いていた。こうしたなか、2011年に東日本大震災が発生。復興需要を契機に息を吹き返した建設業界では、政権交代後の公共工事増加、消費税率引き上げ前の駆け込み需要、公共工事の前倒し実施を受け、倒産件数の減少傾向が続いている。
しかし、ここにきて潮目の変化とも取れる事象が出てきている。国土交通省が発表した6月の住宅着工戸数は前年同月比9.5%のマイナス。消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減とみられるが、特に小規模の下請け業者に恩恵を与えていた分譲マンションの着工戸数は5ヵ月連続の前年同月比減少となっている。この背景には、資材価格の高騰や、人手不足も影響している。「人件費や材料費の上昇によりキャッシュが手元に残らない状態に陥った」(新潟県)、「人件費高騰や資材高が続き収益性が悪化した内装工事業から建築工事業への切り替えを進めていたが、資金繰りがつかなくなった」(東京都)といった倒産事例が7月も確認されている。人手不足は構造的な問題であり、容易に解消されるものではないため、しばらくの間、建設業のリスクとして意識されるであろう。こうしたなか、倒産件数は、6月、7月と2ヵ月連続で前月を上回った。2014年後半には、建設業の倒産件数減少傾向に終止符が打たれる可能性が出てきている。
■地方零細企業の淘汰が、企業倒産件数の押し上げ要因に
金融庁は7月に「金融モニタリングレポート」を公表。そのなかで、地域経済の安定に果たす地域銀行の役割として「事業環境が変化するなかで企業にとって真に有益なアドバイスや、企業の適切な戦略に適った融資を行うことが期待される」としている。これは、人口減少が進むなか、地域経済の雇用やGDPの7割程度を占めているサービス産業の事業環境悪化が避けられないという想定のもと、地域銀行に借手企業に対する適切なコンサルティング機能の発揮を促しているのである。もちろん、再建の見込みが薄い企業を含むすべての企業に対し、等しく支援をするということではない。単に返済条件の変更等により業況が厳しい企業の資金繰りを支援するだけではなく、“廃業”を含めた事業の選択と集中、または、地域活性化を見越した再編において地域銀行が存在感を発揮するべきであるということだ。
当然、その過程においては淘汰される企業も数多く出てくるであろう。赤字体質企業で、かつ後継者未定企業がその筆頭にあげられる。実際に、代表者が引退(死亡を含む)した後に、利払いのみ対応の終了など返済条件の変更を迫られたケースも確認されている。こうした先行き不透明企業が淘汰されることにより、企業倒産件数が今後、押し上げられると想定される。7月まで12ヵ月連続で前年同月比減少となっている倒産件数であるが、この先、建設業の倒産増加、地方零細企業の淘汰が相まって、増加に転じる可能性は高い。

