年間倒産件数は55年ぶり「歴史的低水準」の可能性
経済低迷下でもコロナ融資の効果で倒産件数激減
今後は企業の有利子負債増加が課題に
倒産件数は468件、11月としては最少
負債総額は814億9700万円、11月として48年ぶりの低水準
倒産件数 | 468件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲16.9% |
前年同月 | 563件 |
負債総額 | 814億9700万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲14.4% |
前年同月 | 952億1200万円 |
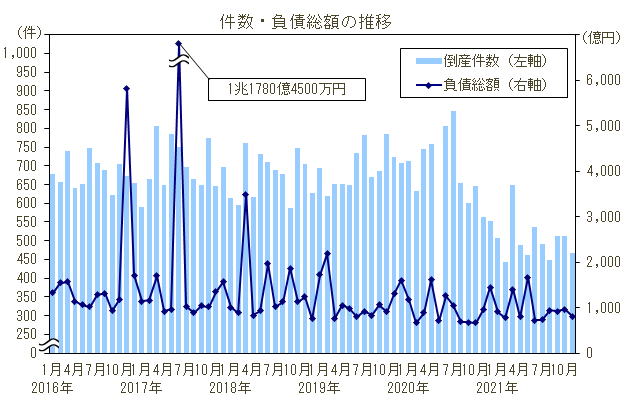
概況
倒産件数は468件、11月として1964年の集計開始以降最少を更新
倒産件数は468件(前年同月563件、16.9%減)と、11月としては2000年以降最少。1999年以前と比較しても、1964年の471件を下回り、過去最少を更新した。また、前年同月比でも6カ月連続の2ケタ減となり、倒産件数が大幅に抑制された状態が続く。
負債総額は814億9700万円(前年同月952億1200万円、14.4%減)と、4カ月ぶりに前年同月比減少に転じたほか、11月として1973年以来48年ぶりの低水準となった。
主要ポイント
- ■業種別にみると、7業種中6業種で前年同月比減少。サービス業(前年同月145件→125件、13.8%減)や小売業(同134件→89件、33.6%減)などのB to C業種では減少傾向が続く
- ■主因別にみると、「不況型倒産」の合計は363件(前年同月429件、15.4%減)と、6カ月連続で前年同月を下回った。構成比は77.6%(対前年同月1.4ポイント増)を占める
- ■負債規模別にみると、1億円以上10億円未満の中規模倒産の占める割合は4カ月連続で増加
- ■地域別にみると、9地域中6地域で前年同月比2ケタの大幅減。関東(前年同月185件→151件、18.4%減)では、東京都が11月として過去40年で最少。一方、東北(同22件→27件、22.7%増)は2020年6月以来17カ月ぶりに増加に転じた
- ■人手不足倒産は9件(前年同月7件、28.6%増)発生、2カ月連続の前年同月比増加
- ■後継者難倒産は44件(前年同月34件、29.4%増)発生、2カ月連続の前年同月比増加
- ■返済猶予後倒産は21件(前年同月28件、25.0%減)発生、2カ月連続の前年同月比減少
■業種別
運輸・通信業を除く6業種で前年同月比減少
業種別にみると、7業種中6業種で前年同月比減少となった。サービス業(前年同月145件→125件、13.8%減)は、理美容業(同16件→2件)のほか、マッサージ業(同15件→4件)などが件数を押し下げた。小売業(同134件→89件、33.6%減)でも、飲食店(同63件→33件)が前年同月から47.6%減と半減しており、緊急事態宣言解除以降の人流増加の影響もあり、B to C業種では減少傾向が続く。また、上記2業種に加え、建設業(同92件→90件、2.2%減)、製造業(同60件→56件、6.7%減)、卸売業(同70件→54件、22.9%減)の5業種は、6カ月連続の減少となった。
一方、運輸・通信業(前年同月17件→20件、17.6%増)は、2カ月ぶりに増加した。■主因別
「不況型倒産」は363件、構成比は77.6%
主因別にみると、「不況型倒産」の合計は363件(前年同月429件、15.4%減)と、6カ月連続で前年同月を下回った。構成比は77.6%(対前年同月1.4ポイント増)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
負債1億円以上の中規模倒産が増加
負債規模別にみると、負債5000万円未満の倒産は277件(前年同月364件、23.9%減)、構成比は59.2%を占めた。5000万未満の構成比が対前年同月で6カ月連続の減少となった一方、1億円以上10億円未満の中規模倒産の占める割合は4カ月連続で増加するなど、負債では大型化の兆しがみられる。
資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人事業主含む)の倒産が340件(前年同月387件、12.1%減)、構成比は72.6%を占め、10カ月ぶりに70%台へ上昇した。■地域別
9地域中6地域で前年同月比2ケタの大幅減
地域別にみると、9地域中6地域で前年同月比2ケタの大幅減。関東(前年同月185件→151件、18.4%減)では、6カ月連続で2ケタの大幅な減少が続き、なかでも、東京都(64件)は11月として過去40年で最少となった。近畿(同183件→137件、25.1%減)は、奈良県を除く2府3県で減少となり、地域全体で2ケタ減。前年同月から半減した卸売業(11件)をはじめ、小売業(31件)やサービス業(33件)でも30%以上の大幅減となった。
一方、北海道(前年同月9件→14件、55.6%増)、東北(同22件→27件、22.7%増)、北陸(同12件→15件、25.0%増)は前年同月から増加し、なかでも東北は2020年6月以来17カ月ぶりに増加へ転じた。■態様別
「破産」は437件、構成比93.4%
態様別にみると、破産は437件(構成比93.4%)。特別清算は12件(同2.6%)となった。民事再生法は19件で、うち12件を個人事業主が占めた。
■特殊要因倒産
人手不足倒産
9件(前年同月7件、28.6%増)発生、2カ月連続の前年同月比増加
後継者難倒産
44件(前年同月34件、29.4%増)発生、2カ月連続の前年同月比増加
返済猶予後倒産
21件(前年同月28件、25.0%減)発生、2カ月連続の前年同月比減少
※特殊要因倒産では、主因・従因を問わず、特徴的な要因による倒産を集計
■景気動向指数(景気DI)
51業種中24業種が新型コロナ前の水準を上回る
2021年11月の景気DIは前月比1.6ポイント増の43.1となり、3カ月連続で改善した。
11月の国内景気は、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着きをみせるなか、外出機会の増加は個人消費関連の景況感を押し上げた。また、半導体製造装置などの好調が続いたほか、「メーカーが半導体部品を入手できるようになった」など、一部で半導体不足の影響が和らぎ輸送用機械・器具製造の生産・出荷量が上向いたことはプラス材料だった。他方、丸太の国内価格が5割上昇するなど木材・鉄鋼や石油製品の価格高騰などで仕入単価の上昇が続いたほか、海外の感染拡大などによる供給制約の影響などはマイナス要因となった。 国内景気は、新規感染者数の落ち着きでプラス材料が多く表れ、回復傾向が続いた。今後は回復傾向で推移
今後の国内景気は、新規感染者数の減少で対面型サービスの持ち直しが期待されるほか、自動車などの挽回生産や設備投資意欲の高まりなども加わり、生産・消費両面で回復傾向が続くとみられる。また、5G関連の環境整備や飲食料品など旺盛な自宅内消費の継続、半導体需要の増加、SDGsへの対応もプラス材料である。さらに政府の経済対策も押し上げ要因となろう。他方で、新型コロナウイルス変異株の感染動向や水際対策の強化に加えて、資源高を背景とした価格の上昇や為替変動リスクはマイナス要因となる。供給制約にともなう企業の収益力の二極化の動き、人手不足感の高まりなども注視する必要がある。
今後は、リベンジ消費や挽回生産などが見込まれるなか、回復傾向が続くとみられる。今後の見通し
■倒産件数は抑制された状況が続くも、コロナ倒産は年間通じて月100件超とハイペース
2021年11月の倒産件数は、前年同月から16.9%減、件数にして約100件の大幅な減少となる468件となった。11月としては1964年(471件)を下回って過去最少、21年の11カ月中10カ月で前年同月比2ケタ減を記録しており、引き続き倒産の発生が大幅に抑制された状態が続いた。コロナ関連の経営支援策が行きわたり、多くの中小零細企業で資金繰りひっ迫の事態が回避されたためで、1年超にわたって倒産が減少している。
負債総額は814億9700万円で、前年同月から14.4%減少した。高松グランドカントリー(ゴルフ場、11月民事再生、負債約46億8000万円)など大型倒産も発生したものの、負債が30億円を超える倒産は少数にとどまったことで、21年7月以来4カ月ぶりの減少となった。依然として、負債額の小さな小規模・零細事業者の倒産が圧倒的多数を占める状況に変化はない。
他方、新型コロナウイルスの影響を受けた関連倒産は引き続き多く発生している。12月7日時点で累計2487件となり、昨年12月以降、年間を通して月100件を上回るペースが続く。緊急事態宣言の全面解除などで対面サービス産業を中心に需要回復への期待感が高いとはいえ、飲食店やアパレル、観光産業などでは厳しさが続くなど、業況は業種間で二極化も進む。■ウッドショックの次は「アイアンショック」 コストアップ続く建設業、小規模中心に倒産増加も懸念
コロナ禍に揺れた2021年の中でも、落ち着いた推移をみせる業種の一つが建設業だ。11月の建設業の倒産は90件にとどまり、約1年にわたり月間で100件を下回る低水準が続いている。コロナ禍当初、建設業では商業地区のオフィスや店舗開発、設備投資計画などが全面的にストップするなど厳しい局面にさらされたものの、金融機関をはじめ資金調達環境が良好であったこと、工期などの問題から工事再開が比較的早かったことも幸いし、経営への影響は限定的にとどまった。その後は防災関連のインフラ公共工事や、5Gなど次世代通信工事、都市部では大型物流施設や再開発事業など民間工事も相応に回復しており、業況が比較的良い状態であることも、建設業の倒産動向が比較的落ち着いている主な要因となっている。
ただ、足元では2021年夏に発生したウッドショックに続き、建築鋼材やセメント、板ガラスなど主要な建材にも価格急騰の波が押し寄せている。「半年間で鋼材価格が2割も上昇したが、工事価格への転嫁は難しい」(中堅鉄骨工事業者)など、当面は採算性に乏しい受注競争が強いられると目されるなか、コスト抑制のしわ寄せを受けやすい中小零細の建設業者では、こうした価格競争に耐えられず倒産や廃業を選択する動きが強まる可能性がある。■2021年は「歴史的低水準」55年ぶり6000件割れの可能性、倒産予備軍企業の動向に注目
こうした情勢下ではあるものの、全国における2021年通年の倒産件数は2年連続で7000件を下回るのが確実で、6000件を割り込む可能性も出ている。年間倒産件数が5000件台となれば、1966年の5919件に次ぐ55年ぶりの歴史的な超低水準となり、企業倒産の発生が極めて抑制された状況を反映している。実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)や返済リスケジュールなど、無条件に近い企業の資金繰り支援策の内容が年内に方針転換するとは考えにくく、そのため年末にかけても倒産が急増する可能性は低いとみる。
一方で、全国で200万件超・総額40兆円に上るコロナ関連融資の副作用が、中小企業の過剰債務問題として顕在化しつつある点は留意したい。全国信用保証協会連合会によれば、9月の代位弁済件数は1765件となり、コロナ禍直後の2020年5月以来、1年4カ月ぶりに前年同月を上回った。直近でピークの2876件(20年6月)に比べると6割前後にとどまるが、多くの中小企業でコロナ融資の返済が本格化した時期での増加は、融資を受けたものの業績が回復せず、返済原資のない企業が多い可能性を示唆する。実際に、日本銀行の貸出・預金動向では、大企業の取引が多いメガバンクなど大手行で貸出残高が減少傾向にある一方で、中小零細が多い地方銀行や信用金庫では逆に増加するなど、中小企業では返済が進んでいるとは言い難く、金融支援で延命を続ける倒産予備軍企業が水面下で増加している可能性が高い。
国内では変異型ウイルスのオミクロン株による感染拡大も懸念されるものの、経済活動自体は総じて正常化に向けて舵を切りつつある。それに呼応して、官民の中小企業支援も緊急対応の意味合いが強い資金繰り支援から、私的整理の議論も含め、早期の事業再生を後押しする「本業支援」に切り替わる過程にある。ただ、こうした枠組みは既存債権の放棄など債権者に痛みが伴うため、実際には同じ経営不振企業でも実抜・合実計画が策定可能な将来性のある企業では引き続き手厚く支援される一方で、金融支援に頼りきったままの企業では法的整理などハードランディングも含め、これまでよりもシビアな判断が下される可能性が高い。そのため、ゼロゼロ融資の申請期限が終了する来年3月を境に、再建困難な不振企業で倒産が増加するシナリオが想定される。

