倒産件数は4400件、6年連続の前年同期比減少
負債総額は9752億600万円、3年連続の前年同期比減少
倒産件数 | 4400件 | 負債総額 | 9752億600万円 |
|---|
前年同期比 | 件数 | ▲7.5% | 2014年上半期 | 4756件 |
|---|---|---|---|---|
負債 | ▲8.3% | 2014年上半期 | 1兆638億8000万円 | |
前期比 | 件数 | ▲0.5% | 2014年下半期 | 4424件 |
負債 | +21.3% | 2014年下半期 | 8039億2000万円 |
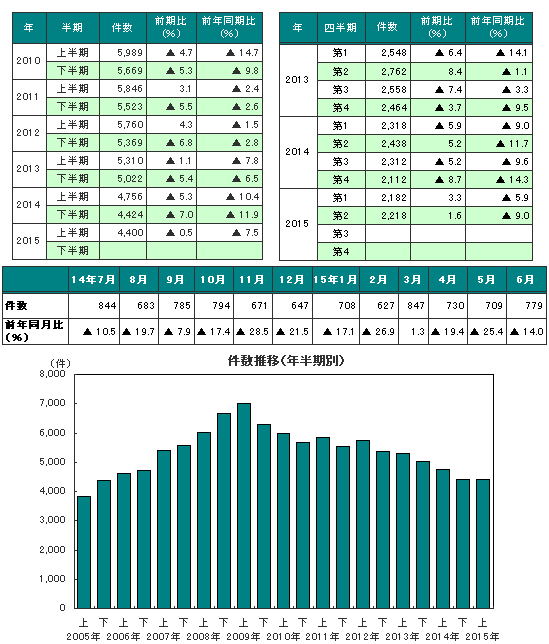
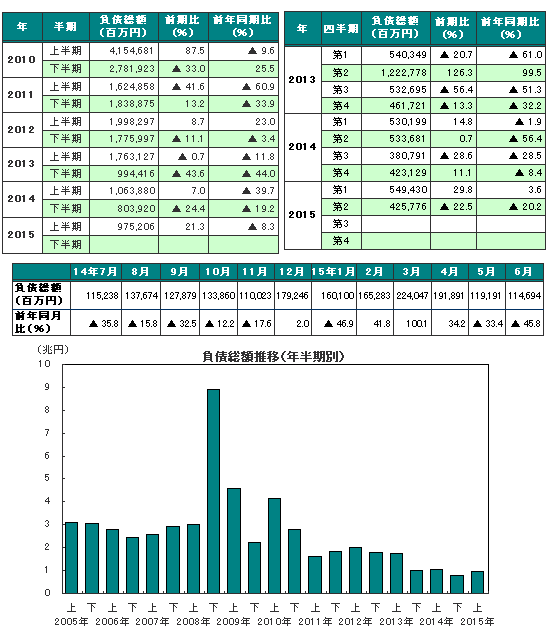
主要ポイント
- ■倒産件数は4400件、前年同期を7.5%下回り、6年連続の前年同期比減少となった
- ■負債総額は9752億600万円、前年同期を8.3%下回り、3年連続の前年同期比減少となるとともに、上半期としては2000年以降で最小を記録した
- ■業種別では、7業種すべてで前年同期を下回った。なかでも、運輸・通信業(180件、前年同期比19.6%減)と建設業(802件、同15.0%減)は2ケタの減少率となった
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は3663件(構成比83.3%)となった
- ■規模別では、負債5000万円未満の倒産は2463件と、前年同期の2599件を5.2%下回ったものの、構成比は56.0%と2000年以降で最高を記録した
- ■地域別に見ると、9地域中8地域で前年同期を下回り、なかでも北陸(133件、前年同期比19.4%減)と中国(204件、同10.5%減)は前年同期比2ケタの減少率となった
- ■負債トップは、江守グループホールディングス(株)(4月、民事再生法、福井県)の711億円
調査結果
■件数
ポイント6年連続の前年同期比減少
2015年上半期の倒産件数は4400件と、2014年上半期の4756件に比べ7.5%減少し、6年連続で前年同期を下回った。四半期別では、前年同期比では13期連続の減少となったものの、前期比では2011年第1四半期以来4年ぶりの2期連続増加を記録した。
要因・背景
- 1.軽油価格低下の恩恵を受け、運輸・通信業(180件)が前年同期比19.6%減少した
- 2.過年度からの公共工事増加もあり、建設業(802件)は前年同期比15.0%減となった
■負債総額
ポイント3年連続の前年同期比減少、上半期としては2000年以降最小
2015年上半期の負債総額は9752億600万円と、前年同期を8.3%下回り、3年連続の前年同期比減少となるとともに、上半期としては2000年以降で最小を記録した。四半期別では、第1四半期は7期ぶりの前年同期比増加となったものの、第2四半期には再び同減少となった。
要因・背景
- 1.負債トップは江守グループホールディングス(株)(4月、民事再生法、福井県)の711億円
- 2.大企業の業績回復や、金融機関の支援などにより、大型倒産が抑制された
■業種別
ポイント7業種すべてで前年同期比減少
業種別に見ると、上半期としては2010年以来、5年ぶりに7業種すべてで前年同期を下回った。なかでも、建設業(802件、前年同期比15.0%減)は2ケタの減少率が7期連続したほか、運輸・通信業(180件、同19.6%減)も同2期連続した。
要因・背景
- 1.建設業…北陸新幹線や九州新幹線をはじめとした、民間設備投資需要がけん引役となり、2009年下半期以降、前年同期比では12期連続の減少を記録
- 2.運輸・通信業…原油価格が2014年末以降下落したことが、運輸業者の燃料コストの押し下げ要因となり、前年同期比では2期連続で2ケタの減少率となった
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比は83.3%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は3663件(前年同期3969件)となり、前年同期比7.7%の減少となった。一方、「不況型倒産」の構成比は83.3%と、前年同期(83.5%)に比べ0.2ポイント下がった。
要因・背景
- 1.「円安関連倒産」は231件(前年同期145件)判明、前年同期比59.3%の大幅増加
- 2.不況型倒産の構成比、業種別では小売業が87.0%と最も高い
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比は56.0%、2000年以降で最高
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は2463件と、前年同期の2599件を5.2%下回ったものの、構成比は56.0%と2000年以降で最高を記録した。一方、負債100億円以上の倒産は10件と、上半期としては2000年以降3番目の低水準となった。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の構成比、小売業(69.8%)が最も高く、2000年以降の最高を記録
- 2. 大型倒産は、大企業の業績回復や金融機関の支援などにより、抑制状態が続いている
■地域別
ポイント9地域中8地域で前年同期比減少
地域別に見ると、9地域中8地域で前年同期を下回り、なかでも北陸(133件)と中国(204件)は前年同期比2ケタの大幅減少となった。一方、九州(352件)は前年同期比では横ばい(同数)だが、前期比では8.6%増加した。
要因・背景
- 1. 北陸は、北陸新幹線開通による影響もあり、建設業やサービス業、運輸・通信業、小売業など、不動産業を除く6業種で前年同期比減少となった
- 2. 関東は2009年下半期以降、12期連続で前年同期比減少が続いている
■態様別
ポイント破産の構成比が93.1%
態様別に見ると、破産が4095件で前年同期比8.0%の減少となったものの、構成比は93.1%と高水準が続いた。このほか、民事再生法(141件)は同13.5%減、会社更生法は2013年下半期以来3期ぶりに発生しなかった。一方、特別清算は164件で同17.1%の増加となった。
要因・背景
- 1. 特別清算は、業績回復した大企業による不採算子会社の整理もあり、押し上げられた
- 2. 民事再生法は、上半期としては2000年以降で最少となった
■上場企業倒産
2015年上半期の上場企業倒産は、スカイマーク(株)(1月、民事再生法、東証1部)、江守グループホールディングス(株)(4月、民事再生法、東証1部)の2件となった。
上場企業倒産としては、2013年下半期以来3期ぶりの発生となる。
■大型倒産
2015年上半期の負債トップは、江守グループホールディングス(株)(民事再生法、4月)の711億円。スカイマーク(株)(民事再生法、1月)の710億8800万円、蒲郡海洋開発(株)(特別清算、2月)の313億9100万円がこれに続く。
■注目の倒産動向
建設業 件数は前年同期比15.0%の減少、6年連続減少
2015年上半期の建設業の倒産は802件(前年同期比15.0%減)となり、上半期でみると2010年以降6年連続の前年同期比減少となった。地域別では、横ばいの四国を除く、北海道から九州まですべての地域で前年同期を下回り、特に北陸新幹線が開通した北陸(前年同期比34.3%減)や、震災復興需要が続く東北(同30.8%減)の減少幅が大きく、全体の減少に寄与した。 近年の建設業の倒産減少には、国土強靭化基本計画を背景としたインフラ整備など公共工事が下支えしてきた背景がある。しかし、ここにきて公共工事は減少傾向にあり、公共投資への依存度が高い地方では建設業の景況感が悪化するなど、警戒感が強まりつつある。 また、業界内外で注目されているのが社会保険未加入業者の排除の動きだ。慢性的な人手不足解決のための労働環境改善の一環として、2014年8月から国土交通省が直轄工事において、元請・下請ともに未加入業者に対するペナルティーを定めたほか、2015年度以降は、競争参加有資格者名簿に登録できる企業を社会保険加入業者に限定している。この動きは、今後、国の他発注機関や都道府県、市区町村、民間へも浸透していくことが予想され、対応できない中小・零細工事業者の淘汰につながる可能性がある。
今後の見通し
■流通構造変化や消費動向に適応できない中堅・中小企業の淘汰進むか
2015年上半期は、栗田出版販売(東京、民事再生法、負債133億8200万円、出版取次)や、志正堂(東京、特別清算、同100億円、文具卸)、アカクラ(東京、民事再生法、同54億3500万円、婦人靴小売)など、流通分野における大型倒産が続いた。いずれも業歴が60年を超える企業であるが、インターネット販売との競合、消費動向の変化等に対応しきれなかったことが原因だ。倒産件数の業種別構成比をみると、卸売業および小売業は前期比増となっており、中でも注目されるのが、倒産件数増加率が前期比(42.1%増)、前年同期比(13.4%増)とも2ケタ台となった「織物・衣服・身の回り品小売業」である。同業界は、円安による仕入れ価格の上昇に加えて、消費の多様化で消費動向把握がより困難となっているほか、個人消費の回復遅れという三重苦を抱える。百貨店を主力売り場とする大手アパレル企業が相次いでブランド統廃合や人員削減を発表するなど、大手といえども生き残りをかけたリストラを断行せざるを得ない環境だ。
6月30日に閣議決定された『「日本再興戦略」改訂2015』では、中堅・中小企業・小規模事業者の“稼ぐ力”の徹底強化、および、サービス産業の活性化・生産性の向上等が掲げられている。しかし、現実には過年度の金融円滑化法をはじめとする金融支援策の恩恵もあって、経営改善に至らないまま延命してきた企業も多い。今後、個人消費の回復遅れが続く中で、環境変化に対応できない中堅・中小企業の淘汰が進む可能性は十分にある。
■設備投資が堅調な中、過去の過剰投資を要因とする倒産も
リーマン・ショック後ほぼ横ばい状態で推移していた設備投資は、2013年度から2014年度にかけては回復傾向を見せ、7月1日に発表された日銀短観では、大企業製造業の2015年度の設備投資計画等における設備投資額(ソフトウエア投資額は含まない)は、前年度比18.7%増となった。国内設備投資の堅調さは景気回復の証左であり、2015年上半期の「設備投資の失敗」や「経営計画の失敗」による倒産は、前期比および前年同期比で大きく減少している。
しかし、一方でシー・エス・ピー(兵庫、破産、負債15億円、アパレル小売)や、みらい(東京、民事再生法、同10億9200万円、人工光型植物工場の農業関連ベンチャー)など、過年度の急激な店舗展開や設備投資の失敗による倒産も発生している。景気回復期の積極投資に伴う借り入れ負担増は、経営を左右する要因となりうるため、注視する必要があるだろう。
■負債総額は上半期としては2000年以降で最小、公共工事の動向に注目
2015年上半期の企業倒産件数は4400件で、前期を24件(0.5%減)、前年同期を356件(7.5%減)それぞれ下回り、上半期では2001年上半期の3905件に次ぐ低水準となった。また、負債総額は9752億600万円と、2000年以降の上半期では最小となった。
こうした数字を見る限りでは、倒産件数、負債総額ともに低位推移が続いている。だが、四半期ベースの件数を見ると2期連続で前期比プラスとなったほか、年半期ベースでは前年同期比でこれまで10.4%、11.9%と2期連続して2ケタ台であった減少率が7.5%にとどまり、ここに来て減少率がやや鈍化している点が注目される。
倒産件数が低水準である要因のひとつに、建設業の倒産減少がある。リーマン・ショック後の2009年上半期には件数構成比で25.9%を占めていた建設業だが、2015年同期は18.2%にとどまっている。背景には、アベノミクスにより国内建設投資が活況を呈し、その恩恵が大手ゼネコンを中心に、地方の中小建設業者にまで及んでいることがあげられる。
しかし、その状況も今後については流動的だ。資材価格高騰や人手不足といった業界全体が抱える問題に加えて、公共工事の減少の影響が現れ始めているからだ。TDB景気動向調査における建設業のDIは、2015年4月以降3カ月連続して悪化し、6月は47.7と前年同月の52.7を5.0ポイント下回るなど、景況感は全国的に明らかに悪化している。その傾向は、特に公共工事への依存度が高い地方で顕著だ。
倒産が増加に転ずる要因として、公共工事の動向のほか、円安、人手不足、原材料・資材価格の動向等には引き続き注目すべきと考える。このほか、為替相場やユーロ圏の動向、チャイナリスク等の予測困難な各種リスクは存在することも忘れてはならない。差し当たり大幅な変動が発生しない限り倒産は低水準が続くと見られるが、前述の倒産件数の減少率が鈍化していることを考えると、これらリスク要因の動きは注視していくことが必要だ。

