倒産件数は706件、3カ月ぶりの前年同月比増加
負債総額は1238億6600万円、4カ月ぶりの前年同月比減少
倒産件数 | 706件 |
|---|---|
前年同月比 | +9.3% |
前年同月 | 646件 |
前月比 | ▲5.5% |
前月 | 747件 |
負債総額 | 1238億6600万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲8.2% |
前年同月 | 1349億8300万円 |
前月比 | +9.8% |
前月 | 1128億5600万円 |
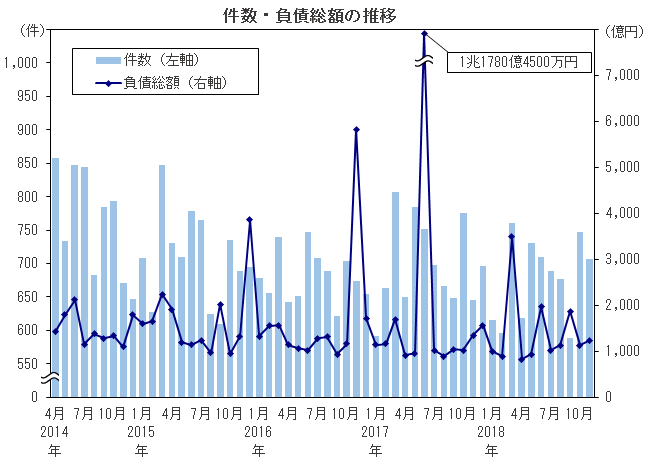
主要ポイント
- ■倒産件数は706件(前年同月比9.3%増)と、3カ月ぶりに前年同月を上回った。負債総額は1238億6600万円(同8.2%減)と、4カ月ぶりに前年同月を下回った
- ■業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を上回った。このうち、製造業(81件、前年同月比19.1%増)は8カ月ぶりの前年同月比増加。また、サービス業(173件)は前年同月比21.8%の大幅増となった。一方、建設業(125件)など2業種は前年同月を下回った
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は560件(前年同月比3.3%増)となり、10カ月ぶりに前年同月を上回った。構成比は79.3%(同4.6ポイント減)を占めた
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は428件(前年同月比5.2%増)となった。構成比は60.6%を占め、小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が466件で構成比66.0%を占めた
- ■地域別に見ると、9地域中7地域で前年同月を上回った。このうち、東北(38件、前年同月比81.0%増)は4カ月連続の前年同月比増加。また、近畿(186件、同15.5%増)は7カ月ぶりに前年同月を上回った。一方、北海道(16件、同33.3%減)、中国(24件、同25.0%減)の2地域は前年同月を下回った
- ■負債トップは、東京グリーン開発(株)(東京都、特別清算)の128億7200万円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント倒産件数は706件、3カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数は706件(前年同月比9.3%増)と、3カ月ぶりに前年同月を上回った。負債総額は1238億6600万円(同8.2%減)と、4カ月ぶりに前年同月を下回った。
要因・背景
件数…業種別ではサービス業など5業種で、地域別では東北など7地域で前年同月比増加
負債総額…負債100億円以上の倒産は1件、負債5000万円未満の倒産が約6割を占めた
■業種別
ポイント製造、サービスなど5業種で前年同月比増加
業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を上回った。このうち、製造業(81件、前年同月比19.1%増)は8カ月ぶりの前年同月比増加。また、サービス業(173件)は前年同月比21.8%の大幅増となった。一方、建設業(125件、同11.3%減)など2業種は前年同月を下回った。
要因・背景
- 1. サービス業は医療業(20件、前年同月4件)で増加が目立ち、なかでも鍼灸、マッサージ、整体、接骨などの治療院(15件、同2件)で大幅増となった
- 2. 建設業は、都市部を中心とした建設需要の拡大などを受け、北陸(3件、前年同月比40.0%減)、中部(24件、同17.2%減)など6地域で前年同月比減少
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比79.3%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は560件(前年同月比3.3%増)となり、10カ月ぶりに前年同月を上回った。構成比は79.3%(同4.6ポイント減)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1. 不況型倒産を業種別に見ると、小売業(137件)が構成比24.5%を占め最多
- 2.「人手不足倒産」は8件(前年同月比14.3%増)、4カ月連続の前年同月比増加
- 3.「後継者難倒産」は49件(前年同月比81.5%増)、集計を開始した2013年1月以降で最多
- 4.「返済猶予後倒産」は38件(前年同月比15.6%減)、2カ月ぶりの前年同月比減少
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比60.6%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は428件(前年同月比5.2%増)となった。構成比は60.6%を占め、小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が466件で構成比66.0%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産では、サービス業(121件)が構成比28.3%(前年同月比2.0ポイント増)を占め最多。小売業(120件)が同28.0%(同2.7ポイント増)で続く
- 2. 負債100億円以上の倒産(1件)が4カ月連続で発生
■地域別
ポイント東北、近畿など7地域で前年同月比増加
地域別に見ると、9地域中7地域で前年同月を上回った。このうち、東北(38件、前年同月比81.0%増)は4カ月連続の前年同月比増加。また、近畿(186件、同15.5%増)は7カ月ぶりに前年同月を上回った。一方、北海道(16件、同33.3%減)、中国(24件、同25.0%減)の2地域は前年同月を下回った。
要因・背景
- 1. 東北は、復興需要の一巡などを背景に、建設業(10件、前年同月5件)で増加が目立つ
- 2. 近畿は、大阪府の製造業(18件、前年同月8件)やサービス業(21件、同15件)、兵庫県の小売業(17件、同4件)などで増加
■上場企業倒産
上場企業の倒産は発生しなかった。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは49.5、4カ月ぶりに改善
2018年11月の景気DIは前月比0.5ポイント増の49.5となり、4カ月ぶりに改善した。
11月の国内景気は、再開発や五輪向け工事が進むなか、夏に相次いだ災害や2016年の熊本地震からの復旧・復興需要が工事量の増加につながり、製造業で出荷量が増えるなど関連業種も改善。戸建て住宅の着工戸数が増えたほか、燃料価格の一服もプラス材料となった。運輸などで年末に向けた需要が発生し、消費税率引き上げや改元へのシステム対応依頼も旺盛な一方で、雇用過不足DIが正社員・非正社員ともに過去最高を更新した。
国内景気は、災害復旧・復興工事や住宅着工などの建設需要が関連業種に波及したほか、年末に向けた需要や燃料価格一服も寄与するかたちで改善し、弱含み傾向が一時後退した。
消費税率引き上げによる駆け込み需要が期待されるも、その反動減や海外リスクに懸念
今後は、好調な企業収益を背景とした省力化投資の活発化や災害からの復興、訪日外国人および五輪需要の拡大を追い風に、設備投資は総じて堅調さが続くであ今後は、省力化需要などを背景に設備投資は総じて堅調に推移し、景気を下支えすると見込まれる。2018年12月に発効予定のTPP11はプラス材料になるとみられるも、輸出は増加ペースが鈍化し、個人消費については緩やかな回復にとどまると予想される。消費税率引き上げによる駆け込み需要が期待される一方で、反動減が景気を一時的に大きく下押しする可能性が懸念される。海外では、米国による関税引き上げを受けた中国経済の減速のほか、日米通商交渉の行方、新興国経済の動向などがリスク要因となろう。
今後は設備投資が国内景気を下支えするなか、消費税率引き上げによる駆け込み需要が期待される一方、その後の反動減や海外リスクも懸念され、不透明感が一層強まっている。
今後の見通し
■倒産件数は3カ月ぶりの前年同月比プラス、医療業で倒産目立つ
2018年11月の倒産件数(706件、前年同月比9.3%増)は3カ月ぶりの前年同月比プラスに転じた。業種別ではサービス業(173件、前年同月比21.8%増)、地域別では今年最多だった東北(38件、同81.0%増)のほか、近畿(186件、同15.5%増)などの増加が大きく影響した。
また、11月は病院経営の翔洋会(福島県、民事再生、負債約61億6400万円)など、医療業の倒産(20件)が目立った。2018年1~11月累計でも医療業は計142件と、年間合計で最多だった2017年(116件)をすでに大きく上回る。このうち、歯科医院は計21件、整体や鍼灸などの治療院は計75件と、どちらもこれまでの年間最多をすでに更新し、医療業全体の倒産を押し上げている。医療機器導入などの設備投資負担のほか、院数増加を背景とした競合激化での患者数減少などから倒産するケースが目立ち、今後さらなる増加も懸念される。
■下請企業の収益改善が課題
経済産業省と公正取引委員会は11月27日、下請取引の適正化を親事業者(約21万社)などに対して要請。取引上の価格決定や支払条件、コスト負担などの適正化に向け、親事業者の担当者のみならず役員などの責任者にまで周知徹底を図り、適切な措置を講じるよう強く求めた。
取引上の地位の格差を背景に、一方的な発注者側の事情によるコストのしわ寄せや取引関係の打ち切り、不合理な取引条件の強要などを受けた下請企業の倒産はかねてから見受けられている。下請中小企業振興法で定める振興基準の改正が年内にも見込まれるなか、取引適正化を通じた下請企業の収益改善が望まれる。
■後継者難倒産が増勢で推移
中小企業の事業承継問題が深刻化していることを背景に、中小企業庁は今年10月、中小企業の経営者、後継者、支援機関などを一堂に会した「全国事業承継推進会議(キックオフイベント)」を開催するなど、より積極的な支援に乗り出した。帝国データバンクの調査では、企業の後継者不在率は60代の経営者で52.3%と2社に1社を数え、70代でも42.0%の企業で後継者を決めていないことが明らかとなっている。
こうしたなか、代表者の体調不良や死亡などで事業継続の見通しが立たなくなったことなどから倒産した「後継者難倒産」は2018年1~11月累計で365件を数え、すでに前年(341件)を大きく上回る。調査開始以降の最多件数(2013年、411件)にも迫る勢いとなっている。
■2018年の年間倒産件数は2年ぶりのマイナスへ
景気は緩やかな回復基調にあるものの、人件費や原材料費、物流費など、企業のコスト負担はすでに幅広い業種で増加しており、厳しい経営環境にある企業は小規模企業を中心に多く存在する。年末に向けて資金需要が高まる時期を迎え、こうした企業の倒産が懸念される。
2018年1~11月の累計件数は7436件(前年同期7680件)と前年同期を3.2%下回っている。東北、中国、九州の3地域ではすでに前年件数を超えるなど地域差が大きいものの、2018年の年間倒産件数は2017年の2.6%増から一転、2年ぶりの前年比マイナスが見込まれる。

