倒産件数は733件、10ヵ月連続の前年同月比減少
負債総額は1790億8300万円、4ヵ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数 | 733件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲22.8% |
前年同月 | 950件 |
前月比 | ▲14.6% |
前月 | 858件 |
負債総額 | 1790億8300万円 |
|---|---|
前年同月比 | +16.0% |
前年同月 | 1544億4000万円 |
前月比 | +25.3% |
前月 | 1429億5600万円 |
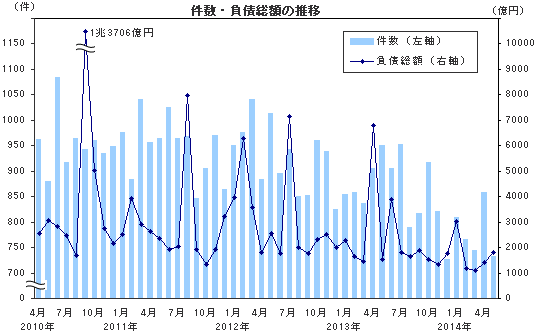
主要ポイント
- ■倒産件数は733件で、5月としては2006年5月(731件)以来の700件台を記録。前年同月比では22.8%の大幅減少となり、10ヵ月連続で前年同月を下回った
- ■負債総額は1790億8300万円で、前年同月比16.0%の増加となり4ヵ月ぶりに前年同月を上回った
- ■業種別に見ると、7業種すべてで前年同月を下回り、なかでも建設業(144件、前年同月比39.0%減)は20ヵ月連続の前年同月比減少となったほか、サービス業(129件、同26.3%減)、卸売業(129件、同16.8%減)など5業種で前年同月比2ケタの大幅減少となった
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は600件(前月716件、前年同月793件)にとどまった一方、「設備投資の失敗」が2ヵ月連続で前年同月を上回った
- ■「返済猶予後倒産」は42件(前年同月比30.0%減)判明
- ■負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産の構成比は50.1%と、19ヵ月連続で過半数を占めた一方、負債100億円以上の大型倒産が4ヵ月ぶりに発生した
- ■地域別では、2010年7月以来3年10ヵ月ぶりに9地域すべてで前年同月を下回った。なかでも、近畿(149件、前年同月比34.9%減)や中部(104件、同32.9%減)など3地域で前年同月比30%以上の大幅な減少となった
- ■ 9ヵ月連続で上場企業の倒産は発生しなかった
- ■負債トップは、(株)白元(東京都、民事再生法)の254億9400万円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は10ヵ月連続の前年同月比減少、負債総額は4ヵ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数は733件で、5月としては2006年5月(731件)以来の700件台を記録。前年同月比では22.8%の大幅減少となり、10ヵ月連続で前年同月を下回った。減少幅22.8%は2010年7月(23.8%)に次ぐ水準。負債総額は1790億8300万円で、前年同月比16.0%の増加となり4ヵ月ぶりに前年同月を上回った。
要因・背景
件数…前年同月からの減少数217件のうち、建設業が92件(寄与率42.4%)を占める
負債総額…負債100億円以上の大型倒産が4ヵ月ぶりに発生((株)白元、負債254億9400万円)したことに加え、負債10億円以上の倒産が今年最多の30件を記録
■業種別
ポイント7業種すべてで前年同月比減少
業種別に見ると、7業種すべてで前年同月を下回り、なかでも建設業(144件、前年同月比39.0%減)は20ヵ月連続の前年同月比減少となった。また、サービス業(129件、同26.3%減)、卸売業(129件、同16.8%減)など5業種で前年同月比2ケタの大幅減少となった。一方、小売業(150件、同9.1%減)も4ヵ月ぶりに減少に転じた。
要因・背景
- 1.建設業…引き続き増加している公共工事や、消費税率10%への引き上げを見越した駆け込み需要による受注増加で大幅に減少
- 2.サービス業…件数が130件を下回ったのは2006年9月(108件)以来7年8ヵ月ぶり
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比81.9%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は600件(前月716件、前年同月793件)となった。一方、好景気時に件数が増加する傾向のある「設備投資の失敗」(9件、前年同月比50.0%増)が2ヵ月連続で前年同月比2ケタの増加。
要因・背景
- 1.「返済猶予後倒産」は42件(前年同月比30.0%減)判明
- 2.「不況型倒産」の件数、建設業(126件、前年同月比40.0%減)をはじめ全7業種で減少
倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
ポイント 負債5000万円未満の構成比50.1%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産の構成比は50.1%と、19ヵ月連続で過半数を占めたものの、件数は367件で、前年同月比28.6%減少となり、2007年9月(303件)以来の水準となった。一方、負債100億円以上の大型倒産は4ヵ月ぶりの発生となった。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が397件、構成比は54.2%を占めた。
要因・背景
- 1.負債5000万円未満の倒産、業種別では建設業(65件、前年同月比44.4%減)で大幅減
- 2.経済環境の改善を背景に小規模企業でも受注状況が改善し、小型倒産が減少
■地域別
ポイント9地域すべてで前年同月比減少
地域別に見ると、2010年7月以来3年10ヵ月ぶりに9地域すべてで前年同月を下回った。なかでも、近畿(149件、前年同月比34.9%減)や中部(104件、同32.9%減)など3地域で前年同月比30%以上の大幅な減少となったほか、関東(301件、同11.2%減)などその他の6地域でも同2ケタの減少となった。
要因・背景
- 1.近畿は、建設業(30件、前年同月比50.0%減)などを中心に4ヵ月連続の前年同月比減少
- 2.関東は、負債10億円以上の倒産(16件、前年同月比60.0%増)が増加
■上場企業倒産
9ヵ月連続で、上場企業の倒産は発生しなかった。
2014年は上場企業の倒産が発生しておらず、2013年に引き続いて沈静化の傾向が顕著となっている。
■大型倒産
負債トップは、(株)白元(東京都、民事再生法)の254億9400万円。(株)関西フィナンシャル・ポート(東京都、破産)の86億8600万円、(株)日本フィナンシャル・ポート(東京都、破産)の50億2100万円が続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは46.2、消費税ショックから脱せず
2014年5月の景気動向指数(景気DI:0~100、50が判断の分かれ目)は、前月比0.6ポイント減の46.2となり、2ヵ月連続で悪化した。
5月は、前月の消費税率引上げにともなう駆け込み需要の反動減の影響が多くの業界で残った。最も大きなショックを受けた『小売』は飲食料品や服飾品、日用品などを中心に通常状態に戻りつつあるものの、高額品は在庫が積み上がるなど反動減から脱することができなかった。加えて、建材関連の製造や卸売の動きが停滞したこともあり、『卸売』『運輸・倉庫』の景況感が悪化した。
10地域中9地域が悪化するも、景気の地域間格差は縮小傾向が定着
地域別では、『北関東』を除く9地域が悪化した。景気DIは消費税増税の影響で2ヵ月連続の悪化となった地域が多いものの、地方を中心に改善してきたアベノミクス効果もあり、地域間格差は3ヵ月連続して2ポイント台と縮小傾向にある。規模別にみると、「中小企業」での収益環境の悪化がみられたなかで、「大企業」が先行して反動減によるショックから脱する兆しも現れていた。国内景気は、一部の業種で改善がみられたものの、消費税増税ショックから脱せられなかった。ただし、今後の景気は、消費税ショックが継続する可能性もあるが、雇用環境の改善や夏のボーナスの増加を含めた賃上げの広がりが期待されるなど、緩やかに上昇していくとみられる。
今後の見通し
■第三者保証、経営者保証の議論に注目
法務省法制審議会民法(債権関係)部会は、今年7月末までに民法の改正要綱仮案を取りまとめる予定だ。現在、保証人保護の観点から検討されている「(経営者を除く)個人保証の制限」や「過大な保証の減額」が、この仮案にどのような形で盛り込まれるか、金融機関側、中小企業側ともに注目している。
今年2月には、全国銀行協会と日本商工会議所を事務局とする民間の研究会が策定した「経営者保証に関するガイドライン」の適用が開始。パブリックプレッシャーのもとで“個人保証(経営者保証)に依存しない融資慣行”の確立を目指しているが、定着には相応の時間が必要なようだ。背景には、中小零細企業経営の規律付けとして経営者保証を求める金融機関が多いだけではなく、借手企業の「融資が受けられなくなったり、金利が上がったりするくらいなら経営者保証を提供する」という本音がある。加えて、2011年の監督指針の改正以降、経営者以外の第三者の個人保証は“原則”抑制しているという金融機関側だが、実際には、信用補完の観点から中小零細企業向け融資に関して第三者保証を取るケースも少なくない。
■価格交渉力を失った製造業者の倒産増加を警戒
「ミセスロイド」、「アイスノン」、「ホッカイロ」といったヒット商品を持つ老舗企業、白元(東京都)が5月29日に民事再生法の適用を申請した。生活雑貨品業界の業界慣習である“製造業者が返品を前提に卸売業者に対して製品を販売する商慣行”への依存が倒産の一因。同慣行は、製造業者の資金繰りを助ける一方、卸売業者に対しリベートの支払いが生じるため、白元の収益性は低下していった。
デフレ経済の影響下、幅広い販売ネットワークを持つ卸売業者や、量販店などの小売業者が価格交渉力を持ち、そこからの値引き要請やリベート要求が強まった業界は生活雑貨品業界だけではない。家電量販店に格安大型テレビが並ぶ家電業界や、海外製品の流入が著しいアパレル業界なども、製造業者が価格交渉力を失っている業界である。5月の製造業の倒産件数は106件(前年同月比9.4%減)となり、3ヵ月連続の前年同月割れとなっている。しかし、倒産件数の沈静化とは相反して、収益性の低下に悩む製造業者は少なくない。“アベノミクス”の景気浮揚策には物価上昇もあるが、デフレ経済下で確立されてしまった企業間のパワーバランスを変移させるのは容易ではない。今後も白元のような、有名商品を持っているにもかかわらず採算の取れなくなっている老舗企業が行き詰まるケースが出てくるであろう。
■想定通りの売上落ち込みは、今後の倒産増加要因
消費税率引き上げ直後である4月の各種経済統計が出揃った。小売業を見ると、全国百貨店売上高は前年同月比12.0%の大幅減少(日本百貨店協会)、チェーンストア販売額は同5.4%の減少(日本チェーンストア協会)、JFAコンビニエンスストア統計(店舗売上高)は同2.2%減少(日本フランチャイズチェーン協会)と、従前の想定通り各業態で前年同月実績を割り込んだ(すべて既存店ベース)。経済産業省が公表した4月の商業販売額の動向でも、卸売業、小売業ともに前年同月を割り込んでいる。また、住宅着工戸数でも駆け込み需要の反動減が現れ、持家、分譲住宅、分譲マンションで3ヵ月連続の前年同月比減少となっている(国土交通省)。こうしたなか、5月の企業倒産件数は、2014年最少となる733件(前年同月比22.8%減)で、10ヵ月連続の前年同月比減少を記録。しかし、各種経済統計の数値が示す通り、4月の売上は“想定通り”減少した。零細企業からは「想定以上の落ち込み」との声も聞かれる。この影響は、企業倒産件数として後に現れるとみられ、年後半の件数増加要因となる。

