倒産件数は794件、15ヵ月連続の前年同月比減少
負債総額は1338億6000万円、5ヵ月連続の前年同月比減少
倒産件数 | 794件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲13.5% |
前年同月 | 918件 |
前月比 | +1.1% |
前月 | 785件 |
負債総額 | 1338億6000万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲12.2% |
前年同月 | 1524億900万円 |
前月比 | +4.7% |
前月 | 1278億7900万円 |
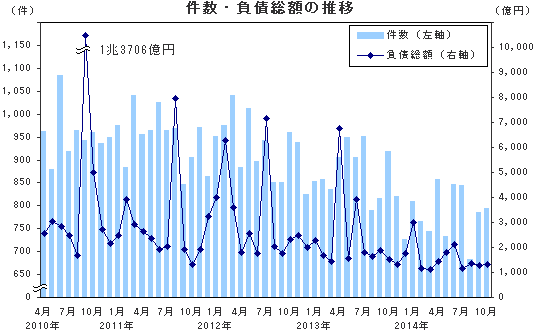
主要ポイント
- ■倒産件数は794件で、前年同月比13.5%の大幅減少を記録し、15ヵ月連続で前年同月を下回り、10月としては2004年(726件)以来10年ぶりに800件を割り込んだ
- ■負債総額は1338億6000万円となり、前月比では4.7%の増加となったものの、前年同月からは12.2%減少し、5ヵ月連続で前年同月を下回った
- ■業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を下回り、5業種とも前年同月比2ケタの大幅減少となった。なかでも建設業(164件、前年同月比21.5%減)は25ヵ月連続の前年同月比減少を記録した
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は649件(前年同月比14.7%減)となった
- ■円安に起因する「円安関連倒産」(39件、前月31件)が目立ち始める
- ■負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は433件で、構成比は54.5%と、24ヵ月連続で過半数を占めた一方、負債10億円以上の倒産は26件と低水準が続いた
- ■民事再生法による倒産が19件と2000年4月の同法施行以来最少を記録
- ■地域別に見ると、北陸(17件、前年同月比51.4%減)、近畿(190件、同21.2%減)、東北(26件、同18.8%減)など9地域中7地域で前年同月を下回り、うち6地域は前年同月比2ケタの減少となった
- ■負債トップは、マキコーポレーション(株)(東京都、破産)の96億800万円。ヴィンテージ(株)(旧:(株)ライブドア不動産、東京都、破産)の66億3000万円が続く
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は15ヵ月連続、負債総額は5ヵ月連続の前年同月比減少
倒産件数は794件で、前年同月比13.5%の大幅減少を記録し、15ヵ月連続で前年同月を下回り、10月としては2004年(726件)以来10年ぶりに800件を割り込んだ。負債総額は1338億6000万円となり、前月比では4.7%の増加となったものの、前年同月からは12.2%減少し、5ヵ月連続で前年同月を下回った。
要因・背景
件数…公共工事の増加や大手メーカーの業績回復の波及により、建設業(164件、前年同月比21.5%減)、製造業(113件、同22.1%減)を中心に大幅減少
負債総額…負債100億円以上の倒産が2ヵ月連続で発生せず、同10億円以上も26件の低水準
■業種別
ポイント7業種中5業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を下回り、5業種とも前年同月比2ケタの大幅減少となった。なかでも建設業(164件、前年同月比21.5%減)は25ヵ月連続の前年同月比減少を記録した。一方、不動産業(38件、同31.0%増)と運輸・通信業(40件、同17.6%増)の2業種は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1.建設業…災害復旧工事やインフラ整備需要の増加もあり、土木工事(22件、前年同月比40.5%減)を中心に減少傾向が続く
- 2.小売業…全体では減少も、駆け込み需要の反動減を受けた家電などで増加が目立つ
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比81.7%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は649件(前年同月比14.7%減)となった。構成比は81.7%(前月84.2%、前年同月82.9%)で、前月を2.5ポイント、前年同月を1.2ポイントそれぞれ下回った。
要因・背景
- 1.「返済猶予後倒産」は44件(前年同月比36.2%減)判明
- 2.円安に起因する「円安関連倒産」(39件、前月31件)が目立ち始める
■倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比54.5%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は433件で、前年同月を13.4%下回ったものの、構成比は54.5%と、24ヵ月連続で過半数を占めた。一方、負債10億円以上の倒産は26件と低水準が続いた。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が450件、構成比は56.7%を占めた。
要因・背景
- 1.負債5000万円未満の倒産、業種別では製造業(44件、前年同月比34.3%減)で大幅減
- 2.大企業・中堅企業の業績回復や資金繰り改善を受け、大型倒産の抑制状態が続く
■地域別
ポイント9地域中7地域で前年同月比減少
地域別に見ると、北陸(17件、前年同月比51.4%減)、近畿(190件、同21.2%減)、東北(26件、同18.8%減)など9地域中7地域で前年同月を下回り、うち6地域は前年同月比2ケタの減少となった。一方、四国(19件、同72.7%増)、九州(75件、同10.3%増)の2地域は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1.関東・近畿は、建設業を中心に3ヵ月連続で前年同月を下回る
- 2.四国は、負債1億円未満の小規模倒産を中心に2ヵ月連続の前年同月比増加
■上場企業倒産
上場企業の倒産は発生しなかった。
2013年8月のワールド・ロジ(株)(破産)以降、上場企業の倒産は14ヵ月連続で発生しておらず、沈静状態が続いている。
上場企業倒産の連続未発生期間としては、1986年9月から91年7月(59ヵ月連続)以来の長さ。
■大型倒産
負債トップは、マキコーポレーション(株)(東京都、破産)の96億800万円。ヴィンテージ(株)(旧:(株)ライブドア不動産、東京都、破産)の66億3000万円が続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは44.1、国内景気は低迷
2014年10月の景気DIは前月比1.0ポイント減の44.1となり、安倍内閣発足以降で初めて3ヵ月連続の悪化となった。深刻な人手不足が続くなか、建設業では材料費や工賃などの上昇を受注金額に反映できない厳しい状況が続いた。結果として、景気の下支え役が期待される公共事業の執行が入札不調などで滞り、役割を果たせないでいる。また、自動車関連は消費税率引き上げの反動減による生産減少が続き息切れ状態となった。『小売』や『サービス』など消費関連は2週連続で週末に上陸した台風もあって下押しされた。特に「家具類小売」はピークだった2014年3月からわずか7ヵ月間で40.9ポイント減と急激に落ち込んだ。
中小企業を中心に景況感の悪化広がる
地域別に見ると、消費者の生活防衛意識の高まりや地域の基幹産業の低迷により、『北海道』『北関東』では、飲食料品関連や自動車関連などで厳しさが増していた。また、規模の小さい企業ほど景況感の悪化幅が大きく、「中小企業」は建設や製造、卸売などが景況感を押し下げた。コスト上昇分を吸収できない中小企業を中心に景況感の悪化が広がっており、国内景気は全国的に低迷している。また、日本銀行による追加金融緩和で為替相場は一段と円安が進むとみられ、輸入企業や内需中心の中小企業の収益圧迫が懸念される。
2015年10月の消費税率再引き上げを考慮に入れた駆け込み需要や政府支出の拡大で、今後の景気は上昇基調で推移するとみられるが、一転して下降に転じるリスクもはらんでいる。
今後の見通し
■円高から円安へ、為替変動に翻弄される中小企業も
デフレ脱却を目指す日本銀行が10月31日に追加の金融緩和を決定して以降、円売りの流れが一段と加速している。2007年以来の1ドル115円という水準である
こうしたなか、円安を起因とした企業倒産、「円安関連倒産」も目立ち始めている。2014年10月の「円安関連倒産」は39件となり、前月(31件)を25.8%上回った。円安は、輸入企業の利益を押し下げるほか、原材料・エネルギーの調達コスト上昇は、幅広い業種に影響を与える。もっとも、足元での急速な円安進行によって突発的に行き詰まったわけではない。2012年末から続く円安局面における、原材料・エネルギーコストの高止まりによる収益悪化を通じて、経営体力を徐々に奪われた結果、倒産に追い込まれた企業が大半を占めている。また、円高局面で発生したデリバティブ損失から財務の健全化を図れていないなか、円安により海外からの仕入れ価格が上昇し採算が取れなくなって倒産に至った“ダブルパンチ倒産”も確認されている。
このデリバティブ損失とは、2007年から2011年にかけて為替が円高傾向を辿っていた時期に、金融派生商品(為替デリバティブ取引)により発生したもの。巨額の損失を被り倒産に至る中小企業が続発し、社会問題化したのは記憶に新しい。この「為替デリバティブ損失倒産(円高関連倒産)」は、集計を開始した2008年1月以降2014年10月までで累計146件判明。注目すべきは、安倍政権下での金融政策の本格化を受け円安が進行した2013年にも、29件の円高による「為替デリバティブ損失倒産」が判明しているという事実だ(ピークは2011年の32件)。同倒産は、2014年もすでに16件判明している。これらは、円高局面時のデリバティブ損失により財務基盤を毀損した企業が、その後も経営再建できずに行き詰った倒産事例と言える。
■中小企業がコスト上昇分を価格転嫁できるかに注目
中小企業経営者を悩ませているのは急激な為替変動だけではない。今年4月1日に実施された消費税率引き上げに伴う価格転嫁も、滞りなく進んでいるとは言い難い。経済産業省は、公正取引委員会と中小企業庁が、転嫁拒否行為に対し9月までに1338件の指導を行ったと公表した。「消費税込みの委託代金を消費税率引き上げ後も据え置いた」、「納入業者に対し消費税率引き上げ対応の価格シールの貼り付け作業を強要した」などといった事例が報告されている。消費税率引き上げに伴う価格転嫁については、事業者間取引よりも、消費者向け取引の方が、同業他社との競合の観点から難航するケースが多く、収益性低下に悩む小売業者は少なくない。消費支出が9月までで6ヵ月連続前年同月を下回っている現状(総務省「家計調査報告、二人以上の世帯」)では、消費者に対し価格転嫁せずに営業せざるを得ない状況を改善させるには至らないようだ。経済事情が違うため一概には比較できないが、1997年に消費税率を3%から5%に引き上げた後には、小売業の倒産件数が、1997年度から2000年度まで4年連続で前年度比増加となったという記録もある。消費者向け取引での価格転嫁の難しさは、数字にもなって表れている。
企業倒産件数全体をみれば、2014年10月は前年同月比13.5%減少の794件。金融機関による支援や大規模な財政出動といった倒産件数の押し下げ要因の効果が色濃く、2014年10月までで15ヵ月連続の前年同月比減少となった。少なくとも年内は情勢が急変するとは考え難いため、倒産の沈静化は続くとみられる。しかし、金融機関の支援スタンスや財政出動の規模は変化する可能性があることに加え、食品関連では小麦価格・飼料価格の高止まり、建設関連では材料費・労務費の高騰などコスト上昇が続いている。こうした価格転嫁問題など様々な懸念点を考慮すると、今後も倒産増加懸念が払拭できない状況が続くであろう。

