倒産件数は501件、12月として平成元年以来32年ぶりの低水準
負債総額は975億5900万円、2カ月連続の前年同月比減少
倒産件数 | 501件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲9.2% |
前年同月 | 552件 |
負債総額 | 975億5900万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲32.7% |
前年同月 | 1450億300万円 |
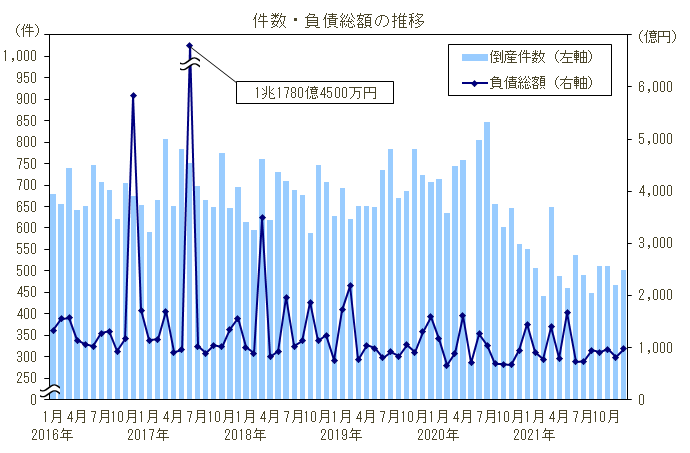
主要ポイント
- ■倒産件数は501件、12月としては2000年以降最少、1999年以前と比較しても1989年(平成元年)以来32年ぶりの低水準
- ■負債総額は975億5900万円(前年同月比32.7%減)と、2カ月連続の減少
- ■負債額最大の倒産はD-PROX㈱(東京都、破産)の約176億円
- ■業種別にみると、7業種中5業種で前年同月を下回った。小売業(前年同月132件→101件、23.5%減)では消費回復の影響もあり、アパレルなどが減少。サービス業(同136件→110件、19.1%減)でも、7カ月連続の前年同月比減となるなどB to C業種で減少傾向が続く
- ■主因別にみると、「不況型倒産」の合計は380件(前年同月418件、9.1%減)と、7カ月連続で前年同月を下回った。構成比は75.8%(対前年同月0.1ポイント増)を占める
- ■負債規模別にみると、負債5000万円未満の倒産は294件(前年同月345件、14.8%減)、構成比は58.7%を占める
- ■地域別にみると、9地域中5地域で前年同月を下回った。なかでも関東(前年同月231件→206件、10.8%減)は、東京都(同120件→105件)などの減少で前年同月比2ケタ減。近畿(同139件→117件、15.8%減)も同様に7カ月連続の2ケタでの大幅減となった
■件数・負債総額
倒産件数は501件、12月としては平成元年以来32年ぶりの低水準
倒産件数は501件(前年同月552件、前年同月比51件・9.2%減)と、12月としては2000年以降最少、1999年以前と比較しても1989年(平成元年)以来32年ぶりの低水準で推移した。引き続き倒産が抑制された状況が続き、7カ月連続の前年同月比減。
負債総額は975億5900万円(前年同月1450億300万円、前年同月比474億4400万円・32.7%減)と、2カ月連続の減少となった。■業種別
小売、サービスなど5業種で前年同月比減少
業種別にみると、7業種中5業種で前年同月を下回った。なかでも小売業(前年同月132件→101件、23.5%減)では緊急事態宣言の解除以降、人出増加や消費回復の影響もあり、アパレルなどの衣料品小売(11件)が減少。サービス業(同136件→110件、19.1%減)でも、7カ月連続の前年同月比減となるなどB to C業種で減少傾向が続く。
一方、運輸・通信業(前年同月16件→27件、68.8%増)では燃料高騰やドライバー不足の影響もあり、貨物自動車運送(20件)で増加。建設業(同99件→104件、5.1%増)は資材価格の高騰や人件費等の増加を背景に、7カ月ぶりに前年同月を上回った。■主因別
「不況型倒産」は380件、構成比は75.8%
主因別にみると、「不況型倒産」の合計は380件(前年同月418件、9.1%減)となり、7カ月連続で前年同月を下回った。構成比は75.8%(対前年同月0.1ポイント増)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
負債5000万円未満の構成比58.7%
負債規模別にみると、負債5000万円未満の倒産は294件(前年同月345件、14.8%減)、構成比は58.7%を占めた。負債5000万円未満の倒産では、サービス業(80件)が構成比27.2%(同2.4ポイント減)を占め最多、小売業(68件)が同23.1%(同2.4ポイント減)と続く。
資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人事業主含む)の倒産が334件(前年同月370件、9.7%減)、構成比は66.7%を占めた。■地域別
9地域中5地域で前年同月比減少
地域別にみると、9地域中5地域で前年同月を下回った。なかでも関東(前年同月231件→206件、10.8%減)は、東京都(同120件→105件)や埼玉県(同35件→21件)などの減少で前年同月比2ケタ減。近畿(同139件→117件、15.8%減)も同様に7カ月連続の2ケタ減となり、大幅な減少傾向が続く。東北(18件)、北陸(10件)、九州(35件)の3地域も減少となった。
一方、北海道(前年同月6→7件、16.7%増)、中部(同72→75件、4.2%増)など4地域は前年同月を上回った。■態様別
「破産」は458件、構成比91.4%
態様別にみると、破産は458件(構成比91.4%)。特別清算は28件(同5.6%)となった。民事再生法は15件で、うち8件を個人事業主が占めた。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは半数超の業種で新型コロナ前の水準を上回る
2021年12月の景気DIは前月比0.8ポイント増の43.9となり、4カ月連続で改善した。
12月の国内景気は、部品などの供給制約が一部で緩和する動きもみられ、51業種中29業種で新型コロナショック前である2020年1月の水準を上回った。外出機会の増加で衣類や娯楽サービスなど個人消費関連の景況感を押し上げた。さらに、半導体製造装置などは引き続き好調に推移したこともプラス材料となった。他方、原材料価格の高騰により仕入単価の上昇傾向が続いたことは、企業の収益環境を下押しする要因となった。農・林・水産業においては、生乳の供給過剰や飼料高騰などもあり、景況感が大きく悪化した。
国内景気は、緩やかな回復傾向が続いたものの、業種間で回復度合いに差がみられた。今後は緩やかな回復傾向が続く見込み
今後の国内景気は、新型コロナウイルス変異株の感染動向に左右される一方、対面型サービス消費や自動車などの生産も徐々に回復が見込まれる。また、企業業績の改善とともに設備投資意欲が上昇傾向にあり、設備投資も増加が続くとみられる。さらに、リベンジ消費や旺盛な自宅内消費の継続、5G関連の環境整備、半導体需要の増加、GoToトラベルの再開、SDGsへの対応もプラス材料となろう。他方、原材料価格の高騰・高止まりは大きな下振れリスクである。さらに、海外経済の回復力鈍化も懸念材料となる。感染拡大防止と経済活動の活発化へのバランスや、人手不足感の高まりなども注視する必要がある。
今後は、変異株の感染動向に左右されつつも、緩やかな回復傾向が続くとみられる。今後の見通し
■倒産激減、1966年以来半世紀ぶりの歴史的低水準に 上場企業倒産は5年ぶり発生ゼロ
2021年の倒産件数は前年比23.0%減の6015件となった。件数にして約2000件の大幅減少となり、1966年に次いで過去3番目に少ない、半世紀ぶりの歴史的低水準を記録した。5年ぶりに発生がゼロとなった上場企業の倒産動向も合わせ、全体的に倒産は沈静化の様相を呈した。
ただ、「倒産減少=景気回復の兆し」とみることはできない。一部業種ではコロナ禍特有の需要から好調を保つ業種もあるものの、総じてコロナ前には届かない水準が続いている。持続化給付金など政府による事実上の資本注入策に加え、各金融機関による無利子・無担保(ゼロゼロ)融資、既存融資のモラトリアムなど、官民一体の複層的な中小企業対策による「資金繰り破たんの先送り」が、結果として記録的な低水準への着地に大きく貢献したとみるべきだ。■1社当たりの負債額平均、13年ぶりに増加 目立つ「コロナ融資後」倒産
一方で、負債総額は前年比1.5%減の1兆1633億900万円と、大幅に減少した倒産件数に比べてほぼ横ばいでの推移となった。倒産1社の負債額平均(トリム幅上下1%)でみると、2020年が約9800万円/社だったのに対し、21年は約1億1200万円/社と1割を超える増加幅となったほか、リーマン・ショックの発生した08年以来、13年ぶりに前年を上回っている。
負債が増加している要因としては主としてゼロゼロ融資などコロナ対応の融資が挙げられ、「コロナ融資後倒産」も、2021年は前年に比べて明らかに発生が目立った。これらのケースの多くが、一旦は資金の供給を受けて当面の資金繰りを凌いだものの、経営が立ち直る前に返済開始時期を迎えた、あるいは返済の猶予期間中に将来への見切りをつけ、自ら事業継続を断念した「あきらめ型」によるものだ。22年からコロナ関連融資の返済が本格化するなか、融資を受けたものの収益改善が難航し、事業に行き詰まる経営不振企業が今後増加する可能性は高い。■「後継者難倒産」が最多更新、膨張した借入金が円滑な事業承継に影を落とす
倒産が減少したなかでも、逆に増加した業種やパターンもある。その一つが後継者の不在で事業継続の見込みが立たなくなった「後継者難倒産」で、2021年は最多の466件が発生した。倒産全体に占める割合も前年から1.9pt増の7.7%と急拡大しており、後継者問題が経営に及ぼすリスクがここに来て顕在化している。改善してはいるものの、依然として約6割の企業が後継者不在のなか、後継者の選定や育成を先送りしてきたところに代表者の突然の病気や死亡など不測の事態に直面し、事業継続が困難となったケースが多くを占める状況に変化はない。 しかし、2021年後半からはコロナ関連融資など「債務の膨張」が足かせとなって円滑な事業承継が進まず、事業継続を断念するケースも発生している。舞台照明の制作・設営を手がけるアント(12月、破産)は、創業代表の死去に伴い一旦は事業引継ぎを模索したものの、コロナ融資などで膨らんだ借入金の返済が困難と後継者が判断し、最終的に事業継続を断念した。
■私的整理の活用で「倒産回避」へ 事業継続か市場からの退出か、判断迫られる1年に
2022年も引き続き、企業継続を中心とした金融支援が行われ、経営不振企業に退場を促す内容へと大きく舵を切る事態は中長期的に考えづらい。また、ゼロゼロ融資などで過大な債務を背負った中小企業の再生手法として、スキーム整備が進む私的整理の積極活用が新たなトレンドとして普及しそうだ。そのため、法的整理による清算や事業再生を一旦回避する動きは今よりも強まるものと予想され、倒産の発生は引き続き低水準で推移する局面が続くだろう。
一方で、債務の利払いを事業利益で賄えず、慢性的な経営限界=財務不健全リスクを抱える「経営破たん懸念企業」は、昨年3月時点で全国約30万社に上る可能性が帝国データバンクの試算で分かった。根本的なリスクを抱えた企業が相当数あるなか、資金繰り支援や債務整理を中心とした支援策では、2021年のような劇的な倒産減少効果は得られない公算が大きく、倒産の発生が前年を上回る月が前年に比べて多くなりそうだ。
足元では変異型ウイルス「オミクロン株」の急速な感染拡大を受け、緊急事態宣言の発出など、正常化しつつある経済活動が再度制限される可能性もちらつく。2021年後半から徐々に持ち直しつつあった観光産業などでは、再三にわたる需要減で経営意欲が削がれ、先行き見通し難から最終的に事業を畳む決断をするケースが増える懸念も残る。コロナ禍を凌ぐ最中にある多くの中小企業で、借入金への依存度をさらに増やしてでも事業を継続させるのか、余力があるうちに会社を畳み市場から退出を選択するのか、その判断を迫られる正念場の1年となる。

