倒産件数は709件、5カ月連続の前年同月比減少
負債総額は1968億6300万円、3カ月連続の前年同月比減少
倒産件数 | 709件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲5.6% |
前年同月 | 751件 |
前月比 | ▲3.0% |
前月 | 731件 |
負債総額 | 1968億6300万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲83.3% |
前年同月 | 1兆1780億4500万円 |
前月比 | +111.0% |
前月 | 933億200万円 |
〈注〉前年同月(2017年6月)の負債総額は、タカタ(株)の負債額を1兆823億8400万円(確定再生債権等の総額)として集計(2018年上半期報・2018年6月報より適用)
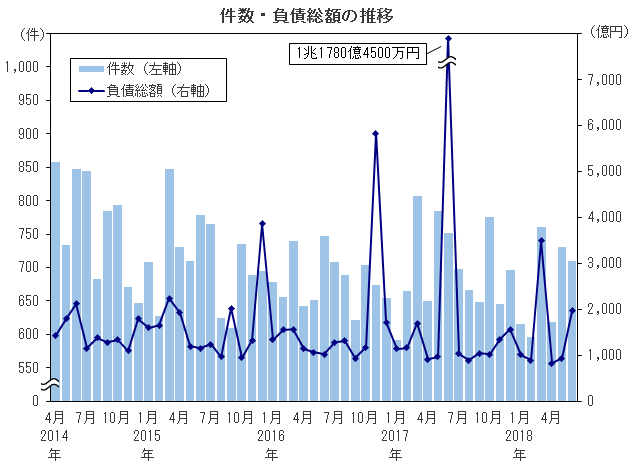
主要ポイント
- ■ 倒産件数は709件で、前年同月比では5.6%減少し5カ月連続で前年同月を下回った。負債総額は1968億6300万円で、前年同月比83.3%の減少となり、3カ月連続の前年同月比減少
- ■業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を下回った。このうち、製造業(83件、前年同月比17.0%減)、不動産業(15件、同42.3%減)の2業種は、3カ月連続の前年同月比減少。一方、卸売業(111件、同2.8%増)とサービス業(176件、同1.7%増)は2カ月連続で前年同月を上回った
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は561件(前年同月比11.2%減)となり、5カ月連続で前年同月を下回った。構成比は79.1%(同5.1ポイント減)を占めた
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は430件(前年同月比5.5%減)となった。構成比は60.6%となり、小規模倒産が大半を占める傾向が続いた。資本金規模別では資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が468件で、構成比66.0%を占めた
- ■地域別に見ると、北海道(23件、前年同月比4.2%減)は7カ月連続、中部(119件、同7.8%減)と近畿(175件、同12.5%減)、四国(10件、同33.3%減)の3地域は2カ月連続で前年同月を下回るなど、9地域中6地域で前年同月比減少となった。一方、関東(253件、同0.8%増)、九州(60件、同42.9%増)の2地域は前年同月を上回った
- ■負債トップは、日本海洋掘削(株)(東京都、会社更生法)の904億7300万円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント倒産件数は709件、5カ月連続の前年同月比減少
倒産件数は709件で、前年同月比では5.6%減少し、5カ月連続で前年同月を下回った。負債総額は1968億6300万円で、前年同月比83.3%の減少となり、3カ月連続の前年同月比減少。
要因・背景
件数…業種別では7業種中4業種で、地域別では北海道や中部など6地域で前年同月比減少
負債総額…負債100億円以上の倒産が2件発生も、小規模倒産が多数を占めた
■業種別
ポイント7業種中4業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を下回った。このうち、製造業(83件、前年同月比17.0%減)、不動産業(15件、同42.3%減)の2業種は、3カ月連続の前年同月比減少。一方、卸売業(111件、同2.8%増)とサービス業(176件、同1.7%増)は2カ月連続で前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 製造業は、飲食料品製造(14件、前年同月比12.5%減)や繊維製品製造(4件、同73.3%減)などが前年同月比2ケタの減少
- 2. サービス業は、ゴルフ場やパチンコホールなどの娯楽業(10件、前年同月比42.9%増)や広告代理(11件、同120.0%増)が前年同月を上回った
■主因別
ポイント「不況型倒産」は561件、構成比は79.1%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は561件(前年同月比11.2%減)となり、5カ月連続で前年同月を下回った。構成比は79.1%(同5.1ポイント減)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1.不況型倒産では、小売業(129件)が構成比23.0%を占め最多
- 2.「人手不足倒産」は14件(前年同月比180.0%増)、3カ月連続の前年同月比増加
- 3.「後継者難倒産」は45件(前年同月比95.7%増)、2カ月連続の前年同月比増加
- 4.「返済猶予後倒産」は44件(前年同月比7.3%増)、5カ月ぶりの前年同月比増加
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比は60.6%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は430件(前年同月比5.5%減)となった。構成比は60.6%となり、小規模倒産が大半を占める傾向が続いた。資本金規模別では資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が468件で、構成比66.0%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産では、サービス業(121件)が構成比28.1%を占め最多。小売業(112件)が同26.0%で続く
- 2. 負債100億円以上の倒産は2件と、大型倒産は低水準が続いている
■地域別
ポイント9地域中6地域で前年同月比減少
地域別に見ると、北海道(23件、前年同月比4.2%減)は7カ月連続、中部(119件、同7.8%減)と近畿(175件、同12.5%減)、四国(10件、同33.3%減)の3地域は2カ月連続で前年同月を下回るなど、9地域中6地域で前年同月比減少となった。一方、関東(253件、同0.8%増)、九州(60件、同42.9%増)の2地域は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1.北海道は、建設業(2件、前年同月比66.7%減)が3カ月連続で前年同月比減少
- 2.九州は、小売業(15件、前年同月比200.0%増)、サービス業(19件、同58.3%増)などが前年同月を上回り、4カ月連続の前年同月比増加
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは49.0、3カ月連続で悪化
2018年6月の景気DIは前月比0.4ポイント減の49.0となり、3カ月連続で悪化した。
6月の国内景気は、原油高などを受けた原材料価格の上昇に人件費や輸送費の高まりも重なり、仕入単価DIが4カ月連続の60台と高水準で推移した。一方で、販売価格への転嫁が緩やかなことなどから景況感の悪化につながった。加えて米中が追加・報復関税の実施を表明したことで貿易摩擦への警戒感が高まり、企業マインドに悪影響を及ぼした。6月18日に発生した大阪府北部の地震は、ライフラインの寸断や生産活動停滞、物流の混乱を招き、一部地域の景況感を下押しした。国内景気は、貿易摩擦の拡大で不透明感が強まるなか、原油高などを受けてコスト負担が増加したことで弱含んだ。
国内景気は輸出や設備投資がけん引も、エネルギー価格の高騰と海外リスクが懸念材料
国内は、世界経済の回復を背景に輸出の増加が続き、設備投資も人手不足の深刻化による省力化需要を受け底堅く推移すると見込まれる。東京五輪や消費税率引き上げにともなう駆け込み需要もプラス材料となろう。個人消費は緩やかな回復が予想される一方で、食品やエネルギー価格の上昇によって弱含む可能性がある。他方、海外動向では保護貿易主義の拡大による貿易摩擦の激化や、欧州の景気減速、中東の地政学的リスクが懸念される。今後は引き続き輸出や設備投資が底堅く推移すると見込まれる一方で、貿易摩擦の激化など海外リスクが国内景気を下押しする可能性について注視する必要がある。
今後の見通し
■倒産件数は4029件、製造業と小売業が倒産件数の減少に寄与
2018年上半期の企業倒産は4029件(前年同期比5.1%減)となり、上半期として2年ぶりに減少した。2月以降5カ月連続で減少し、特に製造業と小売業が倒産件数の減少に寄与する結果となった。6月には東証1部上場の海洋資源掘削業者である日本海洋掘削(負債904億7300万円、東京都)が東京地裁へ会社更生法の適用を申請、1年ぶりに上場企業倒産が発生した。
■SDGsの動きが本格化、企業活動への影響を注視
2015年に国連サミットで採択され、気候変動対策や環境保全など17項目にのぼる国際的な取り組みであるSDGs(持続可能な開発目標)が「経済財政運営と改革の基本方針2018」や「未来投資戦略2018」などで掲げられた。また、6月29日にはSDGs推進本部で29の自治体が「SDGs未来都市」として選定されるなど、政府においてSDGsに対する動きが本格化してきた。さらに、「拡大版SDGsアクションプラン2018」では、働き方改革や女性の活躍推進、人づくり革命などが国内における政策軸の1つとなっている。
2017年11月にはSDGsの達成を柱とした「企業行動憲章」(日本経済団体連合会)が改定されるなど、企業経営に一定の影響を及ぼすとみられる。また、金融機関でもSDGsに合致する事業を積極的に支援する事例も出ており、企業にとって金融機関からの融資に好影響となる可能性も指摘される。一方、漁獲枠やワシントン条約など国際的取り決めに対応できず倒産に至った事例も発生しているなど、企業によるSDGsへの取り組みの行方を注視する必要があろう。
■ゴルフ場経営業者の倒産増加、人口構造の変化への対応が重要に
ゴルフ場経営業者の倒産が急増している。2018年上半期の倒産件数は15件(前年同期7件)発生しており、すでに2017年通年で発生した12件を上回る。
ゴルフ業界では、2020年東京五輪の公式競技に復帰するなど追い風が吹くなかで、①コース造成やクラブハウス建設などの初期投資に関する預託金の償還期限問題、②主要プレーヤーとなる団塊世代の高年齢化など、経営課題は山積している(帝国データバンク「ゴルフ場経営業者951社の経営実態調査」2018年5月)。特に、2018年上半期の大型倒産上位30社のうち3分の1をゴルフ場経営業者が占めるなど、ゴルフ場経営などではサンクコストが巨額になりがちである。
一方で、ゴルフ場跡地のソーラー利用など効果的な転用も視野に入る。こうした産業や企業にとって、競技者数にも影響する人口構造の変化への対応が一層重要となっている。
■倒産件数は抑制された状態で推移も、住宅関連産業の動向に注目
国内景気は、人手不足の深刻化や省力化需要を背景に設備投資が底堅く推移すると見込まれるほか、輸出増加や東京五輪、消費税率引き上げによる駆け込み需要も好材料である。他方、食品や燃料価格の上昇に加え、貿易摩擦の激化や地政学的リスクが下押し要因となる可能性もある。
6月29日、TPP11(包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定、CPTPP)関連法が成立し国内手続きが完了、政府は年内の発効を目指している。また、RCEP(東アジア地域包括的経済連携)も年内合意を目指すとしており、企業を取り巻く国際ルールが大きく変わる可能性がある。 加えて、投資不動産に対する金融機関の融資が厳しくなっているなか、貸家を中心に新設住宅着工戸数が減少傾向にあることは、住宅建設だけでなく関連産業への影響も懸念される。
こうした状況の下、当面の倒産動向は抑制された状態で推移すると見込まれる。

