倒産件数は730件、2カ月ぶりの前年同月比減少
負債総額は1918億9100万円、3カ月連続の前年同月比増加
倒産件数 | 730件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲14.9% |
前年同月 | 858件 |
前月比 | ▲13.8% |
前月 | 847件 |
負債総額 | 1918億9100万円 |
|---|---|
前年同月比 | +34.2% |
前年同月 | 1429億5600万円 |
前月比 | ▲14.4% |
前月 | 2240億4700万円 |
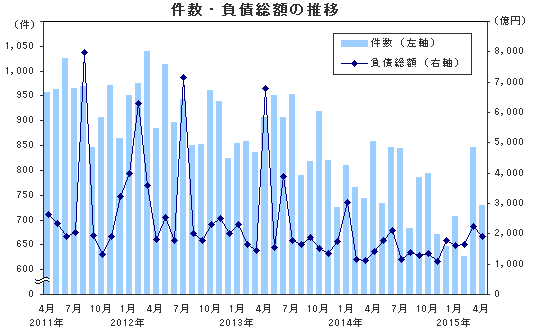
主要ポイント
- ■倒産件数は730件で、前年同月比14.9%の減少となり、2カ月ぶりに前年同月を下回った
- ■負債総額は1918億9100万円で、前年同月比34.2%の大幅増加を記録し、3カ月連続の前年同月比増加となった
- ■業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を下回った。このうち、運輸・通信業(27件、前年同月比41.3%減)、建設業(122件、同27.4%減)など4業種は前年同月比2ケタの大幅減少となった一方、不動産業(28件、同21.7%増)は唯一前年同月を上回った
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は617件(構成比84.5%)となった
- ■「円安関連倒産」は35件判明、16カ月連続の前年同月比増加を記録
- ■負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は409件で、構成比は56.0%と、前年同月を1.2ポイント上回り、30カ月連続で過半数を占めた。一方、負債10億円以上の倒産は25件にとどまり、3カ月ぶりに30件を下回った
- ■地域別に見ると、2014年5月以来11カ月ぶりに9地域すべてで前年同月を下回り、うち8地域が前年同月比2ケタの大幅減少となった。なかでも、四国(9件)は前年同月比47.1%、北海道(23件)は同30.3%の大幅減少となった
- ■東証1部上場の江守グループホールディングス(株)(福井県)が民事再生法の適用を申請し、1月のスカイマーク(株)(東京都)に続き、2015年としては2件目の上場企業倒産となった
- ■負債トップは、江守グループホールディングス(株)の711億円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は2カ月ぶりの前年同月比減少、負債総額は3カ月連続の前年同月比増加
倒産件数は730件で、前年同月比14.9%の減少となり、2カ月ぶりに前年同月を下回った。負債総額は1918億9100万円で、前年同月比34.2%の大幅増加を記録し、3カ月連続の前年同月比増加となった。
要因・背景
件数…2014年5月以来11カ月ぶりに9地域すべてで前年同月を下回り、うち8地域が前年同月比2ケタの減少となるなど、全国的に大幅減少を記録
負債総額…江守グループホールディングス(株)が負債711億円と全体を押し上げる
■業種別
ポイント7業種中6業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を下回った。このうち、運輸・通信業(27件、前年同月比41.3%減)、建設業(122件、同27.4%減)、サービス業(148件、同12.4%減)、小売業(164件、同11.4%減)の4業種は前年同月比2ケタの大幅減少となった。一方、不動産業(28件、同21.7%増)は唯一前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 建設業…2014年4月の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動から、住宅着工戸数が回復しつつあり、木造建築工事のほか電気配線工事や管工事などの設備工事中心に減少
- 2.運輸・通信業…軽油価格が低水準で推移するなど、経営環境が一部改善
■主因別
ポイント 「不況型倒産」の構成比84.5%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は617件(前年同月比13.8%減)となった。構成比は84.5%(前月80.4%、前年同月83.4%)と、前月を4.1ポイント、前年同月を1.1ポイントそれぞれ上回った。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、 業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1. 「返済猶予後倒産」は29件(前年同月比47.3%減)判明
- 2. 「円安関連倒産」は35件判明、16カ月連続の前年同月比増加
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比56.0%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は409件で、前年同月を13.0%下回ったものの、構成比は56.0%と、前年同月を1.2ポイント上回り、30カ月連続で過半数を占めた。一方、負債10億円以上の倒産は25件にとどまり、3カ月ぶりに30件を下回った。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が431件、構成比は59.0%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産、業種別では小売業(113件)が27.6%を占め最多
- 2. 大企業・中堅企業の業績回復や資金繰り改善を受け、大型倒産は低水準で推移
■地域別
ポイント9地域すべてで前年同月比減少
地域別に見ると、2014年5月以来11カ月ぶりに9地域すべてで前年同月を下回り、このうち関東(270件、前年同月比14.6%減)、近畿(178件、同14.4%減)など8地域で前年同月比2ケタの大幅減少となった。なかでも、四国(9件)は前年同月比47.1%、北海道(23件)は同30.3%の大幅減少となった。
要因・背景
- 1. 関東は、千葉県や東京都で建設業、サービス業を中心に減少が目立つ
- 2. 四国は、製造業(0件、前年同月6件)を中心に、建設、小売、サービスなど幅広く減少
■上場企業倒産
東証1部上場の江守グループホールディングス(株)(福井県)が民事再生法の適用を申請し、1月のスカイマーク(株)(東京都)に続き、2015年としては2件目の上場企業倒産となった。
■主な倒産企業
負債トップは、江守グループホールディングス(株)(福井県、民事再生法)の711億円。以下、エフエルワイ(株)(旧:中小企業レジャー機構(株)、東京都、特別清算)の69億6000万円、(株)ディーケイシー(東京都、破産)の65億4000万円がこれに続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは45.3、国内景気は上昇基調にあるなかで一服している
2015年4月の景気DIは前月比0.5ポイント減の45.3となり4カ月ぶりに悪化した。4月の国内景気は、日経平均株価が終値でITバブル時代の2000年4月14日以来15年ぶりに2万円台を回復するなど、金融市場は堅調に推移した。しかしながら、4月に入り食品関連の値上げが相次いだほか、軽乗用車などの自動車税が増税されるなど、個人消費を下押しする要因が重なった。また、予算執行の端境期や統一地方選の影響などで公共事業の発注が低調に推移したうえ、分譲住宅や持家の建築需要が低迷しており『建設』の景況感が大きく悪化した。人手不足にともなう人件費の上昇が企業のコスト負担を高めるなかで、「中小企業」、とりわけ「小規模企業」にしわ寄せが集中することとなった。国内景気は、上昇基調にあるなかで、個人消費や公共工事の低調が悪材料となり、一服している。
今後は一時的な落ち込みから緩やかに改善する見込み
今後は、大手企業を中心に賃金水準が全体的に上昇すると予測されているほか、プレミアム商品券など地方創生にともなう地域活性化策が具体化されることが期待される。また、東京五輪やリニア新幹線などの大型インフラ需要などの波及効果が表れてくるとみられる。税収がリーマン・ショック前の水準に回復すると見込まれるなか、96兆円規模となる2015年度予算の執行とともに、事業費規模で6兆円増額している復興予算など建設需要は高水準で続くだろう。今後の国内景気は、円安水準の継続による輸出拡大や、賃金上昇・採用意欲の高まりで消費の基盤となる所得環境が良くなるとみられており、一時的な落ち込みから緩やかに改善すると見込まれる。
今後の見通し
■建設業の倒産、再び前年同月比大幅減少
3月に2年6カ月ぶりの前年同月比増加となった建設業の倒産件数だが、4月は再び減少に転じた。東日本建設業保証が毎月公表している公共工事前払金保証統計によると2012年度と2013年度の公共工事請負金額(全国合計)はともに前年度比10%以上の増加。2014年度こそ同0.3%減少となったものの依然として高水準だ。公共工事の増減に建設業の倒産件数は影響を受ける傾向があるが、金融機関からの支援などの効果もあったとみられる。
もっとも、長引く資材価格・労務費の高騰から、建設業を警戒する向きもある。公共工事請負金額を四半期でみると、2014年7~9月、10~12月、2015年1~3月と3期連続で前年同期を下回り、一時の勢いを感じられなくなっている。また、請負金額ではなく件数で比較すると、2014年度は前年度比5.4%の減少であることから、案件が大型化してきている可能性が高い。そうなれば、地場の中小建設業者が恩恵を受けにくくなるとも想定でき、これらを踏まえると、今後も建設業の倒産件数が減少傾向を辿るとは考え難い状況になってきている。
■民事再生法による法的整理件数が過去最少に
4月の民事再生法による法的整理は15件で、2014年11月(16件)を下回り過去最少を更新した。構成比を見ても4月は2.1%で過去最低。経営不振企業の早期再建を目的として2000年4月に施行された同法は、経営権を旧経営陣に残すことができるなどのインセンティブがあったこともあり、施行されると多くの企業が同法の適用を申請した。2000年7月に民事再生法の構成比が過去最高となる15.6%を占めたほか、ピークとなった2002年4月には109件を記録している。
それが2012年度以降、民事再生法による法的整理が大きく減少した。背景には、(1)近年の業績回復や資金調達環境の改善、また私的整理スキームの充実により法的整理を選択する大手企業の減少、(2)金融機関に対する返済条件変更等で民事再生法の適用を申請しなくとも資金繰り改善効果を得られ破綻を回避している中小企業の増加などがあげられる。前者は前向きな減少理由であるが、後者は必ずしも前向きな理由とは言えない。近年の中小企業の倒産態様を見ると、民事再生法の構成比が低下し、破産の構成比が上昇する傾向にある(2015年4月における破産の構成比は93.8%で、前年同月と比べ2.1ポイント増加)。これは、再生手続きが困難な中小企業が増加しているということも意味している。
なお今後については、2014年12月に日本弁護士連合会が「特定調停スキーム利用の手引き」を改訂し、一層活用を推進していく姿勢を示していることも影響しそうだ。同スキームの使い勝手が良くなったことで、利用企業の増加が見込まれる。これは民事再生法件数を押し下げる要因であり、前述の背景と相俟って件数は当面、低水準での推移となるであろう。
■今年度に入っても倒産減少トレンド続くが、懸念事項は山積
2015年4月の企業倒産件数は730件となり、前月を117件(13.8%)、前年同月を128件(14.9%)大きく下回った。また、4月としては2006年4月(795件)以来9年ぶりの800件割れとなっている。2013年8月から2015年2月までは19カ月連続で前年同月比減少となったあと、前月(847件)こそ前年同月比13.8%増加となったが、今月再び大きく減少。近年の倒産件数減少トレンドは、今年度に入ってからも続いていると見るべきだろう。
しかし、足元の倒産増加懸念が払拭されたわけではない。各種コスト上昇、生活必需品の値上がりに伴う消費マインドの低下、円安による輸入企業の収益悪化懸念がある。さらには、ここにきて顕在化しつつある“チャイナリスク”の存在、地方建設業者の拠り所となっている公共工事も今後の財政出動の規模次第という危うさもある。また、金融機関から返済条件の変更等を受けている企業の出口戦略にも注目だ。“廃業”という選択肢が定着しつつあるなか、廃業リスクを踏まえた企業間信用の縮小が新たな懸念事項となる可能性もある。よって、減少トレンドが続く倒産件数だが、年後半に向けて増加トレンドに転じる可能性を否定することはできない。

