2020年7月以来、2年ぶりの2カ月連続増加
倒産件数は544件、2カ月連続で前年同月比増加
負債総額は1兆2839億800万円、5年ぶり1兆円超え
倒産件数 | 544件 |
|---|---|
前年同月比 | +1.3% |
前年同月 | 537件 |
負債総額 | 1兆2839億800万円 |
|---|---|
前年同月比 | +1668.9% |
前年同月 | 725億8300万円 |
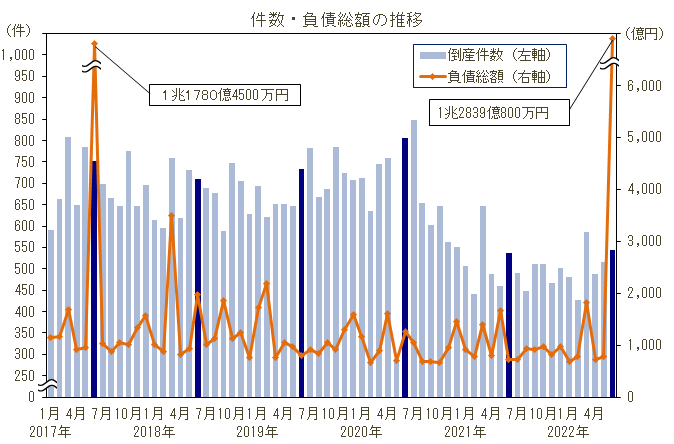
概況
倒産件数は544件(前年同月537件、1.3%増)と、前月から引き続き前年同月比で増加し、2020年7月以来、約2年ぶりの2カ月連続で増加となった。
負債総額は1兆2839億800万円(前年同月725億8300万円)と、自動車部品製造では過去最大の法的整理となったマレリホールディングス(株)(埼玉県、民事再生、負債額約1兆1856億2600万円)の影響で、タカタ(株)が倒産した2017年6月以来5年ぶりの1兆円超えを記録。
主要ポイント
- ■業種別にみると、7業種中5業種で前年同月比増加。サービス業(前年同月118件→135件)は4カ月連続で増加。一方、卸売業(同74件→66件)、小売業(同128件→99件)は減少
- ■主因別にみると、「不況型倒産」は430件、構成比は79.1%を占める
- ■業歴別にみると、業歴「30年以上」が最多、業歴10年未満の新興企業は増加
- ■地域別にみると、9地域中5地域で前年同月比増加。四国(前年同月15件→2件、86.7%減)では、愛媛以外で倒産が発生しなかったこともあり、過去40年で最少
■業種別 推移
7業種中5業種で前年同月比増加
業種別にみると、7業種中5業種で前年同月を上回った。資材・輸送費などコスト上昇が続く建設業(前年同月97件→114件、17.5%増)は、木造建築工事などの総合工事業(同33→47件)などが増加し、全体の件数を押し上げた。サービス業(同118件→135件、14.4%増)では、4カ月連続で増加。特に広告制作(同3件→7件)や経営コンサルタント(同3件→8件)の分野で増加が目立った。また、運輸・通信業(同29件→31件、6.9%増)では、3カ月連続の前年同月比増加となった。
一方、卸売業(前年同月74件→66件、10.8%減)、小売業(同128件→99件、22.7%減)の流通2業種は減少。新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着き、人流が活発化した影響もあり、特に飲食店(同56→35件)が4カ月連続で30%以上減少するなど、倒産抑制が続く。
■倒産主因別
「不況型倒産」は430件、構成比は79.1%
主因別にみると、「不況型倒産」の合計は430件(同396件、8.6%増)で2カ月連続の増加、構成比は79.1%(対前年同月5.3ポイント増)だった。
最多は「販売不振」の422件(前年同月387件、9.0%増)で、構成比は77.6%(対前年同月5.5ポイント増)を占めた。「業界不振」(同2件→6件、200.0%増)も増加した一方、「売掛金回収難」(同5件→1件、80.0%減)は減少した。
このほか、「放漫経営」(前年同月13件→5件、61.5%減)と「その他の経営計画の失敗」(同30件→26件、13.3%減)は2カ月連続の2ケタ減、「経営者の病気、死亡」(同27件→17件、37.0%減)は30%を超える大幅減となった。
倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■倒産態様別
「清算型」倒産は528件、構成比は97.0%
倒産態様別にみると、破産と特別清算を合わせた「清算型」倒産は528件(前年同月522件、1.1%増)で、構成比は97.0%を占めた。民事再生法と会社更生法を合わせた「再生型」倒産は16件(同15件、6.7%増)で、2カ月連続の前年同月比増加となった。
破産は505件(前年同月493件、2.4%増)で、3カ月連続の前年同月比増加となった。破産を業種別にみると、サービス業が125件で最多となり、建設業が112件で続く。負債額別でみると、負債5000万円未満の倒産が299件と、破産全体の59.2%を占めた。
一方、特別清算は23件(同29件、20.7%減)と、2カ月連続で20%を超える大幅減。民事再生法は16件(同15件、6.7%増)で、このうち12件を個人事業主が占めた。
■規模別
負債5000万円未満の構成比58.3%
負債規模別にみると、負債5000万円未満の倒産は317件(前年同月309件、2.6%増)、構成比は58.3%を占めた。このうち、サービス業(98件)が構成比30.9%(対前年同月4.7ポイント増)を占め最多。建設業(69件)が構成比21.8%(同3.0ポイント増)が続く。
資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人事業主含む)の倒産が359件(前年同月351件、2.3%増)、構成比は66.0%を占めた。
■業歴別
業歴「30年以上」が最多、業歴10年未満の新興企業では増加
業歴別にみると、業歴「30年以上」が171件(前年同月208件、17.8%減)で最多、構成比は31.4%(対前年同月7.3ポイント減)を占めた。このうち、老舗企業(業歴100年以上)の倒産は3件発生した。
一方、「3年未満」(前年同月18件→19件、5.6%増)、「5年未満」(同28件→48件、71.4%増)、「10年未満」(同71件→102件、43.7%増)などの新興企業の倒産はいずれも増加、なかでも負債額5000万円未満の小規模な倒産が目立った。
一方、「15年未満」の倒産(前年同月83→63件、24.1%減)では、6カ月連続で前年同月比20%以上の大幅減が続いている。
■地域別
北海道、関東など5地域で前年同月比増加、四国は過去40年で最少
地域別にみると、9地域中5地域で前年同月を上回った。北海道(前年同月11件→17件、54.5%増)は、運輸業(同0件→5件)の増加もあり、4カ月連続で前年同月比2ケタ以上の大幅増。関東(同200件→216件、8.0%増)では、卸売業(同24件→30件)やサービス業(同49件→67件)の増加などが全体を押し上げた。また、近畿(同134件→141件、5.2%増)は、大阪(同65件→68件)が6カ月ぶりの前年同月比増加に転じた。
一方、北陸(前年同月23件→12件、47.8%減)は半減、四国(同15件→2件、86.7%減)では、愛媛以外で倒産が発生しなかったこともあり、過去40年で最少となった。総じて、主に大都市圏で増加、地方圏で減少する傾向がみられた。
■景気動向指数(景気DI)
2022年6月の景気DIは41.4、人流の増加で対面型サービスが改善も、製造業が停滞
2022年6月の景気DIは前月比0.2ポイント増の41.4となり、4カ月連続で改善した。
6月の国内景気は、新型コロナウイルスの感染が落ち着き、人流が戻りつつあるなかで、業種や地域により景況感の改善・悪化が分かれる形で推移した。プラス要因としては、「コロナ感染者数が減少し、徐々にではあるが業績が回復しつつある」(旅館)などの声にあるように、各種イベントの再開や県民割の広がりなど対面型サービスの復調がみられた。一方マイナス要因としては、部品の調達難などで、特に自動車産業を中心として生産活動の停滞が続いた。原材料高に円安が加わるなかで、相次ぐ値上げは消費者心理を下押しする要因となった。国内景気は、プラスとマイナス要因が交錯するなか、業種・地域間で景況感の方向性が分かれ、4カ月連続で改善するも小幅な変動にとどまった。
物価上昇が懸念材料も緩やかに上向く
今後1年間程度の国内景気は、ロシア・ウクライナ情勢の行方や円安の進行、原油・原材料価格の高止まり、海外経済動向など、不透明な外部環境のなかで推移するとみられる。特に、コスト増加にともなう企業の収益力の低下は懸念材料となろう。他方、新型コロナの感染状況次第ながら、GoToキャンペーンなどの需要喚起策や、2021年度補正予算の執行、物価高対策、外国人観光客の受け入れ再開などの経済政策はプラス材料となる。個人消費の回復や自動車の挽回生産などが今後の景気を上向かせるカギになると見込まれる。
今後の景気は、物価上昇の勢いが懸念材料ながらも、緩やかに上向いていくとみられる。
今後の見通し
■増加基調への端境期入りか
2022年上半期(1~6月)の企業倒産は3045件にとどまった。年半期ベースで過去最少となった前年同期(3083件)をさらに下回り、歴史的な低水準が続いた。総額40兆円(2022年3月末時点)にのぼる、実質無利子・無担保等の「コロナ融資」の効果は大きく、多くの企業が資金ショートを回避できた。
だが前年同期比を見ると、倒産動向に“変化の兆し”がみられる。2022年上半期の減少率はわずか1.2%減(38件)と、2021年上半期(21.8%減)から大幅に縮小し、企業倒産は「コロナ禍前半の減少基調から横ばい圏にシフトした」ともいえる。
月別件数を見ても、1年ぶりに増加に転じた5月(517件、前年同月比12.1%増)に続き、6月(544件、同1.3%増)も前年同月を上回り、2カ月連続の増加となった。倒産件数自体は、600~700件台が続いたコロナ禍前に比べて低水準ながら、足元では「横ばい圏から底を打ち、増加基調へシフトする端境期」に入りつつある。
■マレリ再生法も、法的整理回避の動き続く
他方、2022年上半期の負債総額は1兆7630億8300万円となり、前年同期(6280億7600万円)の2.8倍に急増した。これは、経営再建中の自動車部品大手「マレリホールディングス」(以下マレリHD、埼玉県)が6月24日、負債約1兆1856億2600万円(2020年12月末時点)を抱え、東京地裁へ民事再生法を申し立てた影響が大きい。
マレリHD は、2017年6月に民事再生法を申し立てたエアバッグ大手の「タカタ」(元・東証1部上場、負債1兆823億8400万円)を上回り、製造業で国内最大の負債額となった。マレリHDを除く負債総額で見ると、前年同期を下回っており、「大企業や地場大手クラスの法的整理回避の動き」は今後も続くだろう。
事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)から一転して“法的整理”という異例の結論となったマレリHD。3月1日のADR申請以来、取引金融機関を集めて債権者会議を重ねていたが、ADR成立の条件である「全金融機関の同意」を得られず、ADR手続きが不成立となり民事再生法を申請。「簡易型」の民事再生手続きを選択することとなった。
■年後半にかけて緩やかな増加
6月7日に閣議決定された『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画』に、「事業再構築のための私的整理法制の整備」が盛り込まれた。欧州各国において存在する、すべての貸し手の同意を必要とせず、裁判所の認可の下で事業再構築に向けて「多数決」により金融債務の減免等を可能とする法制度についての検討、国会提出に向けた動きが本格化していきそうだ。
今後の倒産動向に影響を及ぼす主なリスク要因としては、①円安・原材料高・値上げの動き、②コロナ融資等の返済本格化とリスケ要請状況、③再び増加に転じた新型コロナウイルスの感染状況などが挙げられる。倒産増が懸念される主な注目業界としては、①倒産件数全体へのインパクトが大きく、減少基調からの底打ちが鮮明な「建設業」、②燃料高と人手不足に直面する「運輸業」、③電力調達価格の高騰による“逆ざや”に苦しむ「新電力」などだろう。
取材現場では「最近、粉飾の事例が増えてきた印象」(金融機関)との気になる声も聞かれる。業界を問わず、コロナ禍で苦境にある中小企業の過剰債務問題は、一朝一夕に解消に向かうものではない。“トリアージ”とも称される企業選別の動きが水面下で進むなか、企業倒産は年後半にかけて緩やかに増加をたどっていくものと見られる。

