倒産件数は744件、8ヵ月連続の前年同月比減少
負債総額は1119億6000万円、2ヵ月連続で最小を更新
倒産件数 | 744件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲11.0% |
前年同月 | 836件 |
前月比 | ▲2.7% |
前月 | 765件 |
負債総額 | 1119億6000万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲22.6% |
前年同月 | 1446億2300万円 |
前月比 | ▲3.9% |
前月 | 1165億4300万円 |
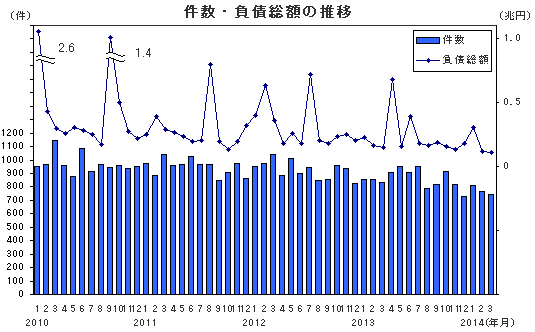
主要ポイント
- ■倒産件数は744件で、前年同月比11.0%の減少となった。8ヵ月連続で前年同月を下回り、2013年度では12月(726件)に次いで2番目に少ない件数となった
- ■負債総額は1119億6000万円で、前年同月比22.6%の減少となった。2000年以降で最小を記録した前月(1165億4300万円)を下回り、2ヵ月連続で最小を更新した
- ■業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を下回った。なかでも、建設業(134件、前年同月比35.9%減)は2ヵ月連続30%超の大幅減で、2000年2月(131件)以来、14年1ヵ月ぶりに130件台にとどまった
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の構成比は83.1%(前月84.3%、前年同月81.5%)で、前月を1.2ポイント下回ったものの、前年同月を1.6ポイント上回った
- ■「金融円滑化法利用後倒産」は41件(前年同月比2.4%減)判明
- ■負債5000万円未満の倒産は420件で、前年同月を0.7%下回ったものの、構成比は56.5%と、17ヵ月連続で過半数を占めた
- ■地域別では、9地域中7地域で前年同月を下回った。なかでも、北陸(27件、前年同月比25.0%減)、中部(104件、同24.1%減)、九州(43件、同20.4%減)の3地域は、前年同月比20%超の大幅減少となった
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は8ヵ月連続の前年同月比減少、負債総額は2ヵ月連続で最小を更新
倒産件数は744件で、前年同月に比べ11.0%減少。8ヵ月連続で前年同月を下回り、2013年度では12月(726件)に次いで2番目に少ない件数となった。負債総額は1119億6000万円で、前年同月を22.6%下回り、2000年以降で最小を記録した。
要因・背景
件数…公共工事の増加などで、建設業が関東を中心に9地域中7地域で前年同月比減少
負債総額…負債100億円以上の大型倒産が発生せず、同10億円以上も17件にとどまる
■業種別
ポイント7業種中5業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を下回った。なかでも、建設業(134件、前年同月比35.9%減)は2ヵ月連続30%超の大幅減で、2000年2月(131件)以来、14年1ヵ月ぶりに130件台にとどまった。一方、小売業(185件、同36.0%増)、不動産業(23件、同4.5%増)の2業種は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1.建設業…内装工事(前年同月比68.0%減)、土木工事(同62.1%減)を中心に大幅減少
- 2.小売業…原材料価格の高騰や中食産業との競争激化などを受け、飲食店(69件、前年同月比72.5%増)の増加が目立つ
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比83.1%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は618件(前月645件、前年同月681件)となった。構成比は83.1%(前月84.3%、前年同月81.5%)で、前月を1.2ポイント下回ったものの、前年同月を1.6ポイント上回った。
要因・背景
- 1.「金融円滑化法利用後倒産」は41件(前年同月比2.4%減)判明
- 2.「不況型倒産」の構成比、四国(70.6%、対前年同月13.6ポイント減)の減少目立つ
倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比56.5%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は420件で、前年同月を0.7%下回ったものの、構成比は56.5%と、17ヵ月連続で過半数を占めた。一方、負債100億円以上の大型倒産は2ヵ月連続で発生しなかった。資本金別に見ると、個人経営と資本金1000万円未満の合計は438件、構成比は58.9%を占めた。
要因・背景
- 1.大型倒産の沈静化で負債10億円以上の倒産は17件にとどまり、2000年1月以降で最少
- 2.負債5000万円未満の業種別では、小売業(123件、構成比29.3%)が最多
■地域別
ポイント9地域中7地域で前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中7地域で前年同月を下回った。なかでも、北陸(27件、前年同月比25.0%減)、中部(104件、同24.1%減)、九州(43件、同20.4%減)の3地域は、前年同月比20%超の大幅減少。一方、東北(28件、同7.7%増)、中国(45件、同4.7%増)の2地域は前年同月を上回った。
要因・背景
関東は、建設業(45件、前年同月比36.6%減)が大幅に減少したほか、茨城、栃木、東京などで製造業が減少し、8ヵ月連続で前年同月を下回る
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは51.0、調査開始以来、初めて50を上回る
2014年3月の景気動向指数(景気DI:0~100、50が判断の分かれ目)は、前月比1.4ポイント増の51.0となり、2002年5月の調査開始以来、初めて判断の分かれ目となる50を上回った。
消費税増税を控えて、駆け込みや買いだめ需要がピークとなり、景気上昇の原動力となった。2月までの駆け込み需要は耐久財を中心としていたが、3月は住宅・マンションの引き渡しや新生活の始まる時期によりインテリアへの支出や白物家電などが好調なうえ、食料品や日用品の買いだめも多く現れた。また、駆け込みで購入した物品や引っ越しなどの配送を担う『運輸・倉庫』も車両やドライバーが不足し、需要が供給に追いつかない状況がみられた。さらに、年度末の季節需要も堅調に推移し、10業界中8業界が改善した。
駆け込み需要がピークを迎え景気を押し上げる
地域別では全10地域が改善しており、『近畿』を除く9地域が50を上回った。特に『四国』では、南海トラフ地震対策などの公共投資や民間の設備投資ともに堅調だった『建設』など10業界中7業界が改善した。規模別では2ヵ月ぶりに全規模が改善したが、とりわけ「中小企業」は『小売』『卸売』『運輸・倉庫』がけん引役を果たしたこともあり大幅に改善した。国内景気は、消費税増税を控えて駆け込み需要がピークとなり、『小売』『運輸・倉庫』を中心に大きく押し上げられた。
総じて、外需関連業種に加えて内需関連業種にも改善の広がりが現れており、国内景気は回復に向けた動きが顕著になっている。
今後の見通し
■“アベノミクス効果”か、負担感増大か
4月1日、消費税率が5%から8%へと引き上げられた。過去を振り返ると、前回の増税時である1997年4月の百貨店(既存店)の売上は前年同月比14.0%減(日本百貨店協会)で、下落幅は統計開始以降最大であった。また、スーパーマーケット(既存店)の売上も同4.6%の減少(日本チェーンストア協会)と、消費税率が引き上げられた後、駆け込み需要の反動減、消費マインドの落ち込みにより、小売業の不振が統計にはっきりと表れた。企業倒産をみても、小売業は1997年度(前年度比13.0%増)から2000年度(同10.3%増)まで4年連続で前年度増加を記録。消費税率引き上げ後、4年連続前年度比増加となったのは、小売業のみである。今回の増税後も小売業に注目である。2013年度の小売業の倒産は1981件(前年度比0.2%減)とほぼ横ばい。増加こそしていないものの、企業倒産全体が減少したなかで小売業は減少していない。デフレ経済のあおりを受けた商品の低価格化進行は著しいうえに、円安などの影響による原材料費値上がり分を価格に転嫁できず、収益性が低下している企業は多い。“アベノミクス効果”を期待したいところだが、物価上昇による家計の負担感増大もあり、小売業を取り巻く環境は厳しそうだ。
また、道路貨物運送業の倒産件数(290件)が2年連続で前年度比増加となるなど運輸業の業界環境はさらに厳しい。円安の影響でトラックの主な燃料である軽油価格の上昇が続くなか、消費税だけではなく、同じタイミングで地球温暖化対策税も引き上げられるため、4月以降一段と燃料費は上がる。実際に、資源エネルギー庁の発表によると4月一週の軽油小売価格は、前週と比べ3.5円大きく値上がりして142.6円/L(税込み)となった。経費の大半を占める燃料費上昇が続く限り、2014年度も行き詰まる運輸業者は多いとみられる。
■返済猶予状態の企業は未だ多く、2014年度も倒産増加懸念払拭できず
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針のなかに、顧客企業のライフステージ等に応じて提案するソリューションの例として、「債務整理等を前提とした顧客企業の再起に向けた適切な助言」や、「顧客企業が自主廃業を選択する場合の取引先対応等を含めた円滑な処理等への協力」といった文言が明記されてから、3年が経過した。この監督指針は、金融機関が単に返済条件の変更等により業況が厳しい企業の資金繰りを支援する(延命させる)だけではなく、“円満な退出”を含めた事業の選択と集中、再編を推し進めることの必要性を示している。
しかし、中小企業者向けの「貸付条件の変更等の状況」(金融庁)をみると、2012年度上半期約61.0万件、2012年度下半期は約61.6万件、2013年度上半期は約58.9万件と貸付条件変更数は横ばいで推移。未だ返済猶予で凌いでいる企業が多いことに加え、業界環境が改善している企業が抜本的な経営改革を行わず返済緩和状態に甘んじているという現実もある。帝国データバンク景気動向調査において景気DIが3月調査で初めて50を上回るなど、景気が回復傾向を示しているときこそ返済条件を当初の約定通りに戻すことが期待されるが、理想通りにはいかず中小企業金融円滑化法施行時と状況があまり変わっていない企業は多い。
なぜならば、景気の先行きへの期待感はあるものの、足元では、(1)円安などを背景とした原材料・燃料価格の高騰、(2)技術者を中心とした人手不足による労務費高騰、(3)デフレからの脱却の遅れによる価格競争、さらには、(4)消費税率引き上げに伴う消費マインドの低下、駆け込み需要からの反動減、(5)金融機関のスタンスの変化など、懸念事項が山積しているからである。2013年度の企業倒産は、前年度比5.7%の減少となったが、問題の先送り感は否めない。とはいえ、政府が公共工事などの2014年度予算の執行を本年度上半期に集中させる方針であることから、倒産件数が急に増加するとは考えにくい。こうした背景を踏まえれば、2014年度の企業倒産件数は増加懸念が払拭されない状態のまま、一進一退で推移する可能性が高い。

