倒産件数は783件、2カ月連続の前年同月比増加で今年最多
負債総額は916億9000万円、2カ月連続の前年同月比減少
倒産件数 | 783件 |
|---|---|
前年同月比 | +13.6% |
前年同月 | 689件 |
負債総額 | 916億9000万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲10.4% |
前年同月 | 1022億8400万円 |
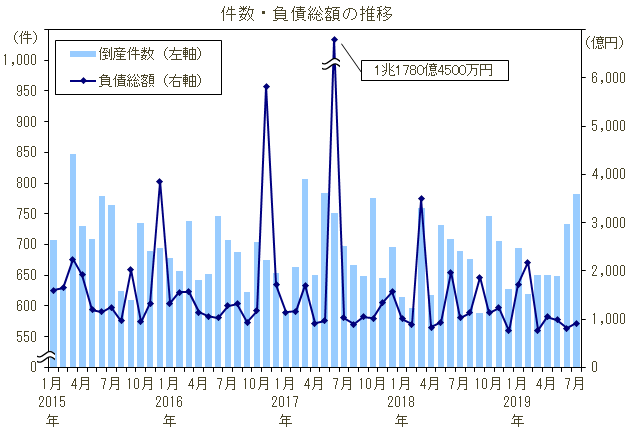
主要ポイント
- ■倒産件数は783件(前年同月比13.6%増)と、7月としては2013年7月(952件、同1.0%増)以来、6年ぶりに前年同月を上回り、2カ月連続の前年同月比増加で今年最多
- ■負債総額は916億9000万円(前年同月比10.4%減)と、2カ月連続で前年同月を下回った。負債5000万円未満の倒産が6割超となったほか、負債1億円前後の倒産を中心に増加した
- ■業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を上回った。製造業(78件、前年同月比4.0%増)は、機械器具製造業などが増加した。小売業(208件、同19.5%増)は、飲食店が原材料費の高騰などを受け大幅増。サービス業(161件、同9.5%増)は、ソフトウェア開発などで増加が目立った
- ■主因別に見ると、「不況型倒産」の合計は613件。構成比は78.3%を占める
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は497件、構成比は63.5%を占める
- ■地域別に見ると、9地域中7地域で前年同月を上回り、なかでも東北、関東、北陸、中部の4地域は今年最多
- ■「人手不足倒産」は14件(前年同月比100.0%増)発生。3カ月ぶりの前年同月比増加
- ■負債トップは、(株)YTフーズ(千葉県、破産)の約71億7500万円
調査結果
■件数・負債総額
倒産件数は783件、2カ月連続の前年同月比増加で今年最多
倒産件数は783件(前年同月比13.6%増)と、7月としては2013年7月(952件、同1.0%増)以来、6年ぶりに前年同月を上回り、2カ月連続の前年同月比増加で今年最多となった。
負債総額は916億9000万円(前年同月比10.4%減)と、2カ月連続で前年同月を下回った。負債5000万円未満の倒産が6割超となったほか、負債1億円前後の倒産を中心に増加した。
■業種別
製造業、小売業など6業種で前年同月比増加
業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を上回った。
製造業(78件、前年同月比4.0%増)は、機械器具製造業(24件、同84.6%増)などが増加した。小売業(208件、同19.5%増)は、飲食店(77件、同42.6%増)が原材料費の高騰などを受け大幅増。サービス業(161件、同9.5%増)は、ソフトウェア開発(18件)などで増加が目立った。
■主因別
「不況型倒産」は613件、構成比は78.3%
主因別に見ると、「不況型倒産」の合計は613件(前年同月比11.9%増)となり、3カ月ぶりに前年同月を上回った。構成比は78.3%(同1.2ポイント減)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
負債5000万円未満の構成比63.5%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は497件(前年同月比10.2%増)、構成比は63.5%を占めた。負債5000万円未満の倒産では、小売業(156件)が構成比31.4%(同3.0ポイント増)を占め最多、サービス業(111件)が同22.3%(同2.1ポイント減)で続く。
資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人事業主含む)の倒産が518件(前年同月比13.6%増)、構成比は66.2%を占めた。
■地域別
東北、関東など4地域で今年最多
地域別に見ると、9地域中7地域で前年同月を上回り、なかでも東北、関東、北陸、中部の4地域は今年最多となった。
東北(44件、前年同月比46.7%増)は、小売業(11件)などが増加。関東(300件、同14.9%増)は、東京都の建設業(26件)、神奈川県のサービス業(14件)などで増加が目立った。近畿(175件、同14.4%増)は飲食料品などの卸売業(34件、同88.9%増)、ソウトウェア開発などのサービス業(43件、同22.9%増)が前年同月比2ケタ増だった。
■態様別
「破産」は731件、構成比93.4%を占める
態様別に見ると、破産は731件(構成比93.4%)、特別清算は26件(同3.3%)となった。民事再生法(26件)は、前年同月を1件上回った。
■特殊要因倒産
人手不足倒産
14件(前年同月比100.0%増)発生。3カ月ぶりの前年同月比増加
後継者難倒産
52件(前年同月比79.3%増)発生。2カ月ぶりの前年同月比増加
返済猶予後倒産
56件(前年同月比107.4%増)発生。3カ月ぶりの前年同月比増加
※特殊要因倒産では、主因・従因を問わず、特徴的な要因による倒産を集計
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは44.6、8カ月連続で悪化
2019年7月の景気DIは前月比0.5ポイント減の44.6となり、8カ月連続で悪化した。
7月の国内景気は、海外経済の低迷にともなう輸出減速などを受けた製造業の悪化基調が、関連業種にマイナスの影響を及ぼしたほか、先行きの不透明感を背景に設備投資意欲DIが2016年10月以来2年9カ月ぶりの水準まで低下したことも悪材料となった。また、月前半を中心に一部地域で起きた記録的な日照不足や平年より低い気温が続くといった天候不順が、消費や食品に関連する業種の景況感を押し下げた。人件費などのコスト負担が引き続き重荷となったうえ、周辺国との関係悪化が一部企業のマインドを下押しした。
国内景気は、製造業の悪化基調や設備投資意欲の低下が続くなか、天候不順も響き、後退局面入りの可能性が高まってきた。
消費税率引き上げによる消費減退など、不透明感が一層強まる
今後は、省力化需要に加え東京五輪の開催や公共投資も寄与し、設備投資は底堅く推移するであろう。個人消費は、良好な雇用環境が引き続きプラス材料ながら、消費税率の引き上げにともない一時的に落ち込むと予想される。また中国を含め世界経済の低迷を背景とした輸出の減速基調は、製造業などの景況感を下押しする可能性がある。海外は、中国経済や日米通商交渉、FRB(米連邦準備制度理事会)の利下げなどが及ぼす影響が懸念されるほか、英EU離脱および日韓関係も注視していく必要がある。
今後の国内景気は、消費税率引き上げにともなう消費減退に加え、日米通商交渉やFRBの利下げが及ぼす影響も懸念され、不透明感が一層強まっている。
今後の見通し
■倒産件数は今年最多、小売業は10年4カ月ぶりの高水準
2019年7月の倒産件数(783件、前年同月比13.6%増)は、7月としては2013年7月(952件、同1.0%増)以来6年ぶりに前年同月を上回り、2カ月連続の前年同月比増加で今年最多となった。業種別では、小売業(208件、同19.5%増)で飲食料品店や衣料品店、飲食店などの倒産が増加し、7月としては過去最多、2009年3月(212件)以来10年4カ月ぶりの高水準となった。販売不振による小規模企業の倒産が目立ち、小売業は1~7月累計でも前年同期比3.4%増と、前年同期を上回る業種のなかで最大の増加幅となっている。
また、負債総額(916億9000万円)は、100億円規模の大型倒産が発生せず、小規模倒産が大半だったことから、7月としては最小だった前年(1022億8400万円)をさらに下回った。
■消費税率引き上げの影響を注視
7月は、食品スーパー2店舗を新潟県内で展開していた(株)サンゴマート(破産、負債約5億8700万円)が来店客数の落ち込みなどから倒産に追い込まれた。10月からの消費税率引き上げを前に、軽減税率レジ導入やシステム改修などのさらなるコスト負担も見込まれたことから、追加融資が難しいなか、事業継続を断念した。
内閣府が発表した直近7月の消費動向調査によると、消費者態度指数(2人以上の世帯、季節調整値)は、前月から0.9ポイント低下し37.8と、10カ月連続の悪化で、2014年4月以来5年3カ月ぶりの低水準にとどまった。消費税率が8%へ引き上げられた前回(2014年4月)は、円安・株高を背景に緩やかな景気回復基調にあったことや、金融機関による積極的な返済条件の変更等(リスケジュール)が継続していたことで、その後の倒産件数は減少傾向で推移したものの、娯楽業やアパレル関連の小売業など一部の業種では倒産の増加がみられた。今回の消費税率10%への引き上げは、前回ほどの駆け込み需要は想定されておらず、反動減も限定的とみられるものの、消費者心理が弱まっているなか、その影響には注視を要する。
■倒産増加が続く可能性も
金融庁は6月28日より、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を改正し、早期警戒制度の新たな運用を開始した。銀行経営の健全性を評価する指標の一つである「収益性」について、「持続可能な収益性と将来にわたる健全性」へと変更し、持続可能な収益に懸念がある地域金融機関への監視を強化するほか、業務改善命令も活用し、厳しく改善を求めていくこととなった。低金利や人口減少により収益環境が厳しさを増している地域金融機関では、リスケが長期間続いている融資先などへの今後の対応が注目される。
また7月31日には、2019年度の最低賃金(時給)の目安を全国平均で過去最大の27円引き上げ、901円とすることが決まった。東京都と神奈川県では全国で初めて最低賃金が時給1000円を超えることとなる。最低賃金は、ここ5年間ですでに14.4%(764円→874円)、ここ10年間では24.3%(703円→874円)も上昇している。コスト負担感は商品・サービス価格に転嫁しにくい中小零細企業ほど強く、今後は飲食、小売、サービスなど労働集約的な業種を中心に、さらなる収益圧迫が懸念される。米中貿易摩擦の一段の深刻化や円高・株安の急激な進行などを受け、企業業績や設備投資の下振れ懸念も拡大するなか、今後の倒産件数は緩やかな増加傾向に転じる可能性が高まっている。

