倒産件数は683件、7年11ヵ月ぶりの700件割れ
負債総額は1376億7400万円、3ヵ月連続の前年同月比減少
倒産件数 | 683件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲13.4% |
前年同月 | 789件 |
前月比 | ▲19.1% |
前月 | 844件 |
負債総額 | 1376億7400万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲15.8% |
前年同月 | 1635億7000万円 |
前月比 | +19.5% |
前月 | 1152億3800万円 |
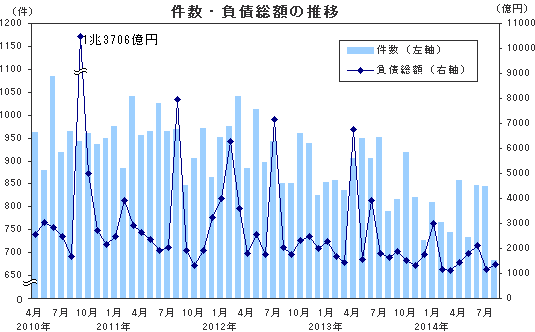
主要ポイント
- ■倒産件数は683件で、前年同月に比べ13.4%の大幅減少。13ヵ月連続で前年同月を下回り、2006年9月(667件)以来7年11ヵ月ぶりに700件を割り込んだ
- ■負債総額は1376億7400万円と、前年同月を15.8%下回った。3ヵ月連続の前年同月比減少となったものの、前月比は19.5%の増加となった
- ■業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を下回り、なかでも建設業(138件、前年同月比16.4%減)は23ヵ月連続の前年同月比減少となった。また、製造業(75件、同21.9%減)と小売業(124件、同20.5%減)で前年同月比20%以上の大幅な減少を記録
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の構成比は81.6%(前月83.3%、前年同月82.4%)と、前月、前年同月ともに下回った
- ■「返済猶予後倒産」は33件(前年同月比6.5%増)判明
- ■負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は367件で、構成比は53.7%と、22ヵ月連続で過半数を占めた一方、負債10億円以上の倒産は20件と低水準が続いた
- ■地域別に見ると、四国(7件、前年同月比58.8%減)、近畿(151件、同23.7%減)など9地域中6地域で前年同月を下回り、うち5地域は前年同月比2ケタの大幅減少となった。一方、北海道、東北、九州の3地域は前年同月を上回った
- ■負債トップは、(株)笠屋町不動産(大阪府、特別清算)の200億円。(株)大鳥(茨城県、民事再生法)の67億3600万円、(医)緑生会(千葉県、民事再生法)の66億5900万円が続く
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は7年11ヵ月ぶりの700件割れ、負債総額は3ヵ月連続の前年同月比減少
倒産件数は683件で、前年同月比13.4%の大幅減少を記録。13ヵ月連続で前年同月を下回り、2006年9月(667件)以来7年11ヵ月ぶりに700件を割り込んだ。負債総額は1376億7400万円となり前月比では19.5%の増加となったものの、前年同月からは15.8%の減少。3ヵ月連続で前年同月を下回った。
要因・背景
消費税率引き上げ前の駆け込み需要により、年度末にかけて小売業を中心に売り上げが増加、企業の資金繰りが大きく改善された。そのため、足元では景気の遅行指標である倒産件数が大幅に減少している。
■業種別
ポイント7業種中6業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を下回り、なかでも建設業(138件、前年同月比16.4%減)は23ヵ月連続の前年同月比減少となった。また、製造業(75件、同21.9%減)と小売業(124件、同20.5%減)で前年同月比20%以上の大幅な減少を記録。一方、運輸・通信業(36件、同5.9%増)は唯一前年同月を上回った。
要因・背景
- 1.小売業…駆け込み需要による資金繰り改善が持続し、4ヵ月連続の前年同月比減少。全体の減少幅への寄与率(30.2%)は全業種中最大となった
- 2.建設業…引き続き好調な公共工事に支えられ、土木工事などで減少が続く
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比81.6%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は557件(前年同月比14.3%減)となった。一方、構成比は81.6%(前月83.3%、前年同月82.4%)で、前月を1.7ポイント、前年同月を0.8ポイントそれぞれ下回った。
要因・背景
- 1.「返済猶予後倒産」は33件(前年同月比6.5%増)判明
- 2.「不況型倒産」の件数、製造業(63件、前年同月比26.7%減)などで大幅に減少
■倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比53.7%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は367件で、前年同月を20.0%下回ったものの、構成比は53.7%と、22ヵ月連続で過半数を占めた。一方、負債10億円以上の倒産は20件と低水準が続いた。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が399件、構成比は58.4%を占めた。
要因・背景
- 1.負債5000万円未満の倒産、業種別では製造業(25件、前年同月比51.9%減)で大幅減
- 2.大型倒産は金融機関による支援効果などにより抑制状態が続く
■地域別
ポイント9地域中6地域で前年同月比減少
地域別に見ると、四国(7件、前年同月比58.8%減)、近畿(151件、同23.7%減)など9地域中6地域で前年同月を下回り、うち5地域は前年同月比2ケタの大幅減少となった。一方、東北(29件、同93.3%増)、九州(62件、同24.0%増)、北海道(26件、同23.8%増)の3地域は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1.近畿は、製造業(11件、前年同月比54.2%減)を中心に7業種中6業種で減少
- 2.東北は、2000年以降で最少だった前年同月(15件)の反動を受け、大幅に増加
■上場企業倒産
12ヵ月連続で、上場企業の倒産は発生しなかった。上場企業倒産の未発生期間が12ヵ月連続となったのは1991年7月以来、23年1ヵ月ぶり。
2014年は上場企業の倒産が発生しておらず、2013年に引き続いて沈静化の傾向が顕著となっている。
■大型倒産
負債トップは、(株)笠屋町不動産(大阪府、特別清算)の200億円。(株)大鳥(茨城県、民事再生法)の67億3600万円、(医)緑生会(千葉県、民事再生法)の66億5900万円が続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは46.2、国内景気は足踏み状態
2014年8月の景気DIは前月比0.7ポイント減の46.2となり、3ヵ月ぶりに悪化した。けん引役として期待された輸出が、中国や、ウクライナ情勢の影響を受けた欧州などの景気停滞もあり再び減少に転じた。生産・出荷が伸び悩む一方で在庫が積み上がるなど、広範囲の業種で回復が遅れている。さらに、西日本に人的・物的被害をもたらした台風や豪雨などの天候不順も、農・林・水産やサービス関連などに悪影響を及ぼした。『農・林・水産』では、燃油や飼料価格高騰によるコスト高に加えて、生産者米価の下落なども響いた。他方、『小売』は自動車や家具などの高額品のほか、雑貨や菓子などの少額嗜好品関連も堅調に推移するなど、2ヵ月ぶりに改善した。
全地域が悪化、先行きに慎重な見方も出始める
地域別では全10地域が悪化した。とりわけ台風が直撃した『四国』『近畿』が低水準となっており、地域間格差が4ヵ月連続で拡大した。規模別にみると、3ヵ月ぶりに全規模が悪化した。特に「中小企業」は小売や運輸関連が改善したものの、住宅着工戸数が増えず建設や製造が大きく悪化した。総じて、輸出減少と生産コスト高が景気押し下げ要因となるなか、天候不順も加わり、国内景気は足踏み状態となっている。また、景気の下押しリスクが顕在化しつつあるなど、先行きに慎重な見方も一部で出始めている。景気見通しはピークの2014年3月以降、伸びが鈍化傾向にあり、景気上昇の勢いは弱まるものとみられる。
今後の見通し
■地域経済活性化支援機構の支援で、間接的に多くの中小企業が破綻を回避か
千葉県で「印西総合病院」を経営する(医)緑生会は、年商を上回る借入や重い人件費負担により資金繰りがひっ迫し、8月に民事再生法の適用を申請した。地域住民の高齢化に伴い、今後、需要が確実に高まっていくとみられるなかでも、設備投資負担から過剰債務に悩む医療機関は多い。こうしたなか、地域経済活性化支援機構は、支援を必要とする医療機関等に対しリスクマネーの供給や経営人材の投入を行うため「地域ヘルスケア産業支援ファンド」を設立した。ヘルスケア関連事業者を、地域一体となって成長させることで地域経済の活性化を目指す。
もちろん、地域経済活性化支援機構の支援対象先は医療機関だけではない。破綻した場合に、地域経済・流通や地域住民の生活・雇用に大きな影響を与えると想定される企業を中心として、幅広い業種で支援を行っている。8月には、依存度の高い下請企業約30社を抱えていた(株)建材社(北海道、建材卸)など5社の再生支援決定を公表。同機構の積極的な支援は、経営不振企業に法的整理以外の選択肢を与えるばかりではなく、地域の中核企業の破綻回避によって周辺取引業者の連鎖破綻も防いでおり、結果として企業倒産件数の抑制に繋がっていると言えよう。
■消費税率再引き上げ判断後が転換期とみられる
企業倒産件数は、8月も前年同月を下回り(13.4%減)、1年以上前年同月割れの状態が続いている。その背景には、中小企業金融円滑化法、および同法期限到来後の資金繰り支援の継続、“アベノミクス”の高揚感や株価上昇、公共工事増加、消費税率引き上げ前の駆け込み需要などがあった。加えて、2012年4月の「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」により大幅に機能を強化された中小企業再生支援協議会(以下、協議会)の存在がある。協議会は、2003年2月の発足以降、年間300~400件程度再生計画の策定支援を完了してきたが、同パッケージを受けて、専門人員の増強と支援スキームの簡素化を図り、2012年度には年間3000件程度の再生計画成立を目指すとした。実際は、2012年度で1511社と目標に遠く及ばなかったものの、2013年度は2537社と、その支援完了数を大幅に伸ばしている。また、2011年度(合計255社)では年売上高5億円以下の支援完了企業は、98社(構成比38.4%)しかなかったが、2013年度は1795社(同70.8%)にまで増加。協議会が中小零細企業支援に力を入れていたことがわかる。「年間3000件の精神は生きている」(協議会関係者)と言うように、2014年度も中小零細企業支援に注力する方針だ。企業倒産件数(減少)と支援完了件数(増加)の推移からすると、これまでは確かに効果があったとみられ、今後の支援にも期待が高まっている。
しかし、件数が増加するにつれて、本格的な再生計画を作成する準備段階とした「3年程度の暫定計画+3年間のリスケ」(暫定リスケ)の策定支援を着地点とする案件が増えてきていることには注意が必要だ。暫定リスケを終えた後、抜本的経営再建計画が策定できなければ、“倒産の先延ばし支援”と同義になってしまう。また、ここにきて、一部金融機関からは「協議会で再生できそうな案件は既に持ち込んだ」との声も聞かれる。つまり、今後の案件は抜本的に解決することが難しいもの(債権の大幅カット、複数金融機関間の調整などを含む案件)が多くなると想定され、これまでのような倒産抑制効果が出るかは不透明であるとみるべきであろう。
経営課題解決の先送りによる倒産件数減少は、長続きしない。資材価格・労務費高騰、消費税率引き上げに伴う消費マインドの低下、価格競争などの倒産増加要因がいまだ存在するからだ。しかし、一方で、“ローカル・アベノミクス”の浸透、円安政策による輸出企業の業績回復、ロボット・バイオ・ヘルスケア分野などにおけるイノベーションの実現による構造変化など、本格的に経営環境を好転させ得る要因もある。企業倒産件数の減少傾向が続くなか、これら上振れ要因と下振れ要因を睨みつつ、消費税率再引き上げの判断後に転換期を迎えるか注目したい。

