倒産件数は858件、4ヵ月連続の前年同月比減少
負債総額は1662億5000万円、3ヵ月連続の前年同月比減少
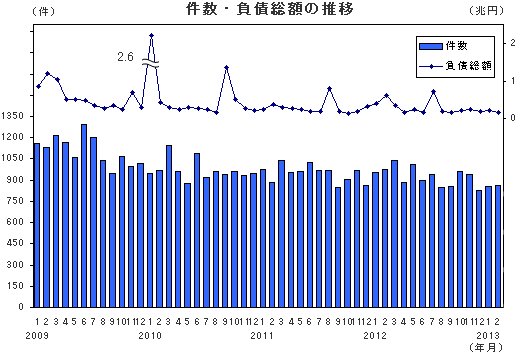
倒産件数 | 858件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲12.1% |
前年同月 | 976件 |
前月比 | +0.5% |
前月 | 854件 |
負債総額 | 1662億5000万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲73.6% |
前年同月 | 6289億8000万円 |
前月比 | ▲27.6% |
前月 | 2294億7600万円 |
調査結果
■件数
ポイント4カ月連続の前年同月比減少
倒産件数は858件(前月854件、前年同月976件)で、前月比は0.5%の増加となったものの、前年同月比は12.1%の減少となり、4ヵ月連続で前年同月を下回った。2007年2月(818件)以来、6年ぶりに3ヵ月連続の900件割れとなった。
要因・背景
- 復興需要や設備投資の増加などを背景に、建設業が5ヵ月連続の前年同月比減少
- 9地域中5地域で前年同月を下回り、うち4地域で20%を超える大幅減少
■負債総額
ポイント3カ月連続の前年同月比減少、2000年1月以降で2番目の低水準
負債総額は1662億5000万円(前月2294億7600万円、前年同月6289億8000万円)で、前月比は27.6%、前年同月比も73.6%の大幅減少となり、3カ月連続で前年同月を下回った。2000年1月以降では、2011年10月の1329億1700万円に次いで2番目の低水準。
要因・背景
- 負債トップは、農林振興事業の社団法人愛知県農林公社(愛知県)で227億円
- 前年同月に発生したエルピーダメモリ(株)などの大型倒産の反動により大幅減少
■業種別
ポイント7業種中5業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を下回った。なかでも、運輸・通信業(28件、前年同月比31.7%減)、小売業(160件、同21.6%減)、サービス業(183件、同14.1%減)の3業種は2ケタの大幅減少となった。一方、製造業(109件、同2.8%増)、不動産業(23件、同27.8%増)の2業種は前年同月を上回った。
要因・背景
- 建設業…労務費の高騰などもあり土木工事が増加となった一方、住宅着工戸数の増加を受けて木造建築工事(14件、前年同月比50.0%減)などが減少
- 小売業…飲食料品小売(22件、前年同月比26.7%減)などで減少が目立つ
■主因別
ポイント 「不況型倒産」の構成比83.9%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は720件(前月686件、前年同月809件)となった。構成比は83.9%(前月80.3%、前年同月82.9%)で、前月を3.6ポイント、前年同月も1.0ポイント上回った。
要因・背景
- 返済猶予後も業績低迷に歯止めがかからず、「金融円滑化法利用後倒産」は33件判明
- 「円高関連倒産」は7件判明、うち為替デリバティブ損失によるものは2件
倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比55.1%、4カ月連続で過半数を占める
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は473件で、前年同月比15.1%の減少となったものの、構成比は55.1%と4ヵ月連続で過半数を占めた。一方、負債100億円以上の倒産は1件にとどまった。資本金別に見ると、個人経営と資本金1000万円未満の合計は488件、構成比は56.9%を占めた。
要因・背景
- 負債5000万円未満の業種別では、建設業(115件)が24.3%を占め全業種中トップ
- 負債10億円以上の倒産は26件、2011年10月、2012年7月と並び過去10年で最少
■地域別
ポイント9地域中5地域で前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中5地域で前年同月を下回った。なかでも、北海道(33件、前年同月比35.3%減)、北陸(19件、同40.6%減)、近畿(210件、同28.3%減)、四国(15件、同37.5%減)の4地域は2ケタの大幅減少となった。一方、東北(34件、同47.8%増)や中国(41件、同32.3%増)など4地域は前年同月を上回った。
要因・背景
- 東北は、職人や資材の不足なども影響し建設業(11件、前年同月比57.1%増)が増加
- 近畿は、大阪府(105件、前年同月比43.5%減)が小売業を中心に大幅減少
■上場企業倒産
上場企業の倒産は3ヵ月連続で発生しなかった。2012年度の累計は5件とすでに前年度の4件を上回っているものの、上場企業の倒産は沈静化が続いている。
■大型倒産
2月の負債額トップは、愛知県が出資する社団法人愛知県農林公社(愛知県、民事再生法)の227億円。以下、西方企画開発(株)(群馬県、特別清算)の92億5000万円、(株)KHコーポレーション(旧:(株)萬世閣、北海道、特別清算)の75億円と続く。 大型倒産は、返済猶予や再生支援機関の支援効果などを受け低水準が続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは39.8、前月比1.8ポイント増と3ヵ月連続で改善
2013年2月の景気動向指数(景気DI:0~100、50が判断の分かれ目)は、前月比1.8ポイント増の39.8となり、3ヵ月連続で改善した。
安倍政権発足以降、円安・株高傾向のなかで、大型補正予算の成立や金融緩和政策の継続が決定されるとともに、設備投資など実需も一部で現れはじめている。また、中国における大気汚染の広がりは国内外で日本の環境関連技術に対する需要を押し上げる期待も高まった。こうした外部要因を背景に『建設』や『不動産』『製造』『小売』など10業界中9業界、51業種中40業種が改善した。
幅広い業種で改善しており、回復に向けて進んでいる
消費税増税前の駆け込みやオフィス市場での空室率の低下、復興需要による被災地域での賃貸物件需要など『不動産』は前月比4.8ポイントの増加となり、2002年5月の調査開始以降で最大の改善幅となった。特に『東北』『北関東』『南関東』など東日本での改善が目立った。さらに、震災復興やインフラ投資機運の高まりで「鉄鋼・非鉄・鉱業」のほか、円安持続で輸出が回復基調となっている「機械製造」や「輸送用機械・器具製造」も改善するなど、『製造』は12業種中11業種で改善した。また、旧正月(春節)需要や大気汚染関連特需があった「中国進出」企業の景況感(39.2、前月比1.7ポイント増)も3ヵ月連続で改善した。
総じて、幅広い業種で改善傾向となっており、国内景気は回復に向けて進んでいる。
今後の見通し
■件数は4カ月連続、負債総額は3ヵ月連続の前年同月比減少
2013年2月の企業倒産は858件で、前月(854件)を0.5%上回ったものの、前年同月(976件)を12.1%下回り、4ヵ月連続で前年同月比減少となった。負債総額は1662億5000万円となり、2000年以降では2011年10月の1329億1700万円に次いで2番目に小さい。負債10億円以上の大型倒産が26件で、7月と並び2012年度最少であったことで負債総額が抑えられた。
■電気料金のほか生活に身近な商品の値上げが相次ぐ
2月14日、東北電力は経済産業大臣に対して電気料金値上げの申請を行った。規制部門で平均11.41%、自由化部門で平均17.74%の値上げを実施したい考えだ。「復興の妨げになる」と不安の声も聞かれるなか、膨れあがるコスト負担を現状の料金水準では吸収しきれないことが背景にある。電気の大口需要家である製造業をみると、2月の倒産は前月比、前年同月比ともに増加している。電力料金値上げとなれば、今後さらに厳しい状況となることが想定される。
値上げは、電気料金だけではない。トラックの燃料である軽油の小売価格は、13週間連続で上昇している(3月4日時点、資源エネルギー庁)。また、カタログやチラシのほか出版物に使用される印刷用紙の値上げの影響は、広告業界から出版業界までに及ぶであろう。2012年に685件もの倒産が発生した飲食業界周辺では、小麦や食用油の値上げが行われる見通しだ。一つ一つの値上げは、微々たるものと言えるであろうが、合算すれば業績に影響を与える程のインパクトがあり、最終的にはエンドユーザーに価格転嫁ができるか否かの問題となる。
■民法改正で企業が融資を受ける際の個人保証の是非が焦点に
法制審議会民法(債権関係)部会は、「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」を2月末に公表した。この中で、企業が金融機関等から融資を受ける際の個人保証のあり方が焦点となっている。現状、中小零細企業においては融資を受ける際に経営者本人のほか、親族や知人が保証人となるケースがある。企業の破綻が生活の破綻に直結する可能性があるという論点から、個人保証の禁止が議論されているが、個人保証がなければ融資を受けることができないという中小零細企業が多く存在するのも事実。2月の負債5000万円未満の倒産は構成比55.1%となり4ヵ月連続で過半数を占めるなど、倒産する多くの企業は中小零細企業だ。現在、「経営者保証」は例外として認める方向で検討が進められているが、今後の展開によっては、金融機関による貸出先選別にも繋がりかねない改正であり、動向に注目する必要がある。
■「金融円滑化法利用後倒産」は、前年同月比32.0%増
2月の「金融円滑化法利用後倒産」は33件判明し、前月を10.8%下回ったものの、前年同月比では32.0%大幅に増加した。集計開始以降、すべての月で前年同月を上回り、累計で686件となった。企業倒産全体は横ばいで推移している一方で、「金融円滑化法利用後倒産」は、前年同月比増加を続けている状況に変わりない。こうしたなか、同法の適用期限である3月末をむかえる。金融庁は、金融機関の方針転換を回避すべく、金融検査マニュアル・監督方針に「貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めること」を明記。それに加え、条件変更実施状況の自主的な開示を求めることで、資金繰りが厳しい中小企業が引き続き金融支援を受けられるように配慮している。しかし、金融円滑化法に基づく返済条件変更等を受けている企業は推定40万社存在し、そのうち少なくとも10万社が債務者区分「要管理先」以下とみられる。金融円滑化法を実質的に延長させることと、資金繰り支援から事業再生支援にシフトすることは同義ではない。同法施行前と現在において、中小企業の財務内容が悪化していることを踏まえると、資金繰り支援を続けるだけでは潜在的な倒産リスクが膨らむ一方だ。2月の倒産は858件と4ヵ月連続で前年同月比減少となっているが、楽観視できる状況でないことは明らかである。

