倒産件数は651件、2カ月ぶりの前年同月比増加
負債総額は1046億6400万円、2カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数 | 651件 |
|---|---|
前年同月比 | +5.3% |
前年同月 | 618件 |
負債総額 | 1046億6400万円 |
|---|---|
前年同月比 | +26.5% |
前年同月 | 827億7000万円 |
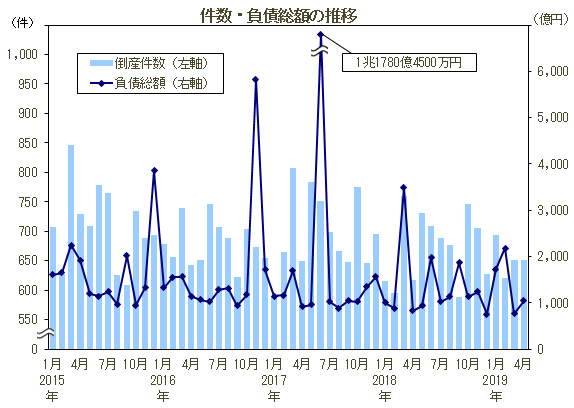
主要ポイント
- ■倒産件数は651件(前年同月比5.3%増)と、負債1億円以上の中規模クラスの倒産(178件、前年同月比11.3%増)が増えたことなどから、2カ月ぶりの前年同月比増加
- ■負債総額は、前年同月比26.5%増の1046億6400万円
- ■業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を上回った。建設業(112件、前年同月比9.8%増)は、職別工事、設備工事は減少も、総合工事(50件、同56.3%増)が前年同月比2ケタ増。また、サービス業(166件、同16.1%増)は、病院のほか、施術所などの医療業(20件、同33.3%増)で増加が目立つ
- ■主因別に見ると、「不況型倒産」の合計は505件、構成比77.6%を占める
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は382件、構成比58.7%を占める
- ■地域別に見ると、9地域中6地域で前年同月を上回った。北海道(17件、前年同月比21.4%増)は、建設業やサービス業などで前年同月を上回り、4カ月ぶりの増加。九州(46件、同9.5%増)は、復興工事需要の落ち着きなどで建設業の倒産が反動増の傾向で推移していることなどを背景に、4カ月連続の増加
- ■「人手不足倒産」は20件(前年同月比42.9%増)発生。9カ月連続の前年同月比増加
- ■負債トップは、(株)ワイ・ケイ・ジャパン(東京都、民事再生法)の約162億4200万円
調査結果
■件数・負債総額
倒産件数は651件、2カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数は651件(前年同月比5.3%増)と、負債1億円以上の中規模クラスの倒産(178件、前年同月比11.3%増)が増えたことなどから、2カ月ぶりに前年同月を上回った。
負債総額は、前年同月比26.5%増の1046億6400万円となった。(株)ワイ・ケイ・ジャパン(負債約162億4200万円、東京都、民事再生法)、土高興業(株)(同110億円、高知県、特別清算)の大型倒産が発生したことなどが影響した。
■業種別
建設、サービスなど4業種で前年同月比増加
業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を上回った。
建設業(112件、前年同月比9.8%増)は、職別工事、設備工事は減少も、総合工事(50件、同56.3%増)が前年同月比2ケタ増。また、サービス業(166件、同16.1%増)は、病院のほか、施術所などの医療業(20件、同33.3%増)で増加が目立った。
一方、卸売業(86件、同16.5%減)など3業種は前年同月を下回った。
■主因別
「不況型倒産」は505件、構成比は77.6%
主因別に見ると、「不況型倒産」の合計は505件(前年同月比1.6%増)となり、2カ月ぶりに前年同月を上回った。構成比は77.6%(同2.8ポイント減)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
負債5000万円未満の構成比58.7%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は382件(前年同月比0.3%増)、構成比は58.7%を占めた。負債5000万円未満の倒産では、小売業(115件)が構成比30.1%(同1.2ポイント増)を占め最多、サービス業(114件)が同29.8%(同4.1ポイント増)で続く。
資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人事業主含む)の倒産が431件(同6.9%増)、構成比は66.2%を占めた。
■地域別
北海道、九州など6地域で前年同月比増加
地域別に見ると、9地域中6地域で前年同月を上回った。
北海道(17件、前年同月比21.4%増)は、建設業やサービス業などで前年同月を上回り、4カ月ぶりの増加。また、北陸(20件)は小売業とサービス業で増加が目立ち、前年同月比81.8%の増加となった。九州(46件、同9.5%増)は、復興工事需要の落ち着きなどで建設業の倒産が反動増の傾向で推移していることなどを背景に、4カ月連続で前年同月を上回った。
一方、中部(90件、同6.3%減)は5カ月連続で前年同月を下回った。
■態様別
「民事再生法」は35件、前年同月の2.2倍増
態様別に見ると、破産は591件(構成比90.8%)、特別清算は25件(同3.8%)となった。民事再生法(35件)は、個人事業主を中心に増加し、前年同月の2.2倍となった。
■特殊要因倒産
人手不足倒産
20件(前年同月比42.9%増)発生。9カ月連続の前年同月比増加
後継者難倒産
34件(前年同月比3.0%増)発生。6カ月連続の前年同月比増加
返済猶予後倒産
37件(前年同月比48.0%増)発生。5カ月連続の前年同月比増加
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは46.8、5カ月連続で悪化
4月の国内景気は、最大10日となる大型連休中の人手確保にともなう人件費および物流費の増加が下押し要因となった。加えて、新年度を迎え工事の発注件数が減少するなか、大型連休や統一地方選挙などが悪材料となり、工事関連が停滞。原油高を背景とした燃料価格の上昇もコスト負担増につながった。他方、連休を控えた前倒し発注による出荷増や、旅行および外食など個人消費を中心とした需要拡大がプラスに働いた。新元号の発表を受けて一部の業種で特需が発生した。
国内景気は、大型連休などを背景としたコスト増や工事関連の停滞が響き、後退局面入りの兆しが引き続きみられる。
設備投資や輸出の鈍化、消費税率引き上げ後の消費の落ち込みを懸念
今後、設備投資は省力化や更新需要で底堅く推移するも、先行きに不透明感が増すなかで、輸出とともに鈍化が懸念される。個人消費は緩やかな回復が続くが、消費税率引き上げにより一時的に大きく落ち込むと予想される。東京五輪などの大型イベントがプラス材料となる一方、人件費などのコスト増は景気の下押し要因となろう。海外は、中国で経済対策による効果が注目されるも、好調な米国では減税効果の剥落による景気減速が危惧される。また、日米通商交渉や米中貿易摩擦の動向なども引き続き注視していく必要がある。
今後の国内景気は、設備投資や輸出の鈍化、消費税率引き上げによる消費の落ち込みが見込まれ、不透明感が一層強まっている。
今後の見通し
■中規模クラスの倒産が目立つ
2019年4月の倒産件数(651件、前年同月比5.3%増)は、3カ月ぶりのマイナスとなった前月から一転し、2カ月ぶりの前年同月比増加となった。小規模倒産が過半を占める傾向に変化はなかったものの、負債1億円以上(178件)では前年同月を11.3%上回り、中規模クラスの倒産が2ケタ増となった。負債額上位では、「さいたま記念病院」を運営していた一成会(民事再生、埼玉県、負債約17億2400万円)や、脳神経外科で有名な「旗の台病院」を運営していたおきの会(民事再生、東京都、負債約16億5800万円)など医療法人の倒産が目立った。病院施設の建設や医療機器導入にともなう借入金負担のほか、人件費の高騰や患者数の減少などから厳しい経営環境にある医療法人は多く、今後さらなる倒産増加も懸念される。
■需要拡大基調も、運送業の倒産が増加
道路貨物運送業の倒産件数は2019年1~4月累計で68件と、前年同期(58件)を17.2%上回る。小規模企業を中心に、車両への設備投資負担やドライバーの退職者増加などがネックとなり、倒産が増加基調で推移している。
配送需要が拡大基調のなか、大手を中心に運賃値上げの動きが進んでいるほか、2018年12月には、運送業者への荷主の配慮義務や国土交通省による標準的運賃の告知制度などを新たに盛り込んだ改正貨物事業者運送事業法が成立するなど、業界を取り巻く環境は大きく変わりつつある。すでに多くの小規模企業では、高値圏で推移する燃料費や、傭車費、人件費など、複数のコストアップ要因で収益が圧迫される状況が続いており、抜本的な収益改善が急がれる。
■円滑な事業承継が喫緊の課題
中小企業庁は4月26日、2019年版の中小企業白書と小規模企業白書をまとめた。小規模企業を中心に企業数が減少傾向にある現状を踏まえ、人口減少と少子高齢化を最大の課題に挙げ、令和時代に求められる経営者の円滑な世代交代の重要性について指摘している。
こうしたなか、後継者不在により事業継続の見通しが立たなくなったなどの「後継者難倒産」は2019年1~4月累計で132件発生し、前年同期(112件)を17.9%上回る。また、倒産や廃業による得意先の減少から、営業基盤が縮小し倒産に至るケースも散発している。今後も企業数が減少基調で推移するとすれば、販路開拓が難しい企業などによる倒産が増加する可能性も。
■地域金融機関の収益性重視への方針転換で、リスケ企業に影響も
金融庁は4月3日、早期警戒制度の見直しを中心とする中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の改正案を公表した。従来の不良債権問題を念頭にした自己資本比率による健全性重視の方針から、将来の収益性を重視する方針へと転換し、地域金融機関への監視を強化するほか、業務改善命令も活用し、厳しく改善を求めていく。今後は、返済条件の変更等(リスケジュール)を続けながらも、抜本的再建策が見出せていない融資先などへの対応が注目される。
現時点では倒産件数全体が急増するような状況にないものの、一部の業種や地域では倒産の増加傾向が見られている。また、日本との関係性が強い米中両国間による貿易摩擦を背景に、国内企業では業績や設備投資が下押しされる懸念も高まっており、当面は楽観視できない状況が続くと想定される。

