倒産件数は747件、2カ月連続の前年同月比減少
負債総額は1128億5600万円、3カ月連続の前年同月比増加
倒産件数 | 747件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲3.6% |
前年同月 | 775件 |
前月比 | +27.0% |
前月 | 588件 |
負債総額 | 1128億5600万円 |
|---|---|
前年同月比 | +10.7% |
前年同月 | 1019億2000万円 |
前月比 | ▲39.6% |
前月 | 1867億6200万円 |
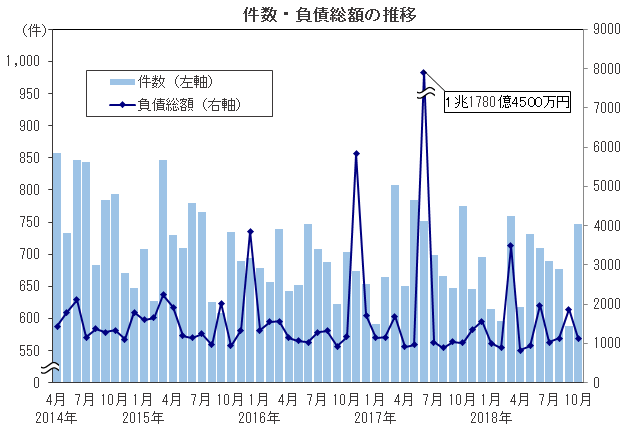
主要ポイント
- ■倒産件数は747件(前年同月比3.6%減)と、2カ月連続で前年同月を下回った。負債総額は1128億5600万円(同10.7%増)と、3カ月連続で前年同月を上回った
- ■業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を下回った。なかでも、建設業(125件、前年同月比16.1%減)、不動産業(16件、同51.5%減)の2業種は前年同月比2ケタ減となった。一方、運輸・通信業(28件、同47.4%増)など3業種は前年同月を上回った
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は603件(前年同月比4.7%減)となり、9カ月連続で前年同月を下回った。構成比は80.7%(同1.0ポイント減)を占めた
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は452件(前年同月比5.2%減)となった。構成比は60.5%を占め、小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が489件で構成比65.5%を占めた
- ■地域別に見ると、9地域中3地域で前年同月を下回った。なかでも、北海道(12件、前年同月比40.0%減)、関東(256件、同10.5%減)の2地域は前年同月比2ケタ減。また、近畿(197件、同2.0%減)は6カ月連続の減少となった。一方、九州(61件、同5.2%増)など5地域は前年同月を上回り、中部(109件)は前年同月と同数だった
- ■負債トップは、(株)エム・テック(東京都、民事再生法→廃止)の253億4933万円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント倒産件数は747件、2カ月連続の前年同月比減少
倒産件数は747件(前年同月比3.6%減)と、2カ月連続で前年同月を下回った。負債総額は1128億5600万円(同10.7%増)と、3カ月連続で前年同月を上回った。
要因・背景
件数…業種別では建設業など4業種で、地域別では関東など3地域で前年同月比減少
負債総額…負債100億円以上の倒産(1件)が3カ月連続で発生
■業種別
ポイント建設、不動産など4業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を下回った。なかでも、建設業(125件、前年同月比16.1%減)、不動産業(16件、同51.5%減)の2業種は前年同月比2ケタ減となった。一方、運輸・通信業(28件、同47.4%増)など3業種は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 建設業は、総合工事(55件、前年同月比7.8%増)は7カ月ぶりに増加も、職別工事(43件、同28.3%減)、設備工事(27件、同28.9%減)が前年同月比2ケタ減
- 2. 運輸・通信業は、ドライバー不足や燃料費の高騰などを受け、道路貨物運送(15件)が前年同月比50.0%の大幅増
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比80.7%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は603件(前年同月比4.7%減)となり、9カ月連続で前年同月を下回った。構成比は80.7%(同1.0ポイント減)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1. 不況型倒産を業種別に見ると、小売業(155件)が構成比25.7%を占め最多
- 2.「人手不足倒産」は18件(前年同月比200.0%増)、3カ月連続の前年同月比増加
- 3.「後継者難倒産」は28件(前年同月比33.3%減)、6カ月ぶりの前年同月比減少
- 4.「返済猶予後倒産」は42件(前年同月比2.4%増)、2カ月ぶりの前年同月比増加
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比60.5%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は452件(前年同月比5.2%減)となった。構成比は60.5%を占め、小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が489件で構成比65.5%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産では、サービス業(131件)が構成比29.0%(前年同月比1.1ポイント増)を占め最多。小売業(120件)が同26.5%(同2.4ポイント増)で続く
- 2. 負債100億円以上の倒産(1件)が3カ月連続で発生
■地域別
ポイント関東、近畿など3地域で前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中3地域で前年同月を下回った。なかでも、北海道(12件、前年同月比40.0%減)、関東(256件、同10.5%減)の2地域は前年同月比2ケタ減。また、近畿(197件、同2.0%減)は6カ月連続の減少となった。一方、九州(61件、同5.2%増)など5地域は前年同月を上回り、中部(109件)は前年同月と同数だった。
要因・背景
- 1. 関東は、五輪関連をはじめとする再開発工事などを背景に、東京都の建設業(8件、前年同月比55.6%減)が2016年6月、2018年3月と並び、2000年以降で最少
- 2. 近畿は、大阪府の建設業(20件)、製造業(7件)などの減少が全体を押し下げた
■上場企業倒産
上場企業の倒産は発生しなかった。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは49.0、2カ月連続で悪化
2018年10月の景気DIは前月比0.4ポイント減の49.0となり、2カ月連続で悪化した。
10月の国内景気は、原油高を受けてレギュラーガソリン価格が8週連続で上昇し約4年ぶりの高値を付けたほか、軽油価格や冬の需要期を迎えた灯油も高騰したことが、悪影響を及ぼした。雇用過不足DI(正社員)が60.2と過去最高を更新し人手不足が深刻化するなか、最低賃金の改定もあり人件費負担が増加したうえ、野菜など食品価格や電気料金も上昇。また中国向け機械輸出に減速感が出てきたほか、日経平均株価が10月に入り3週間余りで3,000円を超えて下落したこともマイナスに響いた。国内景気は、原油高による燃料価格上昇や人手不足の深刻化などがさらなるコスト負担の増加を招き、弱含んだ。
原油高や人手不足、米中貿易摩擦の激化で不透明感が強まる
今後は、好調な企業収益を背景とした省力化投資の活発化や災害からの復興、訪日外国人および五輪需要の拡大を追い風に、設備投資は総じて堅調さが続くであろう。輸出は、世界経済の回復が続くなかで底堅く推移すると見込まれる。個人消費は、エネルギーや生鮮食品価格の上昇が下押し要因となるものの、雇用者所得の増加が寄与し緩やかに回復すると予想される。また、消費税率引き上げに向けた住宅などの駆け込み需要と反動減に加え、原油高や人手不足が及ぼす悪影響を注視する必要がある。海外は、米中貿易摩擦の激化や中国および新興国の景気減速、英EU離脱問題の行方などがリスク要因となろう。
今後は、設備投資の堅調な推移や消費税率引き上げの駆け込み需要が期待される一方、原油高や海外リスクが景気を下押しする可能性が懸念され、不透明感が強まっている。
今後の見通し
■CtoCビジネスの拡大を受け、中古品販売業の倒産増加を懸念
2018年10月の倒産件数(747件)は、建設業が前年同月比2ケタ減と件数全体を押し下げたことから2カ月連続で前年同月を下回ったものの、2018年としては3月(760件)に次ぐ2番目の多さだった。業種別では7業種中3業種が、地域別では9地域5地域が前年同月を上回るなど、「まだら模様」な状態が確認された。小売業では、子供服のリサイクルショップを全国展開していたAKIRA(東京都、負債約13億1300万円)など、中古品販売業の倒産が6件発生。2018年1~10月累計の中古品販売業の倒産は計30件と、年間合計で最多だった2017年(30件)の件数にすでに並んだ。フリマアプリを中心にCtoCビジネスが拡大するなか、リアル店舗の展開を主力とする企業を中心にさらなる倒産増加も懸念される。
■投資用不動産の販売動向に注目
金融庁は10月26日、消費者庁、国土交通省との連携でサブリース契約に関する注意喚起を公表。今年3月にも消費者庁と国土交通省は同様の注意喚起文を公表しており、今回はさらに内容を拡充した。金融庁は2018事務年度(2018年7月~2019年6月)の金融行政方針においても、投資用不動産向け融資の審査や管理態勢に関するモニタリング強化を掲げている。
こうしたなか、事業環境の急速な悪化により、10月は投資用ワンルームマンション販売を手掛ける台東不動産(東京都、負債約1億3400万円)の破産が発生したほか、不動産投資コンサルティング会社による事業停止事例も確認された。帝国データバンクが金融機関の融資姿勢を企業に調査した融資姿勢DIでは、不動産業は直近ピークの2017年2月以降、悪化傾向で推移している。今後は各金融機関で個人投資家向けアパートローンなどの融資審査の厳格化が進むとみられ、その影響が注目される。
■一段のコスト負担増で小規模企業を中心に悪影響も
2018年に入って電気・ガス料金が上昇しているうえ、10月はレギュラーガソリンの店頭価格(全国平均)が約4年ぶりの高水準となった。原油価格の高騰により、とくに燃料を多く使用する道路貨物運送業や漁業などの収益を圧迫している。また、10月からは最低賃金(時給)が全国平均で26円引き上げられるなか、企業のコスト負担は幅広い業種で増している。小規模企業を中心にコスト増を転嫁できない企業は多く、収益のさらなるマイナス要因になると見込まれる。
■2018年の年間倒産件数は、前年比マイナスの公算
2018年度第1次補正予算では、相次いだ自然災害からの復旧・復興に向けた対策に計7275億円が計上された。今後は被災地域を中心に、セーフティネット保証4号などの資金繰り支援や復興需要により、倒産件数の減少が見込まれる。また、来年10月より消費税率が10%へ引き上げられる予定のなか、前回2014年4月に8%へ引き上げられた際と同様、駆け込み需要で大工工事や内装工事などの職別工事業のほか、衣料品小売や自動車小売などで倒産減少も想定される。
金融機関における貸付条件変更等の取り組み姿勢に大きな変化はなく、倒産件数は2018年1~10月累計で6730件(前年同期7034件)と、前年同期を4.3%下回っており、2018年の年間合計は2017年の前年比2.6%増から一転、2年ぶりの減少となる可能性が高い。

