倒産件数は642件、2カ月連続の前年同月比減少
負債総額は1143億6800万円、4カ月連続の前年同月比減少
倒産件数 | 642件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲12.1% |
前年同月 | 730件 |
前月比 | ▲13.1% |
前月 | 739件 |
負債総額 | 1143億6800万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲40.4% |
前年同月 | 1918億9100万円 |
前月比 | ▲27.1% |
前月 | 1567億9300万円 |
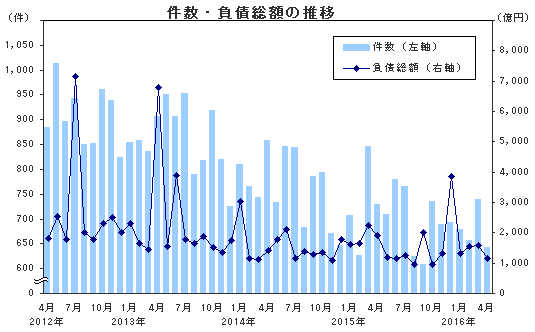
主要ポイント
- ■倒産件数は642件で、前年同月比では12.1%の減少となり、2カ月連続で前年同月を下回った。4月としては2000年以降3番目の低水準にとどまっている。負債総額は1143億6800万円となり、前年同月比では40.4%の大幅減少、4カ月連続で前年同月を下回った
- ■業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を下回り、なかでも製造業(81件、前年同月比26.4%減)と卸売業(94件、同21.7%減)は前年同月比で20%以上の大幅減少。一方、サービス業(153件、同3.4%増)、不動産業(29件、同3.6%増)の2業種は前年同月比増
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は531件(前年同月比13.9%減)となった
- ■規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は368件(前年同月比10.0%減)、構成比は57.3%となり、小規模倒産が半数以上を占めた。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の倒産合計が378件で構成比58.9%を占めた
- ■地域別に見ると、9地域中8地域で前年同月を下回り、なかでも中国(13件、前年同月比56.7%減)、北陸(22件、同31.3%減)の2地域は前年同月比30%以上の大幅減少となった。また、中国、四国を除く7地域で、2カ月連続の前年同月比減少となった
- ■上場企業の倒産は発生しなかった
- ■負債トップは、日本ロジテック協同組合(東京都、破産)の162億8200万円で、2016年に入って最大の倒産となった。以下、(株)ケイディ(埼玉県、特別清算)の55億円、(株)エス・エス・エル(兵庫県、特別清算)の34億円と続く
調査結果
■件数・負債総額
ポイント倒産件数は642件、2カ月連続の前年同月比減少
倒産件数は642件で、前月比では13.1%、前年同月比でも12.1%の減少となり、2カ月連続で前年同月を下回った。4月としては2000年以降3番目の低水準にとどまっている。負債総額は1143億6800万円となり、前月比27.1%の減少、前年同月比では40.4%の大幅減少となり、4カ月連続で前年同月比減少となった。
要因・背景
件数…業種別では7業種中5業種で、地域別では四国を除く8地域で前年同月比減少
負債総額…負債5000万円未満の倒産が57.3%と、小規模倒産が多数を占める傾向が続いた
■業種別
ポイント製造業、卸売業など7業種中5業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を下回り、なかでも製造業(81件、前年同月比26.4%減)と卸売業(94件、同21.7%減)は前年同月比で20%以上の大幅減少。一方、サービス業(153件、同3.4%増)、不動産業(29件、同3.6%増)の2業種は前年同月比で増加。
要因・背景
- 1.底堅い食料品需要やインバウンド効果が食品分野に波及し、食料品・飼料・飲料製造業(13件、前年同月25件)や飲食料品小売業(22件、同41件)が前年同月比で減少した
- 2.2015年度第4四半期における公共工事の発注が前年同期を上回ったことや、新設住宅着工戸数の増加などを背景に、建設業は2カ月連続で前年同月比減少
■主因別
ポイント 「不況型倒産」は531件、2カ月連続で前年同月を下回る
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は531件(前年同月比13.9%減)となり、2カ月連続で前年同月を下回った。販売不振(511件、前年同月603件)が前年同月比15.3%の減少となった一方、売掛金回収難(9件、同3件)は大幅増加となった。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、 業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1.「チャイナリスク関連倒産」は6件判明、前年同月と同水準となった
- 2.「円安関連倒産」は12件(前年同月比65.7%減)判明、8カ月連続の前年同月比減少
- 3.「返済猶予後倒産」は33件(前年同月比13.8%増)判明、3カ月連続の前年同月比増加
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比57.3%
規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は368件(前年同月比10.0%減)、構成比は57.3%となり、小規模倒産が半数以上を占めた。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の倒産合計が378件で構成比58.9%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債10億円以上の倒産は17件と、2カ月連続の前年同月比減で、2015年11月(18件)以来5カ月ぶりに20件を下回るなど、大型倒産は低水準が続く
- 2. 負債5000万円未満の倒産では、製造業(41件、前年同月47件)が7カ月連続で減少
■地域別
ポイント8地域で前年同月比減少、7地域では2カ月連続で前年同月を下回る
地域別に見ると、9地域中8地域で前年同月を下回り、なかでも中国(13件、前年同月比56.7%減)、北陸(22件、同31.3%減)の2地域は前年同月比30%以上の大幅減少となった。また、中国、四国を除く7地域で、2カ月連続の前年同月比減少となった。
要因・背景
- 1. 中国は、広島県で造船や自動車など基幹産業の堅調さが地域に波及し、製造業(5件、前年同月6件)や小売業(3件、前年同月7件)などで減少
- 2. 関東は、倒産件数が増加傾向にあった東京都が7カ月ぶりに前年同月比で減少に転じたほか、埼玉県は4カ月連続で前年同月比減少
■上場企業倒産
上場企業の倒産は発生しなかった。
上場企業の倒産は、業績改善や資金調達環境の改善などもあり、2015年9月の第一中央汽船(株)(民事再生法、東証1部)以降7カ月連続で発生していない。
■主な倒産企業
負債トップは、日本ロジテック協同組合(東京都、破産)の162億8200万円で、2016年に入って最大の倒産となった。以下、(株)ケイディ(埼玉県、特別清算)の55億円、(株)エス・エス・エル(兵庫県、特別清算)の34億円と続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは42.4、国内景気は2カ月ぶりに悪化
2016年4月の景気DIは前月比0.4ポイント減の42.4となり2カ月ぶりに悪化した。
4月は、平成28年熊本地震により宿泊予約のキャンセルが相次いだほか、多くの道路が不通となるなど物流機能の低下を余儀なくされた。また、企業の設備投資に慎重姿勢がみられるなか、大手自動車メーカーによる燃費データ不正問題や電子部品の受注減少も加わり、国内景気がもたつく要因となった。さらに、ガソリン価格の7週連続上昇(4月25日時点)や原料高にともなう鋼材価格の値上げ、人手不足による人件費の上昇など、企業のコスト負担はじわじわと高まってきた。他方、公共工事や住宅着工は増加したものの、全体をけん引するまでには至っていない。企業がさまざまなリスクを抱えるなかで、製造や観光関連などを中心に平成28年熊本地震が打撃を加え、国内景気は再び悪化に転じた。
今後の国内景気は景気回復に向けた好材料乏しく、足踏み状態が続く
今後の国内景気は、消費税率10%への引き上げの行方のほか、平成28年熊本地震の早期の復旧・復興に影響されるとみられる。生産停止された自動車や電子部品など工場の本格稼働や、九州全域に対する観光需要の回復がカギを握る。また、家計の収入および支出は伸び悩みが続くなか、長引く個人消費の低迷から脱却するため、消費税率引き上げの再延期を含めた経済対策が望まれる。海外要因では、米国経済や中国経済の成長鈍化とともに、為替相場の動向も注視する必要があろう。他方、訪日旅行客の増加による観光消費の拡大は引き続き好材料である。今後の景気は、回復に向けた好材料が乏しいなか、足踏み状態で推移するとみられる。
今後の見通し
■4月の倒産件数は642件、2カ月連続で前年同月比2ケタの減少
2016年4月の企業倒産件数は642件と、前年同月(730件)を12.1%下回り2カ月連続で2ケタの減少となった。7業種中4業種で同10%以上減少しており、倒産の減少傾向が続いている。特に製造業は同26.4%減少し、全体の倒産件数を押し下げる要因となった。
小売業界では、食料品販売額が増加するなど(「チェーンストア販売統計」日本チェーンストア協会)食料品需要が堅調に推移しているほか、訪日旅行客によるインバウンド消費などもあり、飲食料品小売業は同46.3%減少した。また、こうした川下の好調さを受けて、食料品・飼料・飲料製造業は同48.0%減と5カ月連続で2ケタの大幅減少となった。
■熊本地震からの復旧・復興に向けた環境整備進む
4月14日から発生した平成28年熊本地震は、製造業や観光業などに多大な影響を及ぼすとみられる。九州の自動車生産台数は年間約135万台で、国内の1割超を占めるが、その中核となる部品工場などが被災し、自動車メーカーの生産計画に見直しを迫るものとなっている。さらに、デジタルカメラやスマートフォンの主要部品となる半導体工場のほか、電力制御部品の生産や食品メーカーの生産も一部停止した。2011年の東日本大震災時には、多くの企業が仕入先の変更やリスク回避のための複数ルートの開拓を行った。4月末時点では熊本地震を要因とした倒産は発生していないものの、万が一、震災からの復旧・復興が長引くことになると、今回も同様のことが起こり、被災地に所在する企業に深刻なダメージを与えることが懸念される。被災地所在企業と取引を行っている企業は全国に延べ3万1000社あり、熊本地震の影響は全国に波及する可能性がある(「熊本地震の現状と今後の復興に向けて」帝国データバンク、2016年4月発表)。特に、熊本県では農産品をユーザーに届ける流通プロセスへの打撃、大分県内の被災地では「旅館・ホテル」が集積している地域に被害が集中するなど、県経済にとっても痛手となりかねない。
他方、日本銀行は、熊本地震の被災地の金融機関を対象に、復旧・復興に向けた資金需要への対応を支援するため、被災地金融機関支援オペ(貸付総額3000億円、無利息で実施等)の措置を導入した。また、政府によって熊本地震が激甚災害に指定されたことで、復旧・復興事業にかかる国庫補助の特別措置が見込まれ、マイナス金利の導入により地方銀行等の収益力低下が予想されたなかで、被災地における資金供給を円滑に行う環境が整いつつある。
■地震・円高・不祥事、企業の抱えるリスクが顕在化
4月28日、日本銀行の金融政策決定会合において、市場で期待されていた金融緩和が見送られた。1月に導入が決定されたマイナス金利の効果を見極めるためとしているが、為替市場や株式市場は敏感に反応し、急激な円高・株安をもたらすこととなった。2016年4月の日銀短観によると、大企業・製造業の想定為替レートは117円46銭。企業の想定為替レートを上回る円高が継続する場合、為替差損にともなう企業業績へのインパクトは非常に大きなものとなる。
家計・企業の両部門において所得から支出への好循環を持続するためには賃金上昇が欠かせないものの、今春闘でのベースアップが伸び悩んでいる。こうしたなかでの日銀の現状維持という決定は企業経営者の景気先行き不透明感を増幅させるものであった。
このような経済環境のなか、三菱自動車工業による燃費データ不正問題が発覚した。同グループの下請け企業は全国で約7800社にのぼることが判明しているが(「『三菱自動車工業』グループの下請企業実態調査」帝国データバンク、2016年4月発表)、とりわけ生産拠点のある愛知県や岡山県に集中しており、影響の拡大が懸念される。
人手不足にともなう人件費上昇やガソリン価格の9週連続上昇(5月9日時点)など、企業のコスト負担がじわじわと高まってきている。さらに、円高・株安の進行のほか、地震など自然災害の発生、企業不祥事の発覚など、企業の抱えるさまざまなリスクがここにきて一気に顕在化してきた。長引く個人消費低迷から脱却するために消費税率引き上げの再延期を含めた経済対策の実施が望まれる一方、米国や中国の成長鈍化のほか、為替相場の動向も注視しなければならない。特に為替相場が円安から円高に変動するリスクは、貿易を行う中小企業や海外進出企業の収益にマイナス要因となろう。各種リスクの高まりにより企業をとりまく経営環境が厳しさを増す一方、政策投入によって倒産は抑制されるなど歪みが生じているなかで、倒産動向は当面低位で推移すると見込まれる。

