倒産件数は4750件、5年連続の前年同期比減少
負債総額は9144億7200万円、2期連続の1兆円割れ
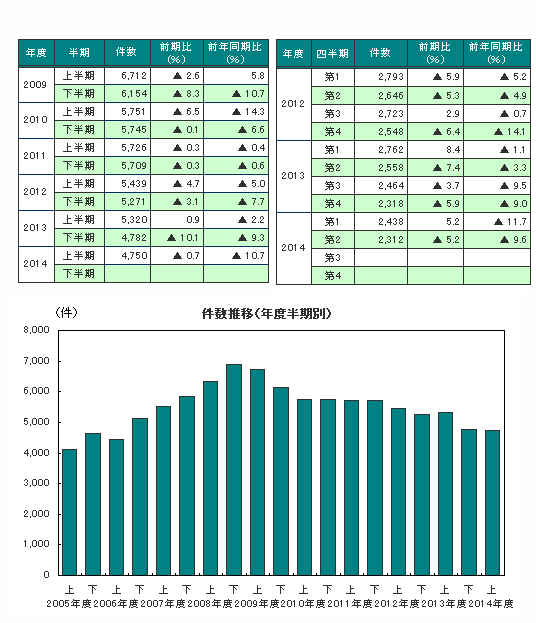
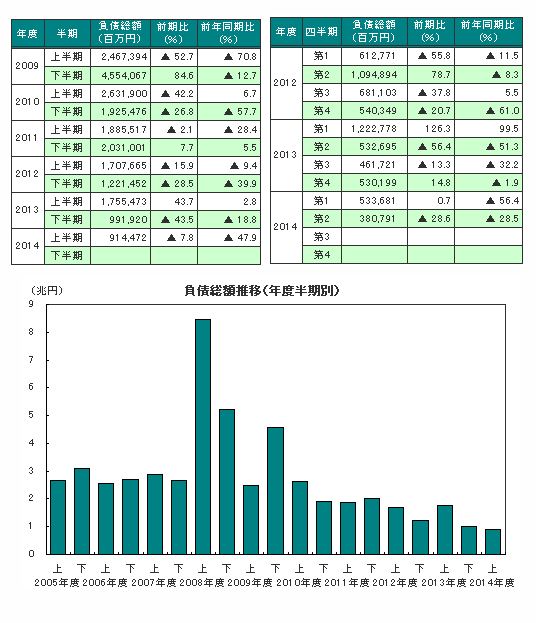
倒産件数 | 4750件 | 負債総額 | 9144億7200万円 |
|---|
前期比 | 件数 | ▲0.7% | 前期 | 4782件 |
|---|---|---|---|---|
負債 | ▲7.8% | 前期 | 9919億2000万円 | |
前年同期比 | 件数 | ▲10.7% | 前年同期 | 5320件 |
負債 | ▲47.9% | 前年同期 | 1兆7554億7300万円 |
■件数
ポイント5年連続の前年同期比減少
倒産件数は4750件と、2013年度上半期の5320件に比べ10.7%減少、5年連続で前年同期を下回った。四半期別では10期連続の前年同期比減少、月別では上半期6ヵ月すべての月で前年同月比減少となった。
要因・背景
- 1.公共工事の増加や駆け込み需要の効果で建設業(968件)が前年同期比19.6%の大幅減少
- 2.輸出関連の大手メーカーの業績回復もあり、製造業と卸売業が前年同期比2ケタの減少
■負債総額
ポイント2期連続の1兆円割れ
負債総額は9144億7200万円と、2013年度上半期の1兆7554億7300万円に比べ47.9%減少し、2013年度下半期に続き2期連続で1兆円を割り込んだ。四半期別では5期連続の前年同期比減少で、月別では上半期6ヵ月中5ヵ月が前年同月比減少となった。
要因・背景
- 1.負債トップは、(株)白元(5月、民事再生法、東京都)の254億9400万円
- 2.前年同期は負債1000億円以上の倒産が2件発生していたため、前年同期比で大幅減少
■業種別
ポイント7業種中6業種で前年同期比減少
業種別に見ると、7業種中6業種が前年同期を下回った。なかでも、建設業(前年同期比19.6%減)、製造業(同15.4%減)、卸売業(同11.6%減)の3業種は前年同期比2ケタの減少となった。一方、不動産業(同7.7%増)は唯一、前年同期を上回った。
要因・背景
- 1.建設業…公共工事の増加や、年度末にかけて生じた消費税率引き上げ前の駆け込み需要などにより、資金繰りが改善し減少傾向が続く
- 2. 輸出関連の大手メーカーの業績回復もあり、機械器具などの製造・卸で減少が目立つ
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比は83.1%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は3947件(前年同期4376件)となり、前年同期比9.8%の減少となった。一方、「不況型倒産」の構成比は83.1%と前年同期(82.3%)を0.8ポイント上回った。
要因・背景
- 1.「返済猶予後倒産」は257件(前年同期302件)判明、前年同期比14.9%減少
- 2.「不況型倒産」の件数、建設業(835件、前年同期1043件)で前年同期比19.9%の大幅減
■規模別
ポイント負債100億円以上の大型倒産、2000年以降最少
負債額別に見ると、負債5000万円未満の小規模倒産は2608件と、前年同期の2923件を10.8%下回った。一方、同100億円以上の大型倒産は5件にとどまり、上半期としては2000年以降で最少となった。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計は2749件、構成比は57.9%を占めた。
要因・背景
- 1.負債5000万円未満の小規模倒産の構成比は、54.9%と8期連続で過半数を占める
- 2.大型倒産は、事業再生ADRなど再生スキームの活用により抑制が続く
■地域別
ポイント9地域中7地域で前年同期比減少
地域別に見ると、9地域中7地域で前年同期を下回り、なかでも中部(前年同期比23.4%減)、中国(同13.9%減)など4地域は前年同期比2ケタの大幅減少となった。一方、四国(同6.7%増)と東北(同5.1%増)は前年同期を上回った。
要因・背景
- 1.中部は、卸売業(95件、前年同期比27.5%減)、建設業(144件、同26.9%減)を中心に7業種すべてで前年同期を下回り、うち製造業を除く6業種が2ケタの大幅減少
- 2.増加した四国・東北の2地域では、製造業の増加が目立つ
■態様別
ポイント清算型の構成比が96.7%
態様別に見ると、破産は4447件(前年同期5026件)となり、構成比は93.6%と高水準が続いた。破産に特別清算を加えた清算型の合計は4593件で、構成比は96.7%にのぼった。一方、会社更生法は1件、民事再生法は156件で、再建型は157件(構成比3.3%)にとどまった。
要因・背景
- 1.再建型手続きが困難な中小零細企業の構成比が高まり、破産が高水準で推移
- 2.民事再生法は、2000年4月の施行以降、過去最少を記録
■上場企業倒産
上場企業の倒産は発生しなかった。
2013年8月のワールド・ロジ(株)(破産)以降、上場企業の倒産は13ヵ月連続で発生しておらず、沈静状態が続いている。
年度上半期として上場企業倒産が発生しなかったのは、1990年度上半期以来24年ぶり。
■大型倒産
負債トップは、(株)白元(5月、民事再生法)の254億9400万円。一般社団法人京都府森と緑の公社(6月、民事再生法)の228億円、(株)笠屋町不動産(8月、特別清算)の200億円がこれに続く。
■注目の倒産動向
建設業 件数は前年同期比19.6%の大幅減で、6年連続減少
2014年度上半期の建設業の倒産は968件(前年同期比19.6%減)となり、6年連続の前年同期比減少。また、月ベースでみても、9月(153件)が前年同月比21.1%の減少となったことで、2012年10月以降24ヵ月連続で前年同月を下回った。これは、2003年9月から2005年5月までの21ヵ月前年同月比減少の連続記録を抜き、2000年以降の最長記録となっている。
2003年から2005年にかけては、ゼネコンなどの過剰債務問題やメガバンクの不良債権処理が峠を越えた時期であり、また「セーフティネット保証」や「資金繰り円滑化借換保証」など政府の中小企業支援策が奏功した時期でもあった。その後、2007年6月の建築基準法改正や2008年9月のリーマン・ショックの影響を大きく受け、倒産件数が著しく増加。2008年度下半期には2000年以降で年度半期ベースの最多となる1792件の倒産が発生した。2014年度上半期は当時に比べるとほぼ半減している。「緊急保証制度」や「中小企業金融円滑化法」の倒産抑制効果のほか、2011年に東日本大震災が発生して以降は、復興需要、政権交代後の公共工事増加、消費税率引き上げ前の駆け込み需要などを受け、倒産件数の減少傾向が続いている。
しかし、近時では資材不足、職人不足が倒産に結び付くケースが散見されるように、資材価格高騰、労務費高騰が建設業者の収益に大きな影響を与えている。また、地方の建設業者の拠り所となっている公共工事は今後の財政出動の規模次第という危うさもある。月ベースの倒産件数では、2014年度上半期の6ヵ月中4ヵ月が前月比増加となっており、今後、資本力の弱い下請け業者を中心とした淘汰が進めば、それにより建設業の倒産件数が前年同月比増加に転じる局面を迎えることが想定される。
今後の見通し
■急激な円安、経営リスクとして意識される
10月1日の東京外国為替市場では、一時リーマン・ショック以前の水準である1ドル110円台をつけた。8月に入ってから円安が急速に進み、わずか2ヵ月で約8円も円安方向に振れている。円安は、自動車メーカーをはじめとする輸出企業の利益を押し上げる一方、海外からの調達が前提となっている企業に対してはマイナスの影響を与える。「円安に振れたことで為替差損が発生したことに加え、中国における生産コストが上昇。多額の赤字を計上し行き詰まった企業」(婦人靴卸・小売)など、急激な円安で採算が悪化し倒産に至る企業も出てきた。
さらに、円安は原材料などの輸入価格上昇に繋がる。内需型の製造業や消費者に対する価格転嫁が難しい小売業では、利益の押し下げ要因となり得る。また、足元では生活必需品の値上げが相次いでいることから、4月の消費税率引き上げと相俟って、消費マインドの低下が警戒されるところだ。実際に「円安による原材料の調達コスト上昇で一段と採算が悪化」(めん類製造)など、製造業を中心としてコスト増加が倒産の一因となる企業倒産が散見され始めている。
こうした状況下、経済産業省は、10月2日付で同省関連の431団体に対し、下請事業者との取引に際して、原材料・エネルギーコスト増加分の適正な価格転嫁を求めた。中小企業・小規模事業者の収益がこれ以上圧迫されないようにするためだ。また、同時に公的金融機関に対し、中小企業向け融資について、返済猶予等の対応に努めるように要請するなど、資金繰り面からも中小企業を支援する。原材料・エネルギーコスト増加、そしてそれを引き起こす急激な円安は、経営上のリスクとして意識し対応していかなければならない。
■地域経済活性化と産業の新陳代謝を両睨み
安倍総理は第187回国会の所信表明演説で、地域活性化の成功事例をいくつもあげ、地方創生に注力していく方針を明確にした。この背景には、同演説で「人口減少や超高齢化など、地方が直面する構造的な課題は深刻」と述べたように、地方経済に対する将来的な危機感がある。もっとも、企業倒産件数をみれば、将来ではなくすでに、全体的な倒産減少局面(2014年度上半期は前年同期比10.7%の大幅減少)にあるにも関わらず、倒産が増加している地域が確認できる。
2014年度上半期の企業倒産件数を地域別にみると、9地域中7地域で前年同期を下回った。しかし、東北(185件、前年同期比5.1%増)、四国(95件、同6.7%増)の2地域は増加している。この2地域の倒産を業種別にみると、大幅に件数が増加しているのは共通して製造業であり、東北(36件)は前年同期比56.5%増、四国(16件)は同77.8%増である。地方の製造業では過剰債務を抱えている企業は珍しくない。また、2次請け、3次請けの製造業者においては、近年、得意先メーカーが生産拠点を海外へ移転することへの対応を迫られるケースも多い。
こうした企業は、“産業の新陳代謝”の流れのなかで変革を求められていると言える。地域経済活性化のためには、地域における各産業や個別企業の生産性向上が不可欠。赤字体質の企業や、構造的な経営課題を抱えている企業は、“塩漬け”や“先延ばし”といった小手先の延命策ではなく、抜本的な経営改善が急務となっている。政府は「日本産業再興プラン」として、地域のベンチャー企業支援策や、中小企業の競争力強化に向けた取り組みを推し進める方針だ。この地域活性化プラットフォームのなかで収益性・生産性を向上させ、抜本的な経営改善を果たす企業が出てくることが期待されている。地域活性化プロセスにおいて、2014年度下半期の企業倒産の推移は、その実行性を問うものといえ、減少が続く現状を変えていく方向性にあるものとみられる。

