企業倒産、底打ちから増加基調が続く
2022年度は3年ぶりの増加へ
倒産件数は574件、10カ月連続の前年同月比増加
負債総額は1005億4600万円、2月としては4年ぶりの1000億円超
倒産件数 | 574件 |
|---|---|
前年同月比 | +34.1% |
前年同月 | 428件 |
負債総額 | 1005億4600万円 |
|---|---|
前年同月比 | +28.8% |
前年同月 | 780億6600万円 |
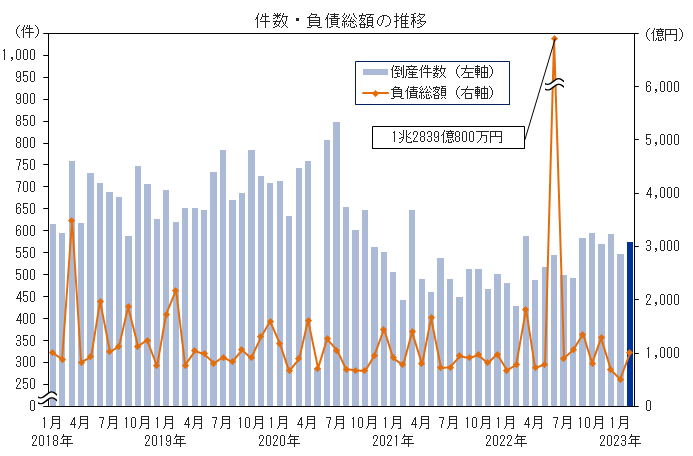
概況・主要ポイント
- ■倒産件数は574件(前年同月428件、34.1%増)と、10カ月連続で前年同月比増加。前年同月から30%以上の増加は、コロナ禍で法的整理の滞留による影響から反動増となった2021年5月を除くと、2009年1月(30.2%増)以来14年1カ月ぶり
- ■負債総額は1005億4600万円(前年同月780億6600万円、28.8%増)と、3カ月ぶりに前年同月から増加。2月としては2019年以来4年ぶりに1000億円超を記録した
- ■業種別にみると、7業種中5業種で前年同月比増加。飲食店(前年同月33件→66件)や飲食料品卸売(同12件→19件)など食品関連産業での増加が続く
- ■主因別にみると、「不況型倒産」は451件発生。「売掛金回収難」は8年6カ月ぶりの急増
- ■規模別にみると、負債「5000万円未満」や「1億円未満」の小規模零細企業の増加が目立つ
- ■業歴別にみると、業歴10年未満の「新興企業」は13年6カ月ぶりの12カ月連続増加
- ■地域別にみると、四国を除く全地域で前年同月比増加。近畿(前年同月88件→142件、61.4%増)や中部(同38件→83件、118.4%増)では大幅な増加が続く
■業種別
7業種中5業種で前年同月比増加 飲食店など食品関連産業での増加が続く
業種別にみると、7業種中5業種で前年同月を上回った。小売業(前年同月83件→127件、53.0%増)は、2020年4月以来2年10カ月ぶりに40件以上増加した。特に飲食店(同33件→66件)は、原材料高や助成金の縮小・終了による収益悪化の影響もあり倍増。また、建設業(同69件→111件、60.9%増)は、設備工事(同14件→31件)などで増加したこともあり、全体でも40件以上の大幅な増加を記録。運輸・通信業(同25件→39件、56.0%増)は、燃料費高騰やドライバー不足の影響を受ける道路貨物運送(同14件→28件)の増加もあり、5カ月連続の増加となった。一方、製造業(同52件→49件、5.8%減)、卸売業(同60件→54件、10.0%減)は減少となったものの、食料品・飼料・飲料製造(同10件→12件)や飲食料品卸売(同12件→19件)では増加しており、飲食店含め食料品関連産業の増加が続く。
■倒産主因別
「不況型倒産」は451件、「売掛金回収難」は8年6カ月ぶりの急増
主因別にみると、「不況型倒産」の合計は451件(前年同月339件、33.0%増)で5カ月連続の前年同月比2ケタ増、構成比は78.5%(対前年同月0.7ポイント減)だった。
最多は「販売不振」の434件(前年同月335件、29.6%増)で、構成比は75.6%(対前年同月2.7ポイント減)を占めた。また、「売掛金回収難」(同0件→10件)は2014年8月以来8年6カ月ぶりに2ケタ件数を記録したほか、「経営者の病気、死亡」(同16件→19件、18.8%増)は2カ月連続の増加となった。
一方、「その他の経営計画の失敗」(前年同月19件→18件、5.3%減)は4カ月連続の前年同月比減少、「放漫経営」(同8件→5件、37.5%減)も7カ月ぶりに減少した。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■倒産態様別
「清算型」倒産は561件、構成比は97.7%
倒産態様別にみると、破産と特別清算を合わせた「清算型」倒産は561件(前年同月427件、31.4%増)で、構成比は97.7%を占めた。一方、民事再生法と会社更生法を合わせた「再生型」倒産は13件(同1件、1200.0%増)で、2カ月連続で前年同月から増加した。
破産は539件(前年同月400件、34.8%増)で、2008年6月-09年8月以来13年6カ月ぶりの長さとなる11カ月連続の前年同月比増加となった。また、特別清算は22件(同27件、18.5%減)と、3カ月連続で前年同月から2ケタ減少が続く。
このほか、民事再生法は13件(前年同月1件、1200.0%増)発生し、施行後最少の前年同月から大幅な反動増となった。
■規模別
小規模零細企業の倒産増加が目立つ
負債規模別にみると、負債「5000万円未満」の倒産は350件(前年同月245件、42.9%増)、「1億円未満」は85件(同59件、44.1%増)発生した。1億円未満合計で前年同月から130件以上増加するなど、小規模零細企業の倒産増加が目立った。
資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人事業主含む)の倒産が404件(前年同月274件、47.4%増)発生し、構成比は70.4%を占めた。
■業歴別
業歴10年未満の「新興企業」は13年6カ月ぶりの12カ月連続増
業歴別にみると、業歴「30年以上」が193件(前年同月150件、28.7%増)で最多、構成比は33.6%(対前年同月1.4ポイント減)を占めた。このうち、老舗企業(業歴100年以上)の倒産は3件発生した。
また、「3年未満」(前年同月15件→27件、80.0%増)、「5年未満」(同31件→40件、29.0%増)、「10年未満」(同64件→97件、51.6%増)など、業歴10年未満の新興企業の倒産(同110件→164件、49.1%増)は、2009年8月以来13年6カ月ぶりに12カ月連続の増加となった。新興企業を業種別にみると、サービス業(同38件→56件、47.4%増)が最多。このほか、総合工事(同3件→10件)や飲食店(同10件→17件)で増加が目立った。
■地域別
四国を除く全地域で前年同月比増加、近畿や中部では大幅な増加が続く
地域別にみると、四国を除く全地域で前年同月を上回った。近畿(前年同月88件→142件、61.4%増)では、サービス業(同20件→40件)や建設業(同11件→27件)などの増加の影響もあり、2008年4月以来14年10カ月ぶりに3カ月連続で前年同月比2ケタ増となった。中部(同38件→83件、118.4%増)は、原材料高によるコスト増を価格転嫁しにくい飲食料品卸売(同0件→3件)や飲食店(同4件→17件)など食品関連産業で増加が目立った。また、関東(同186件→199件、7.0%増)では、不動産業(同4件→17件)や運輸・通信業(同5件→12件)などで大幅増加。このほか、九州(前年同月28件→46件、64.3%増)は5カ月連続で前年同月比2ケタ増となるなど、地方圏においても増加が目立った。
注目の倒産動向-1
■東日本大震災関連倒産
震災から12年、被災→復興へ 震災関連倒産の発生、過去最少
136カ月ぶりに発生「ゼロ」記録も、いまなお苦しむ企業の支援に課題
東日本大震災の発生からまもなく12年を迎えるなか被災地企業の「復興」「収束」が進む。震災発生直後の2011年3月から23年2月の12年のうち、震災被害が倒産の直接または間接的な要因となった「東日本大震災関連倒産」は累計2100件に上った。負債総額は累計1兆7252億円に上った。このうち、12年目となる2022年3月~23年2月の倒産は15件と、発生以降で最少を更新した。同期間では、震災以降136カ月目にはじめて関連倒産がゼロを記録するなど、震災による影響はほぼ収束し、被災地企業を中心に復興へと進んでいる。
ただ、震災関連倒産のうち地震や津波の被害が直接的に経営にダメージを与えた倒産は時間が経過するほど割合が高まっている。直近5年間の関連倒産のうち、津波による流出など「直接被災」が原因となった倒産は40.0%と、12年間累計(12.2%)に比べ大きな割合を占める。震災を乗り越え、補助金等を活用して工場や事業所を再建したものの、地域経済の衰退や取引企業の消失などで当初想定通りに売り上げが回復しないなど、震災後長期間を経過してもなお経営の立て直しが容易でない側面が浮かび上がる。
政府は「第2期復興・創生期間」を2026年3月まで定め、復興支援の総仕上げにかかっている。震災によって被害・影響を受けた企業でも、今後は支援に頼らない本来の自主経営を求められる局面に突入している。一方で、コロナ禍や物価高など、震災直後には想定ができず、企業努力での挽回も難しい新たなマイナス要素も出現している。震災から今なお完全な立ち直りが難しい企業に対する支援の在り方が、今後も重要となってくる。
■コロナ融資後倒産
2022年度は400件に迫る、前年度比2倍ペース 焦げ付き総額は368億円
コロナ融資後倒産は、2023年2月において38件(前年同月20件、90.0%増)発生した。また、2月までの2022年度累計は392件となり、前年度の216件を大幅に上回っている。
「焦げ付き」に相当するコロナ融資損失総額は推計で約368億円に上り、国民一人当たり約300円の負担が発生している計算になる。
■人手不足倒産
2022年度は125件、3年ぶりに増加 「採用難」の人手不足目立つ
人手不足倒産は、2023年2月において9件(前年同月13件、30.8%減)発生し、8カ月ぶりに前年同月を下回った。他方、2月までの2022年度累計は125件となり、前年度の118件をすでに上回った。従業員や経営幹部などの退職・離職に起因した「従業員退職型」に加え、求人しても応募が無く、人手不足が慢性化した末に倒産した「採用難型」も目立ってきた。
注目の倒産動向-2
■コロナ禍に「創業」した企業の倒産動向
コロナ禍に「創業」、目立つ「短命」倒産 平均業歴は1.8年
3年間累計で300件超の見込み、22年度は前年度から3倍と急増
コロナ禍に「創業」した新興企業の倒産が急増している。国内で新型コロナウイルスの感染拡大した2020年2月以降に創業した新興企業の倒産は、累計で294件発生した。このうち、2月までの2022年度累計は220件発生し、21年度(67件)から3倍超に急増した。20年2月以降の倒産件数累計(約2万600件)では約1.4%の割合にとどまるものの、コロナ禍に創業した業歴の浅いアーリーステージ段階の企業で倒産が増加している。平均業歴は1.8年にとどまり、創業から2年未満で事業を終える「短命」倒産が多かった。
業種別にみると、最も多いのが老人福祉事業で、全体の8.8%を占めた。多くが、競争が激しいデイサービスやショートステイなど通所型介護事業で、参入障壁が比較的低く事業規模が小さい企業の倒産だった。老人福祉事業では、コロナ禍で介護報酬の加算など国の支援も行われたものの、他方で感染を懸念した利用の手控えといった動きもあり、参入計画の段階で準備不足が否めないケースが多くみられた。不動産代理・仲介のほか、参入障壁の低い美容室、放課後等デイサービスをはじめ障がい児通所など、総じてサービス業が多くを占めた。一方、コロナ禍に関連した資金繰り支援や支援金などが経営を下支えしていることも背景に、飲食店の各業態ではいずれも倒産は少数にとどまった。
足元では、業歴の浅い企業の倒産割合が増えている。2023年2月の倒産では業歴10年未満の倒産が合計164件に達し、2009年8月以来13年6カ月ぶりの増加ペースが続いている。ポストコロナに向け経済活動が正常化に向かうなか、新興企業の淘汰は強まる可能性がある。
■物価高(インフレ)倒産
2023年2月は53件発生 前年度から3倍ペースで増加、過去最多に
物価高(インフレ)倒産は、2023年2月において53件(前年同月7件、657.1%増)発生した。単月ベースで過去最多だった23年1月(50件)を超え、過去最多を更新した。また、2月までの2022年度累計は396件に達し、このペースで推移すると初の年間400件超えは確実で、前年度から3倍超の大幅な増加が見込まれる。
■後継者難倒産
2023年2月は32件発生 過去最多の19年度と同水準のペース
後継者難倒産は、2023年2月において32件(前年同月42件、23.8%減)発生し、2カ月ぶりに前年同月を下回った。他方、2月までの2022年度累計は437件となり、前年度の476件、過去最多だった19年度(479件)に並ぶペースで推移している。代表者の病気・死亡が多くの理由に挙げられ、事業がそのまま立ち行かなくなったケースが多数を占める。
今後の見通し
■企業倒産は3年ぶり増加確定 「リーマン」以来の急増ペース、「物価高」など酷似
2023年2月の企業倒産は574件発生し、10カ月連続の前年同月比増加となった。増加期間はリーマン・ショック後の08年6月-09年8月(15カ月連続)以来14年ぶりとなる。企業倒産はコロナ前の600件台/月にせまりつつあり、2022年を底として増加基調が鮮明となっている。なかでも、小売業では飲食店が66件と前年同月から倍増したほか、資材価格や職人不足が深刻な建設業、燃料価格やドライバー不足の影響を大きく受けている運輸・通信業では前年同月から1.6倍と急増した。十分な価格転嫁ができず、人手不足も深刻化するなか、コスト負担に耐えかねて事業継続を“あきらめる”中小・零細企業で倒産が増えている。
こうしたなか、2022年度(22年4月-23年3月)の企業倒産は、2月時点の11カ月累計で前年度(5916件)を上回り、3年ぶりの増加が確定した。2月時点で前年度を上回る急増ペースは、08年度以来14年ぶりとなる。08年度当時も、100ドルに迫った原油価格など「物価高」が深刻だった時期で、22年度の経済状況にも酷似する部分は多い。ただ、当時と異なるのは、コロナ融資など長期にわたる金融支援により、外部からの支援なくては「自立」さえままならない中小企業が大幅に増えた点だ。そうした状況も取引銀行が融資先の「選別」色を強めるなど変化している。事業環境の悪化から収益改善を果たせぬまま経営に行き詰まる中小企業の倒産が、08年度当時と同様に増加していく可能性は高まっている。
■「大型倒産」相次いだ2月 目立ち始めた「粉飾倒産」、消費者被害型倒産も発生
「久しぶりに月末らしい慌ただしさだった」 ― 大手総合商社の与信管理担当者は2月をこう振り返る。実際、当月末は大型倒産が各業界で相次いで発生した。先鞭を切ったのは、お好み焼き・鉄板焼き店「いっきゅうさん」など80店舗超を経営していたダイナミクス(東京、負債約106億7800万円)。2022年3月に破産した居酒屋運営のアンドモワ(東京、負債80億円)を上回り、コロナ禍で最大となる飲食店倒産となった。
多くの消費者が被害を受けたのが、太陽光発電設備の小口オーナー販売を手掛けたチェンジ・ザ・ワールド(山形、負債約38億円)だ。企業や自治体の脱炭素支援の取り組みがメディアで取り上げられるなど注目を集めていたスタートアップだが、最終的には個人投資家など1万2000名超の債権者を抱え経営破綻した。オーナー制度をめぐっては、3万名を超える一般消費者が被害を受けたケフィア事業振興会(2018年破産)や、ジャパンライフ(2018年破産)といった倒産事例が記憶に新しい。これらの事件を受け、2022年に改正預託等取引に関する法律が施行されたなか、当社のビジネスが同法に適用することから事業継続を断念した。
産業用ロボットメーカー、トガシ技研(山形、民事再生、負債約56億円)は、融通手形取引を長年続けていた主要得意先との「架空売り上げ」による粉飾決算が明らかになり取引先からの信用が失墜、法的整理による再建を余儀なくされた。トガシ技研のケースは、直近にも大がかりな“手形操作”の末に連鎖倒産を引き起こした総合医業コンサルティング会社のアイテック(東京、2022年10月民事再生)を想起させるなど共通点も多い。ここにきて全国的に「粉飾倒産」が目立っており、取引先のリスク管理も警戒度を一段高める必要がありそうだ。
■見えてきた2023年度の倒産動向 「値上げ」「ポストコロナ」の対応焦点に
「値上げラッシュ」の動きが止まらない。帝国データバンクの調査では、2023年中に値上げする食品や飲料は計1万5813品目で判明した。前年比3倍のペースで増えており、8月にも2万品目の大台を突破する見通しだ。値上げラッシュは当面続くことが確実視されるなかで、価格転嫁の動きとともに、川上から川下までバリューチェーン全体に連なる業者の動向から目が離せない。
今夏以降、ゼロゼロ融資の元本返済をこれまで据え置いてきた企業の返済開始時期が順次到来する。借り換え保証、収益力改善支援、経営者保証制度の見直しなど、官民挙げて「ポストコロナ」の出口戦略が動き出すなか、過剰債務に苦しむ中小企業の経営正常化が以前にもまして急務だ。そうした観点からも2023年度は、企業および産業の新陳代謝を進めながら中小企業の過剰債務問題をいかにソフトランディングさせるかが問われる1年となるだろう。

