倒産件数は765件、7ヵ月連続の前年同月比減少
負債総額は1165億4300万円、2000年以降で最小
倒産件数 | 765件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲10.8% |
前年同月 | 858件 |
前月比 | ▲5.4% |
前月 | 809件 |
負債総額 | 1165億4300万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲29.9% |
前年同月 | 1662億5000万円 |
前月比 | ▲61.4% |
前月 | 3016億9600万円 |
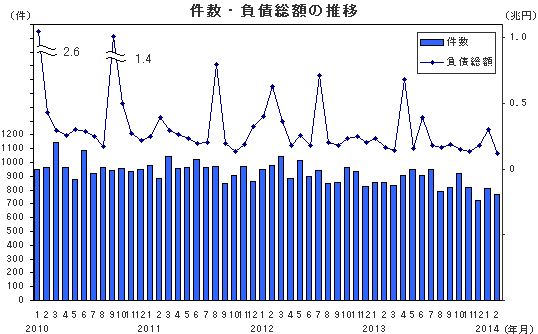
主要ポイント
- ■倒産件数は765件で、前年同月に比べ10.8%減少。7ヵ月連続で前年同月を下回り、2013年度では12月(726件)に次いで2番目に少ない件数となった
- ■負債総額は1165億4300万円で、前年同月を29.9%下回り、2000年以降で最小を記録した
- ■業種別に見ると、7業種中3業種で前年同月を下回った。建設業(148件、前年同月比30.5%減)は17ヵ月連続の前年同月比減少となったほか、2000年以降初めて構成比が20%を下回った
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は645件で、構成比は84.3%となり、前月を0.2ポイント、前年同月を0.4ポイント上回った
- ■「金融円滑化法利用後倒産」は38件(前年同月比15.2%増)判明
- ■負債5000万円未満の倒産は408件で、前年同月比13.7%減少したものの、構成比は53.3%と、16ヵ月連続で過半数を占めた
- ■地域別では、9地域中5地域で前年同月を下回り、北海道(19件、前年同月比42.4%減)で大幅減少となったほか、九州(同18.8%減)、東北(同17.6%減)、関東(同17.6%減)、近畿(同10.5%減)と、5地域いずれも2ケタの前年同月比減少となった
- ■6ヵ月連続で、上場企業の倒産は発生しなかった
- ■負債トップは、(株)MTGOX(東京都、民事再生法)の65億100万円。負債100億円以上の大型倒産は3ヵ月ぶりに発生しなかった
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は7ヵ月連続の前年同月比減少、負債総額は2000年以降で最小
倒産件数は765件で、前年同月に比べ10.8%減少。7ヵ月連続で前年同月を下回り、2013年度では12月(726件)に次いで2番目に少ない件数となった。負債総額は1165億4300万円で、前年同月を29.9%下回り、2000年以降で最小を記録した。
要因・背景
件数…公共工事の増加などで、建設業が関東を中心に9地域中7地域で前年同月比減少
負債総額…負債100億円以上の大型倒産が発生せず、同10億円以上も22件にとどまる
■業種別
ポイント7業種中3業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中3業種で前年同月を下回った。建設業(148件、前年同月比30.5%減)は17ヵ月連続の前年同月比減少となったほか、2000年以降初めて構成比が20%を下回った。また、サービス業(139件、同24.0%減)でも前年同月比で2ケタの大幅減少となった。一方、運輸・通信業(37件、同32.1%増)など4業種では前年同月を上回った。
要因・背景
- 1.建設業…公共工事などの建設需要により全国的に減少傾向が続き、なかでも関東(49件、前年同月75件)、近畿(37件、同52件)で大幅減少
- 2.運輸・通信業…軽油小売価格の高止まりにより、道路貨物運送(27件)で増加が目立つ
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比84.3%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は645件(前月680件、前年同月720件)となった。構成比は84.3%(前月84.1%、前年同月83.9%)で、前月を0.2ポイント、前年同月を0.4ポイント上回った。
要因・背景
- 1.「金融円滑化法利用後倒産」は38件(前年同月比15.2%増)判明
- 2.「不況型倒産」の件数、建設業(133件、前年同月比28.1%減)で大幅減少
■倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、 業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比53.3%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は408件で、前年同月比13.7%減少したものの、構成比は53.3%と、16ヵ月連続で過半数を占めた。一方、負債100億円以上の大型倒産は3ヵ月ぶりに発生しなかった。資本金別に見ると、個人経営と資本金1000万円未満の合計は432件、構成比は56.5%を占めた。
要因・背景
- 1.負債5000万円未満の業種別では、小売業(104件、構成比25.5%)が最多
- 2.負債10億円以上の倒産は22件にとどまり、7月と並んで2013年度最少
■地域別
ポイント9地域中5地域で前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中5地域で前年同月を下回った。なかでも、北海道(19件、前年同月比42.4%減)で大幅な減少となったほか、九州(52件、同18.8%減)、東北(28件、同17.6%減)、関東(267件、同17.6%減)、近畿(188件、同10.5%減)と、5地域いずれも2ケタの前年同月比減少。一方、中国(43件)など4地域では前年同月比増加となった。
要因・背景
関東は、建設業(前年同月比34.7%減)とサービス業(同30.4%減)で大幅に減少。なかでも、公共工事に加えて五輪開催決定などにより需要が好調の東京では、建設関連の倒産が抑制。
■上場企業倒産
6ヵ月連続で、上場企業の倒産は発生しなかった。
2013年度の上場企業倒産の累計は2件にとどまっており、前年度を下回るペースでの推移となっている。
■大型倒産
負債トップは、(株)MTGOX(東京都、民事再生法)の65億100万円。和田工業(株)(東京都、破産)の30億8900万円、(株)武屋(埼玉県、破産)の30億円が続く。
負債100億円以上の大型倒産は3ヵ月ぶりに発生しなかった。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは49.6、消費増税後の不透明感から一時足踏み
2014年2月の景気動向指数(景気DI:0~100、50が判断の分かれ目)は、前月比0.4ポイント減の49.6となり、2013年6月以来8ヵ月ぶりに悪化した。
為替相場は米国の長期金利上昇もあり円高の動きが一服し、株価も概ね安定した動きとなった。しかし、企業の間で消費税率引上げ後の需要回復に対する先行き不透明感が現れてきたなか、大雪による悪天候は小売店やレジャー施設などの来客数を減少させた。また、ガソリンスタンドで厳しい価格競争が続いたほか、家電製品の販売が好調だった半面で修理依頼の減少などの影響を受けて『小売』『サービス』といった前月に景気をけん引した消費関連業界など10業界中8業界が悪化、2013年6月に全業界が悪化して以来8ヵ月ぶりに多数の業界にまたがる結果となった。
小規模企業の収益環境が悪化、特に『不動産』で顕著
規模別では8ヵ月ぶりに全規模が悪化した。とりわけ「小規模企業」は仕入れ単価DIが上昇を続ける一方、販売単価DIが低下するなど、価格面での収益環境に厳しさがみられ、特に『不動産』で顕著に現れた。地域別では自動車関連が好調な『東海』など3地域が改善したものの、『北海道』『九州』など7地域が悪化した。『九州』では日照不足が続き農作物の流通に影響したほか、魚価低迷による不振もあり『農・林・水産』が大きく悪化した。国内景気は、先行きへの不透明感が感じられるなかで悪天候も重なり、一時的に足踏み状態となった。
今後の見通し
■東日本大震災から3年、関連倒産はいまだ収束せず
東日本大震災から3年。公共インフラの本格復旧が進み、災害廃棄物も福島県の一部を除き、今年3月末までに処理可能(復興庁)という段階にまで震災復興は進んできた。しかし、未曾有の災害は企業経営に大きな影響を与えており、震災発生から3年が経過しようとしている現在でも内包していた損失が原因となり倒産に至るケースが続発。この結果、「東日本大震災関連倒産」は、「阪神大震災関連倒産」の約3.8倍にのぼっている。いまだ1ヵ月あたり25件前後の「東日本大震災関連倒産」が発生しており、収束には少なくともあと2~3年かかると推測される。
■経営者保証に依存しない融資慣行、定着なるか
日本商工会議所と全国銀行協会を事務局とした民間の研究会が公表していた「経営者保証に関するガイドライン」の適用が2月1日から開始された。これにより、法人と個人が明確に分離されている場合などについて、金融機関は停止(解除)条件付保証契約やABL、金利上乗せなど、経営者保証の代替となる融資手法の活用を視野に入れ、“経営者保証に依存しない融資”を検討していくことになる。経営者保証の存在により早期の事業再生・清算、業態変更等が阻害され、時機を逸して倒産に至るケースを減少させることが目的の一つだ。
金融庁は監督指針を改定し、同ガイドラインの浸透・定着を図ろうとしているが、「不動産担保、経営者保証」により融資を行うという融資慣行を変革させるのは容易ではない。そうなると、金融機関が融資を躊躇する事態も想定される。同ガイドラインは、中小零細企業向け融資の資産査定の考え方を改めるものではないため、査定への影響は少ないはずだが、経営者への規律づけの弱まりを懸念する声があるのは事実。すでに各金融機関は同ガイドラインを遵守するための態勢整備を実施したと発表しているが、借手企業からの本格的な申し入れはこれからとみられる。
■消費税率引き上げの影響度合いにより、業種間で明暗が分かれる見込み
2013年度の企業倒産は、2014年2月までの11ヵ月間で9358件発生。2012年度の同時期(9874件)と比べ、5.2%の減少となっている。中小企業金融円滑化法、および同法期限到来後も金融機関のスタンスが変化しなかったことによる資金繰り支援の継続、復興工事をはじめとする公共工事増加、消費税率引き上げ前の駆け込み需要などと、“アベノミクスの高揚感”が相まって企業倒産は減少傾向を示している。
しかし、業種別に見ていくと、逆に増加傾向を示している業種もある。例えば「飲食料品販売(卸・小売)」は2月までに688件の倒産が発生し、すでに2012年度(676件)を上回っている。また、「食料品など製造」も2月までで200件発生しており、2012年度(208件)を上回るのは確実とみられる。食品業界では、デフレ経済のあおりを受けた低価格化の進行で採算が悪化していたところに、円安による原材料価格上昇が直撃した。中小の食品関連業者が、コスト増を販売価格に転嫁できていないことは、倒産件数によって裏付けられているとも言えよう。さらに、4月には消費税率引き上げを控える。飲料メーカーが一斉値上げを発表した一方で、販売価格据え置き(本体価格値下げ)を打ち出した流通業者もあることから、増税分をそのまま転嫁できる状況にあるとは言い難く、食品関連業者の倒産は、さらに増加する可能性がある。
3月も企業倒産が現在の水準で発生すると仮定したならば、2013年度の企業倒産は1万件を若干上回る水準になるとみられる。しかし、前述のように、業種によっては前年度を大きく上回る見込みの業種もあり、全業種で倒産が沈静化しているわけではない。2014年度の企業倒産は、為替動向、金融機関のスタンスの変化、財政出動規模の変化に加え、消費税率引き上げの影響度合いにより、業種間で明暗が分かれる結果となるであろう。

