倒産件数は671件、16ヵ月連続の前年同月比減少、今年最少を記録
負債総額は1100億2300万円、2000年以降で最小
倒産件数 | 671件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲18.2% |
前年同月 | 820件 |
前月比 | ▲15.5% |
前月 | 794件 |
負債総額 | 1100億2300万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲17.6% |
前年同月 | 1335億1700万円 |
前月比 | ▲17.8% |
前月 | 1338億6000万円 |
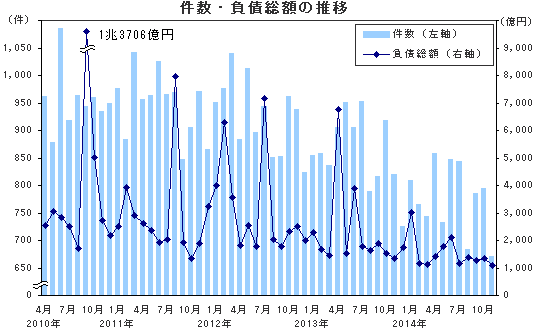
主要ポイント
- ■倒産件数は671件で、前年同月比18.2%の大幅減少を記録し、16ヵ月連続で前年同月を下回った。8月(683件)を下回り今年最少を記録したほか、2006年9月(667件)以来の低水準となった
- ■負債総額は1100億2300万円と、前年同月から17.6%減少し、6ヵ月連続で前年同月を下回った。2014年3月(1119億6000万円)を下回り、2000年以降で最小となった
- ■業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を下回り、なかでも建設業(141件、前年同月比19.0%減)は26ヵ月連続の前年同月比減少を記録したほか、卸売業(96件、同34.2%減)と製造業(80件、同32.8%減)の2業種は30%以上の劇的な減少となった
- ■主因別に見ると、「不況型倒産」の構成比が79.3%と17ヵ月ぶりに80%を割り込んだ
- ■「円安関連倒産」は42件(前月39件)判明し、集計開始以降の最多件数を更新
- ■負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は376件で、構成比は56.0%と25ヵ月連続で過半数を占めた一方、負債10億円以上の倒産は20件と低水準が続いた
- ■民事再生法による倒産が16件と同法施行(2000年4月)以降の最少件数を更新
- ■地域別に見ると、関東(230件、前年同月比26.3%減)、北海道(18件、同25.0%減)など9地域中6地域で前年同月を下回り、うち5地域は前年同月比2ケタの大幅減少となった
- ■負債トップは、(株)テイー・シー・ワークス(東京都、特別清算)の93億円。小路建設(株)(滋賀県、特別清算)の47億円が続く
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は16ヵ月連続前年同月比減少で今年最少、負債総額は2000年以降で最小
倒産件数は671件で、前年同月比18.2%の大幅減少を記録し、16ヵ月連続で前年同月を下回った。8月(683件)を下回り今年最少を記録したほか、2006年9月(667件)以来の低水準となった。負債総額は1100億2300万円と、前年同月から17.6%減少し、6ヵ月連続で前年同月を下回った。2014年3月(1119億6000万円)を下回り、2000年以降で最小となった。
要因・背景
件数…大手メーカーの業績回復や輸出環境改善などにより、金属製品や機械器具などを扱う卸売業(96件、前年同月比34.2%減)や製造業(80件、同32.8%減)で大幅減少
負債総額…負債10億円以上の倒産が20件にとどまったうえ、件数の減少もあり抑制される
■業種別
ポイント7業種中6業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を下回り、うち5業種は前年同月比2ケタの大幅減少となった。なかでも建設業(141件、前年同月比19.0%減)は26ヵ月連続の前年同月比減少を記録したほか、卸売業(96件、同34.2%減)と製造業(80件、同32.8%減)の2業種は30%以上の劇的な減少となった。一方、サービス業(164件、同8.6%増)は唯一前年同月を上回った。
要因・背景
- 1.卸売業・製造業…大手メーカーの業績回復や輸出環境改善もあり、機械器具卸(13件、前年同月比59.4%減)や金属製品製造(8件、同63.6%減)などで減少目立つ
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比79.3%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は532件(前年同月比23.5%減)となった。構成比は79.3%(前月81.7%、前年同月84.8%)で、2013年6月(79.7%)以来、17ヵ月ぶりに80%を割り込んだ。
要因・背景
- 1.「返済猶予後倒産」は今年最少となる22件(前年同月比56.0%減)判明
- 2.「円安関連倒産」は42件(前月39件)判明し、集計開始以来の最多件数を更新
■倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比56.0%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は376件で、前年同月を17.5%下回ったものの、構成比は56.0%と、25ヵ月連続で過半数を占めた。一方、負債10億円以上の倒産は20件と低水準が続いた。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が380件、構成比は56.6%を占めた。
要因・背景
- 1.負債5000万円未満の倒産、業種別では卸売業(46件、前年同月比35.2%減)で大幅減
- 2.大企業・中堅企業の業績回復や資金繰り改善を受け、大型倒産の抑制状態が続く
■地域別
ポイント9地域中6地域で前年同月比減少
地域別に見ると、関東(230件、前年同月比26.3%減)、北海道(18件、同25.0%減)など9地域中6地域で前年同月を下回り、うち5地域は前年同月比2ケタの大幅減少となった。一方、東北(38件、同22.6%増)、中国(31件、同3.3%増)の2地域は前年同月を上回った。四国(11件)は前年同月と同数となった。
要因・背景
- 1.関東・近畿は、建設業や卸売業を中心に4ヵ月連続で前年同月を下回る
- 2.東北は、(株)DIOジャパンの関連会社10社が件数を押し上げた
■上場企業倒産
上場企業の倒産は発生しなかった。
2013年8月のワールド・ロジ(株)(破産)以降、上場企業の倒産は15ヵ月連続で発生しておらず、沈静状態が続いている。
上場企業倒産の連続未発生期間としては、1986年9月から91年7月(59ヵ月連続)以来の長さとなっている。
■大型倒産
負債トップは、(株)テイー・シー・ワークス(東京都、特別清算)の93億円。小路建設(株)(滋賀県、特別清算)の47億円が続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは43.5、国内景気は悪化
2014年11月の景気DIは前月比0.6ポイント減の43.5となり4ヵ月連続で悪化した。11月は、7~9月期のGDPが2期連続マイナス成長となり消費税率再引き上げが延期された。また、前月末に追加金融緩和政策が実施され一段の円安となったことで、為替レートは2年で44%下落した。そのため、仕入価格の上昇が再び加速し、企業の収益環境の厳しさが増している。為替レートの2年間での下落率を平均してみると、2014年は日本が1973年に変動相場制に移行してから最も速いスピードで円安が進んでいることがわかる。急激なコスト増に対する価格転嫁の難しさが浮き彫りとなっていると言えよう。また、人手不足に対し人件費を抑えるために非正規雇用で対応していることも、消費低迷の要因だ。円安を通じた原材料高や賃金上昇の抑制による影響が広がっており、国内景気は悪化している。
今後は下振れ懸念のあるなか、ほぼ横ばいで推移
消費税率の再引き上げが延期されたことで、当分、駆け込み需要は発生しないとみられる。10月末からの追加金融緩和政策によりいっそうの円安が進むと予想されるため、輸入コスト上昇を販売価格に転嫁できない企業の収益悪化は懸念材料である。さらに、人手不足は建設関連での入札見送りなどをもたらし、成長を阻害する要因として景気の下振れ要因となろう。また、総選挙の結果次第では経済政策が停滞する可能性がある。今後は、原油価格の下落による企業や家計へのコスト負担の軽減効果など先行きへの期待感を含みながらも、国内景気は下振れ圧力もあり、ほぼ横ばいでの推移が続くと見込まれる。
今後の見通し
■原油価格下落も、円安と相殺で燃料費は高止まり
資源エネルギー庁が毎週公表している石油製品価格調査によると、トラックの主な燃料である軽油の店頭現金小売価格は、12月1日時点で136.8円/Lとなり、20週連続の値下がりで今年最安値となった。これは、原油生産量の調整が行われていないことに加え、シェールオイルの生産量増加に伴い、原油価格が下落した影響だ。WTI原油先物価格で見ると、今年前半は1バレル100ドルを挟んだ推移であったが、7月頃から下落傾向となり、石油輸出国機構(OPEC)が総会で減産を見送った11月27日以降は、1バレル60ドル台の推移となっている。
実は、20週連続の値下がりでも過去10年の推移でみれば“高止まり”という表現がふさわしく、2004年は1Lあたり90円前後で推移していた。最も影響を受けているのは運輸業であろう。全日本トラック協会の公表によると、この間、トラック運送事業者の運送費に占める燃料費の割合は約10%から約20%と10ポイント程度増加した。今年後半から原油価格の下落が進んだため軽油価格の値下がりも期待できるところであったが、昨今の円安が原油の輸入価格を押し上げ相殺した結果、“高止まり”状態が続いている。問題は、現在の円安水準が当面続くとみられることだ。産油国がどこまでの原油価格下落を許容するかは不透明であるが、減産に転じれば価格上昇が見込まれる。そうなれば、軽油価格が急騰する可能性は高く、運輸業者を直撃する。現在の水準でさえ、運輸業では今年1月から11月までで「円安関連倒産」が86件(前年同期比38.7%増)判明していることからしても、今後の倒産増加を警戒しなければならない。
■借入金平均金利が過去10年で最低となるなか、年間の倒産件数は1万件割れの見込み
2014年11月の企業倒産件数は671件で、前月を15.5%、前年同月を18.2%、ともに大幅に下回った。16ヵ月連続の前年同月比減少で、8月の683件を下回って今年最少を記録。これにより、2014年1月から11月までの累計は8533件となり、年間の倒産件数が2006年(9351件)以来8年ぶりに、1万件を切るのは確実とみられる。 金融庁は11月25日、「年末における中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について」と題する要請を金融機関関係団体等に対して行った。2013年3月末の中小企業金融円滑化法の期限到来後、事ある毎にこうした要請を金融庁等が行ってきたことは、倒産件数抑制に寄与したと言える。同法施行以降現在に至るまで、のべ500万件以上の債権について貸付条件の変更が実行され、多くの中小零細企業の資金繰り破綻を回避させた。
帝国データバンクが11月28日に発刊した『全国企業財務諸表分析統計(平成25年4月~平成26年3月)』によると、企業の2013年度決算では、借入金平均金利が1.82%となり、過去10年で最も低いことが判明した。直近のピークは、2007年度の2.42%。その後、リーマン・ショック後の経済失速に対応するためのゼロ金利政策再開があり、さらには量的金融緩和の効果で、金融機関の貸出金利は低下傾向をたどっているのである。金利の低下は、供給過多状態を表していると言え、企業側(借手側)が融資を受けやすい状態が続いているということだ。もちろん、支払利息負担も軽くなる。そしてこの間、中小企業金融円滑化法の施行により、金利の減免を含む貸付条件の変更を要請しやすい土壌が整っていた。本来なら淘汰される可能性が高い重債務企業の存続を容易にする環境であったといえ、大規模な財政出動と相俟って、企業倒産件数を減少させていると考察される。
しかし、この環境も変化の兆しがある。「金融システムの安定化のためには、金融機関が金利競争から脱却することが必須」との見地などから地域金融機関の再編機運が高まっているのだ。地域経済活性化に向けて、広域化した新たなビジネスモデルの創造を目指す動きもある。11月には、肥後銀行と鹿児島銀行、横浜銀行と東日本銀行がともに経営統合に向けた協議・検討を進めることに合意したと発表した。今後、人口減少・地元市場縮小が想定されているエリアを中心として地域金融機関の再編が起こるであろう。その際、当該エリアの資金調達環境が大きく変化する可能性がある。こうした背景から、今後の企業倒産は、業種や地域によってまだら模様となり、そしてその傾向がいっそう鮮明になっていくと想定できる。

