倒産件数は588件、2カ月ぶりの前年同月比減で今年最少
負債総額は1867億6200万円、2カ月連続の前年同月比増加
倒産件数 | 588件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲9.3% |
前年同月 | 648件 |
前月比 | ▲13.1% |
前月 | 677件 |
負債総額 | 1867億6200万円 |
|---|---|
前年同月比 | +78.9% |
前年同月 | 1043億7800万円 |
前月比 | +65.4% |
前月 | 1129億2900万円 |
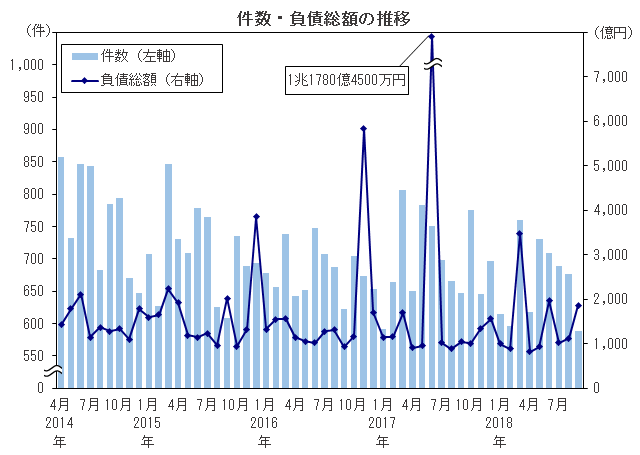
主要ポイント
- ■倒産件数は588件(前年同月比9.3%減)と2カ月ぶりに前年同月を下回り、今年最少となった。負債総額は1867億6200万円(同78.9%増)と、2カ月連続で前年同月を上回った
- ■業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を下回った。なかでも、建設業(98件、前年同月比18.3%減)は2000年以降最少。また運輸・通信業(24件、同20.0%減)は4カ月連続の前年同月比減少となった。一方、卸売業(93件、同5.7%増)は唯一前年同月を上回った
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は443件(前年同月比15.9%減)となり、8カ月連続で前年同月を下回った。構成比は75.3%(同6.0ポイント減)を占めた
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は358件(前年同月比7.0%減)となった。構成比は60.9%を占め、小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が390件で構成比66.3%を占めた
- ■地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を下回った。このうち、近畿(120件、前年同月比34.4%減)は5カ月連続、九州(33件、同21.4%減)は7カ月ぶり、北海道(15件、同34.8%減)と中部(91件、同15.0%減)は2カ月ぶりに前年同月を下回った。一方、中国(27件、同50.0%増)など3地域は前年同月を上回った
- ■負債トップは、(株)ケフィア事業振興会(東京都、破産)の1001億9462万円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント倒産件数は588件、2カ月ぶりの前年同月比減少で今年最少
倒産件数は588件(前年同月比9.3%減)と2カ月ぶりに前年同月を下回り、今年最少となった。負債総額は1867億6200万円(同78.9%増)と、2カ月連続で前年同月を上回った。
要因・背景
件数…業種別では7業種中6業種で、地域別では北海道や近畿など4地域で前年同月比減少
負債総額…(株)ケフィア事業振興会(負債1001億9462万円)が負債総額の53.6%を占めた
■業種別
ポイント7業種中6業種で前年同月比減少、建設業は2000年以降最少
業種別に見ると、7業種中6業種で前年同月を下回った。なかでも、建設業(98件、前年同月比18.3%減)は2000年以降最少。また、運輸・通信業(24件、同20.0%減)は4カ月連続の前年同月比減少となった。一方、卸売業(93件、同5.7%増)は唯一前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 建設業は、職別工事(45件、前年同月比11.8%減)、総合工事(37件、同24.5%減)、設備工事(16件、同20.0%減)で前年同月を下回り、2000年以降最少となった
- 2. 運輸・通信業は、貨物自動車運送(18件、前年同月20件)などが減少し、4カ月連続の前年同月比減少となった
■主因別
ポイント「不況型倒産」は443件、構成比は75.3%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は443件(前年同月比15.9%減)となり、8カ月連続で前年同月を下回った。構成比は75.3%(同6.0ポイント減)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1. 不況型倒産を業種別に見ると、サービス業(104件)が構成比23.5%を占め最多
- 2.「人手不足倒産」は15件(前年同月比66.7%増)、2カ月連続の前年同月比増加
- 3.「後継者難倒産」は30件(前年同月比3.4%増)、5カ月連続の前年同月比増加
- 4.「返済猶予後倒産」は26件(前年同月比27.8%減)、2カ月ぶりの前年同月比減少
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比60.9%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は358件(前年同月比7.0%減)となった。構成比は60.9%を占め、小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が390件で構成比66.3%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産では、サービス業(105件、前年同月比9.5%減)、小売業(89件、同2.2%減)など、7業種中5業種で前年同月比減少
- 2. 負債100億円以上の倒産(1件)が2カ月連続で発生
■地域別
ポイント9地域中4地域で前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を下回った。このうち、近畿(120件、前年同月比34.4%減)は5カ月連続、九州(33件、同21.4%減)は7カ月ぶり、北海道(15件、同34.8%減)と中部(91件、同15.0%減)は2カ月ぶりに前年同月を下回った。一方、中国(27件、同50.0%増)など3地域は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 近畿は、大阪府の製造業(5件、前年同月比64.3%減)やサービス業(11件、同59.3%減)、兵庫県の建設業(1件、同87.5%減)が前年同月を大幅に下回り、全体を押し下げた
- 2. 中国は、広島県の小売業(6件、前年同月比200.0%増)や山口県の建設業(3件、同200.0%増)が前年同月を上回り、3カ月連続の前年同月比2ケタ増となった
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは49.4、足踏み状態続く
2018年9月の景気DIは前月比0.1ポイント減の49.4となり、3カ月ぶりに悪化した。
9月の国内景気は、台風21号により関西国際空港が機能不全に陥ったほか、北海道胆振東部地震が広域で停電を引き起こし、生産や出荷などの企業活動が制約され、個人消費やインバウンドにも悪影響を及ぼした。加えて、原油高にともなう燃料価格などの上昇や人手不足の深刻化が景況感の悪化につながった。一方で、都市部を中心とした建設需要や復興需要が旺盛であったことに加え、日経平均株価が高値で推移したことや、日米間で自動車分野の関税引き上げが当面回避されたことなどが、マインドにプラスに働いた。海外では、米中双方による追加関税の第3弾が発動された。国内景気は、相次ぐ災害で被災地域を中心に景況感が悪化した一方で、旺盛な建設需要などが下支えし、足踏み状態が続いた。
設備投資や復興需要が見込まれるものの、米中貿易摩擦など海外リスクの影響を懸念
今後は、企業収益の増加を背景に設備投資の好調が続くほか、世界経済の回復を受け輸出も堅調に推移すると見込まれる。個人消費は、賃金上昇や就業者の増加を背景に2019年秋までは回復傾向が続くと予想されるが、天候不順や原油高による食品などの物価上昇を受け消費活動が一時的に低迷する可能性を注視する必要がある。また災害にともなう復興需要が発生するほか、東京五輪や消費税率引き上げの駆け込み需要も景気を下支えするであろう。他方、海外は米中貿易摩擦の激化が及ぼす影響や新興国経済の減速が懸念される。
今後は設備投資や輸出が堅調に推移し復興需要も見込まれるものの、海外リスクが高まるなかで、国内景気は不透明感が強まりつつある。
今後の見通し
■倒産件数は4012件で2年ぶりに減少
2018年度上半期の企業倒産は4012件(前年同期比4.4%減)となり、上半期として2年ぶりに減少した。特に土木・建築工事を含む建設業は2000年度以降で最少を記録、さらに金属製品等を含む製造業が倒産件数の減少に寄与する結果となった。多数のオーナーが被害を受けたシェアハウス展開のスマートデイズ(負債60億3500万円、東京都、破産)や債権者が3万3000人を超える各種商品通信販売のケフィア事業振興会(負債1001億9462万円、東京都、破産)グループなどのB to C関連の大型倒産のほか、上場企業倒産では東証1部の海洋資源掘削業者である日本海洋掘削(負債904億7300万円、東京都、会社更生)が目立った。
■相次ぐ自然災害、急がれる事業継続への対応策
2018年度上半期は、豪雨や地震、複数の大型台風の上陸など、各地で相次ぎ発生した自然災害が深刻な事業リスクとなった。過去には、直接被災せずとも自然災害を契機とした企業活動の停滞や経営破たんなどが発生しているが、一方で、事業継続計画(BCP)の策定企業は1割程度と依然として少なく、防災・減災対策、災害発生時や発生後の対応措置に関する準備などが進んでいない実態も明らかとなっている(帝国データバンク「事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2018年)」)。中小企業では企業の存続や事業継続に不可欠となるBCPの策定に必要なノウハウや人材・時間などが不足している。そのため、企業だけでなく政府や行政によるこうした課題の解消に向けた施策の実行が急がれよう。
■地域経済の生産性向上、地域金融機関の活用がカギを握る
地域経済の生産性向上に向けた動きが活発化している。金融庁は9月26日、2018事務年度(2018年7月~2019年6月)における重点施策をまとめた金融行政方針を発表した。同方針では、投資用不動産向け融資の監督強化や金融デジタライゼーションの環境整備、仮想通貨市場の厳正化・国際化、マネーロンダリング対応などの強化が掲げられた。また、地域企業・経済の実態を把握する「地域生産性向上支援チーム」が金融庁に新設され、分析結果などを地域金融機関で活用する仕組みの構築が図られたことも注目される。地域銀行の過半数で本業利益(貸出・手数料ビジネス)が赤字となるなか、金融仲介機能の発揮等により、地域経済の活性化を促す地域金融機関の取り組みが今後の企業業績に大きく影響するとみられる。
■倒産動向は抑制された状態で推移すると見込まれるも、景気下振れリスクに懸念
国内景気は、堅調な設備投資や輸出のほか、賃金上昇や消費税率引き上げ前の駆け込み需要、東京五輪、復旧・復興需要などはプラス要因となろう。他方、天候不順に伴う価格上昇や米中貿易摩擦の激化、新興国経済の減速など、下振れリスクも多い。
他方、企業の人手不足は深刻度を増している。帝国データバンクの2018年9月調査では企業の51.7%が人手不足に直面するなか、2018年度上半期の人手不足倒産は76件(前年同期比40.7%増)判明、大幅な増加が続いている(同「『人手不足倒産』の動向調査(2018年度上半期)」)。人手不足が経営に与える影響は今後も注視していく必要があろう。
こうした状況のなか、金融機関による返済猶予への柔軟な支援は倒産を抑制する要因となっており、今後もこうした流れに大きな変化はないものとみられる。そのため、当面の倒産動向は抑制された状態で推移すると見込まれ、2018年度の倒産件数は概ね2017年度並みの8000~8300件程度になると予測される。

