倒産件数、14カ月連続で前年同月を上回る
6月としては3年ぶり700件超え
倒産件数 | 782件 |
|---|---|
前年同月比 | +43.8% |
前年同月 | 544件 |
負債総額 | 1232億800万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲90.4% |
前年同月 | 1兆2839億800万円 |
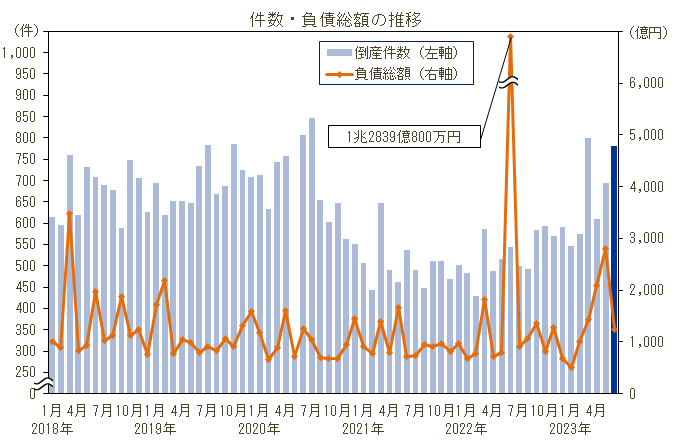
概況・主要ポイント
- ■倒産件数は782件(前年同月544件、43.8%増)と、前年同月から238件増加し、14カ月連続で前年同月を上回った。6月としては2020年(806件)以来3年ぶりに700件を超えた。また、前月に比べると88件(12.7%)増え、3カ月連続で増加した
- ■負債総額は1232億800万円(前年同月1兆2839億800万円、90.4%減)と、マレリHDの法的整理が発生した前年同月からの反動減もあり、前年同月から90%以上の大幅減となった
- ■業種別にみると、『不動産業』を除く6業種で前年同月を上回った。件数が最も多かったのは『サービス業』(前年同月135件→180件、33.3%増)で、16カ月連続で増加。『小売業』(同99件→163件、64.6%増)では、前月に続き「飲食店」が倍増した
- ■主因別にみると、『不況型倒産』の合計は632件で、3カ月連続で80%を超えた
- ■態様別にみると、「民事再生法」は31件とほぼ倍増、3年ぶりの30件台となった
- ■規模別にみると、負債「5000万円未満」の倒産は435件で、全体の55.6%を占めた
- ■業歴別にみると、「30年以上」が最多。『新興企業』は16カ月連続で前年同月を上回った
- ■地域別にみると、『北海道』を除く8地域で前年同月を上回った。『九州』(前年同月37件→75件、102.7%増)は、15年5カ月ぶりに9カ月連続で前年同月を上回った。『関東』(同216件→258件、19.4%増)は、「東京」が5カ月連続で20%を超える大幅増
■業種別
『不動産業』を除く6業種で前年同月を上回る
業種別にみると、『不動産業』を除く6業種で前年同月を上回った。件数が最も多かったのは、『サービス業』(前年同月135件→180件、33.3%増)で、『小売業』(同99件→163件、64.6%増)、『建設業』(同114件→160件、40.4%増)が続いた。『卸売業』(同66件→110件、66.7%増)は、約3年ぶりに100件に達したほか、『運輸・通信業』(同31件→47件、51.6%増)は、6月としては過去10年で最多となった。
業種を詳細にみると、『サービス業』では、2008年5月-09年8月以来13年10カ月ぶりに16カ月連続で前年同月を上回った。『小売業』では、前月に続き「飲食店」(前年同月35件→73件)が倍増し、6月としては2020年に次ぐ過去2番目の件数を記録した。人手不足と建設資材の高止まりが続く『建設業』では、「職別工事」(同40件→73件)と「設備工事」(同27件→43件)の増加が目立った。
■倒産主因別
「不況型倒産」は632件 3カ月連続で80%超え
主因別にみると、「販売不振」が619件(前年同月422件、46.7%増)で最も多く、全体の79.2%(対前年同月1.6ポイント増)を占めた。内訳を業種別にみると、「サービス業」(前年同月94件→147件)が最も多く、「建設業」(同89件→135件)、「小売業」(同87件→135件)が続く。「業界不振」(同6件→11件、83.3%増)などを含めた『不況型倒産』の合計は632件(同430件、47.0%増)となり、3カ月連続で80%を超えた。
「放漫経営」(前年同月5件→17件、240.0%増)は、前月に続き大幅に増加したほか、「その他の経営計画の失敗」(同26件→28件、7.7%増)は2カ月ぶりに、「経営者の病気、死亡」(同17件→23件、35.3%増)は4カ月ぶりに前年同月を上回った。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■倒産態様別
『清算型』倒産は751件 「民事再生法」は3年ぶりの30件台
倒産態様別にみると、『清算型』倒産の合計は751件(前年同月528件、42.2%増)となり、全体の96.0%(対前年同月1.1ポイント減)を占めた。『再生型』倒産は31件(同16件、93.8%増)発生し、6カ月連続で前年同月を上回った。
『清算型』では、「破産」が724件(前年同月505件、43.4%増)で最も多く、15カ月連続で前年同月を上回った。「特別清算」は27件(同23件、17.4%増)発生し、2年ぶりに2カ月連続で前年同月を上回った。
『再生型』では、「民事再生法」が31件(前年同月16件、93.8%増)とほぼ倍増、3年ぶりの30件台となった。このうち、法人で12件発生し、7カ月ぶりに10件に達した。
■規模別
負債「5000万円未満」の倒産は435件 全体の55.6%を占める
負債規模別にみると、「5000万円未満」が435件(前年同月317件、37.2%増)で最も多く、全体の55.6%を占めた。次いで、「5億円未満」が181件(同104件、74.0%増)、「1億円未満」が125件(同92件、35.9%増)と続いた。
資本金規模別では、『個人+1000万円未満』の倒産が536件(前年同月359件、49.3%増)となり、全体の68.5%を占めた。
■業歴別
業歴「30年以上」が最多、業歴10年未満の新興企業の増加続く
業歴別にみると、「30年以上」が245件(前年同月171件、43.3%増)で最も多く、全体の31.3%(対前年同月0.1ポイント減)を占めた。このうち、老舗企業(業歴100年以上)の倒産は7件(同3件、133.3%増)だった。
業歴10年未満の『新興企業』[「3年未満」(前年同月19件→39件、105.3%増)、「5年未満」(同48件→46件、4.2%減)、「10年未満」(同102件→138件、35.3%増)]は223件(同169件、32.0%増)と、16カ月連続で前年同月を上回った。内訳を業種別にみると、「サービス業」(同51件→67件、31.4%増)が最多、「建設業」(同39件→48件、23.1%増)、「小売業」(同36件→44件、22.2%増)と続いた。
■地域別
『北海道』を除く8地域で前年同月を上回る
地域別にみると、『北海道』を除く8地域で前年同月を上回った。最も増加率の高い『四国』(前年同月2件→15件、650.0%増)は、前年同月に発生がなかった「香川」(同0件→5件)などで発生したこともあり、全体で前年同月から大幅増となった。『九州』(同37件→75件、102.7%増)は、前年同月から倍増し、15年5カ月ぶりに9カ月連続で前年同月を上回った。『東北』(同26件→51件、96.2%増)は、「福島」(同5件→16件)の大幅増が目立った。このほか、『関東』(同216件→258件、19.4%増)は、「東京」(同111件→139件)が5カ月連続で前年同月から20%を超える大幅増。『近畿』(同141件→204件、44.7%増)は、「大阪」(同68件→102件)が2年10カ月ぶりに100件台を記録した。
■景気動向指数(景気DI)
2023年6月の景気DIは45.0、回復傾向が一時ストップ
2023年6月の景気DIは前月比0.4ポイント減の45.0となり、5カ月ぶりに悪化した。経済活動や社会生活の正常化に向けた動きがさらに加速するなかで、景気は、長引く人手不足やインフレ傾向などがマイナス要因となり、回復傾向が一時的にストップした。
食品など生活必需品の値上げや電気代を含むエネルギー価格の高騰などが悪材料となった。またインフレに賃上げのペースが追いつかず買い控えの動きも表れるなど、個人消費が低調だった。観光産業では、国や自治体の支援策が一部で販売終了となったほか、平年よりも早い梅雨入りなど天候による影響もみられた。他方、インバウンドや人出の増加、新型コロナ禍からのリベンジ消費、半導体の不足が緩和したことなどはプラス材料だった。
今後の見通しは緩やかな回復傾向で推移
今後1年間の国内景気は、ポストコロナ時代に向けた経済・社会システムの構築に対する動きが加速するなかで推移するとみられる。悪材料として海外経済の減速やウクライナ情勢などは先行き不透明な状態が続く。さらに生活必需品や電気代の値上げ、人手不足、為替レートの変動なども懸念される。他方、ボーナスを含む賃上げの広がりや消費マインドの改善、夏の観光などがプラス材料となろう。DXの推進や脱炭素化などの設備投資は着実に進むと見込まれ、インフレ傾向は徐々に鈍化していくと期待される。今後は、ポストコロナへの対応を進めつつ、緩やかに回復しながら推移していくとみられる。
今後の見通し
■企業倒産、抑制から「反動増」へ 23年上半期は4006件、6年ぶり増加
2023年上半期(1-6月)の企業倒産は4006件だった。前年同期の3045件を約1000件上回り、上半期としては2018年以来5年ぶりに4000件台に達した。3月には17年以来6年ぶりの800件台に到達したほか、昨年5月以降14カ月連続で前年を上回り、増加期間はリーマン・ショック後の08年6月-09年8月(15カ月連続)に迫る。特に今年2月以降は前年比20%超の増加が4カ月連続で続き、この増加期間はIT不況で倒産が急増した02年当時に並んだ。企業倒産はコロナ禍前半の歴史的な低水準を経て、明らかに増加基調へシフトしている。
負債総額は9065億8400万円にとどまった。1兆円超の負債を抱えて民事再生法を申請した、自動車部品大手「マレリホールディングス」(22年6月)のような超大型倒産が発生しなかったため、前年同期(1兆7630億8300万円)からはほぼ半減した。ただ、負債規模の大きい倒産は2023年に入り、散発的に発生している。特に目立ったのが大型の民事再生手続きによる倒産である。有機ELディスプレイメーカー「JOLED」(3月)をはじめ、23年で負債トップの「ユニゾHD」(4月)、国内トップクラスのスマホメーカー「FCNT」(5月)など、主だった23年上半期の倒産はいずれも再建型の法的整理だった。
■問われる「企業の地力」 ファンド出資の再建企業、粉飾発覚による倒産が増加
倒産が急増する背景には、「ゼロゼロ融資」に代表される各種公的支援による抑制効果の一巡に加え、インフレ下におけるコスト負担増が大きく影響している。加えて『2024年問題』に象徴される、建設や運輸業を中心とした「人手不足」を要因とした倒産もここにきて目立ってきている。実際に、ゼロゼロ融資を受けた後の倒産は1-6月で304件と、年半期で初めて300件を超え、原材料高などに起因した物価高(インフレ)倒産(375件)も前年(320件)を既に超えた。人手不足倒産も110件発生し、過去最多ペースで推移している。
2023年上半期の特徴の一つに、「ファンド投資先企業」の倒産があげられる。お好み焼き・鉄板焼き店チェーンの「ダイナミクス」(2月)、会社更生を申請した海外雑貨小売の「アッシュ・ペー・フランス」(5月)など、投資ファンド主導の再建計画が頓挫し、法的整理を余儀なくされたケースが目立った。コロナ禍前にファンドが資金を投じた企業の中には、外部環境の急変で当初の事業計画が頓挫し、経営破綻の危機に瀕している企業は多いとみられる。
大がかりな粉飾決算が発覚した倒産も多発した。産業用機械メーカー「トガシ技研」(2月)をはじめ、粉飾を長期に渡り隠蔽していた企業の倒産が目立つ。ゼロゼロ融資を導入したほぼすべての企業が元本返済のタイミングを迎え、本業の収益力など「企業の地力」が今後問われるなかで、粉飾で資金繰りの実態がごまかせなくなった企業の倒産が増加する可能性がある。
■救済色の強い支援姿勢から転換、支援の対象は「選別」への動きも
政府は6月、「骨太の方針」と成長戦略を練った「新しい資本主義」の実行計画を閣議決定した。少子化対策や労働市場改革、スタートアップなど新興企業の創出に力点が置かれる一方で、市場からの円滑な企業退出の促進を示唆する文言も今回は複数盛り込まれた。政府はこれまで、雇用の維持を目的に企業の倒産や廃業といった市場退出を抑制するため、コロナ以前から続く借入金の暫定リスケ対応をはじめ、コロナ禍のゼロゼロ融資など各種の経営支援を展開してきた。しかし、ここにきて成長産業や高収益企業に集中支援する方針が鮮明となり、救済色の強かったこれまでの支援方針からは一線を画す。外部支援に頼りきりの企業や、賃上げ余力の乏しい低収益企業などでは、従来のような豊富な金融支援が満足に受けられなくなる可能性もある。
足元では、民間ゼロゼロ融資の返済開始時期がこれから本格化することに加え、物価高や電気代、円安等によるコストプッシュ圧力も高まり、従前以上に本業の「収益力」が問われる局面へと突入する。一方、3年以上に及ぶコロナ禍で先行きの見通しが立たず、収益悪化と価格転嫁の板挟みとなって事業意欲を喪失した経営者は各業界で少なくない。今後の企業倒産は、こうした先行き悲観からの「あきらめ型倒産」が全体の件数を底上げする形で、2023年の企業倒産はコロナ禍前の2018-19年の水準(8000件台)への到達も視野に増加が続くとみられる。

